サブスク会計学 ―持続的な成長への理論と実践
藤原大豊 , 青木章通
中央経済社
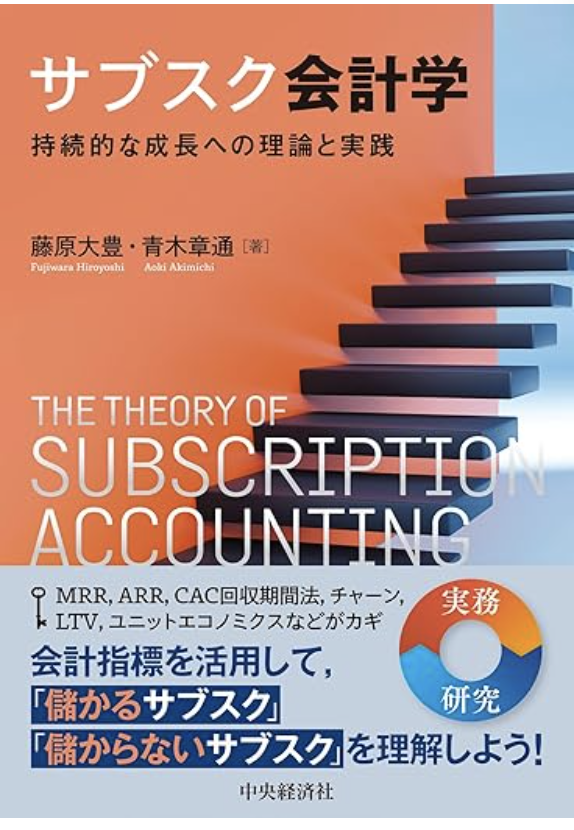
サブスク会計学 ―持続的な成長への理論と実践(藤原大豊, 青木章通)の要約
サブスクリプションビジネスは「予測可能性が高い」「契約後が勝負」「長期継続で収益が拡大する」「経営が安定しやすい」といった特徴を持ちます。しかし、その成功にはユニットエコノミクスの健全化が不可欠です。LTV(顧客生涯価値)を高め、CAC(顧客獲得コスト)を抑えつつ、解約率を下げることで、持続的な成長が可能になります。単なる顧客数の拡大だけではなく、一人ひとりの経済性を高める戦略が重要です。
サブスク会計の知識が重要な理由
サブスクの特徴として「予測可能性が高い」「契約してからが勝負」「長期化するほど儲かる」「経営の安定」が一般的には挙げられている。(藤原大豊, 青木章通)
サブスクビジネスは、日本でもここ数年で急速に普及していますが、失敗する企業も多いのが実態です。その最大の原因は、サブスク特有のルールや収益構造を十分に理解せず、事業をスタートしてしまう点にあります。
サブスクビジネスを成功に導くためには、アイデアや情熱だけでは不十分です。多くの企業がつまずく理由は、このビジネスモデル特有の会計指標を理解しないまま市場に参入してしまうことにあります。
また、サブスクモデルにおいては、月額課金であるがゆえに常に解約リスクが存在し、見込まれていた収益が将来的に失われる可能性を考慮しなければなりません。そのため、売上の計上タイミングおよび金額の管理が極めて重要となります。一括で売上を計上してしまうと、実態を正しく反映できないため、収益を適切に配分することが求められます。
このような特性を踏まえ、サブスクビジネスでは、専用の会計処理ルールを正確に理解し、適切に適用することが、事業の健全な成長と信用維持に直結するのです。
著者の藤原大豊氏(三菱総合研究所 主席研究員) 青木章通氏 (専修大学経営学部教授・㈱サブスクリプション総合研究所フェロー)は、 サブスクモデルでの失敗を避けるために不可欠なサブスク特有の会計指標やビジネスの成功要因、事例を含めて、本書で丁寧に解説しています。
MRR(Monthly Recurring Revenue 月次経常収益)やARR(Annual Recurring Revenue 年次経常収益)をはじめ、CAC回収期間(Customer Acquisition Cost Recovery Period 顧客獲得コストの回収期間)、ユニットエコノミクス(Unit Economics 単位経済性)、チャーンレート(Churn Rate 解約率)、LTV(Lifetime Value 顧客生涯価値)など、主要な指標がどのように機能し、なぜ重要なのかを具体的に学ぶことができます。
サブスクビジネスの一般的な特徴として、「予測可能性が高い」「契約してからが勝負」「長期化するほど儲かる」「経営の安定」などが挙げられます。
まず、「予測可能性が高い」とは、月額や年額で定期的に収益が発生するため、将来の売上や利益を比較的正確に予測できることを意味します。これにより、投資計画や人員配置、マーケティング戦略などの経営判断を、リスクを抑えながら行うことが可能になります。
また、「契約してからが勝負」という特徴は、サブスクビジネスが顧客との関係性の継続に価値を置いていることを示しています。新規顧客を獲得するだけでなく、いかに解約を防ぎ、継続利用を促進していくかが収益を左右します。そのため、顧客体験の質を高め、満足度を維持する取り組みが非常に重要になります。
「長期化するほど儲かる」という特徴は、契約期間が長ければ長いほど顧客一人当たりの収益性(LTV)が高まることを意味しています。初期の顧客獲得コスト(CAC)は一定期間を経て回収され、その後は利益が累積的に増える構造になっています。よって、短期的な売上に一喜一憂するのではなく、中長期的視点での顧客維持戦略を構築することが求められます。
最後に「経営の安定」については、定期的かつ継続的に収益が得られることで、経営基盤が安定しやすいというメリットがあります。これにより、不況や市場の変動にも耐えられる強固なビジネスモデルを構築することが可能になります。ただし、その安定性を享受するためには、上述の各指標を用いた収益管理が不可欠です。
チャーンがサブスクにおいて、重要な指数である!
顧客数減のはずなのに収益増になるのがネガティブチャーン。
サブスクリプションモデルにおいて、チャーン(解約率)は最も重要な指標の一つです。どれほど積極的に新規顧客を獲得したとしても、既存顧客が流出し続けるようでは、ビジネスの持続的成長は望めません。チャーンとは、一定期間内に離脱した顧客の割合を示します。この数値が高いということは、収益の安定性が損なわれ、事業の先行きに影を落とすことを意味します。
一方で、チャーンを適切に管理し、「ネガティブチャーン」と呼ばれる状態を実現することができれば、サブスクリプションビジネスは自律的に成長し続ける極めて強固なモデルへと進化します。
ネガティブチャーンとは、解約による売上減少を、既存顧客からのアップセルやクロスセルによる売上増加が上回る状態を指します。つまり、解約が発生しても、全体として収益が拡大していく構造です。この状態に到達すれば、新規顧客獲得に過度に依存せずとも、事業は継続的にスケールしていくことができます。
このネガティブチャーンを実現した好例が、Slack社です。同社は毎年、新規顧客を着実に増やしながら、継続顧客への課金を強化し、売上を伸ばすことに成功しています。たとえ一定数の解約が発生しても、全体の収益は純増し続け、強力な成長エンジンを内在化するに至ったのです。単なるチャットツールにとどまらず、ワークスペース全体の生産性向上を支えるプラットフォームへと進化したことが、この成長を後押ししました。
チャーン率の重要性を軽視することは、サブスクリプションビジネスにおいて致命的な過ちとなります。チャーンが高い状態で新規顧客を獲得し続けることは、底の抜けたバケツに水を注ぎ続けるようなものです。
対照的に、チャーンを抑え、さらにネガティブチャーンを実現できれば、LTVは劇的に向上し、CAC(顧客獲得コスト)とのバランスも大きく改善されます。それにより、資本効率を飛躍的に高め、成長と収益性を同時に実現する、理想的な経営状態を手に入れることができます。
本書では、アメリカの上場SaaS企業の記事を紹介していますが、年間のグロスチャーンの中央値は4%であることが明らかになリマした。この水準は、健全な成長を目指すうえでの一つのベンチマークと捉えることができます。当然、この4%に満足するのではなく、可能な限り解約率を引き下げ、より強固で盤石な顧客基盤を築くことが重要です。
ネガティブチャーンを達成するためには、チャーン率を限界まで低下させ、既存顧客との関係を深化させ続けることが不可欠なのです。 チャーンとは単なるリスク管理の対象ではありません。
むしろ、サブスクリプションモデルを「自走式の成長マシン」へと進化させるための、戦略的な鍵になります。Slack社の事例は、その現実性と効果を見事に証明しています。サブスクを制するためには、チャーンを制する以外に道はありません。この原理原則は、今後も揺るぐことはないと私は考えています。
サブスクモデルで成功するために必要なこと
顧客獲得のための成長投資を大きくすればするほど将来的に大きな利益を得られる代わりに一時的な損失も大きくなります。
サブスクリプションモデルは、偶然の産物ではありません。 緻密な設計と精緻な管理によってのみ、持続的な成功を手にすることができます。
成長を志向するサブスクリプションビジネスは、まず深い谷を経験します。この収益曲線は「Jカーブ」と呼ばれ、初期投資による赤字拡大ののち、顧客基盤の拡大とともに急速な収益成長を遂げる現象を指します。
サブスクリプションモデルの最大の特徴は、売上の予測可能性が高く、顧客との長期的な関係を築ける点にあります。一方で、初期段階では顧客獲得コスト(CAC)が先行し、収益化には一定の時間を要します。このため、資金繰りや戦略設計の巧拙が、企業の生死を左右することになります。
顧客獲得のために成長投資を拡大すればするほど、将来的なリターンは大きくなりますが、一時的な損失も拡大します。このフェーズでは、現金収支において支出が収入を上回り、現金残高は減少の一途をたどります。現金が枯渇すれば、倒産リスクが高まるため、成長投資には十分な現金残高と高い資金調達力が不可欠です。
また、会計期間単位で損益を見ると、将来的に大きな利益を生み出すサブスクリプション型ビジネスほど、一時的な損失が大きく見える傾向があります。ここで重要となるのが、「ユニットエコノミクス」の理解です。
ユニットエコノミクスとは、顧客一人当たりの収益性を測る指標であり、LTV(顧客生涯価値)とCAC(顧客獲得コスト)のバランスが核心となります。基本的には、LTVを高めるか、CACを低下させるか、この2つのアプローチによってのみ健全な成長が実現します。
新規顧客の獲得コストは、既存顧客を維持するコストの5倍に達するという調査結果もあります。また、わずか5%の顧客離れを防ぐだけで、利益率が25%向上するというデータも存在します。これらの事実が示唆するのは、カスタマーサクセスに注力することが、いかに戦略的に重要かという点です。
つまり、CACよりもCRC(顧客維持コスト)やCEC(カスタマーエンゲージメントコスト)に投資し、解約率を下げるとともに、アップセルやクロスセルによってエクスパンションを促進することが、ARR(年間経常収益)の効率的な増加に直結するのです。この取り組みは結果として、LTVを向上させ、ネガティブチャーンの実現可能性を高めることにもつながります。
赤字が続く中でもさらに赤字を拡大させる企業行動は、一見すると不合理に映るかもしれません。しかし、サブスクリプションビジネス特有の会計構造を踏まえれば、それは極めて合理的な成長戦略だと理解できます。定期収益の予測可能性が高いため、成長投資(販促費)を調整することで、利益水準を自在にコントロールできるからです。
上場企業の開示資料を俯瞰すると、売上高と営業利益の実績・予測推移からも、こうした戦略的特性が裏付けられています。会計期間単位の損益にとらわれるのではなく、投下したS&M(販促費)に対するARRの増加を冷静に分析することが、費用対効果を正確に把握する鍵となるのです。
本書では、意図的に赤字を出しながら利益をコントロールしつつ成長投資を推進するマネーフォワードと、収益を精緻に予測しながら黒字経営を継続するオイシックスの成功事例が紹介されています。両社を比較することで、いわゆる「Jカーブ型」の成長を描くマネーフォワードと、より穏やかな成長曲線を目指すオイシックスの戦略的違いが鮮明に浮かび上がります。
サブスクリプションビジネスの成功は、偶然や運に依存するものではありません。緻密な戦略設計と徹底した指標管理を組み合わせることによってのみ、「安定的で持続可能な成長」は実現されるのです。本書は、その確かな第一歩を踏み出すための強力なガイドとなるはずです。
私自身、サブスクモデルやSaaS企業の経営支援を行うなかで、本書に記載された会計的知見については日常的に意識してきました。しかし、こうして体系立てて整理された形で再確認することで、自らの理解をより高い次元へと引き上げる好機となりました。
著者の一人である藤原氏とは日頃からビジネスを共にする機会があり、常に多くの学びを得ています。本書は氏からご恵贈いただいたものですが、その内容は単なる賛辞を超え、強く推奨できるレベルです。 サブスクリプションビジネスに携わるすべての起業家や経営者や担当者にとって、必読の一冊であると確信しています。
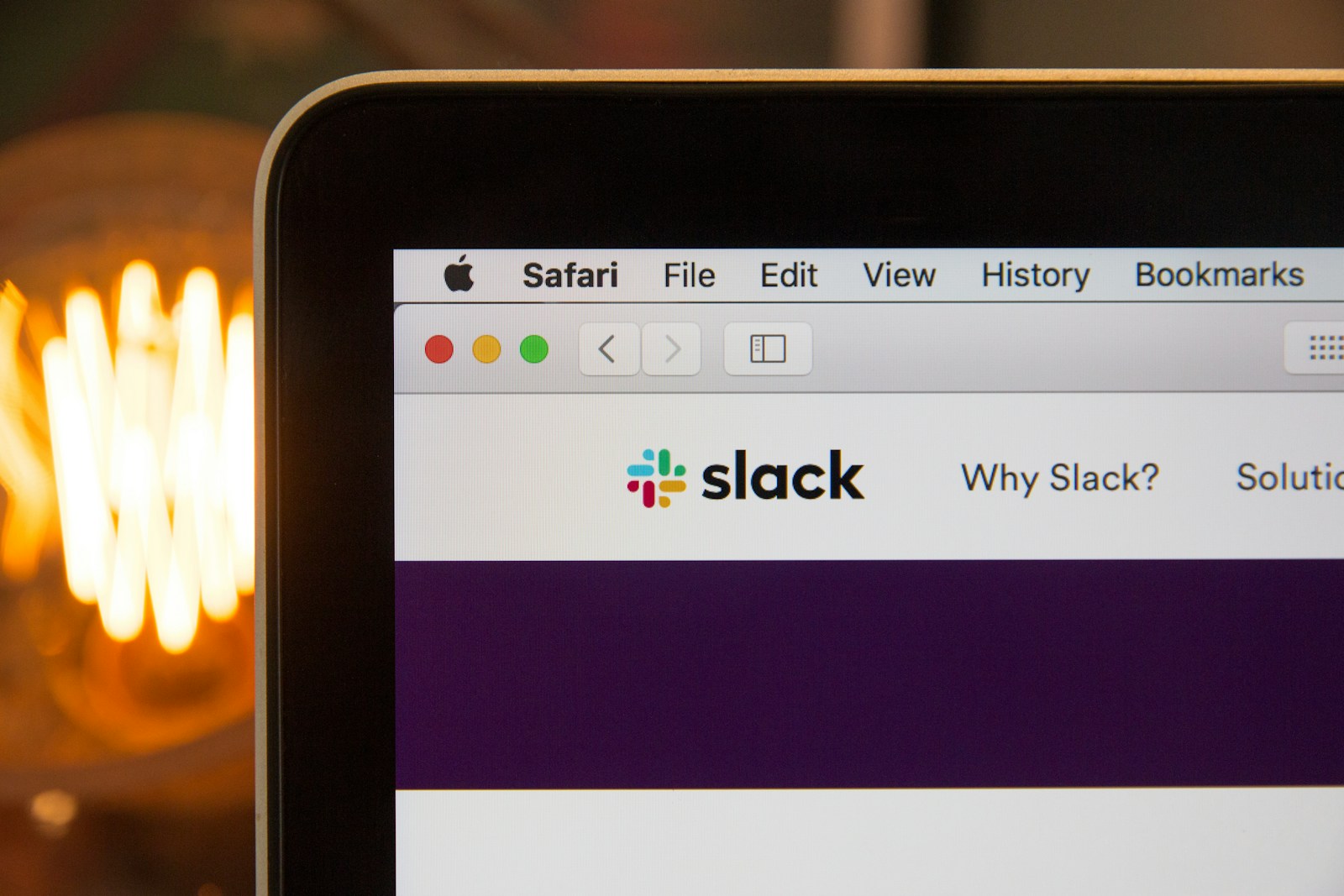






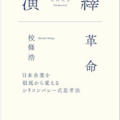






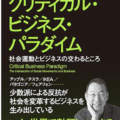


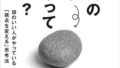
コメント