ライフ・シフトの未来戦略―幸福な100年人生の作り方
アンドリュー・スコット
東洋経済新報社
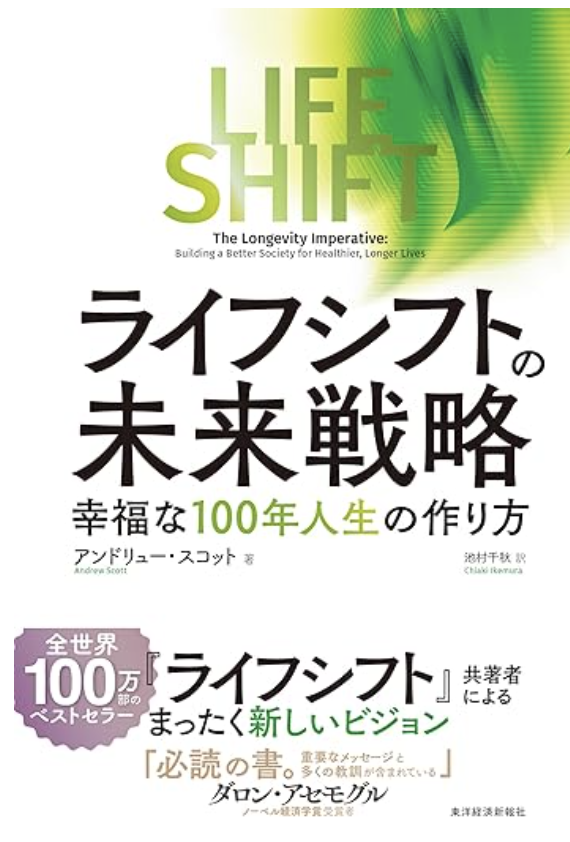
ライフ・シフトの未来戦略(アンドリュー・スコット)の要約
長寿社会への移行は、個人と社会に新たな課題を突きつけています。従来の3段階人生モデルでは対応できず、「マルチステージの人生」が求められるようになりました。この新たなパラダイムでは、学び・働き・休むを何度も繰り返すことが標準となります。 個人は健康・富・スキル・人間関係・目的意識への未来投資を継続的に行い、企業や社会制度も柔軟な働き方や生涯学習支援、予防医療への転換を急ぐ必要があります。
人生100年時代をエバーグリーンにするために必要なこと
不健康な状態で、生き甲斐もなく、人間関係も乏しく、お金の面でも不安に苛まれながら90歳を迎える事態を避けたいと思えば、いま未来のためにもっと投資する必要がある。そのような投資がいまほど重要だった時代はなかった。私たちは老い方を変えなくてはならない。(アンドリュー・スコット)
世界はかつてないスピードで長寿社会へと突き進んでいます。1950年と比べ、世界の平均寿命は20年以上も延びました。日本では男女ともに平均寿命が80歳を超え、さらに総人口に占める65歳以上の割合は約29%に達しています。これは、世界でも類を見ない超高齢社会の到来を示すものです。
この長寿化現象は日本特有の課題ではなく、欧米やアジア諸国においても同様の傾向が見られ、多くの国で平均寿命が80歳前後に到達し、高齢化が社会経済構造に大きな影響を及ぼし始めています。
アンドリュー・J・スコット教授(ロンドン・ビジネス・スクール経済学教授)の最新著書ライフ・シフトの未来戦略―幸福な100年人生の作り方は、この時代の転換期において本質的な問いを投げかけています。
スコット教授は、従来の「高齢化社会」という概念を「負担」と考える視点から脱却し、「長寿社会」を積極的な機会として捉え直すべきだと主張しています。100歳まで生きるという人口構造の変化を問題視するのではなく、長い人生をより充実したものにするための社会設計と個人の姿勢の転換が重要だと指摘します。
著者は、人口の高齢化を「社会的な負担」として捉える従来の見方に異議を唱え、「エバーグリーン・アジェンダ」という新たな概念を提示します。これは、人生全体を通じて健康、教育、社会参加に積極的に投資することで、高齢化を単に寿命を延ばすことから、健康で充実した人生を送る期間を最大化する方向にシフトする考え方です。
前提1──私は高齢になるまで生きる可能性が高い。
前提2──長生きすることに関する最大の不安は、ひどい老い方をすることである。
エバーグリーン型の結論──よい老い方をできる可能性を最大限高めるために、いまできることをするべきである。
彼は単に「高齢者の増加」という側面ではなく、「すべての世代がより長く生きられるようになった」という大きな変化に注目し、これを「第2の長寿革命」の始まりと位置づけています。
この新しい時代を成功させるためには、古い「教育→仕事→引退」という直線的な人生設計を捨て、複数の職業経験、生涯にわたる学び、柔軟な働き方を組み合わせた「マルチステージの人生」へと移行することが必要不可欠だと説いています。
スコット教授の前著ライフシフト2は個人に焦点を当て、長寿時代を生き抜くための個人的戦略を提示していました。これに対して本書では、政府や企業など社会制度全体の変革に分析の視座を移しています。
長寿社会においては、個人の生活戦略を見直すだけでは不十分で、社会経済構造そのものを再考することが次世代の重要な課題となっています。 ここで特に注目すべきは、高齢化をリスク要因として捉えるのではなく、成長を促す原動力として位置づける視点です。
単に寿命を延ばすことを目指すのではなく、健康で充実した長い人生を実現する社会システムの構築が私たちには求められています。 「よりよい老い方を可能にするためには、個人と政府が多大な投資を行う必要がある」と著者は言います。
今、私たちは単に「何歳まで生きられるか」という数字だけを重視する考え方から、「どのように豊かに生きるか」という質を重視する考え方へと転換すべき時期に来ています。長寿は単なる年齢の延長ではなく、その長い人生をどう意味あるものにするかという、私たち全員の意識と価値観の根本的な変化を必要としているのです。
人生100年時代には、自分の健康状態、寿命、キャリアに関して多くの不確定要素が存在します。そのため、長寿化が財務計画に及ぼす影響に対処するには、プランに柔軟性を組み込んでおくことが重要です。 私たちは資産を点検する際、金融資産だけではなく、「無形資産」にも目を向ける必要があります。無形資産とは、スキルや知識、健康状態、友人や人脈、生き甲斐や人生の目的意識、そして変化や困難を乗り越えるための適応力を指します。
これらの無形資産は、長寿化時代において金銭的な資産以上に重要な役割を果たします。
平均寿命が上昇したことで、どの年齢の人にとっても、今後生きられる人生の期間が昔に比べて長くなった。人生が長くなれば、少なくとも死生学的年齢の面では、若くあることのできる年数が増える。そうなれば、自分の未来に投資して新しいスキルを学び、古い知識や行動パターンを捨て去ることがより理にかなった選択になる。
スキルや知識は常にアップデートされ、時代の変化に対応できるように磨かれなければなりません。健康は長寿時代の土台であり、健康管理や運動習慣の維持、栄養管理が重要となります。さらに、人生の充実感を支える友人や人脈の構築、そして変化に適応する柔軟性やレジリエンスを培うことが求められます。
このような無形資産に投資し、その価値を高めていくことは、人生をより豊かにし、不確実な未来に対する備えにもなります。資産の点検とともに、日常的に無形資産を育てていくことで、長寿時代において持続可能で豊かな人生を送ることができるのです。
長い人生を生き抜くために、私たちは健康、富、スキル、人間関係、目的意識への継続的な投資が欠かせなくなっているのです。
長寿社会をより良く生きるためには無形資産への投資も必要!
私たちがこれまで築いてきた社会では、人生終盤の時期のために十分な投資がなされていない。人類の歴史のほとんどの期間、それほど長く生きる人はごく一部にすぎなかったからだ。しかし、状況は変わったのだ。今日、エバーグリーンの課題に取り組むことで得られる恩恵は非常に大きく、しかも重要性を増しており、もはや無視できないものになっている。
長寿社会を豊かに生きるための新しい視点 スコット教授は、健康を医療制度だけの問題ではなく、個人の生活習慣と社会環境の産物として捉えています。現代の医療は「病気の治療」に焦点を当てていますが、これからは「健康の維持・増進」へのシフトが必要です。
日々の食事、運動、睡眠の質といった習慣が将来の健康を左右します。AIや最新技術の進歩により、個人が健康データを自ら管理し、遺伝子検査で将来のリスクを予測・予防できる時代になりつつあります。真の健康社会の実現には、都市計画、交通、栄養環境、社会的つながりなど、多方面からの統合的な支援が不可欠です。
長い人生を経済的に乗り切るには、出費を抑えるか、長く働き続けるしかありません。企業年金だけで悠々自適に暮らせる時代は終わり、多くの人が職業人生の延長を余儀なくされています。長寿社会の恩恵を受け取るためには、政府が「引退年齢の引き上げ」「引退までの就業率向上」「高齢労働者の生産性向上」という3つの役割を果たす必要があります。
現代は一つの職業に生涯を捧げる時代ではなく、「マルチステージ型人生」が新たなスタンダードになっています。複数のキャリア、適宜挟む学び直しや休息といった柔軟な設計が求められます。従来の「教育→労働→引退」という3段階モデルは、平均寿命70歳の時代に合わせたものでした。
現在の80歳以上、さらには100歳を視野に入れた社会では、65歳以降の20年以上をどう生きるかが重要です。この時期を「余生」ではなく、人生の第4ステージとして主体的に設計する必要があります。
学びは若者だけのものではなく、生涯を通じて継続すべき活動です。急速なイノベーションの中で、知識やスキルはすぐに陳腐化するため、常に更新し続ける必要があります。教育機関も全世代の学習を支援する存在へと変革が求められ、オンライン学習やマイクロ資格制度が新たな教育形態として台頭しています。
これからの労働環境には、フルタイムやパートタイム、プロジェクトベース、さらには複数の仕事を組み合わせた柔軟な働き方など、多様なスタイルを受け入れる柔軟性が不可欠です。特に高齢者が持つ豊かな知識や経験を積極的に活用することは、社会全体の生産性を高める大きな力となります。
また、社会保障制度についても抜本的な再設計が必要です。退職後の生活が20年以上にもわたることを考えると、より柔軟で現実的な制度が求められます。若い世代と高齢世代がそれぞれの強みを生かし合い、互いに支え合う世代間連携も今後ますます重要になります。
さらに、地域コミュニティの役割も新たに定義し直す必要があります。多様化が進む社会において、地域単位での相互支援が新しい社会基盤として位置付けられるようになるでしょう。 長寿社会では、「働く・学ぶ・休む」といった人生の各段階において、それぞれが安心して自由に選択できる環境が重要です。しっかりとした生活基盤と、自分らしい人生を選択できる自由、この両方を兼ね備えた社会をつくる必要があります。
これからの時代、個人が「未来の自分」への投資を主体的に行うことは不可欠です。かつては高齢化が「負担」として語られることが多かったですが、今後は、経験や知見を持つシニア層を社会の新たなリソースと捉え、活力に変えていく発想が求められます。
このためには、単なる貯蓄だけでなく、リスキリング、健康への自己投資、人的ネットワークの拡充といった「無形資産」への投資が重要になります。社会全体としても、年齢にとらわれない活躍の場を整備し、ライフステージに応じた柔軟な働き方や学び方を支援する必要があるでしょう。
要するに、高齢化=リスクという固定観念を脱し、高齢化=成長機会へと転換する。そのために、個人も社会も「未来志向」で意識を変えていくことが、これからの豊かな長寿社会を築く鍵となります。
エバーグリーン時代の6つの行動原則
平均寿命が100歳になれば、事情が変わる。新しい友達づくりの可能性が大きく開けてくる。平均寿命が延びると、新しい人間関係に投資する必要性は、これまでより人生終盤の時期にも生じるのだ。
平均寿命が100歳に近づく現代では、人生観や人間関係のあり方の再設計が必要です。長寿化により、人生の終盤でも新たな人間関係への投資が重要となり、これまでとは異なる価値観が求められています。高齢期においても新しい刺激やつながりを求め、快適な領域を超えて変化を受け入れる能力が大切です。
ローラ・カーステンセンは研究を通じて、同世代だけの人間関係に依存することのリスクが明らかにしました。例えば、80歳の人が90歳まで生きる確率は3分の2ですが、80歳同士の2人が共に90歳を迎える確率は6分の1に過ぎません。このため、世代を超えた人間関係の構築が精神的安定に効果的です。
若い世代との関係に意識的に投資することで、孤独感や社会的孤立を予防できます。 長寿社会では、家族、地域、職場、趣味など多様なつながりが精神的豊かさの基盤となります。誰とどう関わるかという問いが個人の幸福に直結し、加齢は衰えるだけでなく、新たな資質や能力が開花する時期とも捉えられます。
人生の各指標(身体能力、収入、社会的ネットワーク、幸福感)のピークは時期が異なるため、年齢差別的価値観に縛られず、次のステージに備える柔軟な姿勢が重要です。
私たちはいま、老いという概念を根本から見直す転機に立たされています。 変化のプロセスに乗り出し、「老いるとはどういうことか」を自らの経験として再定義できるようになれば、これからの人生はもっと軽やかに、もっと自由に歩んでいくことができるようになります。
なぜなら、より長く、より健康的で、より生産的な人生を実現するための基本的なメカニズムは、寿命が80歳であっても、100歳であっても、120歳であっても変わらないからです。大切なのは、健康と仕事と生きがいを、できるだけ長く維持するという一点に尽きます。
著者が提唱する「エバーグリーン時代の6つの行動原則」は、長寿社会を豊かに生きるための実践的な指針です。これらの原則は、単に寿命を延ばすだけでなく、人生の質を高め、各段階を充実させるための知恵が詰まっています。
1. 時間の意識を変える
私たちは過去の世代よりも長い時間を生きることが予想されています。この貴重な時間をどう活かすかを戦略的に考え、人生の進捗を意識しながら歩みを進めることが大切です。長い人生の中で、時間という資源をどう配分するかが重要になります。
2. 未来の自分を友とする
健康、経済、人間関係、生きがい、スキルは、今この瞬間から意識的に投資しなければ、将来失われる可能性があります。老化は突然やってくるものではなく、人生全体を通じて徐々に進行するプロセスです。未来の自分のために今から準備を始めることで、将来の選択肢を広げることができます。
3. 老い方を自分で選ぶ
「どう老いるか」は私たち自身が決めることができます。過去の世代の生き方を踏襲するのではなく、新しい知見と価値観に基づいて、自分らしい老い方を主体的に設計していく勇気が求められています。
4. 知見と新情報をバランスよく取り入れる
効果が実証されている方法を実践しながらも、医学やテクノロジーの進展に目を向け、新たな可能性を柔軟に取り入れていく姿勢が大切です。生涯学習の態度が、人生全体の質を向上させる鍵となります。
5. 人生の終盤にこそ可能性があると信じる
老いは衰退ではなく、長寿という「特権」を享受できる時期です。研究データが示すように、高齢期は想像以上に充実した時期になりうるのです。希望を持ち続けることが、その可能性を現実のものにします。
6. 未来への投資が現在にも恩恵をもたらすことを理解する
健康と経済的基盤の持続可能性を高めることは、未来だけでなく今この瞬間の選択肢も広げてくれます。エバーグリーンの視点で人生を設計することは、あらゆる年齢において人生を豊かにする選択肢を増やすことにつながります。
最も重要なのは、私たち自身が変化の先駆者となることです。社会全体の変化を待つのではなく、自ら一歩踏み出し、行動を変えていくことが未来を変える第一歩となります。
私たちの世代がこの変化のすべてを見届けられないかもしれませんが、人の老い方と寿命の可能性は今後劇的に進化していくでしょう。 長寿社会において、これらの原則を意識した生き方は、単に長く生きるだけでなく、充実した人生を送るための羅針盤となります。今この瞬間から、自分の行動を少しずつ変え、未来への投資を始めることで、誰もが「エバーグリーン時代の先駆者」になれるのです。
62歳の今、私は両親や祖父母が同じ年齢だった頃とは全く違う若さを感じています。引退はずっと先のことだと思い、いくつもの役割を同時に楽しんでいます。 社外取締役、アドバイザー、大学教授、そして書評ブロガーとして活動する日々は、とても充実しています。考え方を変えるだけで、仕事も趣味も新しい喜びを与えてくれるのです。
アンドリュー・スコットが提案する「長く生きる時代の新しい生き方」を自分の経験に照らし合わせると、その考えに深く共感します。私自身が今、その理論を実際に生きているからこそ、その価値がよく分かるのです。今後もしばらくは引退を考えずに、自分の人生後半戦をエンジョイしたいと思います。









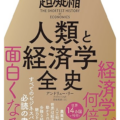






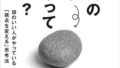

コメント