哲学のはじまり
戸谷洋志
NHK出版
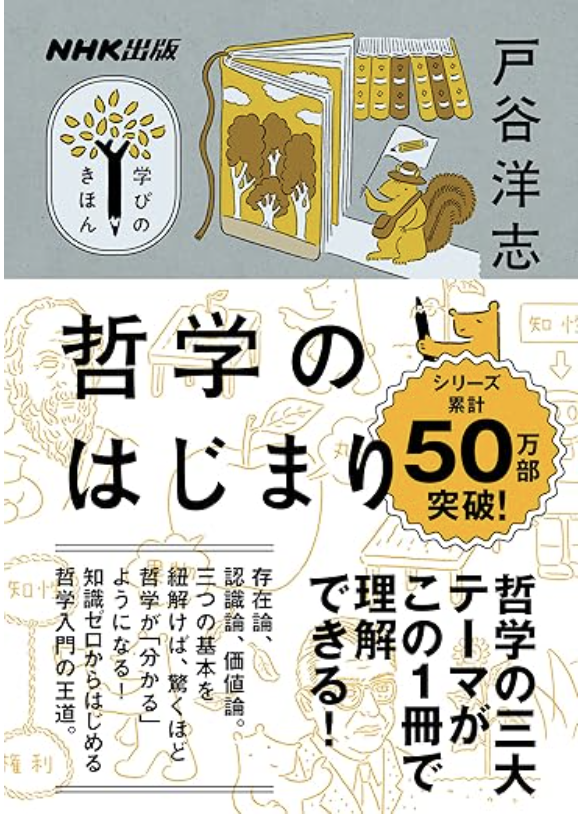
哲学のはじまり(戸谷洋志)の要約
AIが加速する現代において、人間に求められるのは単に効率的な解答を導き出す力ではなく、「適切な問いを立てる力」です。哲学は「問い」そのものを探究し、人間存在や価値観などAIが苦手な領域を深掘りします。哲学的思考は常識を疑い、既存の枠組みを再検討し、真の自由と創造的な生き方を可能にします。哲学を学ぶことで、AI時代を主体的に生きるための明確な判断基準が養われるのです。
哲学とは何か?を改めて考えてみる。
少なくとも哲学は、私たちに思考する自由を取り戻させてくれるのです。考え抜いた結果、行き着いた答えは平凡かも知れません。しかし、哲学する前と後は違うので す。なぜなら、哲学することで、それまでなぜ正しいのかを考えもしなかった常識を、自分なりの理屈を持って説明できるようになるからです。この意味において、知を愛する営みである哲学は、同時に、自由であることを何よりも尊重する営みなのです。(戸谷洋志)
AI時代において、なぜ哲学が重要になるのでしょうか? AIの発展が加速する現代、人間に求められる能力は急速に変化しています。これまでは効率的に答えを導き出すことが価値とされてきましたが、AIがその領域を担うようになると、人間に必要なのは「何を問いかけるか」という本質的な問いの力になります。
哲学はまさに「問い」を探究する学問です。「正解を見つける」ことよりも、「正しい問いを立てる」ことに重点を置き、人間存在の意味や倫理観、価値観といったAIが簡単には扱えない領域に踏み込んでいます。
関西外国語大学英語国際学部准教授の戸谷洋志氏による著書哲学のはじまりは、哲学の歴史や重要な哲学者(アリストテレス、プラトン、デカルト、カント、ヘーゲル、フッサールなど)の思想を丁寧に辿りながら分かりやすくまとめた一冊です。
哲学者たちが世界の何に疑問を抱き、その思想がどのように展開されたのかを示すことで、知識ゼロからでも哲学を学び、楽しめる一冊になっています。
デカルトは「哲学は私たちがすでに知っていることを教える」と述べました。これは、哲学が「当たり前」を問い直し、常識を再検討する営みであることを示しています。普段は当たり前に思っていることを疑い、問い直す姿勢を促す哲学への入り口として、この書籍は非常に適しています。
哲学的思考は批判的で創造的な視点を提供します。物事を表面的に捉えるのではなく、その背後にある構造や意味を探ります。AIは膨大なデータを扱いますが、そのデータにどのような意味や価値を与えるのかを決定するのは人間の哲学的思考なのです。
また、哲学を通じて、私たちは自分の言葉で説明し直す能力を養います。専門的な議論を重ねても、最終的には日常生活の文脈に戻ってきて自分の言葉で説明できるようになることが重要です。
みんなと同じ「当たり前」に従って生きることが、私たちにとって幸せであるとは限りません。「当たり前」は、同調圧力となって、私たちから選択肢を奪い、可能性を制限するからです。本当は別の生き方もできるはずなのに、まるで1つしか答えがないかのように思い込ませるもの、それが「当たり前」なのです。哲学は、そうした制限から、私たちを解放します。そこに哲学の最大の価値があるのでしょう。
日常の「当たり前」はしばしば同調圧力となり、私たちの自由や可能性を無意識に制限しています。この「当たり前」は、一つの道筋しか存在しないかのような錯覚をもたらします。
哲学の本質的な価値は、こうした制約から私たちを解き放つところにあります。哲学的思考は既存の概念や規範の枠組みを問い直し、新たな視点を提供することで、人間が自由に自らの生き方を選択し、創造的な可能性を追求できるよう促します。哲学とは単に抽象的な議論や知識の蓄積ではなく、具体的な日常生活における実践的な営みでもあります。それは、個人が直面する現実を再解釈し、自らの可能性を広げるための重要な手段なのです。
哲学がもたらす思考の変容は、自らの人生を主体的にデザインし、社会的に押し付けられた常識に囚われない生き方を可能にします。哲学を通じて、人々は自分自身と世界との新たな関係性を築き、真に自由で意味のある人生を追求する力を獲得できるのです。
哲学の3つの領域とは?
哲学することで、それまでなぜ正しいのかを考えもしなかった常識を、自分なりの理屈を持って説明できるようになるからです。この意味において、知を愛する営みである哲学は、同時に、自由であることを何よりも尊重する営みなのです。
AI時代に哲学を学ぶことで、私たちは自分自身の判断基準や行動指針を明確にすることができます。AIが示す選択肢の中で、自らの価値観や倫理観をもとに最適な判断を下すことが求められます。
その際、哲学的な視点は強力な武器となります。 哲学の領域は一般的に「存在論」、「認識論」、「価値論」の3つに分けられます。ただし、これはあくまでもざっくりとした分類であり、実際には問題が重なり合ったり、どこにも属さない問題も存在します。しかし、このような分類に従って問題を考えることで、混乱を避け、問題の整理がしやすくなります。
①存在論
存在論は、あるものが「何であるか」を問う哲学の基本的な領域です。これは存在する対象そのものの本質や特性について考察する分野であり、例えば人工知能(AI)について「人工知能とは何か」「人工知能と人間の根本的な違いは何か」といった問いを立てます。
さらに「電卓や単純な計算機器は人工知能と言えるか」「真の人工知能とはどのようなものか」といった具体的かつ詳細な議論も、存在論の枠組みで行われます。
②認識論
認識論は、私たちが「どのようにして知るのか」を問題にする領域です。存在論が対象そのものを問うのに対し、認識論はその対象を知るための方法や条件を考えます。例えば、「ある文章が人工知能によって書かれたと、私たちはどうやって判断するのか」「人工知能はどのようにして問題の解答を導き出すのか」といった問いが認識論の主題となります。認識論では人間や機械が知識や情報をどのように獲得し処理するかについて、多角的な議論が展開されます。
③価値論
価値論は「よいものとは何か」を問い、価値を分析する領域であり、ここで言う価値には主に二つのカテゴリーがあります。一つは美的価値、つまり「美しさ」を問うもので、美学(エステティクス)として知られています。美学は芸術作品や自然現象を評価し、何が美的に優れているのかを考察します。
もう一つは道徳的価値、すなわち「正しさ」を問うもので、倫理学(エシックス)と呼ばれます。倫理学は、人間の行為や社会のルールが道徳的に適切かどうかを検討します。例えば「人工知能の利用は道徳的に許されるか」「AIの判断が道徳的であるとはどういうことか」といった具体的な問いを扱います。
これら3つの領域は互いに影響し合いながら哲学的な探求を深めます。存在論、認識論、価値論のそれぞれが提供する視点は、複雑な現代社会の課題に対して明確で体系的な理解を可能にし、日常的な問題から高度な技術的課題まで、幅広い議論の枠組みを提供する役割を果たしています。
存在論をビジネスに応用する
哲学はビジネスにも深い示唆を与えます。経営において問うべき真の問題は、「次に何をすべきか」という表面的なものではありません。それよりもはるかに根源的で重要なのは、「自分たちはそもそも何者であろうとしているのか」という存在そのものへの問いです。この問いと真摯に向き合うことで、経営者は哲学から多くの示唆を得ることができます。今日はプラトンやアリストテレスの哲学的思考から経営を考えてみます。
AIが加速する現代において、人間に求められるのは単に効率的な解答を導き出す力ではなく、「適切な問いを立てる力」です。哲学を学ぶことで、AI時代を主体的に生きるための明確な判断基準が養われるのです。
古代ギリシャの哲学者プラトンは、「人間はかつて完全な理想(イデア)を見ていた」と考えました。私たちが何かを「本物だ」と直感的に感じる瞬間は、新しく学んでいるのではなく、過去に見ていた理想を無意識に「想起」しているのです。
この考え方を企業経営に応用すると、企業が困難に直面した時に必要なのは新たな戦略ではなく、創業時に掲げた理想や顧客に提供したかった本質的な価値を再確認し思い出すことなのです。企業が進むべき道を見失ったとき、本当に必要なことは初心への回帰です。
一方、アリストテレスは「すべての存在は内なる本質(形相)によって導かれ成長する」と述べています。植物のひまわりを例に挙げると、種から芽を出し成長しながら、常に太陽を目指して伸びていきます。
企業経営においても同様で、社会や市場が変化し、事業モデルが変わっても、内なる本質、すなわちパーパスを持ち続けている限り、企業は柔軟に進化していくことができます。重要なのは、変化すること自体が本質からの逸脱ではなく、むしろ本質に近づくための前進であることを理解することです。
ハイデガーの哲学は、私たちが世界に偶然的に「投げ込まれた」存在であると示しています。つまり、人間は自分の意志とは関係なく状況や環境に置かれますが、その偶然性を受け入れ、自らの意思で人生を積極的に選び取る姿勢を「決意性」と呼びました。
経営者が市場の予測不能な変化や思いがけない困難に直面したときにも、この「決意性」が求められます。企業は、起こる出来事にただ翻弄されるのではなく、その都度、自分たちの存在意義を再確認し、新しい方向性を主体的に選び直す必要があるのです。
サルトルは、「存在が本質に先立つ」と述べました。これは、人間がまずこの世界に存在し、その後で自らの行動を通じて自分自身の本質や意味を創り出すという考え方です。企業にも同様に、創業時から明確で固定された本質があるわけではありません。
企業は日々の意思決定や行動の積み重ねを通じて、「自分たちとは何か」を自ら創造し、明確化していくものなのです。本質は与えられるものではなく、自分たち自身で築き上げていくべきものです。
これら4人の哲学者の考え方を統合すると、経営とは自分たちの原点を常に思い出し、内なる本質に向かって変化し、偶然性を積極的に受け入れて新たな道を選び直し、自らの行動を通じて本質を創造していく旅路であると言えます。
ひまわりが姿を変えながらも、常に太陽に向かって進むように、企業もまた、環境や状況の変化に柔軟に対応しながら、自らの存在意義や目的を見失うことなく歩み続ける必要があります。経営とは、絶え間ない自己定義と自己実現のプロセスであり、これこそが哲学を経営に活かす真の意義です。
哲学を学ぶことは、私たちが日々直面する課題に対して、表面的ではなく本質的で持続可能な答えを見つけるための力を与えてくれます。正解のない時代に問いを立て、哲学的に思考することで、リーダーは複雑な現実に対して柔軟かつ創造的な解決策を見つけ、組織を未来へと導いていくことができるのです。




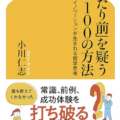


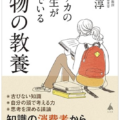










コメント