人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論
嶋村吉洋
プレジデント社
人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論 単行本(嶋村吉洋)の要約
社会資本こそが人生の質を左右すると本書は指摘し、「コミュニティが先、起業は後」という考え方を提案します。金融資本や人的資本だけでは力を発揮できず、信頼や応援といった社会資本があってこそ能力が価値へと変換されます。コミュニティを育てることで、まず内部消費による安定した売上が生まれ、次に信頼を基盤にした紹介が広がり、最後に市場でストーリー性のあるブランドとして受け入れられていきます。
幸福になるための3つの資本
「成功」という言葉の霧は人それぞれですが、私の考、える「成功者」とは、「社会資本」「人的資本」「金融資本」という”3つの資本”に恵まれて、誰からも束縛されず、またお金にも縛られない自由な立場で、自分のやりたいことを実現できている人たちを指します。(嶋村吉洋)
幸福をつくる3つの資本──金融資本(ファイナンシャル・キャピタル)・人的資本(ヒューマン・キャピタル)・社会資本(ソーシャル・キャピタル)であると作家の橘玲氏は指摘します。このフレームは一見シンプルですが、人生戦略として捉えると、実は驚くほど深い意味を持っています。多くの人が「稼ぐ力」や「スキルの棚卸し」に意識を向け、金融資本と人的資本を増やそうとします。
しかし、人生の質を決定づけているのは、必ずしも数字で測れるこれらではありません。 本当の意味で人を動かし、未来を開き、危機を乗り越えさせてくれるのは、「誰とつながっているか」「誰が自分を応援してくれるか」「どれだけ信頼が積み上がっているか」という社会資本です。
金融資本はもちろん重要です。将来の安心を生み、挑戦の余白をつくり、人生の選択肢を増やしてくれる。しかし金融資本は、外部環境に揺さぶられやすいという宿命から逃れられません。市場が動けば資産は上下し、企業の方針次第で給与も待遇も変わる。“安定”のように見えて、実は外部依存の強い資産なのです。
人的資本も不可欠です。スキルを磨き、経験を積むことで収入も役割も広がる。しかし、どれほど優れた能力を持っていても、それを評価し、機会を与えてくれる人がいなければ、その才能は眠ったままです。人的資本とは“潜在能力”であり、それを価値へ変換するには「舞台」と「観客」が必要になります。
では、社会資本とは何か。 信頼、つながり、応援──これらの目に見えないエネルギーそのものです。そしてこの資本こそ、3つのうち最もレバレッジが効く資本です。 社会資本は外部環境に強い。景気が悪くなっても、職場が変わっても、人との信頼関係は一朝一夕では揺らぎません。
人生の土壇場で助けになり、困ったときに情報も支援も集めてくれます。そして、この社会資本の力は、抽象論ではなく、私自身が身をもって体験してきた現実でもあります。 私が出版に挑んだときも、独立を決断したときも、順調だったわけではありません。
むしろ、もしあの時点で社会資本がなかったら、今の私は存在していなかったと断言できます。出版社との出会いも、独立後に最初のクライアントとつながれたのも、すべてコミュニティのご縁のおかげです。挑戦に背中を押し、支えてくれたのは、間違いなく仲間たちでした。 思い返すと、私が積み上げてきた経験やスキルそのものよりも、「徳本を応援したい」「この人と一緒に仕事がしたい」と言ってくれる人がいたことが、すべての出発点でした。
まさに社会資本が、人的資本と金融資本を“価値に変換する舞台”を整えてくれたのだと、今でも強く感じています。 だから私は、社会資本の重要性に誰よりもリアルに頷けます。
さらに、社会資本は複利で増える。紹介、応援、機会、情報──一つの縁が別の縁を呼び込み、つながりが雪だるま式に広がる。“資本が資本を呼ぶ装置”として働き、金融資本と人的資本を押し上げる牽引力さえ持っています。 そして何より、社会資本はどれだけ使っても減らないどころか、使うほど深まり、強まり、広がっていく。
これは他の資本には絶対にない特徴です。 偶然の出会い、思いがけない引き寄せ、突然のオファー──人生の跳躍はいつも予測不能な方向からやってきますが、その背後には必ず「人」がいます。社会資本が豊かなほど、この偶発的な幸運が自然に起こる。
だからこそ、人生100年時代において最優先されるべき資本は、社会資本へと静かに移り変わっているのです。 ここまで理解すると、「コミュニティを先につくる」という嶋村吉洋氏の本書のアドバイスが、単なる理想論ではなく極めて成功確率の高い戦略であることがよく分かります。(本書の関連記事はこちらから)
起業が先か?コミュニティが先か?
起業してからコミュニティづくりを始めると、資金・メンタル・人材・体力などのあらゆる面で非常に苦しくなるからです。先に自分や自社のコミュニティづくりをしてから起業すれば、この苦しさの多くを回避できるはずです。これは起業だけでなく、他の分野でも同じことが言えるでしょう。
「コミュニティが先、起業は後。」 これは本書が繰り返し強調する根幹のメッセージです。 支えてくれる仲間も、応援のつながりも、信頼の蓄積もない状態で事業を立ち上げれば、初速が足りず疲弊するのは当然です。
コミュニティ内で価値観が共有され、そこからビジネスの芽が生まれてきたら、次に重要になるのは、それをどのように具体化し、売上につなげていくかという点です。コミュニティは「楽しい」だけでも成り立ちますが、継続性をもたせるためには、どんなに小さくても利益が生まれる仕組みが必要です。
このプロセスには3つのステップがあります。最初に動き出すのが内部消費です。メンバー自身が商品やサービスを利用し、コミュニティの経済を支えていく段階です。三菱グループや華僑のような大きな組織が、身内のサービスを優先的に使うのと同じで、コミュニティが自らの意思で内部の価値を循環させることで、初期の安定した売上が成立します。
美容室やカフェをメンバーが頻繁に使うだけで、外へ流れていたお金がコミュニティ内に戻り、事業も活動資金も自然に強化されていきます。「利用する」のではなく「応援したい」という気持ちが背景にあるため、内部消費は単なる売上ではなく、コミュニティそのものを支える温度のあるエネルギーとして機能します。
内部消費が定着してくると、次に広がっていくのは紹介(リファラル)の循環です。信頼を土台にした口コミは、あらゆる広告より強く、人の意思決定を動かします。知人からの推薦はテレビCMやSNS広告をはるかに上回る信頼性を持ち、紹介された人は初めから安心して商品やサービスを受け取ってくれるため、リピーターにもなりやすいのです。
実際、コミュニティ由来のカフェが手づくりスイーツの紹介キャンペーンを仕掛けたところ、SNSを通じて話題が広がり、近隣地域からも人が集まり、売上は1.5倍に伸びたといいます。紹介は広告費が不要なうえ、新たな人を呼び込み、コミュニティの活性化にもつながる、極めて効率のよい成長エンジンになります。
内部での支えと外からの紹介が重なり、コミュニティの経済圏が徐々に大きくなると、ようやく一般市場へ展開していく段階に入ります。このフェーズでは、商品そのものだけではなく、コミュニティのストーリーがブランド価値を押し上げます。
地方の農業コミュニティがつくったジャムが都市部のマーケットで支持される背景には、農家のパーパスやビジョンがあります。「誰が、どんな思いでつくったのか」という物語が存在し、それが共感で選ばれる理由になっていたのです。
市場での売上は単なる収益ではなく、コミュニティへの再投資を可能にし、新しい商品開発や拠点整備につながり、さらに大きな循環を生み出します。 この一連の流れは、コミュニティの価値観が商品に宿り、顧客理解が研ぎ澄まされ、オンラインとオフラインの両方で接点が増えていくことで、より強固になります。
つまり、コミュニティ発のビジネスは、内部で支えられ、信頼を媒介に外へ広がり、最後に市場で評価されるというプロセスを踏むのです。 こうして見ていくと、コミュニティを基盤にしたビジネスは、単なる売買の関係ではなく、人と人のつながりが経済に変換されていく流れそのものだと理解できます。
価値観の共有があり、信頼があり、応援の文化がある。そこから生まれる売上は、数字以上に意味を持ち、コミュニティの未来を支えるエネルギーになります。
仲間がいれば初速が上がり、壁にぶつかったときは支援が集まり、挑戦に伴うリスクは大幅に軽減される。コミュニティは起業のための重要なプラットフォームなのです。
①信頼性の構築
②価値観の共有
③ストーリーの付加
の3つのステップでコミュニティ発のビジネスは成功するのです。
誰もが「コミュニティ×ビジネス」で人生を輝かせることができる。
そして、著者は「17時以降」のアクションが大事だと指摘します。勤務時間後のわずかな時間こそが、未来の資産──社会資本──を育てる貴重な時間なのです。学び、交流、発信、小さな挑戦。それらが積み重なり、コミュニティとなり、やがてビジネスとなって人生を押し広げていく。
もっとも、私自身は夜の活動よりも朝活を選びました。一番生産性が高い朝の時間帯を「自分のためのゴールデンアワー」と決め、そこで読書をし、記録し、考え、そして読書会を主催してきました。朝の読書会は、人を惹きつける磁場のように作用し、共感と学びを軸にしたつながりを自然に広げてくれました。
そこでは無理をしない関係が育ち、肩書きではなく価値観でつながる人脈が増えていきました。気づけば、読書会をきっかけに生まれたご縁が、新しい企画や仕事につながり、人生の可能性を押し広げてくれていたのです。
朝の小さな行動が、社会資本へと変換され、未来の選択肢を増やしていく──この循環を、私は身をもって実感しています。
誰もが「コミュニティ×ビジネス」で人生を輝かせることができる──これは特別な人だけの話ではありません。順番さえ間違えなければ、誰でも再現できる未来です。 起業とは目的ではなく、育てたつながりから生まれる結果なのです。 この生き方こそ、これからの時代の新しいスタンダードになると、私は確信しています。
本書はご恵贈いただきました。
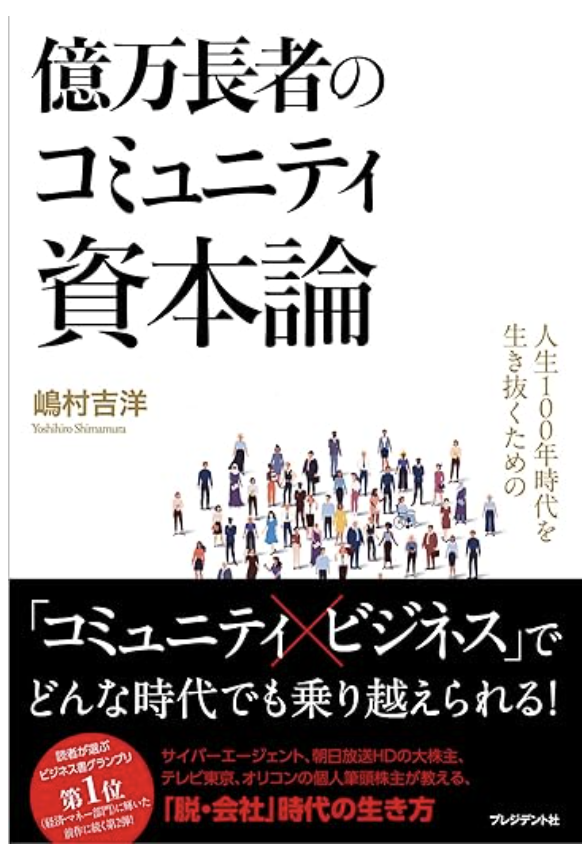




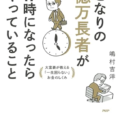

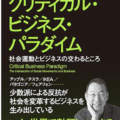



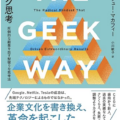




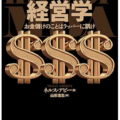


コメント