「越境企業」のはじめ方
瀬戸口航
ディスカヴァー・トゥエンティワン
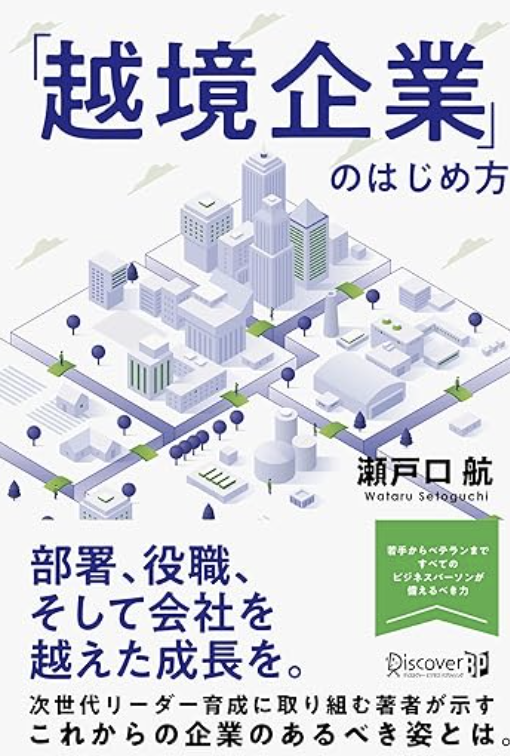
「越境企業」のはじめ方(瀬戸口航)の要約
越境学習は、得た知見を組織に還元することで、イノベーションの創出につながります。新たな環境で多様な価値観に触れることで視野が広がり、既存の枠を超えた発想が生まれます。しかし、受け入れ先の確保や業務の一時離脱による生産性の低下などの課題もあります。企業は学びを組織全体に還元する仕組みを整え、越境者の成長を支援することで、持続的な変革と競争力の強化につなげることが求められます。
越境が若手教育に必要な理由
この不確定要素の強い時代の中で生き抜く力をつけるための「場」と「経験」を提供することだと考えています。そこで重要になるのが、自社内の学びだけにとどまらない「越境学習」という考え方です。(瀬戸口航)
企業が持続的に成長し、変化の激しい社会の中で競争力を維持するためには、次世代リーダーの育成が不可欠です。デジタル化やグローバル化が急速に進む現代において、過去の成功体験や既存の昇進制度に依存するだけでは、企業を牽引できる真のリーダーを育てることは難しくなっています。こうした背景から、企業は新たな人材育成のアプローチを模索し、従来の枠を超えた学びの機会を提供しようとしています。
その中でも、近年注目を集めているのが「越境体験」を通じたリーダーシップ開発です。越境体験とは、単なる社内異動や昇進を超えて、異業種や外部組織との関わりを通じて新たな視点を得る学習機会を指します。
例えば、NPOやスタートアップでの一定期間の業務経験、業界横断的なプロジェクトへの参加、海外の現地企業との協働などが挙げられます。こうした経験を通じて、参加者はこれまでの環境では得られなかった気づきや洞察を手に入れ、視座を広げることができます。
ファーストキャリア代表取締役社長の瀬戸口航氏によると越境体験を通じて得られる最も重要な学習効果は、社会全体を俯瞰的に見渡し、本質的な課題を見出す力の醸成です。日常の業務では気づきにくい社会課題や、業界全体の構造的な問題に触れることで、より広い文脈で自社の位置づけや役割を捉えなおすことができます。
企業の中で日常業務に従事していると、どうしても目の前の業務や社内の事情に意識が向きがちです。しかし、異なる業界や組織の課題に触れることで、自社の事業がどのような役割を果たすべきかを、より広い視点で捉え直すことが可能になります。このような思考は、長期的な経営戦略の策定にも欠かせません。
また、異業種や異文化のステークホルダーと協働することで、コミュニケーション能力や調整力も大きく向上します。企業ごとに価値観や文化が異なる中で、共通の目標を達成するためには、相手を理解し、柔軟に対応するスキルが求められます。
最近では大企業からベンチャーに越境することがトレンドになっていますが、お互いの働き方を知ることで、Win-Winの関係が築けます。大企業からイノベーションを起こすためには、このような越境が進むことを期待しています。私が特任教授をしているiU(情報経営イノベーション専門職大学)でも3年時に、長期インターンを単位にし、企業との交流を積極的に行なっています。これも企業サイドから見れば、学生との越境体験になります。
グローバル化が進む中で、多様な価値観を持つ人々と協働する力は、リーダーとしての資質の一つとしてますます重要視されています。 さらに、越境体験はスキルの向上だけでなく、自己の価値観や信念を明確にする機会にもなります。
慣れない環境に飛び込み、未知の課題に直面することで、自らの判断軸を磨き、それに基づいて意思決定を行う力が養われます。この経験を通じて、どのような状況でも主体的に考え、行動できるリーダーシップが形成されます。
越境から始まるイノベーション
越境による一番の効果は、自分の前提を見直すことです。いつもと違う場所、違う人たちと違う課題に取り組む中で、それまで自分が当たり前だと思っていた前提や価値観が通じない。そこで恥ずかしさや苦い思いをすることで『混乱するジレンマ』を味わい、社会のためという大義に向き合い内省することで、リフレーミングが起きます。
企業の持続的な成長には、社員一人ひとりが自ら考え、行動する力を持つことが不可欠です。そのための手段として、越境体験は極めて有効な学習機会となります。普段の業務環境を離れ、異なる文化や価値観を持つ人々と協働し、未知の課題に取り組むことで、自分自身の前提を見直す機会を得ることができます。
社内では「常識」とされていた考え方が通用しない場面に直面し、自らの価値観が揺さぶられることで、固定観念から解放されるのです。 この「混乱するジレンマ」を経験することによって、社員は物事を多角的に捉える力を養い、視野を広げることができます。これまでの経験や環境に依存していた思考から脱却し、新たな視点で課題を発見し、解決策を模索する力が培われます。
さらに、自社の枠を超えた環境での経験を通じて、課題解決力だけでなく、リーダーシップや多様性への適応力、共感力も磨かれます。異業種や異文化の中で人を巻き込み、協働しながら目標を達成する力は、経営の現場においても非常に重要な資質となります。
また、越境体験は社員のキャリア形成の機会としても活用されています。新たな環境に飛び込み、自らの強みや弱みを再認識することで、今後のキャリアの方向性を見つめ直すことができます。例えば、ある業務に携わる中で、自分の得意分野や新たな可能性に気づくこともあれば、想定外の分野に関心を持つこともあります。こうした経験を通じて、自らのキャリアを主体的に設計し、次のステップへとつなげる意識が芽生えるのです。
企業としては、越境体験を社員のチャレンジ精神の醸成にもつなげています。新しい環境に挑戦することで、「まずはやってみる」という姿勢が身につき、変化を恐れず、積極的に挑戦できる風土が育まれます。こうした経験を積んだ社員は、職場に戻ってからも、自ら課題を見つけ、変革を推進する力を発揮するようになります。その結果、組織全体の活性化にもつながり、企業の持続的な成長を支える重要な要素となるのです。
特に、越境体験はイノベーションの創出にも大きな影響を与えます。異業種の知識や価値観が交差することで、新たな発想が生まれることは、「メディチ・エフェクト」とも呼ばれています。これは、ルネサンス期のフィレンツェにおいて、メディチ家が芸術家、科学者、哲学者など、多様な分野の人々を支援し、その交流を促した結果、数々の革新的なアイデアや作品が生まれたことに由来しています。
現代のビジネス環境においても、異なる業界や専門分野が交差することで、新たな価値創造が生まれることが証明されています。企業が社内の枠組みを超えて他業界や異なる文化圏との接点を持つことで、これまでにないビジネスモデルやサービスが生まれる可能性が広がるのです。 フランス・ヨハンソンは、創造性やイノベーションの研究を進める中で、「アイデアは交差点から生まれる」という考えに至りました。
異なる分野の人々が交わることで、新たな発想が生まれ、それまでにないアイデアが形になるのです。もし、創造的なアイデアを生み出したいのであれば、意識的に交差点に身を置くことが重要になります。
メディチ・エフェクトが発揮される背景には、異分野の知識や視点の組み合わせが、従来にはないアイデアを生み出すという原理があります。ある分野では当たり前の考え方や技術が、別の分野では革新的な解決策になり得るのです。例えば、新幹線や航空機の設計において生物の構造が参考にされる「バイオミミクリー」や、金融業界でAI技術が活用されるなど、異なる分野が交差することで生まれるイノベーションは枚挙にいとまがありません。
企業においても、社内の専門性にこだわらず、異業種との協業や外部ネットワークとの交流を積極的に取り入れることで、より創造的な発想が生まれる土壌が育まれます。
また、メディチ・エフェクトが有効に働くためには、単なる情報の共有にとどまらず、異なる価値観を持つ人々が互いの知見を掛け合わせ、共創する環境が必要です。企業が意図的に「交差点」を作り、異業種や異文化の人材と接点を持つ場を増やすことで、創造的なアイデアの創出が加速します。
こうした視点を踏まえ、社内の枠を超えた越境体験を設計し、社員に多様な環境での経験を積ませることが、イノベーションの種を生み出す重要なステップとなるのです。
本書で紹介されている越境体験をした社員の調査によると、「考えの異なる相手の意見を受け入れられる力」「物事を多面的に見る力」「相手が理解しやすいように物事を伝える力」の3つが、業種や役割に関係なく向上していることがわかっています。これらのスキルは、今後のビジネス環境において不可欠であり、企業としても積極的に伸ばしていくべき能力です。
特に、社内に閉じた環境では得られない「異質なものとの接触」は、新しいアイデアを生み出すために極めて重要です。 経営者の視点から見ると、越境体験は単なる個人の成長支援ではなく、組織全体の競争力を高める戦略的な投資です。
変化の激しい時代において、企業が生き残るためには、柔軟な発想と挑戦を恐れない文化を醸成することが求められます。そのためにも、社員の越境体験を促し、新しい価値を生み出せる組織づくりに注力することが、持続的な成長の鍵となるでしょう。イノベーションを生み出す土壌として、越境の機会を積極的に提供し、メディチ・エフェクトのような異分野の融合を促すことで、企業の未来はより大きく開かれていくはずです。
リーダーシップ・エクスペリエンスが変える未来
越境者は自分の組織に成果を還元しないでいると、せっかくホームに戻っても浮いた存在になりかねません。組織からの投資に本業で返していくことを大前提として、越境学習に打ち込むことが誰にとっても健全なスタンスです。
越境体験の導入にはいくつかの課題も存在します。まず、受け入れ先の確保やプログラム設計には、一定の調整が求められます。居心地の悪い刺激のあるアウェーへ越境することで、社員がさまざまな知見を得られます。
また、越境体験を終えた社員が組織に戻った後に、その学びを社内にどう還元するかも重要な課題となります。さらに、一時的に業務を離れることによる生産性の低下や、経験者の成長をどのように評価しキャリアにつなげるかといった課題も、企業が慎重に検討すべきポイントです。
越境人材が真の成長を遂げるためには、人事担当者の適切なサポートが求められます。 越境学習は、個人の経験として終わらせるのではなく、企業全体の学びに還元することが重要です。そのため、人事担当者は、越境者がどのような学びを得ているのかを関係者に定期的に報告・共有し、成長を可視化する役割を担います。
さらに、現場マネジメントや外部メンターと連携しながら、越境者の進捗を共通理解として把握し、フィードバックの仕組みを構築することも求められます。このプロセスを通じて、越境者が組織内外でどのような変化を遂げているのかを明確にし、本人の成長を促すことができます。
人事担当者だけでなく、現場マネジメントや外部メンターも、越境者の成長を支える「越境伴走者」となります。しかし、過度な介入は逆効果となるため、適切な距離感を保つことが求められます。越境者が主体的に学び、挑戦できる環境を整えながらも、成果を過度に求めたり、プレッシャーを与えたりしないよう配慮することが大切です。
また、心理的安全性を確保し、失敗を恐れず挑戦できるような支援体制を構築することも必要です。適切な距離感を維持しながら支援することで、越境者のモチベーションを維持し、最大限の成長を引き出せます。 越境学習が単発の施策で終わらず、企業の成長戦略として機能するためには、組織全体で越境文化を醸成することが不可欠です。
そのためには、越境の意義や効果を経営層に伝え、制度として定着させることが求められます。また、越境者の学びを社内ナレッジとして共有し、組織の知見として蓄積する仕組みを整えることも重要です。加えて、越境プログラムの成果を分析し、継続的に改善を行うことで、より効果的な制度へと進化させることができます。
越境学習は、個人の自己認識を高め、キャリア自律を促す重要な機会となります。自身の強みや課題を見つめ直し、新たな環境での挑戦を通じて成長を実感することで、自らのキャリアを主体的に築いていく意識が芽生えます。
また、優秀な人材に向けた「リーダーシップ・エクスペリエンス」は、次世代を担うリーダーの育成にもつながります。未知の状況に対応しながら意思決定を行い、多様な価値観を持つ人々と協働する経験は、リーダーシップを磨く絶好の機会となります。
企業が越境学習を積極的に推進することは、単に個人の成長を促すだけでなく、組織全体の発展にも寄与します。越境の機会を提供することで、優秀な人材が新たな挑戦を求めながらも、自社にとどまり続ける動機づけとなり、結果的に離職防止にもつながると考えられます。
私たちファーストキャリアは、「人の成長を偶発から必然に変える」というミッションを掲げていますが、ミッション・ビジョン・バリューを包含した、事業におけるあり方を示したスローガンとして「若者と未来をつなぐ」という文言を置いています。
企業が人材を育てるという考え方は、もはや社内だけで完結するものではありません。業界全体、さらには社会全体で若手の成長を支えるという視点を持つことが、長期的に見て企業の競争力を高めることにもつながります。だからこそ、若者たちが主体的に学び、挑戦できる環境をつくり、それを企業が支援することが求められています。
その手段として越境学習が有効であり、単なる経験ではなく、成長を「偶発」から「必然」へと変える仕組みを構築していくことが、これからの企業の使命の一つになると感じます。
人材育成を単なる企業のための投資として捉えるのではなく、社会全体でより良い未来を創るための活動として位置づけるという著者のメッセージに共感を覚えました。企業と若者が共に未来をつくり上げていくという視点を持ち続けながら、越境学習をはじめとする新たな成長の機会を提供し続けることが、今後ますます重要になってくると考えています。










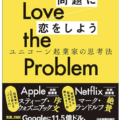


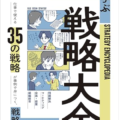




コメント