スケーリング・ピープル 人に寄り添い、チームを強くするマネジメント戦略
クレア・ヒューズ・ジョンソン
日経BP
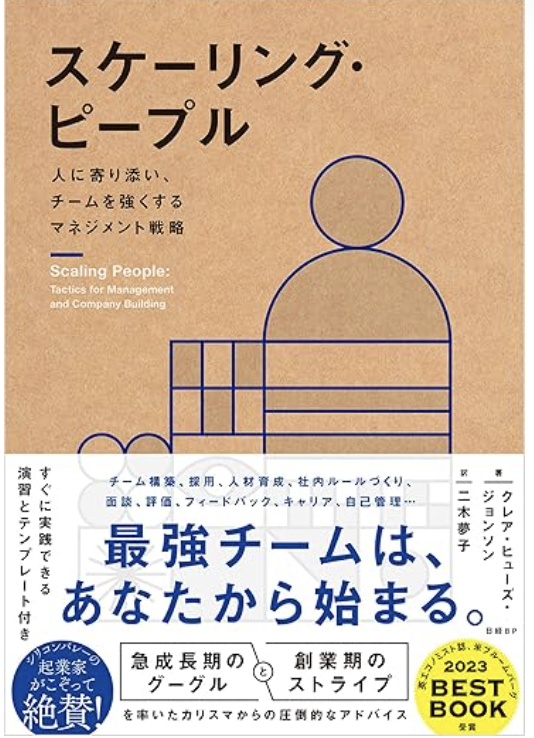
スケーリング・ピープル(クレア・ヒューズ・ジョンソン)の要約
クレア・ヒューズ・ジョンソンの『スケーリング・ピープル』は、自己認識、率直な対話、構造化された仕組みづくりを通じて、成長を支える組織文化を築くための実践的ガイドです。採用・育成・評価におけるコア・フレームワークを体系的に提示し、リーダーの自己理解とチームへの共感を起点に、変化に強い組織をつくる具体策が詰まっています。
事業運営の4つの基本原則
マネジメントとは、単に相互補完的なチームをつくることではなく、周囲全体を見渡し、自分とは異なる強みを持つ人を探し出す、相互に自己認識力を高めることでもある。自己を認識するだけでなく、弱みを見せて他人の助けを求める余裕がなければ、一緒に遠くまで行くことはできない。(クレア・ヒューズ・ジョンソン)
ビジネスの急成長は、プロダクトや売上だけでなく、「人」と「組織」のあり方に真価が問われるフェーズを迎えます。企業文化をどう築き、人材をどう育て、どのようにスケールさせていくのか――。この問いに対する最前線の答えが、クレア・ヒューズ・ジョンソンのスケーリング・ピープルに詰まっています。
YouTubeやGmailの成長を牽引したGoogle時代、そして急成長するフィンテック企業StripeでCOOを務めた彼女は、実際に組織を率い、チームを動かし、文化を設計してきた当事者です。本書は、そうした現場知と経営戦略の両軸から、働く人と組織づくりに関わるすべてを丁寧かつ体系的にひも解いています。
自分のワークスタイルを分析し、強みや限界を可視化することで、個の力とチームの総合力がシンクロし始めます。マネジメントとは、互いを補完するだけではなく、異なる強みを持つ仲間を見つけ出し、相互に成長のきっかけを与え合うプロセスでもあるのです。“弱さを見せること”を恐れず、助けを求める余裕を持つ。それが、強いチームの原動力になります。
ジョンソンは、マネージャーが共感力を持ち、状況に応じて柔軟かつ率直にチームと向き合うことが、組織の成果だけでなく、健全な職場文化の形成にも寄与すると繰り返し強調しています。
著者はこれを「事業運営の基本原則」と呼び、組織の核をつくるための4つの指針を示します。
①自己認識力を高め、相互認識力を築く
②言いにくいことを、あえて伝える
③マネジメントとリーダーシップを、明確に区別する
④オペレーティング・システムに立ち返る
これらは、一見抽象的に映るかもしれません。しかし実際には、マネジメントのキャリアを歩む中で何度も立ち戻るべき「軸」であり、本書の至るところに織り込まれている実践的なフレームワークです。
自己認識、つまり自分の気持ちや考えをしっかり理解することは、チームをうまくまとめたり、良い結果を出したりするうえで大切です。
著者は、良いマネージャーにはこの自己認識が欠かせないと伝えています。 また、職場ではお互いに思いやりを持ち、誠実に接することが大切です。上司はただ命令するのではなく、部下が自分で考えて行動できるようにサポートすることが求められています。
そのうえで、正直でわかりやすいコミュニケーションや、仕事の進め方にルールや決まりを持つことも必要です。柔軟さとルールのバランスが、変化の多い状況でもチームを安定させてくれます。 ジョンソンは、共感と自己認識を持ちながら、正しく率直に向き合うことが、成果と良い職場づくりの両方につながると強調しています。
特に重要なのは、これらの原則が直接「結果を出す方法」を示しているわけではない点です。成果を生むのは、あくまでチーム環境と実行力の掛け算。そしてその土台には、組織として共有される思考の枠組み、すなわち「コア・フレームワーク」の存在があります。
ジョンソンはこのコア・フレームワークを以下の4つの分野に適用すべきだと言います。
1.ゴールとリソースの確立と計画
2.総合的な採用アプローチ
3.意識的なチーム育成
4.フィードバックとパフォーマンスのしくみづくり
まず、「ゴールとリソースの確立および計画」においては、企業としてのミッションや価値観を明文化し、それらを核としたオペレーティング・システムを整備することが求められます。組織の隅々まで方向性を浸透させるためには、年間戦略や四半期ごとの目標設定、そして定期的な進捗確認の機会を設けることが欠かせません。
優れたオペレーティングシステムとは?
会社とチームにとっての明確に定義されたミッションなしではゴールの設定が難しいのと同様に、明確なゴールなしでは進捗を測るための優れた指標の設定は難しい。
成長と成果の実現には、共通の判断基準や運営ルールが欠かせません。年間計画や四半期ごとのゴール設定、定期的なコミュニケーションといった基本要素が整っていれば、従業員全員が組織全体の進捗と優先事項を把握しやすくなります。さらに、これらの仕組みを部門・チーム単位で展開することで、優先順位が明確になり、部門間の相互依存を最小限に抑えることができます。
優れたオペレーティング・システムが機能していれば、成果の定義、進捗報告のタイミング、達成度の評価指標といった運営の土台が明確になります。そして何より、こうした仕組みは組織内に安心と信頼を生み出します。人は、自分に何が求められているかが分からない状況では不安を感じやすく、職場においてもそれは同様です。誰と、なぜその仕事に取り組むのか、どのような協力体制が必要なのかを全員が理解することが重要です。
組織のミッションが明確でなければ、目標の設定自体が難しくなります。また、明確なゴールがなければ、適切な進捗指標も設計できません。
ゴールには大きく2種類があると著者は言います。1つは「実施したかどうか」が明確に分かるバイナリーなタスク(例:「○○機能のパイロット版を開発する」)、もう1つは成果の変化を測る定量的な目標(例:「決済手段の利用シェアを20%増やす」)です。
理想的には、これらのゴールも企業全体から部門、チーム、個人単位へと展開・接続されていく必要があります。 また、オペレーティング・システムとその運用リズム(ケイデンス)においては、次の点について定期的にフィードバックを求め、改善を重ねることが重要です。
・組織、部門、チームのミッションと、それぞれのメンバーが担う役割が明確に共有されているか
・計画と実行のスケジュール、進捗を測定する方法が整備されているか
・チーム間で依存関係のある業務について、リーダー間で合意が取れ、優先順位と責任の所在が明確か
・成果の測定方法、業務の各要素の責任者、スケジュールが全員に共有されているか
・進捗管理、意思決定、部門間の連携を促進する仕組みが機能しているか
・ゴールに関する最新情報や変更点が、関係者に適切に伝達されているか
・成果を適切に称え、失敗も共有・学習の機会として活かしているか
・社内コミュニケーションが、企業の価値観や経営方針を支える役割を果たしているか
これらを継続的に確認し、改善していくことが、強固で透明性の高い組織運営につながります。
こうした仕組みを通じて、リーダーから現場に至るまで一貫した判断と行動が可能となり、日々の業務が戦略と接続されたものになります。共通の目標を持ち、共通の言語で会話ができる組織は、変化に対しても柔軟かつ迅速に対応できる強さを持つのです。
人材こそがすべてだと信じるなら、採用プロセスもまた“すべて”であるべきだろう。活躍する人、
会社に最もポジティブなインパクトをもたらしてくれる人をあらゆる職階で見つけることがゴールになる。
続いて、ジョンソンは、初期の人材採用が組織の将来を大きく左右する重要な意思決定であると主張しています。単にスキルセットに合致する人材を集めるのではなく、内部昇進と外部採用のバランスを取りながら、組織の価値観や文化にフィットする多様な人材を戦略的に確保することが必要です。
そのためには、構造化された面接プロセスの導入が不可欠であり、このプロセスでは、候補者が組織のミッションやビジョンにどの程度共鳴するかという文化的適合性が重視されます。採用の段階からカルチャーフィットを意識することで、入社後の早期離脱やミスマッチを防ぎ、長期的に活躍できる人材を迎える土壌を整えることができます。
このような採用戦略は、組織の持続的成長を支える強固なチームづくりを可能にし、採用を単なる人事活動ではなく、経営戦略の中核として位置づける発想に基づいています。
全てはリーダーの自己認識から始まる!
マネジャーとしてのあなたの仕事は、観察して、機会を与えることだ。部下の仕事は、話を聞き、行動を決意することだ。
3つ目の要素である「意識的なチーム育成」に関しては、マネジメントとリーダーシップの違いを正確に理解し、それぞれの役割を適切に実行することの重要性が語られています。リーダーやマネージャは業務の管理にとどまらず、チームの関係性や働く環境そのものに意識を向けることで、個々のメンバーが自発的に動ける状態をつくり出すことが可能になります。
心理的安全性が確保され、誰もが安心して意見を述べられるチーム環境では、自然と創造性や挑戦心が育まれます。こうした土壌を築くには、リーダーが明確なビジョンを示し、価値観を共有しながら、メンバー同士の協働を促進する役割を果たす必要があります。組織のパフォーマンスは、構造や制度だけでなく、日々の人間関係や対話の質によって大きく左右されるのです。
「フィードバックとパフォーマンスの仕組みづくり」については、単発的な評価ではなく、継続的な対話と振り返りの文化を醸成することが強調されています。本書では、「フィードバックは贈り物である」という考えが貫かれていますが、この姿勢は単なる理想論ではなく、組織を成長させるための実践的な考え方です。
マネジメントとは繰り返されるプロセスだ。学んで、前進する。そして互いの経験から学ぼうとする。
日常的な1on1や定期的なチェックインを通じて、メンバー1人ひとりの状況を丁寧に把握し、都度的確な支援を行うことで、パフォーマンスは大きく向上します。また、ネガティブなフィードバックであっても、それを信頼関係のもとで伝え合える文化があれば、学習と成長のスピードが加速し、組織全体の進化につながっていきます。
こうしたアプローチの中核には前半で紹介した「自己認識」という概念が中心にあります。リーダーはまず、自分自身の価値観や意思決定の癖、他者との接し方を深く理解する必要があります。自己理解が深まれば、他者への対応もより的確になり、健全な関係性を築くことが可能になります。加えて、不快な会話や意見の対立から逃げずに向き合う姿勢を持つことが、信頼と透明性をベースとした職場文化の醸成につながっていきます。
メンバーとの困難な対話を回避せず、むしろ成長のチャンスとして活用することで、チームはより強固な結びつきを得ることができます。
本書は、こうした理論だけでなく、それを現場でどう実践するかという視点においても非常に充実した一冊です。人材育成を体系的に行うための設計、リーダーシップの定義とその評価指標の構築、フィードバックを組織の文化として根づかせる方法論など、今日の企業にとって必要不可欠な知見が網羅されています。
たとえば、社員一人ひとりが自己管理能力を高め、日常的にフィードバックを受け入れる土壌が整えば、モチベーションは内側から自然と高まり、ひいては組織全体のパフォーマンスも向上していきます。その先にあるのは、一過性の成果ではなく、変化に強い持続的な競争力です。
著者のジョンソンが提案する原則は、急成長フェーズにあるスタートアップだけでなく、成長に停滞感を感じている大企業にとっても有効です。組織が拡大すればするほど、方針の一貫性は揺らぎやすくなり、部門間の連携も希薄になりがちです。そうした分断や複雑性に対して、著者のアプローチは効果があることを本書のケースが実証しています。
彼女の原則は、社員の成長を支え、チームの協働を促進し、そして変化に強いレジリエントな組織文化を育みます。適応力を備えながらも、組織の中核にある価値観やビジョンをぶらさない──そのバランスを実現するための“軸”を、彼女は理論と実践の双方から提示しているのです。


















コメント