いつもひらめいている人の頭の中
島青志
幻冬舎
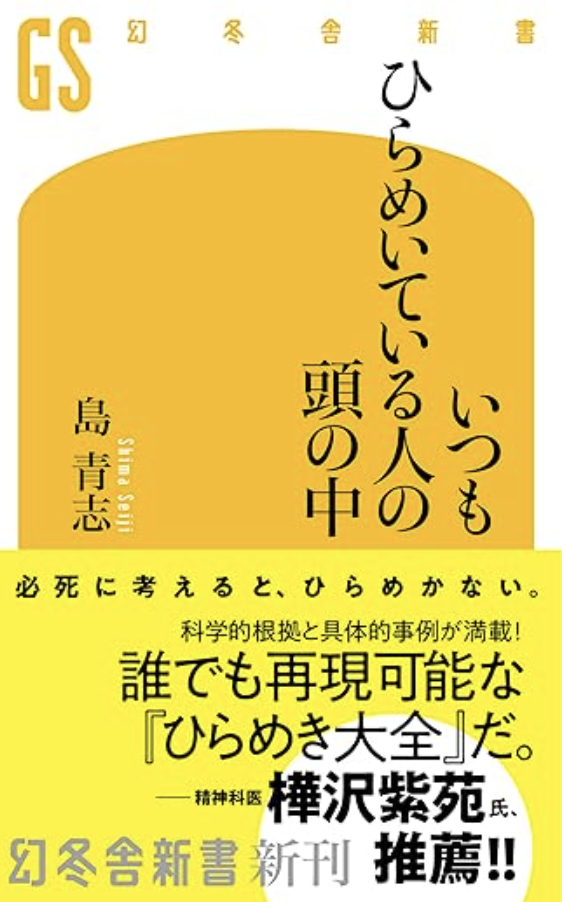
いつもひらめいている人の頭の中 (島青志)の要約
ひらめきや創造性は、特別な才能ではなく誰にでも備わっている力です。日常の中で感性を磨き、無意識のひらめきを捉え、行動と検証を重ねることで、創造力は育まれます。アート思考とデザイン思考を融合させ、直感と論理の対話を繰り返すことが、現実を変えるアイデアを生み出す鍵となるのです。
アイデア作成のための4つのステップ
彼らのように「ひらめき」や「創造性」でビジネスのアイデアを見つけることや、人生を変えることは、誰もが可能であるということです。 「神様は、金持ちにも貧乏人にも1日24時間という時間だけは平等に与えてくれた」という表現がありますよね。私はそれに「ひらめき」「創造性」を加えたいと思います。(島青志)
スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツといった、いわゆる「天才」と称される人物たち。その生き方に多くの人が魅了され、彼らが生み出したアイデアは世界を動かし、ビジネスの常識を根底から塗り替えてきました。 とはいえ、ジョブズやゲイツが最初からすべてを持ち合わせていたわけではありません。
「ひらめきの力」は、生まれつきの才能ではなく、日々の姿勢や習慣、小さな選択の積み重ねによって育まれていくものです。むしろ彼らこそ、試行錯誤のプロセスを信じ抜き、それを継続した人たちなのです。
ブランディング&イノベーションデザイナーの島青志氏は、ひらめきや創造性によってビジネスのアイデアを見つけ、人生を変えることは誰にでも可能だと述べています。 「神様は、金持ちにも貧乏人にも、1日24時間という時間だけは平等に与えてくれた」という言葉がありますが、島氏はこれに加えて、「ひらめき」と「創造性」もまた、すべての人に等しく与えられている資源であると語っています
多くの人が、社会的な制約や過去の経験、自分への過小評価によって、無意識に自らに制限をかけてしまっています。しかし、その制限は、意識の切り替え一つで外すことができるのです。 創造性は、誰の中にも眠るエネルギーであり、人生を動かす原動力です。
では、どうすればそのひらめき力を育めることができるのでしょうか?本書では、その問いに対して「4つのステップ」を明らかにしています。
1. ひらめきの材料をインプットする(準備)
すべてのひらめきには素材(ひらめきの種)が必要です。知識を関心を持って、取り入れる必要があります。読書、映画、旅行、人との会話、美術館の体験、街で見かけた風景。
感性のアンテナを立て、「何か気になる」「心が動いた」という小さなサインを見逃さず、ストックしていく。この地道な作業が、ひらめきの土台となります。知識のつながりを大切にすることで、アイデアが生まれやすくなります。
2. 無意識の力を強化する(孵化)
ひらめきは、意識して考え詰めたときよりも、リラックスした無意識の時間にこそ訪れやすいものです。これは、脳内で「デフォルト・モード・ネットワーク」が活性化している状態であり、創造性にとって非常に重要なプロセスとされています。散歩や瞑想、音楽、美術、自然に触れるような“何もしない時間”こそが、実はひらめきのために必要なことです。
特に、音楽やアートに触れることで、感性を刺激し、アート思考が磨かれていきます。近年では、他者と意見を交わしながら作品を鑑賞する「対話型鑑賞法」が、創造的思考の活性化に効果的であると注目されています。
3. ひらめきの瞬間を逃さない(ひらめき)
「これかもしれない」と感じた瞬間が訪れたら、そのひらめきを逃さずにキャッチすることが大切です。メモを取る、人に話してみる、スケッチを描くようにしましょう。
著者は、物語相関図や因果ループ図を書くことも効果的だと述べています。アイデアは、完成された形ではなく、断片的で曖昧なまま現れるものです。「なんとなく面白い」という感覚こそが創造の芽であり、その直感を信じて育てていくことが、創造のはじまりにつながります。
そして、そのアイデアに対してデザイン思考でアプローチすることで、構造的かつ現実的なかたちへと落とし込むことが可能になります。感覚を言語化し、共感を軸に課題と向き合うプロセスが、ひらめきを実践へと導いてくれるのです。
4. 失敗の発見と研磨(検証・フィードバック)
最後のステップは、ひらめきを行動に移し、検証し、磨き上げていく段階です。スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツも、数えきれないほどの試行錯誤を重ねることで、革新的な成果にたどり着きました。試すこと、転ぶこと、そして再び立ち上がること——そのすべてが、創造というプロセスの一部なのです。
失敗は「仮説の検証」であり、次のひらめきを生むために欠かせぬプロセスです。重要なのは、振り返りと改善を惜しまない姿勢です。その繰り返しによって、創造力は鍛えられ、やがて指数的な成長へとつながっていきます。
この4ステップは、特別な人だけのものではありません。繰り返すことで誰にでも身につけられます。ひらめきを信じ、柔らかい視点で世界を捉え直す勇気があれば、あなたにもその扉は開かれます。
AI時代にひらめきの力が重要な理由
良いひらめきは、まさにアートとデザインの狭間で生まれます。これは、既存の枠組みを超え、新しい価値を創造するための大切な視点と言えるのではないでしょうか。
著者の島氏が本書を通じて最も伝えたいのは、凡人の中に眠る「ひらめき力」を育て、意識的に磨き上げていくことです。その力を信じ、自らの思考の限界をしなやかに超えていくことが、創造性を開花させる鍵になると語っています。
そして、自分自身の中に眠る可能性と真正面から向き合うこと——それが、創造的な人生への確かな起点となるのです。革新的なアイデアは、遠い世界のものではありません。むしろ、私たちの何気ない日常の中にこそ、その原石はひっそりと潜んでいるのです。
アート思考とは、自分の内面や感性、直感に従って自由に発想する思考法であり、デザイン思考とは、ユーザーのニーズや社会課題に焦点を当てて、構造的に解決策を導き出すプロセスです。この2つの思考法を融合させることで、感性豊かなひらめきを、実用的で社会に役立つ形へと具体化することが可能になります。
創造性とは、直感的な発想と論理的な構造のあいだで繰り返される「対話」です。このプロセスを意識的に繰り返すことで、アイデアの質は飛躍的に高まり、より現実的で実現可能なアウトプットが生まれます。
ダイソンのサイクロン掃除機も、Airbnbも、最初は小さな気づきや直感から始まりました。目の前の情報を違う角度から見つめ直すだけで、人生は大きく変化する可能性を秘めているのです。
創造性を妨げる最大の障壁は、私たち自身の「脳のバイアス」だと著者は述べています。脳は、本能的に「重要」だと判断した情報しか取り込まないように設計されています。これは自分を守るための仕組みでもありますが、一方で、新しい視点や情報を遮断してしまう関所にもなっているのです。この関所を突破するには、「自分の限界は自分がつくっている」と気づくことが何よりも重要です。
脳には、何歳からでも進化できるという「可塑性」があります。その可能性を信じることから、すべては始まります。一番を目指す必要はありません。成長や協力、対話、共創の中にこそ、持続的な成功の種があるのです。挑戦を恐れず、失敗を味方にし、柔軟な思考を保つこと。それが、ひらめきの回路を開き、脳をしなやかにしていきます。
創造性の源泉は、「自分で考え、自分で決める力」にあると著者は述べています。報連相に頼りすぎず、自分で思考し判断する力を磨くことで、脳の創造的な領域が活性化されていきます。冷静な論理的思考と共感的な感性、その両方のバランスが、新しいアイデアを生み出す土壌となるのです。他者の意見に耳を傾け、受け入れ、再構築する柔軟さこそが、創造性を深める鍵になります。
数学者アンリ・ポアンカレは、創造性とは「知の美しい組み合わせ」であると語りました。創造は、ゼロから生まれるのではなく、蓄積された知識を最適に組み合わせることで生まれます。その「最適さ」を判断するのが、美意識なのです。 この創造プロセスは、「準備」「孵化」「ひらめき」「検証」の4段階に分けられるとされています。
この考え方はキャサリン・バトリックによってアーティストの行動原理として検証され、ジェームス・W・ヤングの名著アイデアのつくり方でも引用され、現代の創造メソッドとして広まりました。(アイデアのつくり方の関連記事)
ヤングのアイデアづくりの5つのステップ
1. 資料集め
2. 諸君の心の中でこれらの資料に手を加えること
3. 孵化段階
4. アイデアの実際上の誕生 <ユーレカ!分かった!みつけた!>という段階
5. アイデアを具体化し、展開させる段階
私もヤングの本を広告会社に入社したときに読み、このメソッドを身につけることで、創造性を育めました。本書はその名著を現代風にアップデートし、アート思考やデザイン思考を組み合わせることで、よりわかりやすく解説しています。
ひらめきは「人と人の間で起こる」ものなのです。
AIが私たちの生活に当たり前のように存在する時代だからこそ、大切なのは「感じ、考える力」になります。反復的な作業や情報の整理はAIに任せ、人間にしか生み出せない“転”の発想にこそ、創造性の本質があるのです。
AIはひらめきを持ちませんし、行動することもできません。しかし、私たちには、体験し、語り、動く力があります。そこから生まれたアイデアは、行動によって形になります。成功とは特別な才能ではなく、小さな実践の積み重ねによってもたらされる副産物なのです。そのプロセスを楽しむ姿勢が、未来の可能性を大きく広げてくれるのです。






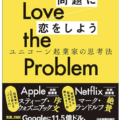









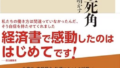

コメント