LIFE UNIVERSITY(ライフ・ユニバーシティ) もし大学教授がよい人生を教えたら
ブルース・フッド
サンマーク出版
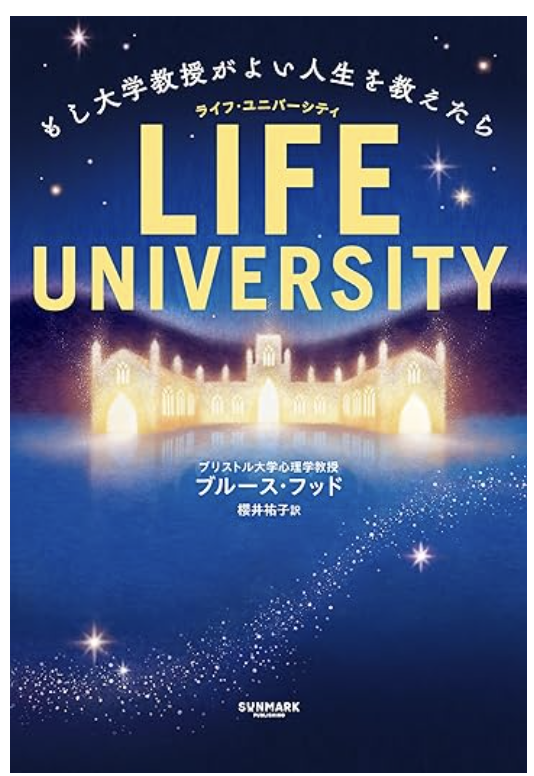
LIFE UNIVERSITY(ライフ・ユニバーシティ) もし大学教授がよい人生を教えたら (ブルース・フッド)の要約
ブルース・フッドは、幸福になるための7つのレッスンを提示します。自己は他者との関わりで育まれること、交流が幸福を支えること、比較の罠から感謝で抜け出すこと、楽観と悲観のバランスを取ること、「今」に注意を向けること、人とのつながりを恐れないこと、そして自己中心性を超えて思いやりを育むこと。これらを実践することで、幸福は目標ではなく結果として自然に根づいていくと説きます。
他者視点でつながりを強化することで、幸福度が高まる!
科学と教育を通じて、人を幸せにできると知ったのだ。(ブルース・フッド)
私自身、大学で教えるようになってから、良い授業とは何か?良い先生とは何かを自問するようになりました。学生たちが心から納得し、自分の人生を見つめ直すような講義とはどうあるべきか。そんな問いを抱えていた時に出会ったのが、LIFE UNIVERSITY(ライフ・ユニバーシティ) もし大学教授がよい人生を教えたら(原題 The Science of Happiness: Seven Lessons for Living Well)です。
イギリス・ブリストル大学の発達心理学教授ブルース・フッドが、自らの人気講義「The Science of Happiness(幸福の科学)」をもとに書き下ろしたこの一冊は、科学と実践を架橋する内容に満ちており、私は一気に読み終えた後も、ページの余白にメモを取りながら何度も読み返すことになりました。
この講義は、評価や単位の対象にならないにもかかわらず、毎年500人の学生が殺到し、教室は常に満席になるほどの人気を博していたそうです。
特筆すべきは、著者の講義後の調査によると、受講生の幸福度が実際に向上したというデータがあることです。エビデンスベースで「幸福とは何か」を探求するこの講義は、多くの若者たちに希望と行動のヒントを与えてきました。そして今、それが書籍という形で、より多くの人々に届けられるようになったのです。
著者は、こうした状況の中で重要なのは、自己中心的な視点から他者中心的な視点へと意識をシフトすることだと説いています。他者中心的な視点とは、単に人に合わせるということではありません。相手の立場に立ってものごとを考え、私たちが社会の中でつながり合い、影響を与え合って生きている存在であるという前提を持つことです。この視点の転換こそが、自分の存在意義を再確認し、より深い満足感や幸福感を得るきっかけになるのだと、著者は強調しています。
自分の幸福を、他者との比較や評価ではなく、「誰かの役に立っている」という実感から見いだすことができたとき、幸福はより確かなものになるのかもしれません。
「悩みは打ち明けると半分になる」ということわざがあるように、人は他者に思いやりを持って接し、手を差しのべることで、相手だけでなく自分自身の心も軽くなると著者は述べています。他者とのやりとりの中で、思いがけない安心やつながりが生まれ、ふとした瞬間に幸せを感じることがあるのです。
誰かのために動くことが、結果として自分を救ってくれる——そんな幸福の循環が、この本のメッセージの根底に流れているように感じます。
年収や職業、結婚相手や恋人といった、人生の満足度に関わる多くの要素がありますが、これら以上に、大人になってからのウェルビーイングを予測する最大の要因は、幼い頃にどのような他者との関係を築いてきたかにある、とフッドは指摘します。
つまり、人とどのようにつながるか、その基礎は幼少期にすでに形づくられているのです。 私たちは孤立するために生まれてきたわけではありません。誰かと関わり、支え合い、学び合う中でこそ、人は心のしなやかさや自己肯定感を育てていけるのです。その意味で、つながりの質は、人生全体の幸福感に深く関わる「土壌」のようなものなのかもしれません。
著者はまた、幸福に関する大切な視点として、「遺伝だけですべてが決まるわけではない」という点を強調しています。確かに、遺伝は幸福に対してある程度の影響を与えており、研究によればその割合はおよそ半分程度だと言われています。
けれども、たとえ幸福を感じやすい遺伝的な傾向を持っていたとしても、それだけで人生全体の幸福が決まるわけではありません。 むしろ、私たちがどのような環境で過ごし、日々どんな行動を選び取っているか——その積み重ねこそが、最終的に「幸福の土壌」を形づくるのだと、著者は伝えてくれます。
そしてもう一つ見逃せないのが、私たちが本来持っている「ネガティブ・バイアス」の存在です。これは、人類が進化の過程で身につけた、生存を守るための本能のようなものです。危険やリスクに敏感であることは、過去の環境では必要不可欠な能力でした。
しかし現代においては、このバイアスが過剰に働き、ストレスや不安を生み出す原因にもなってしまっています。 著者は、このネガティブ・バイアスに対しても希望を示します。偏りすぎた思考は、気づきと習慣によって少しずつ変えることができるのです。ネガティブに引っ張られがちな自分に気づいたとき、立ち止まり、意識的にポジティブな視点を選び直す。そんな小さな思考のトレーニングが、やがて大きな変化を生み出すのだと著者はわかりやすく教えてくれます。
幸福度を高めるための7つのレッスン
幸福度を高め続けるためには、努力して幸せを実践しなくてはならないのだ。
本書では、7つのレッスンを通じて、幸福度を高めるための視点と行動を学ぶことができます。どれも複雑な哲学ではなく、日常に取り入れやすい知恵として整理されており、私たちが陥りがちな思考のクセや、無意識に行っている比較、そして人間関係のあり方に対する新たな気づきを与えてくれます。幸福度を高めるためには、7つの行動を意識し、日々努力を続けることがポイントになります。
・LESSON 1 自己重要感 ——「自分」はどうつくられる?
私たちが「自分」だと思っている感覚は、固定された実体ではなく、常に変化し続ける柔軟で可塑的なものだと著者は語ります。自己は錯覚にすぎないが、だからこそ変えられるのです。自己は孤立した存在ではなく、他者との相互作用の中で絶えず育まれます。
赤ちゃんが笑顔を見せるのは、生理的な反射ではなく、周囲とつながるための自然な行動です。その瞬間から「自分」は他者によって形づくられているのです。幼少期の親密な関係や遊びの体験は人格形成の基盤となり、大人になっても出会いや経験を通じて自己は更新され続けます。
著者が「自己は錯覚だ」と言うのは決して悲観ではありません。むしろ希望です。変わらない自己がないからこそ、環境や人間関係を通じて自分を変えることができるのです。他者と関わりながら新しい自分を築き、自分が意味ある存在だと感じるとき、そこに幸福が芽生えます。
・LESSON 2 交流 —— 人間にとって最も大事な感覚とは?
人間にとってもっとも大切なのは、社会的な交流です。私たちは孤独に生きるために生まれたのではなく、つながることで安心を得て心を支え合う存在です。著者は、幼児期にどのような人間関係を築いたかが、大人になってからの幸福度を大きく予測すると指摘します。
年収や学歴以上に、幼いころにどんな関わりを持ったかが、その後のウェルビーイングを左右するのです。 子どもの成長を支える環境も重要です。取り組みに関心を持ち、必要なときには励ましや助言を与える。ただし根拠のない褒め言葉で甘やかすのではなく、失敗する機会を与え、そこから学べるように支援する。
親に「成功しなければ愛されない」と思わせないことが大切です。束縛ではなく協力的な環境が、健全な自己形成と幸福の土壌を育みます。 他者の心を推し量る力が欠けていると、幸福を見つける機会は狭まります。
思いやりや共感によって初めて信頼や安心が育まれます。現代は孤立しやすい時代ですが、著者は交流を回復することこそ幸福の核心だと強調します。
・LESSON 3 比較 —— 比べると知覚が歪む
幼児が自信に満ちているのは、自分を他人と比べないからです。昨日の自分と今日の自分を比べて成長を実感し、小さな成功でも自信を深めます。しかし大人になると、この自然な比較は失われ、他者との比較ばかりが強調されます。そのために自分の進歩を見落とし、不安や劣等感を抱えてしまうのです。
私たちの比較は、注意の盲点や確証バイアス、後づけバイアスといった思考の歪みに影響されます。そして多くの場合、目にするのは他人の「成功」や「輝く部分」ばかりです。その結果、自分を不当に低く評価し、「自分は不幸だ」と錯覚します。
著者は、この比較の罠から抜け出すカギとして「感謝」を挙げます。感謝の気持ちを持つと、注意が人生の良い面に向かい、嫉妬や羨望にとらわれなくなります。感謝は社会的なつながりを強め、自分の価値を再確認させてくれる。比較を前向きな成長の視点に変えることができるのです。私は感謝日記の実践によって、幸福度が高まっていることを実感しています。
・LESSON 4 傾向 —— 楽観・悲観・思い込み
私たちは未来を悲観的に捉える傾向がありますが、データは寿命や生活水準が改善していることを示しています。悲観的に考えるのは脳が危険を過大評価する仕組みを持っているからです。悲観と楽観は性格の固定要素ではなく、状況によって変わるものだと著者は説明します。 楽観的な人は失敗を切り替えるのが早く、挑戦を続けます。悲観的な人は失敗を全体化しますが、他者の視点を取り入れることで罠から抜け出せます。
著者は、楽観性を高めるために ABCDE法 と WOOP心理対比法 を紹介しています。 ABCDE法は、Adversity(逆境)、Belief(信念)、Consequence(結果)、Disputation(反論)、Energization(活力)で構成されます。失敗を「自分は無能だ」と結びつけるのではなく、「準備不足だった」と反論し、行動につなげます。思考を修正することで感情も変わり、再び力が湧いてくるのです。
WOOP心理対比法は、Wish(願望)、Outcome(結果)、Obstacle(障害)、Plan(計画)の4つです。願望を描き、結果を想像し、障害を予測し、具体的な計画を立てる。このプロセスによって行動は続きやすくなります。WOOPは現実的な障害をあらかじめ想定する点で非常に効果的です。
・LESSON 5 注意 —— 想像の世界を漂わないために
私たちはしばしば、過去や未来にとらわれて「マインドワンダリング」をします。しかしこれは幸福度を下げます。反芻思考や自己批判的な雑念は、自己中心的な思考に直結し、問題を大きくしてしまいます。
けれども「今」に注意を戻せば、心は整い、幸福感は高まります。問題と自分の間に距離を置くことで、冷静に対応できるようになります。その方法のひとつは、人とのつながりです。他者との交流が、頭の中の不安の渦から抜け出す助けになります。
幸せな人生を送るために必要なこと
他者の心を推し量るこの能力が欠けていると、幸せを見つけるチャンスが狭まってしまう。
・LESSON 6 他者存在 —— 「自分は人に好かれない」と皆が思うが、大体誤解
多くの人は「自分は他人に好かれていない」と思い込みますが、これは誤解です。実際には、自分が思う以上に人から好意的に受け止められています。それでも不安にとらわれ、孤立や自己否定を招いてしまいます。 幸福を高める方法のひとつが、知らない人に話しかけることです。
多くの人はためらいますが、短い会話や笑顔のやり取りだけでも安心感をもたらしてくれます。人は共同で活動すると境界が薄れ、一体感を感じます。ダンスや音楽、スポーツといった活動は連帯感を高め、思いやりを育てます。日常の交流も同じ効果を持ち、スマホを視界から外すだけで質が向上するのです。
・LESSON 7 自分中心から抜け出す —— 自分を広げる
自己中心的な視点にとらわれると、不安や孤独が強まりやすくなります。私たちの脳は本来、危険やネガティブな情報に敏感にできているため、どうしても比較にとらわれやすいのです。誰かと比べて落ち込み、誰かの成功を見て焦り、自分を小さく感じてしまう。そうしたときこそ著者は、自己中心性を抑え、他者中心の視点へシフトすることが幸福へのカギになるのだと強調しています。
思いやりとは、相手の苦しみをそのまま背負い込むことではありません。相手を少しでも幸せにしたいと願う前向きな気持ちであり、その意識が自分自身の幸福を長続きさせます。著者は、自己中心的な幸せは短期的で一時的なものに対し、他者中心の幸せは持続的で人生を深く豊かにすると語ります。そのバランスを意識することが、私たちの幸福感を安定させるのです。








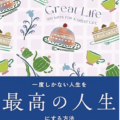









コメント