
米国防総省・人口統計コンサルタントの 人類超長期予測――80億人の地球は、人口減少の未来に向かうのか
ジェニファー・D・シュバ
ダイヤモンド
人類超長期予測―(ジェニファー・D・シュバ)の要約
人口統計の三大要因「出生・死亡・移動」は、社会の未来を形作る重要な要素です。これらの要因を理解し、適切に調整することで、持続可能な社会を実現するための道を切り開くことができます。政策立案者は、これらの変化に対して柔軟に対応し、未来に向けた投資を行うことで、より良い社会を築くための準備を進めるべきです。
世界人口80億人時代に私たちがやるべきこと
出生率と死亡率を変えた革命は、人類がたどる道をも大きく変えた。移動と都市化は、他者や環境との人類のかかわり方をいまもなお変え続けている。(ジェニファー・D・シュバ)
2022年、世界人口が80億人を突破したと国連が発表しました。わずか11年で70億人から80億人に達し、このまま人口が増加し続けると、環境問題や食料問題に対する懸念が広がっています。
私たち人類は長い道のりを歩んできましたが、21世紀の世界人口はかつて見られなかった形で変わり続けています。今日、地球上にはこれまでにない数の人々が暮らしており、人類史上最も高齢化した社会が出現しています。また、富裕国と貧困国の出生時平均余命にはこれまでにない隔たりが生じています。
本書の著者のジェニファー・D・シュバは、世界人口の増加が必ずしも世界全体の成長と安定をもたらすものではないと指摘し、特に経済成長が不十分でインフラが未成熟な低所得国における人口増加が気候変動やパンデミックへの対応を難しくし、世界全体への脅威となる可能性があると警鐘を鳴らしています。
世界のいくつかの地域、特に東アジアや東南アジア諸国は、労働力人口の増加に伴い、教育や産業育成への積極的な投資を行い、「人口ボーナス」を活用して成長を遂げてきました。これらの国々は、人口増加を経済成長のエンジンとし、インフラ整備や教育の向上に注力することで、持続可能な発展を実現しています。
今後の数十年を見据えると、世界の最貧困国の大半では、依然としてすさまじい人口増加と、きわめて若い人口構成が続くと予測されています。たとえ出生率が多少低下したとしても、特に中央アフリカと西アフリカの非常に高い出生率が原動力となり、サハラ以南のアフリカの人口は今世紀のうちに6倍に増える見込みです。
これらの国々では、インフラの整備や教育の充実が不十分なため、人口増加がむしろ経済の足かせとなる可能性があります。経済基盤が脆弱な地域での急激な人口増加は、食糧不足、医療崩壊、失業率の増加など、多くの社会問題を引き起こすリスクが高まります。
また、気候変動の影響を受けやすく、パンデミックへの対応も難しいため、世界全体の安定に対する脅威となり得ます。
著者は、これらの課題に対して政策と投資について早急に世界規模で議論を行う必要性を訴えています。特に低所得国における人口増加が世界全体に波及する可能性を考えると、持続可能な人口政策の推進が喫緊の課題であることを認識しなければなりません。具体的には、以下のような対策が求められます。
世界人口の増加とともに、私たちが直面する課題も複雑化しています。特に、低成長国における人口増加は、経済発展や生活の質の向上に対して大きな挑戦を突きつけています。著者が指摘するように、持続可能な未来を実現するためには、若い世代への教育、インフラ整備、医療と衛生環境の改善、家族計画と女性の権利向上、そして国際的な協力が不可欠です。
▪️教育の充実
若い世代に対する教育の充実は、労働力の質を向上させ、経済成長の基盤を築くために不可欠です。教育は、知識やスキルを提供するだけでなく、創造性や問題解決能力を養います。特に、科学技術や工学、数学(STEM)分野の教育に重点を置くことで、次世代のイノベーターやリーダーを育成することが可能となります。さらに、教育機会の均等化を図り、農村部や貧困層の子どもたちにも質の高い教育を提供することが求められます。
▪️インフラ整備
道路、電力、通信インフラの整備は、経済活動の効率化と生活の質の向上に直結します。良好なインフラは、物流の改善やビジネスの円滑な運営を支え、地域経済の発展を促進します。例えば、道路が整備されることで農村部の農産物が都市部に迅速に運ばれ、農業収入の増加や生活の質の向上につながります。
電力供給の安定は、企業の生産性向上や教育機会の増加に寄与します。また、通信インフラの整備により、情報のアクセスが容易になり、デジタル経済の発展を支援します。 医療と衛生環境の改善 健康で働ける環境を整えることで、生産性の向上と安定した社会を実現します。
▪️医療アクセスの向上
予防医療の推進、衛生環境の改善は、労働力の健康状態を保ち、労働参加率を高める重要な要素です。感染症の予防や栄養改善プログラムを導入することで、特に母子保健の向上が期待されます。また、安全な飲料水や適切な衛生施設の整備は、疾病の予防に不可欠です。
▪️家族計画と女性の権利向上
人口増加の抑制には、家族計画の推進と女性の社会的地位の向上が重要です。家族計画は、望まない妊娠を防ぎ、家族の経済的安定を支えるための基本的な手段です。さらに、女性の教育機会を増やし、労働市場への参入を促進することで、経済成長への寄与が期待されます。女性が社会の中で重要な役割を果たすことができるようにするためには、法的・社会的支援が必要です。
▪️国際的な協力の必要性
これらの課題に取り組むためには、国際的な協力が欠かせません。先進国と低成長国の間で知識や技術を共有し、資金援助を行うことで、低成長国が持続可能な発展を遂げる手助けをすることが求められます。国際機関やNGOは、グローバルな視点での問題解決を支援する重要な役割を果たします。例えば、国際的な開発プロジェクトを通じてインフラの整備や医療支援が行われることで、低成長国の発展を加速させることができます。
脆弱国家指数とは?
「脆弱国家指数」は、国民に基本的なサービスさえ提供できず、暴力行為が蔓延し、無秩序に陥る危険が高い国々を示す指標です。特にイエメン、ソマリア、南スーダン、シリアなどは、崩壊の危機に瀕している、あるいはすでに崩壊しているとされています。
これらの国々の共通点は、人口構造が非常に若いことです。 若い人口構造のリスクとチャンス 2019年のデータによると、もっとも脆弱な20カ国の中位数年齢は18.95歳と非常に若く、リストに含まれるシリアの中位数年齢も25.6歳と他国と比べればやや高いものの、依然として若年層が多い国となっています。
若い人口構造は、以下のようなリスクとチャンスをもたらします。
▪️リスク
・社会不安と暴力の増加
若い人口が多いと、仕事の機会が限られている場合に社会不安が高まりやすくなります。失業や低賃金労働に対する不満が、暴力行為や犯罪の増加につながることがあります。
・教育とスキル不足
若い世代に対する教育や職業訓練の不足は、経済成長を阻害し、長期的な貧困の連鎖を生む可能性があります。
・政治的不安定
若い人口が多い国では、政治的な不安定さが増すことがあり、民主化が遅れると著者は言います。汚職・不正行為・効率の悪い組織などが、国の成長が阻害します。
▪️チャンス
・人口ボーナスの活用
若い人口は、適切な教育と訓練を受けることで、経済成長の大きな原動力となります。人口ボーナスを活かすための政策が整備されれば、労働力の質が向上し、経済の発展が期待できます。
・イノベーションの促進
若い世代は、技術の適応力が高く、新しいアイデアやイノベーションを生み出す潜在力があります。これにより、スタートアップや新産業の発展が促進される可能性があります。
・社会の再構築
若い世代は、社会の変革に対する意欲が高く、積極的にコミュニティの改善や社会問題の解決に取り組むことができます。
脆弱国家に対する支援は、国際的な協力が不可欠です。以下のような具体的な対策が求められます。
・教育と職業訓練の拡充
若い世代に対する教育機会の提供と、職業訓練プログラムの強化が必要です。特に、技術教育や起業家精神の育成を重視することが重要です。
・インフラ整備と経済支援
道路、電力、通信などのインフラ整備を通じて、経済活動の基盤を強化することが求められます。国際的な経済支援も必要です。
・平和構築とガバナンスの強化
紛争解決と平和構築のための支援が必要です。ガバナンスの改善と透明性の向上を図ることで、政治的不安定さを軽減することができます。
「脆弱国家指数」が示す通り、若い人口構造を持つ脆弱国家は、社会不安や経済停滞のリスクを抱えています。しかし、適切な教育、職業訓練、インフラ整備、国際協力を通じて、これらの国々が持つ潜在的な力を引き出し、持続可能な発展を実現することが可能です。若い世代の力を活かすために、私たちは積極的な支援と協力を続ける必要があります。
人口政策を正しく行うことによって、国の豊かさが左右されます。パキスタンとバングラデシュの人口政策と経済成長を見れば、それが正しいことを理解できます。
1975年から1980年にかけて、バングラデシュとパキスタンの合計特殊出生率は共に6.6でした。しかし、バングラデシュは独立直後に地域ごとに避妊具の配布を開始し、バングラデシュ国際下痢性疾病研究センター(ICDDR/B)と協力しました。この取り組みにはアメリカ国際開発局(USAID)から一部資金と支援が提供されました。
バングラデシュの合計特殊出生率は独立時の6.9から急激に減少し、30年後には女性1人当たりの出生数が3人未満になりました。2020年から2025年の間には、バングラデシュの合計特殊出生率は1.93にまで低下すると推計されています。一方、パキスタンの合計特殊出生率は3.2になると予測されています。
バングラデシュの中位数年齢はパキスタンよりも約5歳高く、出生時の平均余命もバングラデシュの方が長いです。これらの要因は、バングラデシュの経済見通しにとって非常に好ましいものです。
バングラデシュの「機会の窓」は最近開いたばかりだが、今世紀半ばまで閉じることはないだろうから(今後の出生率低下のペースにもよるが)、今後数十年にわたって注目すべき国である。一方、パキスタンの「機会の窓」は2035年頃まで開かない見込みで、国が適切な軌道に乗るかどうかは、今後の数十年で決まるだろう。
人口統計学者のリチャード・チンコッタとエリザベス・レーヒー・マドセンが開発した統計モデルによると、「2030年までにバングラデシュは世界銀行の所得分類で上位中所得国(1人当たり国民総所得が約4000〜約12000ドル)に達する見込みがある」とされています。バングラデシュの出生率低下と人口構造の変化は、同国の経済成長に大きく寄与することが期待されています。
人口80億時代の課題とその解決策とは?
2050年には、世界人口の70%が都市に暮らすと予測されています。その大半は中・低所得国で進行するでしょう。現在、先進国は都市化によって経済的な恩恵を享受していますが、世界では約8億人がスラムで暮らしており、基本的には「スーパースター」的な都市だけがイノベーションや資本、人材、投資を引きつけています。
都市化によって経済的利益が生じる一方で、環境変化ももたらされ、所得や生活の質が損なわれるリスクがあります。特に低所得国では、人口増加が食糧不安という危機をもたらし、輸入品依存や自給的農業の問題が顕在化しています。気候変動による干ばつや洪水の悪化も、急増する都市部を脆弱にしています。
2020年、先進国の中位数年齢は42歳で、2035年には45歳に達しているだろう。2020年、中位数年齢が40歳以上の国は38カ国になった。高齢化の波はヨーロッパ、北アメリカ、そしてアジアで高まっている。アジアではもはや日本だけではなく、中国、韓国、シンガポールが第2波となり、あとを追っている。
中位数年齢を見ると世界の高齢化が進んでいることがわかります。日本ではこの分野では先進国で、他国に比べ、いち早く超高齢化社会となり、課題が山積みになっています。著者は日本では、高齢者が犯罪を何度も起こし、刑務所が老人ホームになっていると指摘します。
高齢者への給付金支給や早期退職を保障している国では、政策を変えなければ経済が縮小し、政府は財政難に直面するでしょう。また、介護施設の不足や低い給付金額が家族に負担をかけ、出生率を押し下げる可能性もあります。経済発展が早かった国々では、年金制度の見直しが急務です。
人口は私たちをのみ込む波ではなく、政策によってその流れを変えることができます。人口ボーナスを最大限に利用するためには、教育やインフラ、医療、家族計画などへの投資が不可欠です。国際政策に詳しいメリリー・グリンドルは、「十分なガバナンス」を目標に小さな変化の力を評価することを推奨しています。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックから学んだことは、優れた医療体制が不測の事態への準備を整えるということです。例えば、マラリアやHIVに対する取り組みは、世界的な健康改善に寄与しています。しかし、パンデミックへの対応に資金が集中することで、他の医療分野への影響が懸念されています。
高齢化社会では、労働市場に女性と高齢者を参入させる政策が重要です。オートメーション化や移民受け入れも、労働力不足を補う手段となります。健康の向上も、高齢化する世界で生活の質を高く保ち、生産性を向上させる鍵となります。
たとえば、ベトナム難民がアメリカでネイル産業を成功させたことで、ネットワーク効果が発揮されました。この成功により、アメリカでのベトナム女性の就労機会が増え、彼らの生活が豊かになったのです。 アメリカ国内でのベトナム人コミュニティは強固なものとなり、特にベトナム女性にとっての就労機会が大幅に増加しました。
アメリカに移住したベトナム人と、本国にいるベトナム人とのつながりが強いため、ベトナム国内の人々もアメリカでの成功に触発されます。豊かになりたいと願うベトナム人は、アメリカでの成功を目指し、移住を決意することが増えています。この移住の流れは、アメリカでのベトナム人コミュニティのさらなる拡大と、ネイル産業の成長を支え続けています。
人口高齢化の労働力不足解決のため、ヨーロッパ諸国やカナダは積極的に移民を受け入れてきました。ドイツは移民政策に寛容であったため、近年では多くのトラブルを抱えています。特に、人種、文化、宗教の多様化が進む中で、移民に対する社会的な緊張が高まっています。この状況は、移民に積極的だった他のヨーロッパ諸国でも同様です。
移民問題に対する反発として、ヨーロッパのいくつかの国では極右政権が誕生し、移民排斥運動が活発化しています。一部の極右勢力は、移民を排斥するための活動を強化しています。デモや抗議活動を通じて、移民受け入れに反対する声を上げています。
結果、ヨーロッパの一部の国では、移民受け入れ政策の見直しが進められています。新しい法律や規制を導入し、移民の流入を制限しようとしています。
多くの有権者にとって、ブレグジットは文化や価値観をめぐる主導権争いだった。イギリスとEUとの関係は常に複雑ではあったものの、一部の有権者にとっては主権問題が最優先だった。
政治学者エリック・カウフマンの研究は、移民問題がブレグジットの支持に与えた影響を裏付けています。カウフマンによれば、2060年までに移民の流入でイギリスの民族構成がどのように変わるかという予測に触れるだけで、移民規制への支持が25パーセントポイント上昇するそうです。
この傾向はブレグジットの投票結果にも反映されました。イングランドの多様性に富んだ大都市(ロンドン、バーミンガム、リーズ)の有権者の84%がEU残留に投票した一方、郊外では87%がEU離脱に投票していました。 実は、 ブレグジットは文化や価値観、主権問題をめぐる複雑な争いだったのです。都市部と郊外での投票傾向の違いは、移民問題や主権に対する見解の相違を反映しています。
一方日本はこれまでのところ、移民の受け入れには消極的で女性や高齢者の社会進出を後押ししたり、ロボティクスで労働力不足の解消を目指しています。
移民問題は先進国と途上国の利害が対立しているため、今後も解決策を見出すことが難しくなると著者は指摘します。
都市への人口集中は経済的な活力を生み出す一方で、環境問題や社会的不平等をもたらしています。都市化が進むことで、都市のインフラやサービスの需要が増加し、政策立案者には新たな課題が生じています。これらの課題に対処するためには、人口統計に影響を与える三大要因「出生・死亡・移動」を適切に調整することが重要です。
人口統計に影響を与える「出生・死亡・移動」は、密接に関連し合い、人口構造を形作っています。これらの要因を適切に調整することで、社会の持続可能性や経済の安定を図ることができます。例えば、出生率を向上させるための子育て支援策や、死亡率を低下させるための医療制度の充実、地方への移住を促進する政策などが考えられます。
世界には80億人近い多様な人たちがいるが、人口動態は予測可能なパターンをたどる場合も多く、世界の戦略的環境を理解する一助になる。ひとたび死亡率が下がれば、たいていは続いて出生率も下がる。出生率が下がると、人口の中位数年齢は高くなり、若者、中年、高齢者の人口の割合が変化する。
持続可能な社会を築くために 今後もさまざまな変化が予想される中、政策立案者、企業、権利擁護者、支援機関の人々は、これらの変化に適応し、持続可能な社会を築くための戦略を練る必要があります。私たちは相互に依存し、連結した世界に生きています。一国の難題や脅威が全体に影響を及ぼすのです。これには感染症の流行、気候変動、経済危機などが含まれます。
経済的に連結している世界では、幸運も分かち合うことができます。今、私たちは地球上の80億人をどう活用すれば、望む明日の世界を形成できるかを考える必要があります。
著者は「予測とは未来を予言することではない——現在への投資を促すことだ」と述べています。これを信じ、今できることを実践していくことが重要です。
本書は人口問題の書籍ですが、安全保障から政治、経済、文化、ジェンダー、環境問題まで幅広い分野にわたる幅広い知識を得られることが魅力になっています。読み応えのある一冊ですが、読む価値があり、おすすめです。
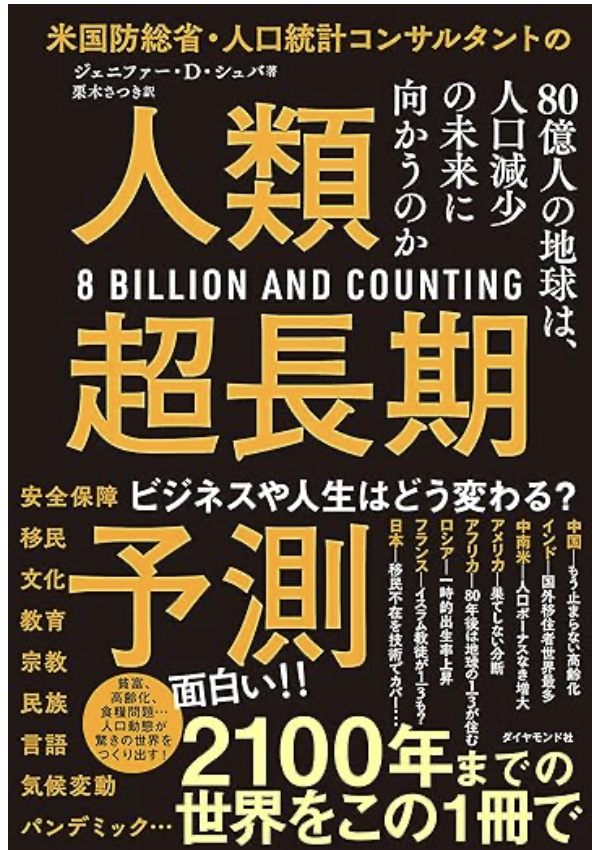
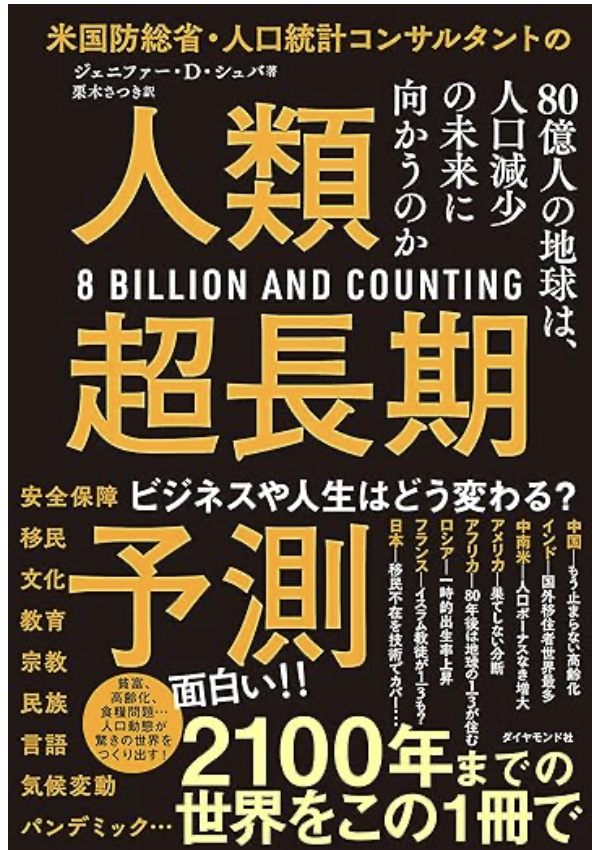





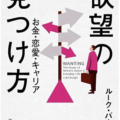


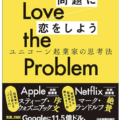


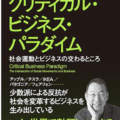
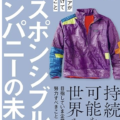



コメント