思いがけず利他
中島岳志
ミシマ社
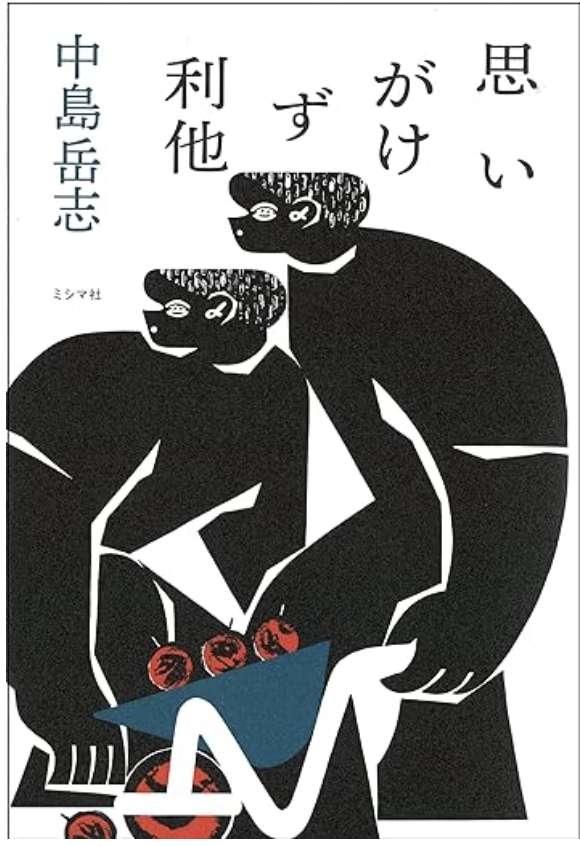
思いがけず利他(中島岳志)の要約
利他的な行動を実践するためには、自己を「器」のような存在と捉え、他者への貢献を意識的に取り入れる「与格的主体」を取り戻すことが重要です。自分の力には限界があると考えることで、利他の心が芽生えるのです。利他の本質を理解し、実践することで、私たちはより豊かな日常を送ることができるでしょう。
利他とは何か?
利他には様々な困難が伴います。偽善、負債、支配、利己性……。利他的になることは、そう簡単ではありません。(中島岳志)
本書では、利他とは何か、なぜ重要なのか、どのように実践すべきかといった問いに対して、著者である中島岳志氏の独自の考えが示されています。利他とは、他者の利益を優先する行動や思考を意味します。しかし、利他には様々な困難が伴います。
例えば、偽善の疑いを持たれたり、負債や支配の関係が生じたり、さらには利己的な動機が隠されていることもあります。これらの要因から、利他的になることは容易ではありません。
著者が指摘するように、利他の本質には「思いがけなさ」があります。これは、利他的な行動が計画されたものではなく、突発的かつ自然発生的に起こるという意味です。こうした行動は、純粋な驚きや感動を伴うため、他者に対して強いポジティブな影響を与えることができます。
2020年2月、東京工業大学において「未来の人類研究センター」が設立され、「利他プロジェクト」が開始されました。著者とその仲間たちは、このプロジェクトを通じて、利他についての研究を深め、その成果を社会に還元することを目指しています。彼らは、利他の概念がどのように機能し、どのように実践されるべきかを探求し、実際の社会問題に応用することを目指しています。
このプロジェクトの背景には、現代社会が抱える様々な課題があります。経済的格差、社会的孤立、環境問題など、これらの問題は利己的な行動が原因とされています。したがって、利他主義の実践は、これらの問題を解決するための一つの鍵となる可能性があります。また、研究によると、利他が社会全体の効率性や幸福度を高めることが明らかにされています。
例えば、地域社会におけるボランティア活動や、企業の社会貢献活動など、具体的な事例を通じて、利他主義がもたらすことをポジティブ・ネガティブの両面から検証しています。
利他行為は、その本質が他者のために行動することにありますが、時には利己的な行動につながることもあります。ドイツ語のギフトには贈り物と毒という2つの意味があると言います。過度の贈り物が返礼という形で、相手へのプレッシャーになることもあるのです。
利他的な行動から、他者を支配しコントロールしようとする欲望が生じることで、表面的には利他的な行動に見えるものが、実際には自己利益を追求するための手段として利用されることがあります。
利他的行動の背後にある利己性は、多くの場面で見受けられます。例えば、企業がSDGs(持続可能な開発目標)に取り組むことを宣伝する際、表面的には社会貢献をアピールしていますが、その真の目的が自己利益を高めることにある場合もあります。顧客は企業のCMを通じて、企業の利己的な一面を認識し、期待を下げることがあります。
これは、企業が真の利他行動ではなく、マーケティング戦略としてSDGsを利用していると見なされるからです。 利他と利己のバランス 利他行動を純粋に利他的なものとするためには、自分自身の利益を排除し、他者のために行動することが重要です。
しかし、現実的には、完全に利己心を排除することは難しいかもしれません。そのため、利他と利己のバランスを取ることが求められます。利他的な行動が本当に他者の利益になるようにするためには、その行動が他者にどのような影響を与えるかを慎重に考える必要があります。
著者は本書で、インドの宗教家シャンカラ、親鸞、落語の「文七元結」、数学者、料理研究家、ボランティアから利他の深掘りを行います。
利他は、人間の意図的行為ではない。人間の中を神が通過するときに現れるものである。 (シャンカラ)
彼らは考える間もなく「身が動く」人たちなのです。この与格的な情動によって、行動することが利他の基軸になっていると著者は指摘します。
与格的主体が利他の原動力?
利他的になるためには、器のような存在になり、与格的主体を取り戻すことが必要であると私は思います。数学者や職人のような「達人」は、与格的な境地に達した人たちであり、そこに現れた自力への懐疑こそ、利他の世界を開く第一歩ではないかと思います。
ヒンディー語の学習を通じて、著者は利他の本質に迫るための重要な概念「与格構文」を体得しました。与格構文は、自己の意志や力が及ばない現象を表現する際に使われます。例えば、「私はうれしい」という表現は、ヒンディー語では「私にうれしさが留まっている」と表現されます。同様に、「風邪をひいた」は「私に風邪が留まっている」となります。
この与格構文の考え方を使うことで、利他行動の本質に迫れます。利他的な行動を実践するためには、自己を「器」のような存在と捉え、他者への貢献を意識的に取り入れる「与格的主体」を取り戻すことが重要です。自分の力には限界があると考えることで、利他の心が芽生えるのです。
利他とは、自己の意志や力で行うものではなく、外部から「やってくるもの」なのです。この視点に立つと、利他はオートマティカルなものであり、受け手によって起動されるという性質を持つことが明らかになります。
利他の根底には「偶然性」の問題があります。重要なのは、偶然は偶然には起こらないということです。この器に「やってくるもの」が利他であり、その力は自己を超えた存在からもたらされるのです。私たちは偶然を呼び込む器になることを目指すべきなのです。
利他は時に目立たないものです。しかし、誰かが活躍し、個性が輝いているときには、必ずその輝きを引き出した人がいます。利他において重要なのは、「支配」や 「統御」から距離を取りつつ、相手の個性に「沿う」ことで、主体性や潜在能力を引き出すあり方なのではないかと思います。
相手に共感を与える利他のためには、いくつかの要素が欠かせません。
・自己の限界を認識する
自分の力や能力だけでは解決できない問題に対して、他者の協力や助けを求める姿勢を持つことが重要です。
・謙虚さを持つ
謙虚な態度で他者と接することで、自然と他者からの助けを得やすくなります。
・受け入れの姿勢を持つ
利他の行動が「やってくるもの」であるという認識を持ち、それを受け入れる準備を整えておくことが大切です。
・他者の視点を尊重する
他者の立場や考えを理解しようとする姿勢が、利他行動の出発点となります。相手にとってネガティブなものは利他ではなく、利己的な行動なのです。利他が起動するのは、与える時ではなく、受け取る時なのです。
逆に言えば、私たちは他者の行為や言葉を受け取ることで、相手を利他の主体に押し上げることができます。これは、利他的な行為が一方向のものではなく、双方向の相互作用によって生じるからです。つまり、利他を生み出すのは「与えること」だけではなく、「受け取ること」も重要な要素となります。
発信された利他的な行為が受信されるまでには、時に長い時間がかかることがあります。しかし、この時間的な隔たりがあるからこそ、利他的な行為は深い意味を持ちます。過去に発信された言葉や行為が、未来のある瞬間に受信され、その価値が認識されるとき、その瞬間こそが利他が起動する瞬間です。
利他となる種は、すでに過去に発信されています。私たちはそのことに気づかないことが多いですが、何かのきっかけで「あのときの一言」や「あのときの行為」の利他性に気づく瞬間があります。この瞬間、私たちは過去に発信されたものを受信し、その行為が利他として機能し始めます。発信と受信の間には時間的な隔たりがありますが、この隔たりが利他の本質的な特性を形成しているのです。
利他の行為が真に効果を発揮するためには、発信者と受信者の双方が重要な役割を果たします。発信者が行った利他的な行為や言葉は、時間を経て受信者によって認識され、その価値が再評価されます。このプロセスを通じて、受信者は発信者を利他の主体として認識し、その行為の意義が新たに見出されるのです。
たとえば、私自身も上司からのアドバイスの価値に後から気づくことが何度もありました。その当時は理解しきれなかった言葉や指導が、時間を経てから深く心に響くことがあります。このように、利他の行為は受け取る側がその意義を理解したときに初めて完全に作用するのです。
死者への弔いが利他を生み出す理由
発信者にとって、利他は未来からやって来るものであり、受信者にとっては、過去からやって来るもの。これが利他の時制です。すると、私たちはあることに気づかされます。それは「利他の発信者」が、場合によってはすでに亡くなっており、この世にはいないということです。
利他の行動がどのように発動するのかを考えるとき、私たちは死者から多くのヒントを得ることができます。日常生活は、過去の無名の死者たちの行為や言葉によって支えられていることに気づくことが重要です。彼らの存在を再認識し、その影響を受け入れることが、利他的な行動を引き起こす一歩となります。
過去の死者たちとの対話を通じて、私たちは自己の存在が他者からの贈与で成り立っていることを理解することができます。私たちが死者を弔う時に、利他の行動を起動させるのです。死者の存在を認識し、彼らの言葉や行為から学び、それを未来の他者に向けて発信することが、利他の本質とされています。
過去の知恵や経験を受け継ぎ、それを未来に向けて発信することで、私たちは他者のために行動することができます。これは単なる個人的な利他行動ではなく、未来の人たちに価値を提供し、社会全体の発展と安定に寄与するものです。
私の存在にかかわる「偶然」や「運」に目を向けることで、私たちは他者へと開かれ、共に支えあうという連帯意識を醸成すると言うのです。
偶然や運に目を向けることは、私たちの人生や社会における連帯意識を生み出します。この認識を持つことで、謙虚さや共感、社会的責任感が育まれ、より良い社会の実現に繋がるのです。過度の自己責任論に陥ることは、利他には悪影響を及ぼします。利他は偶然によって生まれると考える人が増えることで、社会的再配分によりポジティブになれるのです。
私たちの人生は、予期しない出会いや出来事によって彩られています。これらの偶然の邂逅に驚き、それを受け入れることで、未来への希望や目標が生まれます。このプロセスが連続的に繰り返されることで、私たちは充実した人生を送ることができるのです。
偶然の出会いや出来事は、私たちに新たな視点や可能性をもたらします。例えば、思いがけない人との出会いが人生を大きく変えることがあります。これらの出会いは、私たちに新たなインスピレーションや目標を提供し、自己成長の機会を与えてくれます。
スタンフォードのクランボルツ博士が指摘するように。偶然の出来事を受け止めることは、柔軟性と適応力を求められる行動です。予期しない状況に直面したとき、それを拒絶するのではなく、受け入れることで、私たちは新たな経験を通じて成長することができます。この受容のプロセスは、私たちの人生における豊かさを増し、困難な状況を乗り越える力を養います。(クランボルツの計画的偶発性理論)
利他の概念を日常生活に取り入れることで、自分自身に良い変化がもたらされる可能性があります。例えば、過去の歴史や文化に目を向け、その中から学びを得ることで、自分の行動が他者に対してどのような影響を与えるかを考えるようになります。このような視点を持つことで、日常の行動がより意義深いものとなり、他者との関係も深まるでしょう。










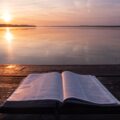




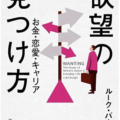

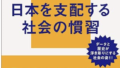
コメント