
価値循環の成長戦略 人口減少下に“個が輝く”日本の未来図
デロイト トーマツ グループ
日経BP
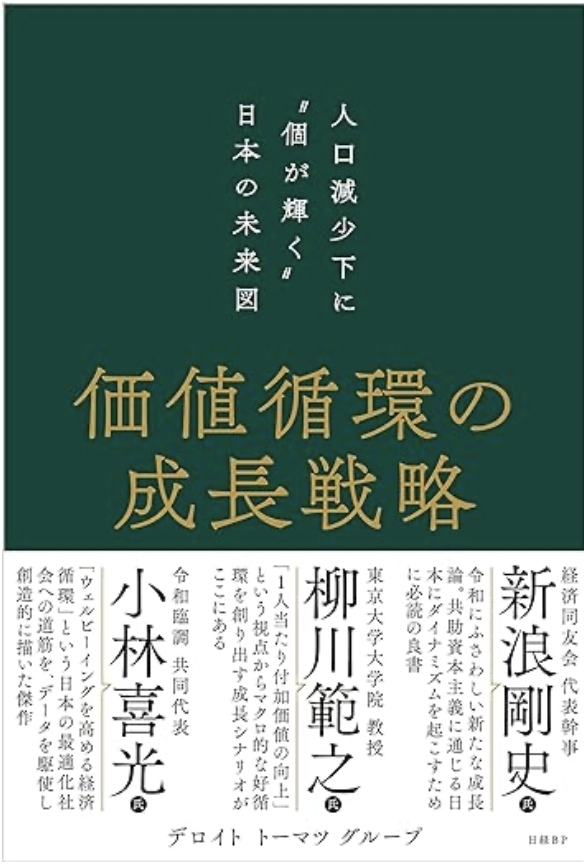
価値循環の成長戦略(デロイト トーマツ グループ)の要約
デロイト トーマツ グループが提唱する「価値循環成長戦略」は、人口減少という課題に直面する日本経済の成長を、新たな視点から捉え直した革新的なアプローチです。この戦略の核心は、人口減少社会において日本人1人当たりの付加価値を向上させることにより、日本全体の持続的な成長を実現することにあります。
「4つのリソース」と「4つの機会」を組み合わせ、価値循環を起こそう!
これからの時代は、一人ひとりの付加価値や個人としての豊かさに軸足を置き、「質的な成長」を最優先で追求するモデルに転換することが求められているのだ。(デロイト トーマツ グループ)
日本は現在、人口減少という大きな課題に直面しています。しかし、この状況を悲観的に捉えるのではなく、むしろ社会の在り方を根本から見直し、新たな成長モデルを構築する好機と捉えるべきだというのが、デロイト トーマツ グループの主張になります。(デロイト トーマツ グループの関連記事)
人口が減少するということは、逆説的に一人ひとりの「希少性」が高まることを意味します。これまでの日本社会は、ともすれば全体の規律や効率性を重視するあまり、個人の可能性や豊かさの実現を軽視してきた面があります。しかし、これからの時代は「個」に焦点を当て、一人ひとりの付加価値や幸福感を最大化することが、社会全体の持続可能な発展につながると著者たちは指摘します。
従来の経済成長モデルは、全体の規模を拡大することで個人の豊かさを実現しようとしてきました。しかし、これからは発想を転換し、個人の成長と豊かさを主眼に置き、その集合体として社会全体が発展していくという新たなアプローチが求められています。この「質的成長」モデルこそが、人口減少時代における持続可能な発展の鍵となるのです。
新しい成長モデルの中心となるのは、既存の「壁」をものともせずに挑戦する個人と企業です。従来の制度や慣行にとらわれず、新たな価値を創造する人材が、より多くの機会を獲得し、高い付加価値を生み出します。そして、そうした人材を惹きつける企業がさらなる成長を遂げ、それらが集まる地域の経済も活性化していくという好循環が生まれるのです。
人口が減少しても、ヒト・モノ・データ・カネという「4つのリソース」を効果的に循環させることで、経済活動の質と量を高め、付加価値の向上を実現することができます。これらのリソースを、従来の常識や制約にとらわれることなく柔軟に活用することが、新たな成長の源泉となります。 人口減少下でも拡大する「4つの機会」 さらに、人口減少下でも成長が見込まれる4つの機会に着目することが重要です。
「グローバル成長との連動」「リアル空間の活用・再発見」「仮想空間の拡大」「時間の蓄積が生み出す資産」という4つの機会を的確に捉え、「4つのリソース」と組み合わせることで、新たな市場を創出し、持続的な成長を実現することができるのです。
真の「協調」社会へ これからの日本社会に求められているのは、過度な同調性から脱却し、自律した個人が輝きながらも、互いに「壁」を乗り越えてつながる真の「協調」社会です。多様性を尊重しつつ、個々の強みを生かし合うことで、社会全体としての創造性と生産性を高めることができるでしょう。
大循環、グローバル循環、小循環の3つの循環を相互に作用させよう!
成長戦略を実現するには、個別最適志向に陥りがちで様々な領域で根強く残る「縦割り」発想やセクショナリズムといった「壁」を乗り越え、循環を促す新たなつながりを創出するための変革を、大胆に進めていくことが求められる。「循環型成長モデル」を構成する「大循環」「グローバル循環」「小循環」。これら3つの循環を一連のものとして切れ目なく連動させることが、人口減少下において日本が成長していく道筋になる。
日本が成長するためには、以下の3つの循環を相互に作用させる必要があります。
①大循環 (マクロ経済)
社会課題の解決を新しい需要やイノベーションの機会と捉えます。 官民が協力して資源を有効活用し、新たな市場を作ります。
②グローバル循環 (国際経済)
海外から人材・物資・資金などを取り入れ、日本の成長を促進します。 国際的な投資や人材交流、イノベーション、市場創出を進めます。 これにより、大循環で生まれた成長の機会をさらに拡大します。
③小循環 (個人の経済)
大循環とグローバル循環で生まれた成長の恩恵を個人レベルに還元します。 一人一人の生産性を高め、豊かさや幸福感の向上を目指します。
これら3つの循環が相互に作用することで、持続可能な経済成長と個人の幸福を実現することが期待されます。
人口減少時代において、企業は「共通化」と「差異化」という2つの軸をバランスよく活用しながら、成長戦略を再構築することが求められます。これにより、人口減少という課題に対応しつつ、新たな市場機会を最大限に活用することが可能となります。
人口減少は、顧客の減少と労働力の減少という二重の課題をもたらします。しかし、この変化は以下のような機会も生み出しています。
・過度な混雑の緩和
・効率的な人員配置の実現
・きめ細やかなサービス提供の可能性
人口減少が進む中で、企業の戦略も大きな転換期に差し掛かっています。これまでのビジネスモデルでは、「高品質な商品をよりリーズナブルな価格で、多くの消費者に提供する」ことが成功の鍵とされてきました。大量生産・大量販売手法は、20世紀の経済成長を支える重要な要素でした。
しかし、市場の成熟化やデジタル技術の進展とともに、新たな戦略の必要性が高まっています。今後は「特定の顧客層に対し、高付加価値の商品を、より高価格で、継続的に販売する」というアプローチが求められます。
この新しい戦略は、主に2つの要素に焦点を当てています。
①取引の「頻度」を増やすこと。同じ顧客から反復して購入してもらうことで、長期的な関係を構築し、安定した収益基盤を築きます。
②取引の「価格」を引き上げること。高品質で高付加価値な商品やサービスを提供することで、顧客の支払い意欲を高め、利益率の向上を目指します。
この戦略の転換は、単なる販売手法の変更に留まりません。企業と顧客との関係を再定義し、より深いつながりを築くことを目指しています。顧客のニーズを深く把握し、それに合致する商品開発やサービス提供を通じて、顧客満足度を高め、ロイヤルティを確立します。
「共通化」と「差異化」では、頻度と価格をどのようにすれば上げることができるのか。頻度を上げるには、顧客との取引を一過性で終わらせずに継続させ、「回転」させることで「量」を増やしていく仕組みが必要だ。また、価格を上げるには「回転」によって収集できるデータ・情報を「蓄積」し、顧客のニーズや課題に沿う形で製品やサービスの「質」を高めることが求められる。つまり、価値循環とは「回転」と「蓄積」を繰り返すことで、 顧客の人数に依存せずに取引の「量と質」を高め、全体としての付加価値向上を実現することなのだ。
企業や地域が持続的に成長するためには、「回転」と「蓄積」による価値循環が重要です。「回転」は取引や利用の頻度を高めることで、「共通化」によって促進されます。一方、「蓄積」は独自性や専門性を深めることで、「差異化」によって価値を高めていきます。
この価値循環を基盤として、3つの成長パターンが考えられます。1つ目は「ライフライン化」です。これは幅広い製品やサービスを提供することで、顧客の日常生活に不可欠な存在となる戦略です。2つ目は「アイコン化」で、独自の技術や知見を磨き上げ、市場で唯一無二の存在となることを目指します。そして3つ目は「コンシェルジュ化」です。これは顧客との接点の頻度を高めながら、同時に取引単価も向上させる高度な戦略です。
価値循環を起こすための戦略を適切に組み合わせることで、企業や地域は持続的な成長を実現し、競争力を強化することができます。顧客のニーズや市場環境の変化に柔軟に対応しながら、自社の強みを最大限に活かすことが成功への鍵となるでしょう。
例えば、日本マクドナルドは、高単価商品の導入とモバイルオーダーによって、顧客との接点を増やし、成長を遂げています。また、オイシックス・ラ・大地は、サブスクリプションモデルや独自のメニュー開発によって差異化し、顧客に独自の価値を提供しています。
徳島県那賀町が温泉やジビエといった既存の観光資源にドローンを組み合わせて「日本一、ドローンの飛ぶ町」という独自性を創出しています。また、北海道更別村が「課題先進村」という特徴を活かしてイノベーション・ハブ化を進めているように、地域固有の資源や課題を巧みに活用して差異化を図り、外部人材や企業を呼び込むことで成功しています。
人口減少エリアが地域の価値を再発見し成長につなげる戦略は、国や企業の成長戦略にも応用できる可能性を秘めています。これらの事例から分かるように、「共通化」と「差異化」のバランスを保ちながら、顧客との関係を構築し続けることが成長の鍵となります。特に、人口減少が進む日本の成熟市場においては、顧客との継続的な接点を通じて独自の価値を提供することが不可欠です。
価値循環成長戦略のための7つのアジェンダ
デロイト トーマツ グループが提唱する「価値循環成長戦略」は、日本が直面する様々な課題を機会に変え、新たな成長の道筋を示すものです。この戦略の核心となるのが、7つの「成長アジェンダ」です。これらのアジェンダは、日本の強みを活かしつつ、社会課題の解決と経済成長の両立を目指しています。
①モビリティー革命 移動の未来を創造する
日本は長年「自動車大国」として知られてきましたが、今後は「モビリティー大国」への転換が求められています。これは単に自動車を製造するだけでなく、自動運転技術、シェアリングサービス、次世代公共交通システムなど、人々の移動に関わるあらゆるサービスや技術を包括的に提供する国へと進化することを意味します。
この転換により、高齢者や地方居住者の移動問題解決、都市の渋滞緩和、環境負荷の低減など、多様な社会課題に対応することが期待されます。
②ヘルスケア 世界の長寿を支える
日本は世界有数の長寿国であり、高度な医療技術を有しています。この経験と技術を活かし、健康長寿ソリューションを世界に展開することで、グローバルヘルスケア市場でのリーダーシップを確立できる可能性があります。予防医学、遠隔医療、AI診断支援など、最新技術を駆使したヘルスケアサービスの開発と普及は、国内の医療費削減にも貢献し、持続可能な社会保障制度の構築にもつながるでしょう。
③エネルギー 多層的な未来を築く
エネルギー安全保障と環境保護の両立は、日本にとって重要な課題です。「多層的エネルギーミックス」の構築を通じて、再生可能エネルギー、水素エネルギー、次世代原子力など、多様なエネルギー源を効率的に組み合わせることを目指します。この取り組みは、日本のエネルギー自給率向上と同時に、環境技術の輸出による経済成長にも寄与する可能性があります。
④サーキュラーエコノミー 資源の循環を極める
資源の乏しい日本にとって、サーキュラーエコノミーの推進は不可欠です。高度なリサイクル技術の開発、バイオマス資源の活用、製品の長寿命化など、様々なアプローチを通じて「少資源国」から「再生資源大国」への転換を図ります。この取り組みは、環境負荷の低減だけでなく、新たな産業と雇用の創出にもつながる可能性を秘めています。
⑤観光 日本全体をテーマパークに
日本の豊かな文化遺産、自然景観、食文化は、世界中の旅行者を魅了する潜在力を持っています。「日本全国テーマパーク化」構想は、これらの資源を最大限に活用し、日本全体を魅力的な観光地として再構築することを目指します。
⑥メディア・エンターテインメント グローバルな感性を育む
日本のアニメ、ゲーム、音楽などのコンテンツは、すでに世界的な人気を誇っています。今後は、この強みをさらに発展させ、よりグローバルな視点を取り入れたコスモポリタン的なエンターテインメントの創造を目指します。多様な文化背景を持つクリエイターの協働、業界大連合でのグローバル化、IPへの投資を呼び込むことで、コンテンツを強化し、世界中の人々の心を掴むことでビジベスが飛躍します。
⑦半導体 イノベーションの中心地を築く
半導体産業は、デジタル社会の基盤を支える重要な分野です。日本は、かつての半導体大国としての地位を再び確立するべく、オープンなエコシステムを構築し、世界中の企業や人材が集まる「オープンなシリコン城下町」の創造を目指します。R&Dでの日本独自のポジションを確立することが重要です。
半導体人材の育成、産学官連携の強化、スタートアップ支援、国際的な研究開発拠点の設立など、多角的なアプローチにより、イノベーションの加速と産業競争力の強化を図ります。
人口減少時代における成長アジェンダは、単独での推進ではなく、相互に連携し合うことで、より大きな成果を生み出すことができます。モビリティー、エネルギー、ヘルスケアなどのアジェンダで壁を超え、協力し合うことで、持続的なイノベーションが促進され、未来の産業の発展が期待されます。さらに、企業、政府、学術機関、市民社会が一体となった横断的なアプローチにより、真の価値循環成長が実現するのです。
日本は今、大きな転換点に立っています。これらの成長アジェンダを積極的に推進することで、社会課題の解決と経済成長の両立を図り、持続可能で活力ある社会を築いていくことができるでしょう。私たち一人一人が、この新しい成長モデルの担い手となり、より良い未来の創造に参画していくことが求められています。
現在の日本を縛っているのは人口動態や経済状況といった外的要因のみならず、私たち一人ひとりの中にある内的要因、つまり「意識や思い込みの壁」なのだ。
しかし、これらの構想を実現するためには、私たち一人ひとりの意識改革が不可欠になります。「人口減少下では経済成長は不可能」「日本に明るい未来はない」といった思い込みの壁を乗り越える必要があります。 これらの思い込みは、必ずしも事実に基づいたものではありません。
むしろ、漠然とした不安や諦めの気持ちから生まれたものかもしれません。この壁を乗り越えるためには、一人ひとりが変化を起こす意思を持つことが重要です。 思い込みの壁を乗り越えた先には、個人レベルでの「循環型成長」が待っています。
この意識改革を通じて個人レベルでの「循環型成長」を実現することで、自己の価値向上とウェルビーイングの追求が日本全体の幸福度向上につながり、「今日より明日が良くなる」と実感できる社会、すなわち日本が目指すべき明るい未来の姿が見えてくるのです。
新刊 最強Appleフレームワーク: ジョブズを失っても、成長し続ける 最高・堅実モデル!
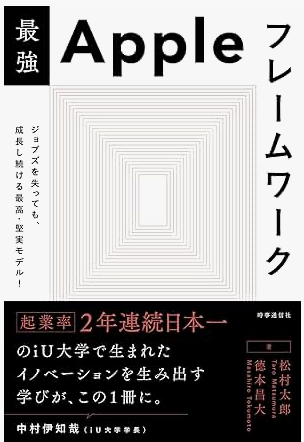
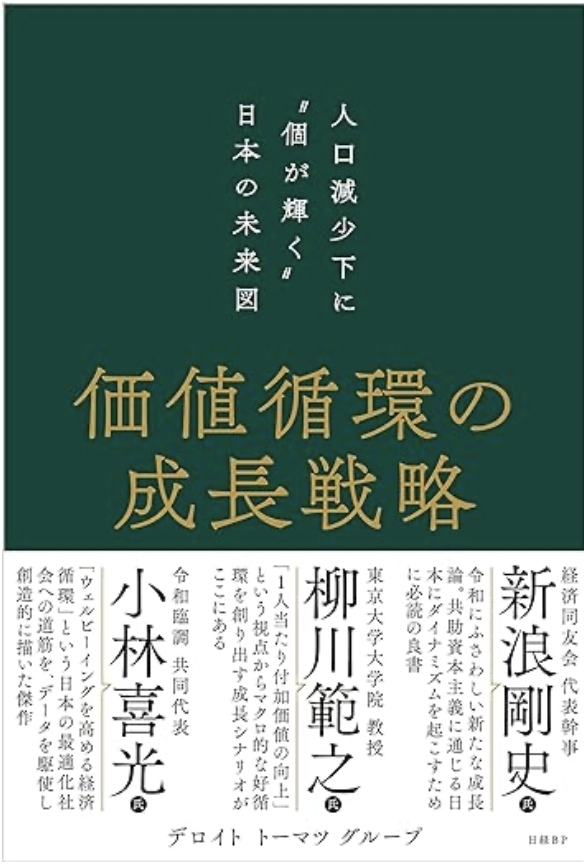
















コメント