経営は無理をせよ、無茶はするな オーバーエクステンション戦略のすすめ
伊丹敬之
日経BP 日本経済新聞出版社
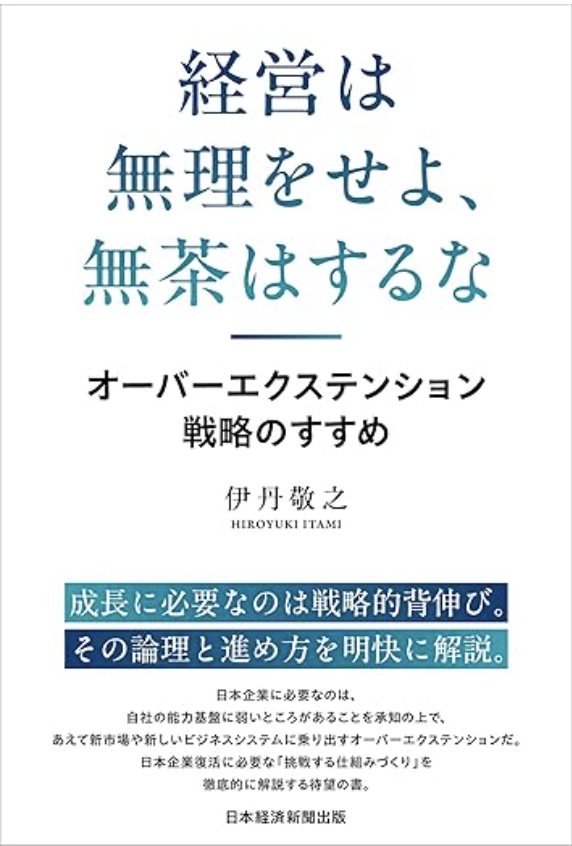
経営は無理をせよ、無茶はするな(伊丹敬之)の要約
成長が強く求められている日本企業にとって、これまでの延長線上にある戦略だけではもはや限界に直面しています。そうした中で注目されるのが、「オーバーエクステンション戦略」です。これは、自社の能力に足りない部分があると認識しながらも、あえてその限界を超えて挑戦し、現場の学習を通じて能力基盤を拡大していく、いわば“背伸びの戦略”です。 この戦略を成功させるには、「無理」と「無茶」の境界を見極めながら、あえて困難なプロセスに踏み出し、やり抜く姿勢が不可欠です。
企業の成長に必要なオーバーエクステンション戦略とは何か?
オーバーエクステンション戦略とは、自分に十分な実力がないことを承知の上で、あえて新しい事業活動に挑戦するという戦略である。その挑戦の過程で、実力不足の苦しみのなかで現場が学習し、その学習の結果として企業の能力基盤の大きな拡大につながる。だから、オーバーエクステンションは、多くの企業が成長の踊り場での挑戦としてとってきた戦略なのである。(伊丹敬之)
1990年代初頭のバブル崩壊以降、日本経済は長期にわたる停滞期に入りました。いわゆる「失われた30年」と呼ばれるこの時代、日本企業の多くは低成長と守りの経営を強いられ、リスクを取って挑戦する企業文化は徐々に希薄になっていきました。内部留保を優先し、投資や新規事業への積極的な姿勢は影を潜めるようになったとも言われています。
しかし現在、急速に進むテクノロジー分野のイノベーションにより、社会は大きく変化しており、もはや従来の延長線上にある戦略では限界が見え始めています。 こうした環境変化の中で注目されているのが、「オーバーエクステンション」という考え方です。これは、自社の能力基盤に弱点があることを認識したうえで、あえて新市場や新たなビジネスシステムに挑戦する、いわば“背伸び戦略”を意味します。
伊丹敬之氏(一橋大学名誉教授)は、かつての優良企業の多くが、成長の転機においてオーバーエクステンションという戦略的な挑戦を経験していると指摘しています。しかし近年では、日本企業全体にそのような挑戦を避ける傾向が強まっており、堅実な投資すら控える姿勢が目立つようになっています。
だからこそ今、従来の延長線上にとどまるのではなく、あえて背伸びをするような挑戦――すなわちオーバーエクステンションが、再び求められる時代に入っているのです。
トヨタ自動車、ヤマト運輸、アマゾンなどの具体的事例をもとに、その導入プロセスを明快に解説しているのが本書経営は無理をせよ、無茶はするな オーバーエクステンション戦略のすすめです。日本企業の再生に必要な「挑戦する仕組みづくり」を徹底的に論じており、成長に悩む経営者におすすめの一冊です。
著者は、これからの日本企業がグローバルな競争を勝ち抜くために必要な視点を提供しています。本書で提唱されているオーバーエクステンション戦略とは、現状の能力をやや超えるレベルで、積極的に新たな事業に挑戦するという考え方です。これは単なる現状維持ではなく、成長を目指す企業にとって不可欠な戦略と言えます。
重要なのは、それが単なる無謀な挑戦ではなく、「戦略的な背伸び」であるという点です。この戦略は、企業が既存の枠組みを超えて新たな成長機会を掴むうえで、欠かすことのできない考え方です。 著者はまた、歴史上の軍師たちも、まさにオーバーエクステンション戦略を用いて戦っていたと指摘しています。
漢に天下をもたらした韓信の「背水の陣」はその代表例だと著者は言います。彼は兵士たちの退路を断つことで、彼らに強い危機感を与え、潜在的な能力を最大限に引き出しました。 さらに、敵軍はこの戦法を軽視して油断し、結果的に挟み撃ちにされて敗北します。これは、兵の心理――緊張と緩み――を巧みに利用した戦略であり、韓信は自軍の柔軟な動きを計算し尽くしていたのです。
この戦略の本質は、孫子の兵法にも通じるものであり、まさにオーバーエクステンション戦略と本質的に重なると著者は述べています。自らの実力をあえて超える「背伸び」を選ぶことで、現場に危機感が生まれ、それが潜在力を引き出します。そして、その困難な経験を通じて、組織全体が大きく成長していくのです。
また、オーバーエクステンションは、実力を超える挑戦でありながら、そのリスクの大きさから、組織全体に対して正面から提示されることは少なく、しばしば「密輸入」のように静かに導入されます。
トヨタのハイブリッド開発では、技術幹部が明確な目標を表には出さず、徐々に現場を導いた例が典型です。これは、組織のリスク受容性の低さや、現場が怯む可能性を見越しての戦略的行動でした。重要なのは、密輸入を偶然に任せるのではなく、組織的に「育てる」仕組みを構築することです。
オーバーエクステンションを成功に導くための4段階のプロセス
最終的な成功にたどり着くまでのプロセスで、4つのマネジメントがきちんと工夫される必要がある。
オーバーエクステンションを成功に導くためには、「助走」「踏み切り」「学習」「やり切る」という4つの段階に対応したマネジメントが必要不可欠です。それぞれの段階には異なる課題と役割があり、企業は段階ごとに適切な戦略と組織運営の工夫を求められます。
オーバーエクステンションにおいても、事業を本格的に立ち上げる前に十分な準備を整える「助走」というフェーズが極めて重要です。助走のマネジメントでは、以下の3つの要素が鍵となります。
1つ目は、「目指すべき大きな目標をつくること」です。助走段階では、目標の詳細まで定まっていなくても構いませんが、組織としての方向性が明確でなければ、準備に一貫性が生まれません。
ヤマト運輸が「個人向け宅配サービス」という当時の業界では常識外れの構想を掲げたことや、アマゾンが書籍販売から始めてインターネット小売の全体を見据えていたことは、その好例です。トヨタのプリウスにおいては、「地球環境対応車の開発」が長期的ビジョンとして共有されていました。
2つ目は、「基礎的な能力基盤の確認」です。ただ夢を語るだけでなく、それを支える可能性が自社内に存在するかどうかを冷静に見極める必要があります。たとえ不完全であっても、技術、組織、人材などに一定の可能性が感じられれば、それは挑戦の足場になります。確認を怠ると、踏み切り後に破綻するリスクが高まります。
3つ目は、「踏み切り前の論理的準備」です。なぜこの挑戦を行うのか、どのような価値があるのか、どのようにリソースを投入すべきかといった思考を、経営陣・現場の双方で共有しておく必要があります。ジェフ・ベゾスが書籍を初期商材としたのも、「本は種類が多く、在庫管理や配送のしやすさにも優れている」という論理に基づいた選択でした。
次の「踏み切り」は、戦略の本格的な実行フェーズです。ここからは「調査」や「準備」ではなく、現実の事業としてリスクを伴う行動が始まります。プリウスの開発も、単なる研究段階から、市場投入の時期を定めた上で量産化に進む決断がなされた時点で、この段階に入りました。
アマゾンのケースでも、マーケットプレイスを導入してサードパーティの参加を促したことが、大規模な顧客価値の提供につながりました。この仕組みにより、商品ラインナップは爆発的に増え、顧客満足度も上昇しました。アマゾンが単なる書店から「すべてが揃うオンラインストア」へと進化した背景には、踏み切りのタイミングを的確に捉えた決断があったのです。
「学習」の段階では、十分な準備を経てもなお、不足する実力や知見に直面します。この段階では、現場が試行錯誤を重ねながら、不足を埋めていくプロセスが不可欠です。
プリウスの開発では、技術開発と生産体制の整備が並行して進められ、極めて厳しい学習フェーズとなりました。ヤマト運輸の宅急便も、整備されていないシステムの中で現場が創意工夫しながらサービスを提供するという形で学びが進みました。
アマゾンにおいても、マーケットプレイスの存在は学習を加速させる要因となりました。社外のサードパーティが同じプラットフォーム上で競合することで、小売部門は自然と自社のパフォーマンスを見つめ直すようになります。ランキングなどを通じて外部との比較が可視化され、競争と改善のサイクルが回り始めるのです。これが内発的な成長エンジンとして作用しました。
最後の「やり切る」段階では、想定外の問題や困難が必ず発生します。その中でも、目標を見失わず、現場と経営が一体となって取り組み、成果に結びつける粘り強さが問われます。
プリウスは初代で採算が取れなかったものの、3代目で商業的成功を収めました。ヤマト運輸も、全国配送網を整える過程で行政との摩擦を乗り越えるなど、困難な道のりを走り抜いています。
こうして「助走」「踏み切り」「学習」「やり切る」の4つの段階を着実に進めることによって、オーバーエクステンションは単なる“無理な挑戦”に終わらず、企業の能力基盤を押し広げ、持続的成長につながる戦略として結実するのです。それぞれの段階におけるマネジメントの工夫と判断が、企業の未来を大きく左右すると言えるでしょう。
無理と無茶の境界線とは?時には無茶が組織に必要な理由
意識的に強調すべきは、無理をきちんとやり遂げる努力、そして無理の範囲に最終結果を抑え込む努力である。無茶の境界線を越えて致命的な失敗にならないように注意はした上で、しかし無茶になるかもしれない大きな目標に挑戦し、それを無理の範囲に抑え込むのである。
オーバーエクステンションが「無理」に収まるのか、「無茶」に転ぶのかは、構想段階での見極めが極めて重要です。成功する戦略的な挑戦は、あくまで「無理」の範囲内に踏みとどまり、無茶になってしまう挑戦は、能力基盤の見積もりが甘く、失敗の確率が高くなります。
ユニクロは「無理」なオーバーエクステンションによって成長を遂げてきた企業だと考えられますが、時に「無茶」な挑戦も行ってきました。初期の海外進出や農業事業への進出などは、必要な能力への発想が浅く、安易な判断が招いた失敗だったのでしょう。
ただし、柳井氏はこうした失敗を否定的に捉えていません。むしろ、「失敗は大きな目標に挑戦する際には不可避なものだ」と述べ、次のように語っています。
新しい事業は、そもそも失敗することが多いのである。事業計画をきちんと作っても、ほとんどその通りには進まないことが多い。しかし、その失敗を生かすも殺すも経営姿勢である。失敗には次につながる成功の芽が潜んでいるものだ。したがって、実行しながら考えて、修正していけばよい。失敗の経験は、身につく学習効果として財産になる。(柳井正)
このように、失敗から学ぶ姿勢こそが成長を支えるのです。とくに、自分たちがこれまでのビジネスで慎重に築いてきた枠を超える挑戦──たとえば多角化や海外展開などでは、荒っぽい思考や思い込みが入りやすくなります。「自分たちならできる」という過信が、必要な能力の見積もりを甘くする要因となるのです。
とはいえ、「無茶」がまったくない組織よりも、たまに無茶を経験する組織のほうが健全とも言えます。なぜなら、その経験が「無理」をしてでも挑戦する姿勢を生み、結果として企業の成長につながっていくからです。
現場がこうした困難な挑戦に耐えるには、次の3つの心理的条件が大切です。
・先に希望を感じられる明るいビジョンがあること
・目指す目標に使命感を持てること
・自分たちの苦労をトップが理解してくれていると感じられること
経営側の役割としては、これらを支える行動が求められます。つは、将来へのビジョンを現場が共感できるかたちで提示すること。もう1つは、オーバーエクステンションの先にある展開を、論理的に説明することです。
「いまの苦労を乗り越えれば、先に希望がある」と現場が納得できれば、心理的な耐性も高まり、「無理」を「無茶」にしないための力となると著者は指摘します。
「無茶がたまにある方が、 むしろ企業成長のためには健全である。その方が、無理に挑戦するようになる」という著者の言葉が響きました。ベンチャー経営者も含め、今の日本の経営者に求められているのは、この姿勢かもしれません。
経営者だけでなく、ビジネスに関わる多くの人にとって、本書の内容は大いに参考になると思います。困難な時代だからこそ、オーバーエクステンション戦略を手がかりに、新たな挑戦へと一歩を踏み出す勇気が求められているのです。














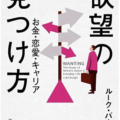



コメント