FRAGMENT UNIVERSITY 藤原ヒロシの特殊講義 非言語マーケティング
藤原ヒロシ
集英社
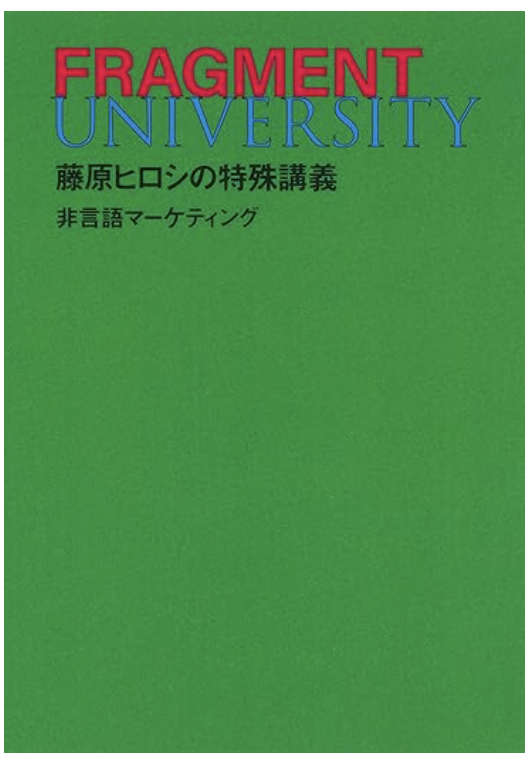
FRAGMENT UNIVERSITY (藤原ヒロシ)の書評
藤原ヒロシ氏の創作哲学は、「違和感のミックス」から生まれるイノベーションにあります。既存のものへの敬意、定番を疑う視点、そして小さなひねりによって大きなうねりを生み出す発想が、コラボレーション成功の鍵となります。本書は、非言語的マーケティングと感性主導の協業論を通じて、共創の本質とそのビジネス的意義を明快に提示しています。
パンクな発想がイノベーションを起こす理由
違和感と違和感がぶつかり合うミックス。 (藤原ヒロシ)
藤原ヒロシ氏は、1980年代の日本におけるストリートカルチャーの黎明期から現在に至るまで、ファッション、音楽、アートといった多様なジャンルで活躍を続けている稀有な存在です。
ミュージシャンとしてのキャリアを起点とし、裏原宿系ファッションシーンにおいてキーパーソンとしての地位を確立。その後も、多様なブランドとの協業や独自プロダクトの展開を通じて、時代ごとに変化する「かっこよさ」の価値観を柔軟に捉え、常にその最前線を提示し続けてきました。
枠に収まることをあえて避け、ジャンルを横断しながら独自のスタイルを研ぎ澄ませてきたその在り方は、時代を越えて人々の感性に響き続けています。
私自身、藤原氏とほぼ同世代として、同じ時代の空気を吸いながら生きてきました。1977年のセックス・ピストルズに端を発するパンクの衝撃、そしてその後に続くスカ、レゲエ、ブラックミュージック、ラップなど、多様なカルチャーに深く影響を受けてきました。
だからこそ、本書に込められた「断片を集め、再構成し、新たな価値を生み出す」という思想に、強く心を動かされました。そこには、かつて夢中になったあの時代の精神が、今もなお確かに息づいており、自分の原点をあらためて思い出させてくれるのです。
藤原氏がパンクに魅力を感じた理由は、それまでの音楽ムーブメントと異なる価値観にありました。たとえば、1960年代後半のサイケデリック・ロックなどは、一つのスタイルを皆で共有し、継続して盛り上げていく文化が主流でした。それに対してパンクは、「人の真似をするな」「オリジナルであれ」という精神を前面に出し、ジャンルにとどまることなく常に新しい表現へと進んでいく姿勢を重視していました。
藤原氏は、「パンク・イコール・パンク」ではなく、「パンク・イコール・サムシングエルス(何か別のもの)」であるという考え方に共鳴していたと語っています。ジャンルや枠組みにとらわれない発想は、後の彼の表現活動の基盤となっていったように思います。
また、藤原氏が強く影響を受けた人物のひとりに、パンクの仕掛け人として知られるマルコム・マクラーレンがいます。1970年代のイギリス社会では、経済の低迷や若年層の高失業率が社会不安を生み、既存の体制や均質性への反発がカルチャーとして表出しました。
そうした背景の中でマクラーレンが打ち出した「アンバランスこそが美しい」という価値観に、藤原氏は深く共鳴しています。あらゆる場面でバランスや調和が重視される社会にあって、不均衡や不完全さをあえて肯定するその姿勢は、藤原氏の感性や美学をかたちづくるうえで、重要な土壌となったと言えるでしょう。
本書の中では、そうした思想と地続きのものとして、「断片の収集と再構成」というアプローチが語られています。タイトルにも含まれる「FRAGMENT(断片)」とは、バラバラで意味の定まらない破片のようなものを指しますが、藤原氏にとっては、それらを一度フラットに並べ、自由に組み直すことで新たな意味を与える素材でもあります。 高級なものもチープなものも、意味のあるものもないものも、一度すべてを対等な関係で並べてみる。
そして、それらをつなぎ合わせることで、これまでにない関係性や価値を見いだしていく――この手法は、1980年代以降に発展したヒップホップ文化の「サンプリング」にも通じるものがあります。 異なる文脈や出自を持つ要素同士を大胆に接続することで、思いがけない化学反応が生まれる。そのプロセスこそが、藤原氏の創造性の中核をなしているのです。
「違和感と違和感がぶつかり合うミックス」からこそ、イノベーションは生まれる――それは藤原氏の実践から浮かび上がる重要な示唆です。新たな発明や発見が生まれにくいと言われる現代においては、異質なもの同士が交差する「アイデアの交差点」を意図的に設計することが求められています。その際に必要となるのは、違和感を見逃さない感性と、それを恐れず受け入れる柔軟な姿勢である――本書はそのことを確かな説得力をもって伝えてくれます。
コラボレーションにおいて重視すべき3つの視点
アウトサイダーであるとか、「僕と君とは違う」と認めるからこそいい情報が入ってくるということで、人間関係のつくり方と情報を入手する経路のつくり方はすごく似ている。そしてそのつくり方は自由でいい。
藤原ヒロシ氏は、人間関係の築き方と情報の受け取り方には共通点があると述べています。重要なのは、自分と他者が「異なる存在」であるという前提を受け入れる姿勢です。アウトサイダーであることを肯定し、距離や違いを尊重することで、かえって新しい情報や価値が自分のもとに自然と流れ込んでくるという考え方です。
これは、あらかじめ設定された枠組みに依存しない柔軟なネットワーク形成の考え方であり、情報収集や人脈づくりにおいても、形式にとらわれない自由なアプローチが有効であることを示唆しています。 こうした発想は、現代のビジネスにおけるコラボレーションの在り方にも応用可能です。
本書では、藤原氏の実践をもとに、協働において重要となる3つの視点が整理されています。これは、共同で企画やプロジェクトに携わる人だけでなく、外部パートナーと連携して新しい価値を生み出そうとするあらゆる立場のビジネスパーソンにとって有益な視点です。
藤原ヒロシ氏の名前が持つ影響力は、コラボレーションの現場においても具体的な効果を発揮しています。たとえば企業が藤原氏と協業する際、その知名度や実績がプロジェクト推進の後押しとなり、社内の意思決定を円滑に進めやすくなることがあります。上層部の承認を得やすくなるといった効果は、いわば“ネームバリューが持つ推進力”といえるでしょう。
スターバックスとの事例にも見られるように、著名なクリエイターとの協業は、単なる話題性を超え、企業内部の動きを加速させる役割を担うことがあります。
本書では、藤原氏の実践に基づき、コラボレーションにおいて重視すべき3つの視点が示されています。これは、共同開発やブランド提携に携わるビジネスパーソンにとっても、実務的なヒントとなる考え方です。
第1の視点は、「既存のものに敬意を示すこと」です。コラボレーションは、白紙の状態から新たなアイデアを生み出すだけのものではありません。相手のブランドが培ってきた歴史や価値に敬意を払い、それを理解したうえで関係を築く姿勢が、協業の質を高める重要な要素となります。藤原氏がナイキとの取り組みで見せたように、プロダクトに対する深い理解と愛着があるからこそ、価値あるアップデートが可能になるのです。新しさだけを追い求めるのではなく、「既存の価値をいかに引き出すか」という視点こそが、持続可能な関係の出発点になります。
第2の視点は、「定番を疑うこと」です。多くの人にとって完成された名品であっても、そこに違和感を見出し、再定義しようとする姿勢が、革新の種になります。藤原氏は、エアジョーダンのように長年愛され続けるプロダクトに対しても、自らの視点で「どんな変化が加えられるか」を探り続けています。
完成されたものをただ受け入れるのではなく、あえて疑い、必要であれば再構築することで、そこに新たな価値が生まれるのです。真っ白なエアフォース1といったシンプルなプロダクトにおいても、そうした発想が活かされています。
第3の視点は、「小さなひねりで大きなうねりを生むこと」です。これは、藤原氏のプロダクトづくりにおける特徴的な手法であり、ビジネスにおけるブランディング戦略にも通じる考え方です。素材、色、ロゴの配置など、ディテールに最小限の変更を加えるだけで、そこにストーリーが加わり、プロダクトに深みと共感が生まれます。大きな変化ではなく、“意味のある微差”を加えることで、結果として市場に大きな反響をもたらすことが可能になるのです。
このような藤原氏のアプローチは、従来の「言語的なマーケティング」、すなわち言葉による訴求とは異なる「非言語的なマーケティング」の可能性を示唆しています。説明ではなく、感性や文脈、体験を通じて価値を伝える。そうした手法は、顧客に「語らずして伝える力」を与え、ブランドと深い関係性を築く起点となります。
コラボレーションは、単なるリソースの共有ではなく、価値観と物語の接続によって成立する行為です。本書は、その本質を丁寧に掘り下げ、現代のビジネスにおける“共創”の意義と可能性を改めて示してくれます。
語るべきストーリや背景を持つことで、単なる商品が文化的文脈を持ったコンテンツへと昇華されていきます。 藤原氏のこうしたアプローチは、従来の言語的マーケティングとは異なる「非言語的なマーケティング」の可能性を提示しています。機能やスペックを言葉で説明するのではなく、デザインや文脈、物語を通じて価値を“感じさせる”手法です。それは、
一見すると戦略的ではないように見えながらも、結果として非常に強いブランド共感と支持を生み出しています。 本書が描くコラボレーション論は、現在のビジネス環境において、単に合理的な「提携」や「分業」にとどまらない、感性と関係性に基づいた創造のあり方を示しています。他者への敬意と、違和感を受け入れる柔軟な感性。
そして、語るべき小さな「ひねり」。これらが、これからの協働において求められる視点であることを、本書は教えてくれます。










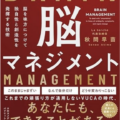




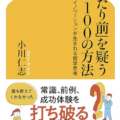


コメント