フュージョンストラテジー―リアルタイムデータとAIが切り拓く産業の未来
ビジャイ・ゴビンダラジャン, ベンカット・ベンカトラマン
東洋経済新報社

フュージョンストラテジー―リアルタイムデータとAIが切り拓く産業の未来(ビジャイ・ゴビンダラジャン, ベンカット・ベンカトラマン)の要約
『フュージョン戦略』は、物理資産からデジタル能力への競争優位のシフトを背景に、産業界がリアルタイムデータとAIを融合させ、製品・サービス・ビジネスモデルを再構築する道筋を示します。三種のデジタルツインやデータオントロジーを活用し、フュージョン製品・サービス・システム・ソリューションを通じて、持続的な顧客価値を創出することが求められているのです。
リアルタイムデータとAIが切り拓く競争優位の新法則
データ主導の世界においては、独自のデータグラフと差異化されたビジネスアルゴリズムを有する企業だけが、競争を制することも明らかになってきている。(ビジャイ・ゴビンダラジャン, ベンカット・ベンカトラマン)
現代の産業界は、かつてないほどの変革の波にさらされています。グローバル化、サステナビリティへの対応、人材不足、そして何よりも急速に進化するデジタル技術への適応という課題に直面しているのです。これまでのように、物理的資産や過去の経験だけでは競争に勝てない時代が到来しています。
こうした中、産業界のリーダーたちは、変化を恐れず、新しい視点で自らのビジネスを再定義する必要に迫られています。 フュージョンストラテジー―リアルタイムデータとAIが切り拓く産業の未来は、そうした時代の要請に応える形で登場した、極めてタイムリーかつ示唆に富んだ一冊です。
著者のビジェイ・ゴビンダラジャンとベンカット・ヴェンカトラマンは、それぞれ戦略とイノベーション、情報システム分野の世界的権威であり、本書を通じて産業界に向けた明快なロードマップを提示しています。
本書が伝えようとしている核心的なメッセージは、競争優位の源泉が物理的資産からデジタル能力へと移行しているという事実です。これまで企業は工場や設備、在庫などを武器に競い合ってきましたが、今やセンサー技術、AI、クラウドコンピューティングの進化により、リアルタイムでデータを収集し、それを洞察に変える能力こそが成功の鍵となっています。
この新たな競争環境において、著者らが提唱するのが「フュージョン戦略」です。これは、製品を製造・運用する物理的な能力と、そこから生まれるデータを活用するデジタル能力を高度に統合することによって、企業価値を最大化しようとするアプローチです。単なる技術導入ではなく、事業の根本的な変革を伴う戦略的な取り組みなのです。
その中核にあるのが「三種のツイン」の概念です。プロダクトツイン、プロセスツイン、パフォーマンスツインという3つのデジタルツインを連携させることで、設計から製造、実運用に至るまでの製品のライフサイクル全体をリアルタイムで把握し、最適化することが可能になります。これによって、企業はより迅速かつ的確に意思決定を行い、新たな顧客価値を創出できるのです。
リアルタイムデータは、その多様性と複雑性ゆえに、従来の分析手法では十分に活用しきれません。本書では、その課題を解決する手段として、データオントロジーの構築と拡張が強調されています。オントロジーとは、データに含まれる要素やその関係性を体系的に整理・定義する枠組みのことです。
たとえば、自動車業界では「車両の位置情報」「走行目的」「利用者の嗜好」「天候条件」など、さまざまな視点からのデータをつなぎ合わせることで、より高度なモビリティサービスを実現できます。 このようなデータの意味づけを明確にすることで、AIやアルゴリズムが文脈を正しく理解し、より精度の高い予測や提案を可能にします。
つまり、データオントロジーは単なる技術的な基盤ではなく、ビジネス価値を引き出すための戦略的資産でもあるのです。産業界がこのオントロジーの設計と活用に投資を惜しまないことが、競争力を左右する重要なポイントとなってきています。
フュージョン戦略の4つのベクトル
いまこそ、産業界企業は、フュージョンの未来を構築すべきである。これまでは、規模、設計、特許、品質、顧客満足度といった、有形資産を基盤とした優位性で勝利を収めてきた。これらは今後も重要ではあるものの、デジタル技術が産業界に変革をもたらすとき、フュージョン戦略が新たな次元を切り拓いてくれるのだ。
本書では大規模言語モデル(LLM)や生成AIの可能性にも言及されています。機械の故障予測や原因分析、さらには再設計の提案まで、AIが担う役割は今後ますます大きくなると予測されます。AIは、単なる業務効率化の手段にとどまらず、企業の意思決定プロセスそのものを進化させる力を持っているのです。
そして、こうした変革の推進に欠かせないのが、著者が強調する「4つの価値ベクトル」です。物理製品にデジタル技術を統合する「フュージョン製品」、接続された製品を通じたサービス提供「フュージョンサービス」、製品とサービスを融合させて包括的な価値を提供する「フュージョンシステム」、そして全体的な顧客体験を構築する「フュージョンソリューション」。
これらは、企業が提供価値を再構築するための新たなフレームワークであり、今後の産業戦略の中核を成すものです。 この4つのベクトルを活用するためには、データ分析の深化が不可欠です。記述的分析に始まり、診断的分析、予測的分析、そして処方的分析へと進化するデータ活用のプロセスは、企業がリアルタイムで変化に対応し、的確なアクションを実行するための礎となります。
いまこそ、産業界企業はフュージョンの未来を構築すべきときです。これまでは、規模、設計、特許、品質、顧客満足度といった、有形資産を基盤とした優位性で勝利を収めてきました。これらの要素は今後も重要ではありますが、デジタル技術が産業界に変革をもたらす現代においては、フュージョン戦略が新たな次元を切り拓く鍵となるのです。
企業がフュージョン戦略を取り入れた暁には、自社のアルゴリズムが製品、プロセス、サービスの提供形態に磨きをかけ、データネットワーク効果を最大限に活用できるようになると著者は指摘します。 フュージョン戦略こそが、産業界の変革を推進する原動力なのです。工業化時代の末期に完成した既存の戦略を少しずつ変えるだけでは、十分な効果は期待できません。
フュージョンプロダクト戦略が、産業分野でより理解され、重要になっていくにつれ、既存企業はこれまで以上に社内の部門横断的な変化を受け入れ、サプライヤー、顧客、パートナーとの企業横断的な関係を再構築することが求められます。
新たな競争優位は、使用中の製品からモジュールを納入したサプライヤーにいたるまで、バリューチェーン全体にわたって始めから終わりまでデータを追跡できる可視性にあるのです。 優れた機械の核となるアイディアは、自動車に限らず、現場でリアルタイムデータを追跡・収集可能な多くの産業機械に適用できます。
たとえば、石油・ガス産業では、機器についたさまざまな種類の錆の高解像度画像を使って、故障の可能性と期間の予測モデルを訓練でき、シュルンベルジェやハリバートンなどの企業は、機器の改良に役立てることができるはずです。同様に、さまざまな油田の地震データの画像化によって、シェル、エクソン、アラムコなどが石油探査の経済を再定義できる可能性もあります。
別の業界では、スマートガラスを開発するビュー社が、太陽光の強さに応じてガラスの透過度を自動調整することで、オフィスビルのエネルギー効率を飛躍的に高めています。同様に、コーニングは、スマートフォンの落下による破損を防ぐために、ゴリラガラスの衝撃データを大量に収集し、次世代製品の設計に活用しています。
自動車は、フュージョンプロダクトの最も明快な実例として、以下の4つの本質的要素からなる産業機械の未来像を示唆しています。
第1に、リモートかつリアルタイムでパフォーマンスを追跡でき、ネットワーク効果をもたらす製品。第2に、記述的・診断的・予測的・処方的の4つの分析を統合的に活用するAIベースのビジネスアルゴリズム。第3に、それらの分析に基づいたパーソナライズされた価値を顧客に即座に提供する能力。そして第4に、AIの活用により次世代製品の開発を持続的に推進する力です。
フュージョンプロダクトの価値は、短期的な非効率の解消だけでなく、長期的な生産性向上を通じて、顧客に持続可能なメリットをもたらします。たとえば、ダウンタイムの削減や、リアルタイムのフィードバックをもとにした即時のアップグレード、データ主導の製品改善など、アナログ時代には存在しなかった価値創出の連鎖が可能となるのです。 さらに、この新たな
製品カテゴリーを収益化する方法として、3つのアプローチが挙げられます。1つ目はプレミアム価格戦略です。テスラのように、自社製品のパフォーマンスや信頼性を具体的なデータに基づいて訴求することで、価格に見合う価値を顧客に納得させることができます。
2つ目は、データを活用したパフォーマンス契約であり、リアルタイムの製品稼働状況に基づいたサービスレベルの保証を提供できます。UPSやハーツといった法人顧客にとっては、これは非常に魅力的な提案となります。
3つ目は、製品から得たデータをもとに新たな分野に進出することです。たとえば、テスラがドライバーの運転データを活用して革新的な自動車保険を展開しているように、企業はデータの再活用を通じて、隣接する産業分野に新たなビジネスモデルを構築することが可能になるのです。
これからは、機械がデジタル化され、プロセスが合理化され、サービスの提供はソフトウェア、データ、分析によって強化されていきます。そのような時代には、戦術的な施策や個別の技術導入だけではなく、戦略的で統合されたアプローチこそが真に効果的であり、持続的な競争優位をもたらすのです。
加えて、フュージョンシステムをめぐる競争を制するために最も効果的なアプローチは、顧客業務に深く組み込まれたデータグラフと、三種のデジタルツインの動的な相互作用を戦略的に活用することです。
こうした統合が実現できなかった場合、顧客価値の中心が第三者のサービスプロバイダーへと移行してしまい、自社の立場が脅かされるリスクが高まります。すなわち、顧客と製品とのつながりを深め、持続可能な価値提供を可能にするためには、データとツインを連動させたフュージョンシステムの構築が不可欠なのです。
データとAIは今すぐ取り組むべき!
目覚ましい結果を求める競争では、データと分析を活用して、サービスの質を高め、顧客の収益性を向上させ、自社の組織を顧客業務に深く組み込ませることに焦点を当てることが大切だ。
優れた機械の競争において、最終的に勝利するのはデジタルファーストのアーキテクチャを備えた企業です。これは単なるテクノロジー導入の話ではありません。製品の性能を最大化し、顧客の課題を解決するという目的のもと、先端技術の融合をいかに戦略的に取り入れるかが問われているのです。そのためには、今後の成長と競争優位を見据えた明確なロードマップを描き、そこに沿って継続的な投資と組織改革を進めていく必要があります。
競争が激しさを増す中で求められるのは、データと分析を活用して、顧客の業務に自社の組織を深く組み込ませ、サービスの質を向上させることです。これにより、自社は単なる製品供給者から、代替困難な価値創出パートナーへと進化できるのです。
スマートシステム間の競争を勝ち抜くには、相互接続されたエコシステム内での自社の役割を見極め、柔軟にポジションを変えながら、迅速かつ巧みにデータフローを設計・管理することが不可欠です。
カスタマイズ化が進む時代においては、リアルタイムの顧客ニーズに対応できる能力が決定的な差別化要素となります。そのためには、生成AIと深い業界知識を組織内に内包し、個別ニーズに即応するソリューションを提供する体制を整えることが求められます。
経営者は先送りするのをやめ、今すぐ決断すべきです。データとAIは「未来の話」ではなく、「今この瞬間に取り組むべき現実」です。数多くの企業のCEOたちと著者たちが対話を重ねる中で浮かび上がってきたのは、彼らがデジタルの破壊的影響を確実に理解し、すでに新たな秩序への移行を見据えて行動しているということでした。デジタルファーストへの転換は、経営幹部の間でも共通の認識となりつつあります。
意見の相違があるとすれば、それは「いつ」「どのようなスピードで」「どの資源を再配分するか」に関する判断だけです。従来の能力への依存をいかに早く脱し、新たな競争優位の構築に向けて動き出すか。もはや、先延ばしにできる課題ではありません。人材ポートフォリオの刷新を含む変革のスピードこそが、次なる産業地図における位置づけを左右することになるのです。
今求められているのは、過去の延長線上に安住することではなく、未来に向けてフュージョンアプローチを選び取る明確な意志です。現在のコアコンピタンスが、明日の成功を保証するものとは限りません。まさに今、未来を形づくる一歩を踏み出すときなのです。
加えて、顧客価値を一層高めるには、デジタル技術を活用し、競合他社や異業種のエコシステムとも連携しながら、データネットワーク効果を引き出す発想が不可欠です。特に、自前主義や単独企業中心の思考が根強い日本の製造業こそ、この「つながる」価値を再認識しなければなりません。
製品の利用状況だけでなく、周辺環境データや顧客プロファイルなども含め、リアルタイムかつ多面的にデータを取得・分析することによって、真のハイパーパーソナライズが実現されます。これを可能にするには、外部企業が保有する情報を活用した包括的なデータグラフの構築が不可欠です。
そして、そのためには新製品や新サービスの企画段階から、こうした連携と接続性を前提とした「フュージョンファースト」の発想をアーキテクチャに組み込む必要があります。連携を前提とした設計思想こそが、今後の持続的な競争優位の土台となるのです。













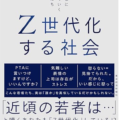
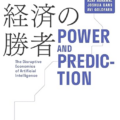
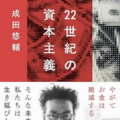


コメント