きみに冷笑は似合わない。 SNSの荒波を乗り越え、AI時代を生きるコツ
山田尚史
日本経済新聞出版
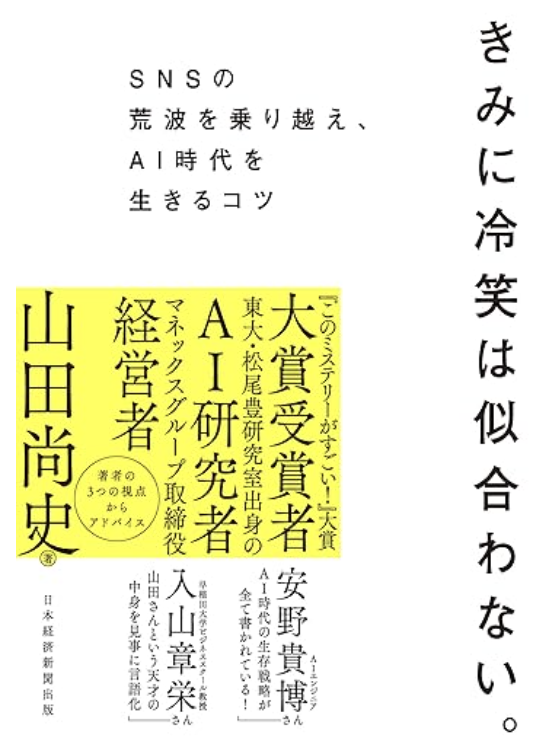
きみに冷笑は似合わない。SNSの荒波を乗り越え、AI時代を生きるコツ (山田尚史)の要約
山田尚史氏の『きみに冷笑は似合わない。』は、AIの進化やSNS社会の冷笑文化に流されず、私たちが「人としてどうあるか」を問い直すための羅針盤のような一冊です。テクノロジーの進歩は止められませんが、最後に未来を決めるのはAIではなく、私たち自身の生き方です。効率や冷笑に支配されるのではなく、時間をかけて信頼を築き、習慣を重ね、行動で示す。その営みこそが、AI時代を生き抜く本当の力になるのです。
AI時代はEQが重要なスキルになる!
人と人とのつながりや納得感といった、IQではなくEQ(心の知能指数)で価値を出す部分でしか、人間の働く余地はなくなってしまうということになる。(山田尚史)
AI技術の進化は、もはや一部の専門家だけが扱う特別な話題ではなくなっています。私たちの日常に、AIは確実に入り込みつつあり、日々存在感を高めています。数年前までは夢物語とされていた生成AIも、いまやビジネスの現場や創作活動、さらには教育の領域にまで活用され、あらゆる分野において「人間とAIの役割」が再定義されつつあります。
こうしたテクノロジーの急速な発展により、私たちは根源的な問いを突きつけられるようになりました。それは、「働くとは何か」「人間にしかできないこととは何か」といった、避けては通れない本質的なテーマです。
きみに冷笑は似合わない。 SNSの荒波を乗り越え、AI時代を生きるコツの中で、起業家であり小説家でもある山田尚史氏は、AIによる業務の代替が進むなかで「すべての働く人が、働く意義や人間の価値を再確認する必要がある」と指摘します。
実際、OpenAIのサム・アルトマンは「AIは『中央値の人間』のパフォーマンスをすぐにでも出せる」と述べています。これは、平均的なスキルではもはや競争力が保てないという現実を示すものであり、私たちが従来の「普通」を見直さなければならないことを意味しています。同様に研究者のアンドリュー・ンは、AIの処理コストの低さに着目し、人間の優位性は短期なものでしかないと指摘します。
こうした時代背景の中で、山田氏は「AIには不可能で、人間にしか果たせない仕事」として、創造性や感性、さらには他者とのつながりといった人間力を挙げています。定型的な業務の多くをAIが担うようになれば、私たちに求められるのは、より非定型で、人間独自の感情や知恵を必要とする領域へと移行していくのです。
それは単なるタスクの消化ではありません。その場の空気を感じ取り、相手の立場を想像し、自分自身の言葉で語りかける――まさに人間ならではの営みが問われる時代になっているのです。
このような視点に立つと、幅広い教養を身につけることの重要性がこれまで以上に高まります。ビジネスやテクノロジーの知識に加えて、哲学、歴史、文学、芸術といった分野に触れることは、単なる情報の蓄積ではなく、人間性や想像力、他者理解を育む土壌になります。
リベラルアーツや芸術が注目を集めているのも、そうした「人間らしさの厚み」が、結果的に判断力や創造性の質を左右するからです。
すぐに役立つ情報やスキルとは異なり、多様な作品にじっくりと触れることには、即時的なリターンはならないかもしれません。しかし、そうした体験の積み重ねによって、自分が何に心を動かされるのか、どんな価値観を大切にしているのかが少しずつ見えてきます。そしてそのプロセスを繰り返すうちに、自分が本当にやりたいこと、人生で追求したい方向性が、自然と輪郭を帯びてくるのです。
また、外見や立ち居振る舞いといった「非言語的な印象」も、信頼や安心感の形成に直結する要素として無視できません。どれだけ論理的に正しいことを語っていても、聞き手が安心して耳を傾けられる雰囲気がなければ、伝わるものも伝わらない。言葉の前に、所作が伝えるものがあるということを、私たちは無意識のうちに感じ取っています。
私自身も、こうした時代の流れを受け止め、意識的に人とのつながりを深めるための行動を取っています。学びを深めるためのコミュニティに積極的に参加したり、集合天才というコンセプトのもと、周りのスペシャリストとともに課題を乗り越えるネットワークを築いています。
さらに、移動距離を増やし、未知の場所や人に出会うことで、クランボルツ博士の計画的偶発性理論の考え方を実践するようにしています。これは一見、非効率に見えるかもしれませんが、AIには再現できない「人間らしい偶然性」や「身体感覚」を通じた発見が、未来を切り開くヒントになると感じています。
市場が成熟し、モノや情報の差別化がますます難しくなった現代において、最終的な選択の基準は「誰から買うか」「誰から学ぶか」といった、提供者そのものの魅力や信頼感へと移り変わっています。これはすなわち、スキルや情報量の優劣ではなく、「人間としてどうあるか」が競争力になる時代の到来を意味しているのです。
AIがどれほど精度の高い選択肢を瞬時に提示できたとしても、最終的にその選択を受け入れるかどうかを決めるのは、私たち人間です。そしてその判断のプロセスには、効率や論理といった数値化できる基準だけではなく、「感情」や「共感」、さらには「直感」や「余白」といった非数値的な要素が深く作用しています。
だからこそ、人間としての魅力を日常の中で磨いていくことが欠かせません。 それこそが、これからの時代を生き抜くための、もっとも確かな武器になると私は考えています。 そしてその武器は、AIではなく、私たち一人ひとりの生き方そのものに宿っているのです。
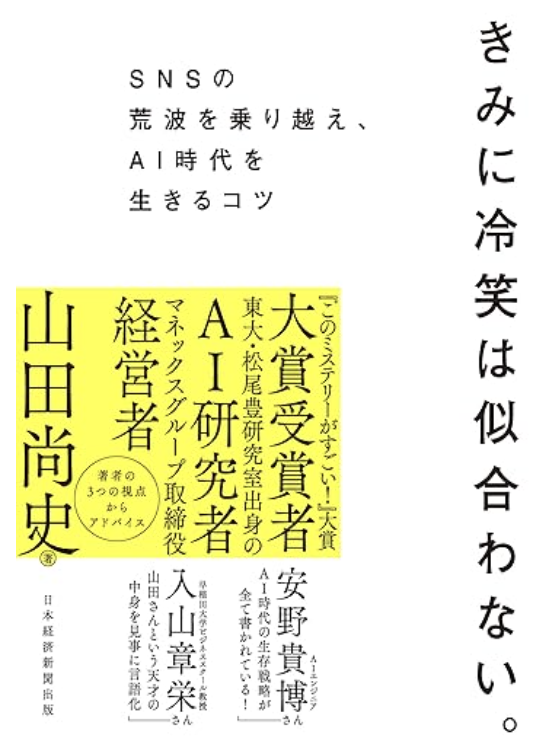
タイパを追い求めることよりも重要なこととは?
タイパにとらわれず、時間割引率を見直す。
一方で今の社会は、「タイパ(時間対効果)」が過剰に重視される傾向にあります。 いかに短時間で成果を出すか。どれだけ効率よくタスクをさばけるか。 そうした“スピードの価値”が、まるで絶対的な正解かのように、ビジネスや学びの現場を支配しています。
即効性のあるアウトプット、目に見える短期成果、わかりやすい実績。 こうしたものにばかりスポットライトが当たり、「早ければ早いほど良い」という価値観が、半ば無自覚に私たちの思考に染みついているのです。
けれども──そのスピード至上主義は、私たちをどこに連れて行こうとしているのでしょうか。 成果を焦るあまりに、プロセスが軽視され、深く考える余白が奪われていく。 たとえば短時間で資料を量産できたとしても、その中身が薄ければ、意思決定はむしろ危うくなる。 AIを活用し、「とりあえずやった」という作業が増えれば、組織は次第に疲弊し、やがて燃え尽きていくのも時間の問題です。
この背景には、「時間割引率(Time Discount Rate)」という概念が関わっています。 私たちはつい、将来得られるかもしれない大きな成果よりも、今すぐ得られる小さなリターンに飛びついてしまう。 目先のメリットを優先し、本来時間をかけるべきことに待てなくなる傾向です。 現代のように、即レス、即断、即成果が求められる社会では、この時間割引率が極端に高くなりがちです。
その結果、「いまこの瞬間に効くこと」ばかりを選び、「少し先に効くもの」「ゆっくり効いてくるもの」を敬遠してしまう構造ができあがってしまっているのです。 しかし、。本当に価値あるものは、時間をかけなければ育ちません。
信頼、成長、関係性。いずれも、即席では手に入らないものばかりです。 自分の足で歩き、何度も転びながら、それでも歩き続けたその先にこそ、本当の成果がある。 そして私は、あえて遠回りするような時間の使い方こそが、長い目で見ればもっとも効果的であることを、自分の人生から学んできました。
一方で、SNSの世界にはまた別のプレッシャーがあります。 誰かが夢を語れば「意識高い系」と揶揄され、失敗すれば「それ見たことか」と嘲笑され、成功すれば「どうせ裏がある」と疑わてしまいます。挑戦する者を監視し、足を引っ張ろうとする冷笑が、まるで空気のように社会に蔓延しています。
著者は、この冷笑文化の本質を鋭く見抜いています。冷笑的な態度は、一見すると知的で冷静な視点のように映るかもしれません。しかし実態は、「何かを批評している自分」に酔いしれているだけで、具体的な行動は何一つ起こさない、きわめて不毛な姿勢なのです。
匿名で他人を遠くから評しても、自分の人生は一歩も前に進みません。 大切なのは、他人をどう見るかではなく、自分がどう動くか。 批評家ではなく、実践者になること。 手を動かし、現場で信頼を積み上げていくこと。 それが山田氏が一貫して伝え続けているメッセージです。
この姿勢は、著者が紹介しているDeNA会長・南場智子氏が提唱する「コトに向かう」という考え方にも通じます。 信頼は、言葉やパフォーマンスでは生まれません。 実際に課題に向き合い、解決へと導いた行動の積み重ねでしか、築かれないのです。
SNSという舞台でも同じです。 2024年の時点で、世界のSNSユーザーの平均利用時間は1日143分にも及びます。 最も長いブラジルでは、なんと1日4時間にもなると言うのです。 これは、人生の16%をSNSに費やしている計算になります。 その時間が、本当に自分の価値を高めることにつながっているのか?私たちは一旦立ち止まって見直すべきタイミングに、来ているのではないでしょうか。
実際、成果を出し続けている人たちは、SNSに過剰な自己演出を持ち込みません。 バズらせるために無理をしません。 むしろ、等身大のままで行動し、その結果をひたすら積み重ねています。 成功も信頼も、演技や演出では築けません。 確かな行動と、その積み重ねだけが、周囲からの信頼を生み、やがて静かに評価となって返ってくる。 山田氏の語るメッセージは、冷静で、誠実で、だからこそ力強いのです。
SNSの冷笑に流されず、タイパに支配されず、 あえて時間をかけ、自分の手で未来を創り出していくこと。 その誠実な営みこそが、AI時代を生き抜くための、人間にしかできない「本当の強さ」につながると私は考えています。
かつての私も、SNS上ではドリームキラーによる冷笑やネガティブな言葉に直面することが少なくありませんでした。 しかし、そうした声に振り回されるのではなく、応援してくれる方々の言葉を信じ、その想いを行動のエネルギーへと変えてきました。 その結果、数多くの挑戦を実際に形にし、さまざまな成果へと結びつけることができたのです。
少なくとも環境のせいにし続けて行動 を起こさないのでは、何も変わらない。
山田氏は、こうした社会的プレッシャーの中で「Weの視点」を持つことの重要性を強調しています。個人最適ではなく、組織全体の最適を志向する「We思考」の人材は、自然と信頼を集め、組織の中核を担うようになります。これは単なる協調性ではなく、主体的に課題を捉え、共に解決していくリーダーシップの在り方です。
さらに著者は「自己責任主義の功罪」にも触れています。「他人を変えるより、自分の行動を変える方が早い」という一節は、時代のスピード感を考えれば極めて現実的です。他人に期待するより、自ら変わることで現実を動かす。この姿勢がストレスを減らし、成果を確実に前進させるのです。
そして山田氏は、このブログでもお馴染みのジェームズ・クリアーのAtomic Habitsやベンジャミン・ハーディのFull Powerといった書籍を引き合いに、アイデンティティと習慣形成の関係についても言及しています。
自己変革に本当に必要なのは、過激な自己洗脳や劇的な環境の変化ではありません。むしろ、日々の小さな習慣をコツコツと積み重ねていくことです。両書ともに、私自身の思考と行動を確実に変えてくれた書籍であり、この二冊を紹介している著者のセンスには強く共感を覚えました。(ジェームズ・クリアーの関連記事、ベンジャミン・ハーディの関連記事)
「自分はこういう行動をする人間になる」とアイデンティティを明確にし、そのために必要な行動を日常に組み込むことが何よりも大切なのです。行動が積み重なれば、それは習慣となり、やがて自分を変えることができます。
私自身も、この考え方を実践してきました。かつてアルコール依存に苦しんでいたとき、理想の自分――すなわち著者になるというアイデンティティを明確に描き、悪い習慣を良い習慣へと置き換えることを意識しました。お酒を飲む時間を学び(インプット)と発信(アウトプット)の時間へと転換したことで、最終的には夢であった出版を実現することができたのです。
この経験からも実感していますが、習慣とは一見すると小さな積み重ねにすぎないように見えるかもしてません。しかし、その継続こそが未来を形づくる大きな力を持っていると、私は確信しています。
本書は、AIの進化やSNS社会の冷笑文化に流されず、私たちが「人としてどうあるか」を問い直すための羅針盤のような一冊です。テクノロジーの進歩は止められませんが、最後に未来を決めるのはAIではなく、私たち自身の生き方です。
効率や冷笑に支配されるのではなく、時間をかけて信頼を築き、習慣を重ね、行動で示す。その営みこそが、AI時代を生き抜く本当の力になるのです。
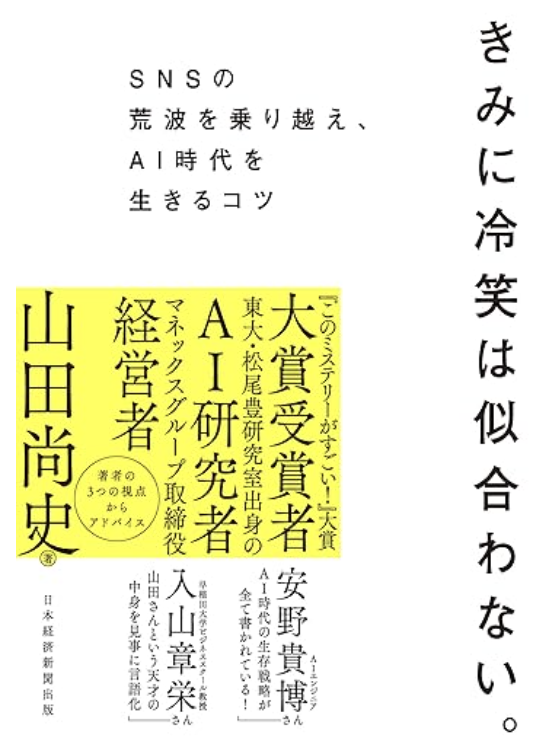









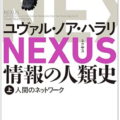





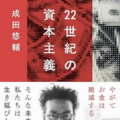


コメント