全社デジタル戦略 失敗の本質
ボストン コンサルティング グループ
日経BP
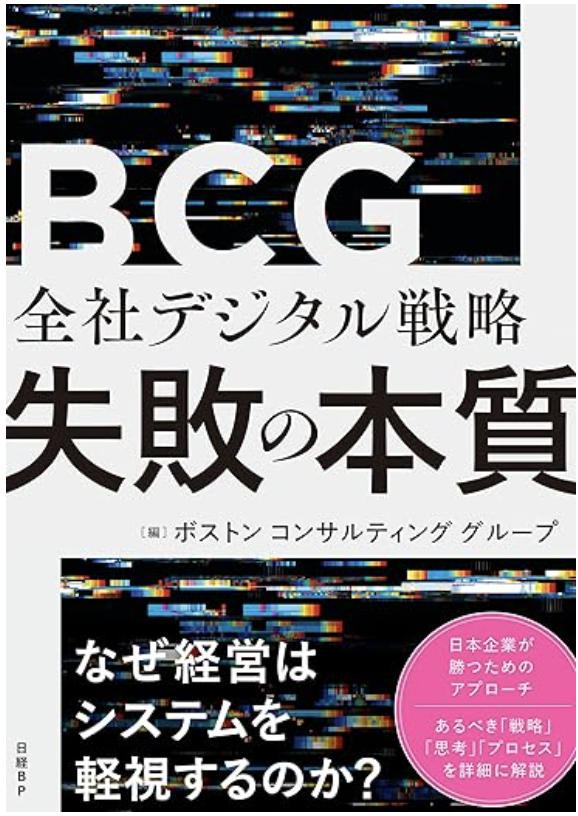
全社デジタル戦略 失敗の本質(ボストン コンサルティング グループ)の要約
BCGは、日本企業におけるIT・デジタル投資の失敗要因を、組織文化や意思決定構造、システム老朽化など多角的に分析し、成功に向けた経営のマインドセットと実践方法を本書で示しています。経営層のリテラシー不足や現場任せの体質が変革の壁となる中、企画構想段階からの主体的関与や、生成AI・自動化技術を活用した業務再設計が重要とされます。DXの本質とは、企画構想、要件定義、そして実装における行動変容にあるのです。
日本企業のIT投資が失敗する理由
日本企業がシステム投資を行う際の生産性の問題だ。欧米企業の3倍の工数がかかるという非効率さである。その分、日本企業は無駄なシステム投資をしてしまっているのだ。この無駄を他の投資に回せるようにしたい。(ボストン コンサルティング グループ)
IT・デジタル投資は、多くの企業にとって避けては通れない経営の要所でありながら、現実にはその多くが期待通りの成果を上げられていないのが実情です。特に日本企業においては、過去の成功体験や業務慣行が足かせとなり、変化への適応が後手に回る傾向が強く見られます。
ボストン コンサルティング グループも、欧米企業と比べて3倍のコストと工数を要するという現状を指摘しています。 日本企業や日本人は、真面目で規律を守り、品質を重視し、他者のために尽力するという文化的美徳を備えています。それは本来、変革を推進するうえでの強みとなるはずですが、現実にはその美徳が柔軟性やスピードを阻む構造的な障壁ともなり得るのです。
IT・デジタル施策において求められるのは、単なる業務効率化ではなく、構造的な見直しと意思決定の再設計です。にもかかわらず、その前提が共有されないままプロジェクトが進行してしまえば、目的の曖昧な機能追加や、効果の見えにくい投資に陥り、生産性をむしろ下げてしまうという逆説が生じます。
とりわけ、経営層がIT・デジタルを「専門領域」として現場に任せきりにしてしまえば、組織の本質的な変革は進みません。経営と現場が同じビジョンを持ち、投資の目的を明確にし、ビジネスの構造と一体で捉えることが求められます。
また、「2025年の崖」と呼ばれる課題も、すでに明らかになっています。これは、老朽化しブラックボックス化したレガシーシステムがDX推進を阻み、企業の競争力そのものを危機に晒すという警鐘です。加えて、IT人材の不足がそれに拍車をかけており、全体としての構造改革が急務となっています。実際、調査でも、継ぎはぎで構築されたシステムが複雑化し、新たなビジネス展開の足かせとなっている企業が多数確認されています。
2025年崖の正体は、単なる技術的な遅れではなく、経営が変革の主導権を持たず、デジタルを真に活用する文化や体制が整っていないという構造的問題です。
こうした状況に対する示唆を与えてくれる一冊が、ボストン コンサルティング グループによる全社デジタル戦略 失敗の本質です。本書は、IT・デジタル投資における失敗の構造と、そこから導かれる教訓を多角的かつ論理的に整理しています。パンデミック、インフレ、社会構造の変化といったマクロ環境、さらに少子高齢化や技術者不足といった日本固有の課題に着目し、単なる成功事例ではなく、失敗の実例にフォーカスしている点が特徴です。
本書が優れているのは、単に「どうやれば成功するか」を語るのではなく、「なぜ失敗するのか」「その本質は何か」を突き詰めている点にあります。失敗の分類、業務プロセスごとの注意点、ビジネスとデータの整合、意思決定とデータの関係性などを体系立てて解説しており、実務に直結した知見が得られます。
特に重要なのが、初期段階である企画構想フェーズです。この段階で、自社が目指す成果とそれを支えるシステムの役割を正しく定義しなければ、要件定義や設計段階で軸がぶれ、結果として「完成したのに使えない」「一部業務しか対応できない」「データが分断され全体最適が困難」といった事態に陥ります。
この一連のプロセス──企画構想、要件定義、そして実装という各フェーズにおいて重要なのは、ベンダー任せにせず、自社として何を成し遂げたいのか、そのためにどのような要件が必要なのかを主体的に定義し続ける姿勢です。各フェーズでの進捗を自社の基準で検証し、想定と現実のギャップを継続的に見直していくことで、はじめて投資の最適化が実現されます。
さらに深刻なのが、移行時のデータトラブルによる本番稼働の停止です。システムが動いていても、実データとの不整合により在庫や売上の把握ができず、事業継続に支障をきたすケースも少なくありません。これは単なるシステム不備ではなく、ビジネスとデータの整合を軽視した意思決定構造そのものの問題なのです。
こうした失敗を未然に防ぐには、まずはビジネスポリシーとデータポリシーを明確にし、それに基づいてシステムと業務を統合的に設計していくことが求められます。データは単に記録するためのものではなく、意思決定の根拠となり、戦略の方向性を支える資産です。
だからこそ、「どのようにデータが生成され、どこで誰がそれを活用し、どう判断がなされるか」という全体像を共有し、意思決定構造を見直す必要があるのです。
ITにおいても経営者のリーダーシップが重要
筆者の仮説として、「デジタル領域においても小さなトライアルの積み重ねが必要」「アジャイルが重要」という言葉に踊らされて取り組みを小さく始めてしまうがゆえに、何を目的に、何を捨ててでも効果を出すべきなのかが見えなくなっているのが実態だと考えている。経営が失敗を恐れて、まず小さな動きをとってしまいがちなのは、IT・デジタルに対するビジネス側のリテラシーが低いからこその選択なのだと考える。
こうした現象の背景には、経営層のIT・デジタルに対するリテラシーの低さがあります。失敗を恐れるあまり、安全圏から小さな動きを繰り返す。これは慎重さではなく、理解不足ゆえの回避行動とも言えます。経営の意思が伴わない小さな成功は、組織の構造や文化を変える力にはなりません。むしろ、変革への本質的な覚悟を先延ばしにする温床にもなりかねないのです。
解決策として提案されているのは、経営層が自ら針路を示し、主体的に関与すること、投資を“手の内化”し、その目的や期待成果を明確にすること、さらに全社的な人材育成と業界・国を超えた連携体制の構築です。
IT・デジタル投資を成功に導くためには、経営としてのマインドセットもまた問われます。BCGでは以下の4つのマインドセットを身につけることが重要だと言います。
まず第1に、すべてのIT・デジタル施策を常に自社の事業ストーリーと連動させて考えること。技術は手段であり、目的は事業の成長と価値創出にあるという原点に立ち戻る必要があります。
次に、経営自身が絶えず学び、関心を持ち続ける姿勢です。変化のスピードが加速する中で、現状維持の姿勢は確実に取り残されるリスクをはらんでいます。
さらに、任命のあり方が成否を分ける場面も少なくありません。IT責任者やプロジェクトリーダーの人選は、単なる形式ではなく、経営としての意思の表明であり、その責任は経営層が自ら負うべきものです。
最後に求められるのは、大胆な意思決定と、細心の状況観察の両立です。構想においては大胆に、実行においては慎重に。そうしたバランス感覚こそが、変革を持続可能なものにします。
海外では、IT人材が専門人材として市場で認識されており、職種としての流動性が高く、専門性を磨きやすい環境が整っています。これにより、IT人材のキャリアパスが明確であり、企業内の情報システム部門においても、業種や企業を超えて転職し、知識やスキルを横断的に蓄積・活用する文化と仕組みが存在します。
たとえばERP導入においても、専門家が業界を超えて経験を重ねることで、その知見がより広範囲にわたって活かされる傾向があります。一方で日本では、キャリアの閉鎖性や社内異動中心の人事制度が、専門性の蓄積や共有を阻害している現実があります。
実際に、トップがIT・デジタルに対して明確な思いを持ち、組織に方向性を示しているユニクロのような企業は、すでに着実な成長を遂げています。そして、こうした企業は今後の持続的な成長にも大きな期待が寄せられています。
もちろん、トップの思いだけで成果が得られるわけではなく、それは十分条件とは言えません。しかし、少なくとも変革を推進するための必要条件として、経営トップの姿勢と発信が問われているのです。
今後の注目点の一つとして、AIエージェントの登場も見逃せません。各種エージェントの進化は、それぞれの業務機能の高度化を加速させています。これまで企業が単純作業を低コストで外部委託してきた業務領域が、今後は自動化の対象へとシフトしていきます。
つまり、ベンダーに依存していた業務を、自社で自動化すべきコア業務として再構成する必要が出てくるということです。 この変化は、単にテクノロジーの進化にとどまらず、企業の生産性や競争力に直結する本質的な転換点を意味します。だからこそ、何を外に出し、何を自社の中に取り込むべきかという選択と集中が、これまで以上に問われるようになります。
そしてこの問いに真正面から向き合うことこそが、デジタル変革の真の出発点となるはずです。 さらに、これからの日本企業が遅れを取り戻していくためには、無駄なデータ整備や無理なシステム統合といった“正しそうに見える努力”にとらわれるのではなく、本当に意味のあるデータの整備に集中することが重要です。
そのうえで、業務効率を高めるための自動化を着実に実践し、日々の業務そのものを変えていく視点が求められます。同時に、生成AIをはじめとする先端技術を柔軟に取り入れ、事業会社自身がIT・デジタルを本業の一部として扱う覚悟と仕組みづくりが必要です。
ITは外部に依存するものではなく、自社の競争力そのものとして育てていくべき領域になっています。そして、こうした企業は今後の持続的な成長にも大きな期待が寄せられています。もちろん、トップの思いだけで成果が得られるわけではなく、それは十分条件とは言えません。しかし、少なくとも変革を推進するための必要条件として、経営トップの姿勢と発信が問われているという本書の主張に共感を覚えました。
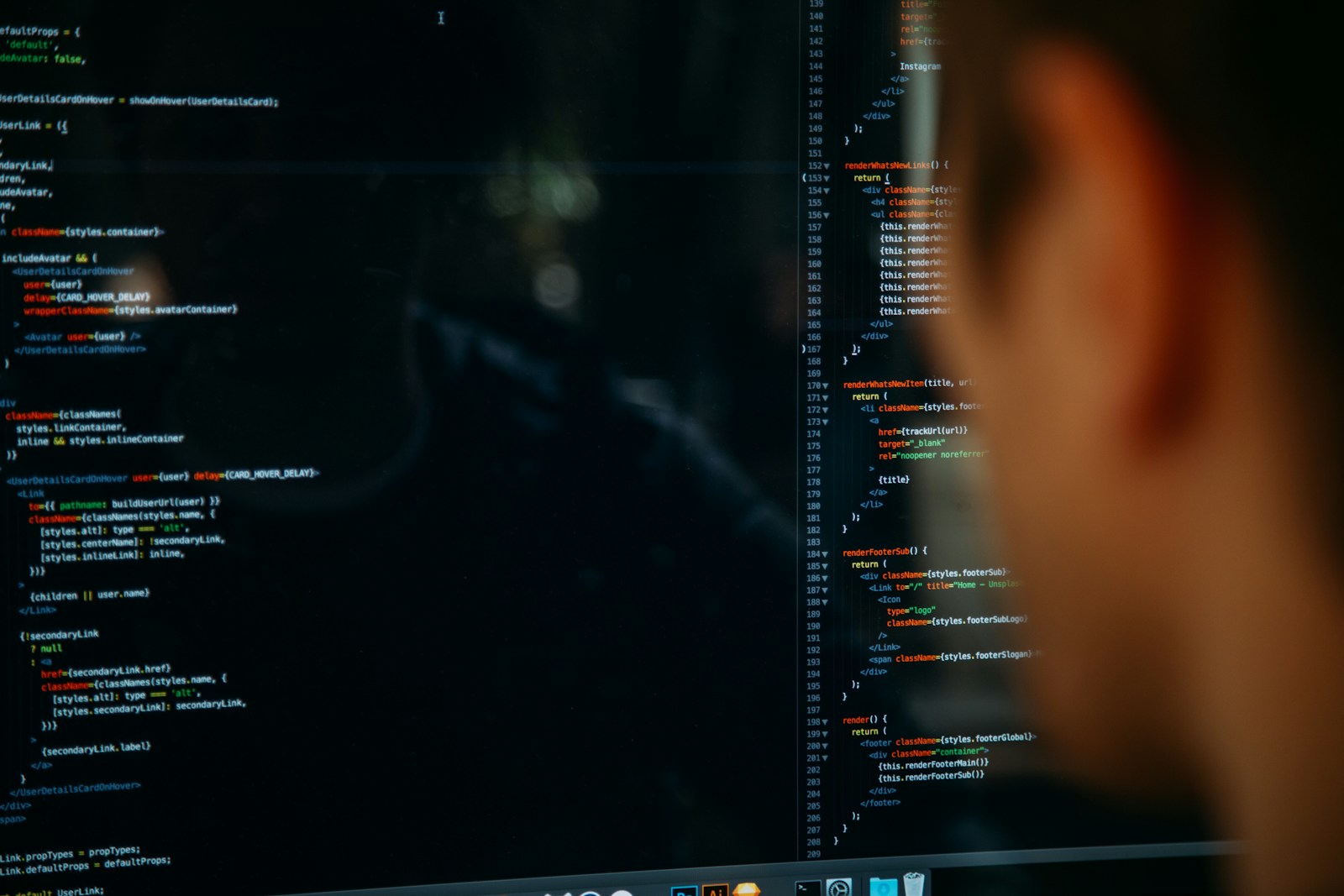




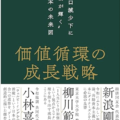




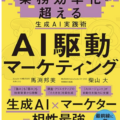
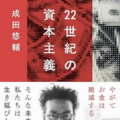




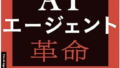
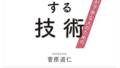
コメント