スタンフォード大学の人気教授が明かす 教養としての権力
ジェフリー・フェファー
日経BP
スタンフォード大学の人気教授が明かす 教養としての権力 (ジェフリー・フェファー)の要約
スタンフォード大学教授ジェフリー・フェファーは、善意と努力だけでは報われない組織の現実に切り込みます。『教養としての権力』では、影響力を発揮したいにもかかわらず、権力を得ることにためらいを持つ人々に対して、自己の内面と向き合い、行動を変えるための具体的な指針を提示します。本気でキャリアを築きたいなら、権力を正しく理解し、戦略的に活用する覚悟が不可欠であると説いています。
権力を得るための7つの法則
よい人が権力を手に入れるには、権力が消滅も分散もしておらず、権力の仕組みや戦略も変わっていないこの世界で成功するために必要な、長年の社会科学研究に裏打ちされた法則やルールを理解することが絶対的に欠かせない。簡単に言えば、権力の法則から逃げるのではなく、それらを受け入れる必要がある、ということだ。(ジェフリー・フェファー)
なぜ、あの人は出世するのか――その問いに、能力や誠実さだけでは説明できない現実があることを、多くのビジネスパーソンがうすうす感じているのではないでしょうか?
自分は努力を重ね、周りからも好かれ、実績も着実に出している。それなのに、組織の中では評価されず、キャリアが停滞してしまう。そこには、「正しさ」だけでは乗り越えられない壁が存在しているのです。
スタンフォード大学経営大学院の教授ジェフリー・フェファーは、そうした停滞の背景に「能力主義への盲信」と「権力への忌避」があると喝破します。善人であろうとする人ほど、オフィス政治を拒絶し、自己を抑制する。そしてその姿勢こそが、成長の足を引っ張っているのです。善意ある人が組織に影響を与えたいならば、まず「権力を持つ覚悟」が必要なのだとフェファーは主張します。
スタンフォード大学の人気教授が明かす 教養としての権力は、従来のリーダーシップ本とは一線を画します。そこにあるのは、「本物であれ」「謙虚であれ」といった耳ざわりのよい教訓ではなく、組織の中で実際に力がどのように働き、誰がそれを使いこなしているかという、冷徹で現実的な分析です。そしてその現実を直視した上で、権力を善に活用するための具体的なフレームワークが提示されている点にこそ、この書の価値があります。
著者は権力を得るためには、以下の7つの法則を身につけるべきだと言います。
法則1 自分の殻を抜け出せ
法則2 ルールを破れ
法則3 権力を演出せよ
法則4 強力なパーソナルブランドを確立せよ
法則5 ネットワークをつくれ
法則6 権力を活用せよ
法則7 成功すれば(ほぼ)すべてが許される
7つのルールは、単なる処世術ではなく、行動変容を迫るフレームです。
最も本質的なことを言うと、権力はツールである。権力もほかのツールと同様、使い方をマスターすれば、それを使ってすばらしいことも、身の毛がよだつほど恐ろしいことも、その中間のすべてのこともできる。ここで大事なのは、権力があなたの気に入らない方法で利用された実例を見て、「権力を使うのはごめんだ」と決めつけてしまわないことだ。権力は社会生活について回るのだから、そういうものだと受け入れ、活用するしかない。
法則1 自分の殻を抜け出せ
その第一歩は、インポスター症候群に打ち勝つことです。インポスター症候群とは、どれだけ成果を出していても「自分にはその資格がない」「周囲は自分を過大評価している」と感じてしまう心理状態のことです。こうした思い込みが、自己表現や権力の獲得を妨げる最大の障害になります。
必要なのは、自分を卑下する癖を手放し、ポジティブなセルフイメージを意識的に構築することです。「出しゃばると嫌われる」「評価は自然に伝わるもの」といった内面化された信念は、もはや通用しません。世界は公平でフェアではない中で、自ら切り開くべきです。影響力の武器で有名な心理学者のロバート・チャルディーニは「先に有能だと印象づけること」が良いと述べています。
成功するには、人を味方につけるための謙虚さだけでなく、傲慢さを併せ持つ必要がある。
権力を得るためには、積極的に前に出て、自分を売り込み、声を上げる行動こそが求められます。経験を積めば、必ず慣れて自信もついてきます。自己疑念を乗り越えることが、権力の入り口なのです。その際、セルフイメージや自己表現をポジティブに変えることが重要だと著者は指摘します。
法則2 ルールを破れ
さまざまな力が「ルールを守れ」「同調せよ」というプレッシャーになるが、権力への道を歩むためには、期待に背き、常識を、ルールを──ただし「ルールを破れ」という法則は別として──破らなくてはいけない。
組織や文化に根づいた「暗黙の了解」に戦略的に挑む必要があります。時にルールを破ることも、目的達成のためには正当化されます。フェファーは、『「人と違う」思いがけない行動に出て、主導権を握ることが欠かせない』という言葉で、勇気ある逸脱の価値を説きます。本書で紹介されている起業家のジェイソン・カラカニスのルール破りの行動は私たちに勇気を与えてくれます。
法則3 権力を演出せよ
「自信と魅力にあふれた、権力を持つ人物」という印象を与える方法を身につけなくてはならない。
自分を権威ある存在として演出することも不可欠です。見た目、話し方、態度、言葉の選び方すべてが、周囲の評価を形成します。成果を出していても、それを「見える形」で伝えられなければ、存在しないのと同じです。 なぜ外見が重要なのかといえば、進化心理学の観点から、顔の特徴や非言語的なシグナルは、生存や繁殖に有利な適応行動を導くための手がかりとして、私たちの脳に深く組み込まれているからです。
私たちは意識せずとも、相手の顔立ちや態度、声のトーンやポーズ、身だしなみなどから「この人は信頼できるか」「能力があるか」を瞬時に判断しています。つまり、外見的な演出は単なる印象操作ではなく、進化の過程で形成された反応を活かした戦略なのです。
「自信や怒りを表そう」という勧めは、「弱さを見せて相手の心を開こう」という、よく聞くリーダーへのアドバイスとは相容れません。どちらのアドバイスに従うべきかは、あなたが権力と成功を求めるのか、部下との距離を縮めたいのかで決めればよいでしょう。どちらも実行可能ですが、フェファーが数々の研究から読み解いた結論は明快です。すなわち、権威と成功の印象を与えて権力を手に入れた方が、一般によりよい結果をもたらすということです。
パーソナルブランディングとネットワーク効果が重要な理由
パーソナルブランドの「フライホイール(弾み車)効果」がよく表れている。あるきっかけが別の何かにつながり、そしてものごとが回り始める。
法則4 強力なパーソナルブランドを確立せよ。
権力を得たければ、強力なパーソナルブランドの確立が求められます。仕事そのものではなく、あなた自身が語られる存在になる必要があります。パーソナルブランドと物語、そして公私両面を織り合わせた説得力のあるストーリーを用意したら、次はそれを広める段階です。
ここで重要なのが、ブランドの「フライホイール(弾み車)効果」です。あるきっかけが別の何かにつながり、連鎖的に注目と信頼を高めることができます。あなたのブランドに合う媒体を選び、適切な発信を行うことも戦略の一部です。
私自身、書籍を執筆することで、自分のブランドを高めることができました。ただのサラリーマンだった私が本を書くことで、一歩抜きん出た存在に変わることができたのです。著者という肩書を得たことで、初対面の相手にも信頼と敬意をもって接してもらえるようになりました。さらに、大学教授という立場を得たことで、社会的な信頼も高まり、発信する言葉への重みも変わりました。
また、このブログを毎日更新することで、発信力を鍛え、「あきらめない人」であるというブランドへの信頼が生まれました。日々の継続が、読者や知人の紹介を生む連鎖を生み、結果的に出会いの質と量が大きく変わっていきました。発信を重ねることによって、「何かを継続できる人」「実績を積み重ねる人」というイメージが定着し、ブランドが強化されていったのです。。
法則5 ネットワークをつくれ
組織や社会で何らかの目標を達成するには、ネットワークが欠かせないのだ。
権力とは、常に他者との関係性の中で生まれます。そのためには、仕事での人脈作りにもっと時間を使うべきなのです。仕事で成功し業務遂行能力を高めるために、ネットワーク力は欠かせません。 しかし、実際には多くの人がネットワークづくりを楽しいと思えず、戦略的な人間関係構築に対してどこか後ろめたさや抵抗を感じています。
だからこそ、時間の使い方と、誰と時間を過ごすのかを意識的に選ぶ必要があります。つながる相手は偶然で決めるのではなく、意図を持って構築されるべきなのです。 ネットワークを広げ、自分の提案を必要としている人やサポートしてくれる人との出会いを加速すべきです。
あなたの目的やニーズが、相手にとってどのような利益や意味を持つのかを常に意識することが重要です。人は、自らの目的と関連していると気づいたときに初めて、他者を支援する強い動機を持ちます。「自分を支援することで、相手は何を得られるのか」と問うことから、真の説得は始まるのです。
戦略的ネットワーク構築においては、次の4つの原則が有効だと著者は指摘します。第1にマーク・グラノベッターが提唱した「弱い紐帯」の活用。直接の親密な関係よりも、普段あまり接点のない知人から新たな機会がもたらされる可能性が高いという知見です。
第2に仲介者として異なるグループをつなげる立場に立つこと。第3にネットワークの中心に位置すること。情報と影響力が集まりやすいポジションを確保する必要があります。第4に、相手にとって価値あるものを提供すること。信頼と関心は、等価交換の連鎖の中で育まれていくものです。
法則6 権力を活用せよ
権力とは、蓄えて満足するものではなく、行使して初めて意味を持ちます。実際、権力を行使する人は「強力な人物だ」という印象を周囲に与えます。そして人は本能的に権力に群がる傾向があるため、権力を活用し、力を誇示すればするほど、自然と味方や支援者が増えていくのです。周囲に影響を与え、物事を前進させる行動を恐れず実行することが、さらなる信頼と資源を引き寄せる循環を生み出します。
権力をうまく活用して変化を起こせば、権力はますます強化される一方で、行使をためらったり避けたりすれば、現体制が存続し、権力は弱まるのです。つまり、権力とは使うことでこそ意味を持ち、有効に使えばさらに盤石にできるのです。
成功すれば、すべてが許される??
法則7 成功すれば(ほぼ)すべてが許される。
この法則こそが、ジェフリー・フェファーがもっとも強調する現実です。
スティーブ・ジョブズが一度アップルを追放されたという歴史的な事実は、多くの経営者に「権力とは脆いものだ」という認識を植え付けました。
この教訓から、今日の創業者たちは権力構造を制度的に補強する手段を講じています。たとえば、マーク・ザッカーバーグはメタ(旧Facebook)において議決権の6割以上を保有し、実質的に誰も彼を排除できない仕組みを構築しています。
ニューズ・コーポレーションではルパート・マードックとその家族が全議決権を保持し、グーグルではラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンが3種類の株式を通じて支配権を維持しています。スナップ(Snapchatの親会社)は上場時、通常株主に議決権を一切与えない構造を採用しました。
これらは単なる防衛策ではありません。「成功すれば(ほぼ)すべてが許される」という現実を、企業ガバナンスの仕組みに組み込んだ戦略的選択なのです。
この法則と特に関連が深いのが、「人は勝ち馬に乗りたがる」という経験則です。だからこそリーダーは、自分が今後もその座にとどまり、権力を握り続けるという姿勢を明確に打ち出さなければなりません。「何が何でもこの地位を守る」という意思と行動こそが、支持と忠誠を呼び込むのです。
また、フェファーは物語の力にも注目します。自分の物語を紡ぎ、それが真実とみなされるまで繰り返し語り続けることは、権力を維持する上で極めて有効です。ベンチャーキャピタリストや投資家、社員、顧客は、創業神話やヒーロー的なストーリーに惹かれます。その多くは起業家個人を中心に据え、仲間たちの役割を意図的に希薄化する構成をとります。
事実かどうかよりも、人々が求めるのは「納得感」と「ビジョン」であり、その語りが信じられれば、現実は後から追いついてくるのです。
ここで思い出すべきは、「こんなことをしたら嫌われるのではないか」「反発されたらどうしよう」といった取り越し苦労が、どれほど多くの行動の芽を摘んできたかということです。 しかしフェファーは断言します。成果さえ出せば、多少の摩擦や逸脱は、結果によって正当化される。それが組織における現実の力学なのです。
もちろん、権力の濫用によって人が傷つくケースがあることもフェファーは認めていますが、だからこそ善意ある人が権力を持ち、それを正しく行使することが重要なのです。権力を恐れて避ければ、結局は他者の意志に飲み込まれるだけです。
さらに、研究によれば、職務上の権限や社会的地位は健康状態にも大きく影響します。人は権力を持つと、自律的な意思決定が可能になり、ストレスが軽減され、幸福感が向上します。心身ともに健康が促進され、人生そのものが充実していくのです。
フェファーが伝えるのは、力を求めることは自己を捨てることではなく、本来の自分を活かすための選択であるということ。権力とは、行動の自由を手にし、他者に良い影響を与える手段でもあります。
本書は影響力を行使したいにもかかわらず、権力を得ることにためらいを持つすべての人に向けた、覚悟と実践の書です。本気でキャリアを築きたい人にとって、これは避けて通れない一冊です。
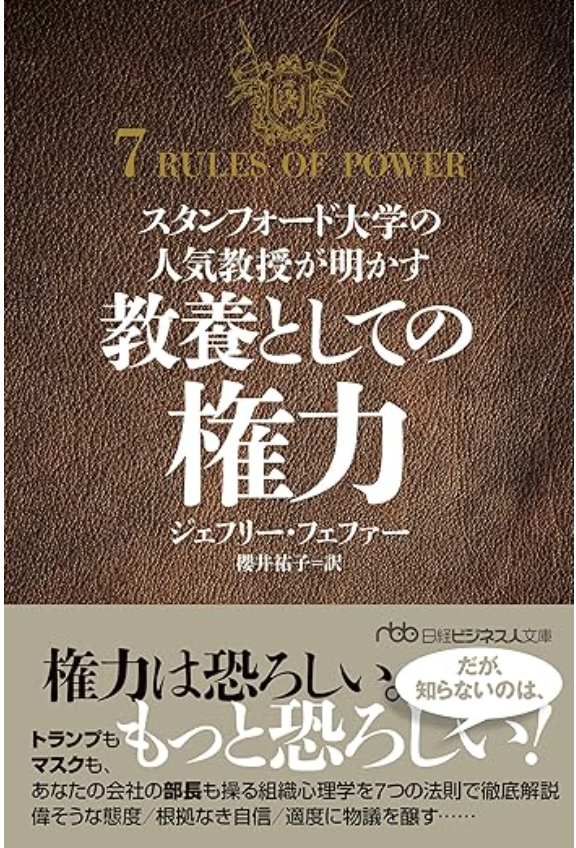


















コメント