二項動態経営 共通善に向かう集合知創造
野中郁次郎, 野間幹晴, 川田弓子
日本経済新聞社
二項動態経営 共通善に向かう集合知創造 (野中郁次郎, 野間幹晴, 川田弓子)の要約
経営とは「生き方」であり、矛盾や葛藤を統合しながら最善を模索する営みです。二項動態経営はその実践であり、SECIモデルは知の創造を支える仕組みです。感性や対話を通じて意味を生み出す「ヒューマナイジング・ストラテジー」と共に、人間中心の経営を再構築していくことが今、求められています。
二項動態経営とは何か?
経営とは何か、と聞かれたら、迷わず「生き方(a way of life)」だと答えるだろう。経営は、人間の営為そのものであり、そこに関わる人間の生き方が色濃く投影される。壮大な共通善の実現に向かって、目の前の動く現場・現実・現物の流れのなかで、文脈に応じて時空間を共創し、新たな意味や価値を生成する、人間たちのダイナミックで社会的なプロセスが経営である。(野中郁次郎, 野間幹晴, 川田弓子)
「経営とは、生き方(a way of life)である」。 野中郁次郎氏は、二項動態経営 共通善に向かう集合知創造の冒頭でそう語ります。 この言葉は、単なる比喩ではありません。経営とは、合理的な意思決定や戦略的選択の技術ではなく、矛盾や不確実性に満ちた現実の中で「どう生きるか」を問う、人間の営為そのものだという意味です。数字でも理論でもなく、そこに関わる人間の思考、感情、関係性、そして覚悟が経営を形づくります。
本書は「経営=生き方」という視点を、理論と実践の両面から掘り下げた羅針盤ともいえる一冊です。経営とは、「短期の利益」か「長期の理想」か、「現場の現実」か「理念の純粋さ」か、「効率」か「人間性」かといった、二項対立の選択を日々迫られる場です。
経営者は常にその狭間で揺れながら決断を下し続けなければなりません。そうした現場の葛藤に、この本は光を当てています。
野中氏の提唱する「二項動態」とは、対立を解消するのではなく、矛盾や相反する要素を統合し、新たな価値を創造していく知のあり方です。経営は唯一の正解を探すのではなく、複数の未完成な真理を掛け合わせ、状況に応じた最適解を紡ぎ出す創造行為です。
たとえば、製品開発において「高付加価値」と「低コスト」という一見相反する要件を同時に追求する必要があるように、「あれかこれか」ではなく「あれもこれも」を実現する姿勢こそが、二項動態経営の本質です。
この二項動態的な思考は、葛藤や緊張を乗り越え、創造の源泉へと導きます。創造性や多様な知を組織内外のスクラムで結集し、無限のイノベーションを目指す営みでもあります。それは、簡単で楽な道ではありませんが、日本的経営の再構築に向けた鍵となる「生き方」でもあります。
たとえばダイキンは「FUSION(融合)」という経営コンセプトを掲げ、短期収益と中長期成長、国内外の市場、自社と買収企業といった二項のはざまを乗り越える経営を実践しています。現会長の十河政則氏は、変化を見据えながら迅速に行動へ移す仕組みを構築し、この10年で売上高を倍増させ、2023年度には海外売上比率が8割を超えるに至りました。さらに、過去に2度撤退した北米市場でも再び首位を狙うポジションを築いています。
こうした成果は、過去に安住することなく、二項対立を超えた選択と自己変革を重ねてきたからこそです。 また、2008年に中国大手の珠海格力電器へインバータ技術を開示し、2015年には冷媒「R32」の特許を無償開放するなど、技術を共創しながら競争するという、いわば「握手しながら戦う」姿勢を貫いたことで、中国市場での競争優位を築きました。
さらに、顧客との関係性や規制変更への働きかけなど、泥臭くも現実に根差した戦略を積み重ねてきた点も、ダイキンの強さの一因です。
バンダイナムコにおいては、「散らかし屋」と「片づけ屋」という二つの役割を通じて、挑戦と制御を両立させています。業績好調な部署も含めて組織改編を繰り返し、不均衡な状態を意図的に生み出すことで、ゆらぎを活かした知の変容を起こしています。このような構造は、二項動態的思考の実践であり、異質性が組み合わさることで集合知の創発を促す仕掛けとなっています。
ユニ・チャームでは、国内外市場の二項性を捉え、「共振の経営」によりSECIモデルを体現しています。1300に及ぶスクラムを通じてOGISM(A)表やOODA-Loopメソッドを実践し、知のローカル化とグローバル展開を同時に進めています。また、社長と中堅社員を結ぶ戦略担当秘書制度を通じて、トップの考えを現場に伝える仕組みを築いています。これらは、集合知の創造を日常業務に組み込み、組織全体で実践知を育む好例です。
二項動態の鍵となるのは、多様性から生まれる異質性です。同質性の集団は死角を生み、思考のミラーリングに陥りやすくなります。環境変化に対応するには、原則を踏まえつつも臨機応変に舵を切る「動的均衡」の感覚が求められます。過去の成功や固定観念にとらわれることなく、いまこの瞬間の文脈を洞察し、「より善い」選択を重ねる実践知が重要です。
人間の創造性は、暗黙知や無意識下の記憶が偶発的に結びつくことで生まれるセレンディピティに支えられています。AIのような合理的な存在では生み出せない「点と点をつなぐ力」が、革新の源です。その機会を捉える力は、感性や主観、経験に根ざしており、直接経験から得られる感覚が極めて重要です。
二項動態経営とSECIモデル
二項の矛盾から生まれる葛藤、衝突、緊張から逃げずに、両極端の異質性・共通性に互いの暗黙知も含めて真剣に向き合うことで、動く現実のなかで新たな意味や価値をダイナミックに共創し、自己変革・自己超越を達成できる。それは、SECIプロセスの本質そのものなのである。
二項動態経営は、経営者が複雑な現実のなかで「何がより善いか」を動的に判断していく“生き方”そのものです。単なる意思決定の技術ではなく、矛盾やジレンマと向き合いながらも、理想と現実の狭間で、その都度最適な選択肢を模索する姿勢が求められます。
経営とは論理でも計画でもなく、人間としての覚悟と感性が問われる営みであるという視点が、まさにここに凝縮されています。 このような動的な意思決定において、極めて重要なのが「知の創造」です。
そして、この知の創造を支える枠組みとして、野中氏が長年提唱してきた「SECIモデル(セキモデル)」があります。これは、企業や組織が継続的に新しい知識を生み出し、それを価値に変換していくための知識創造のダイナミズムを表した理論です。
SECIモデルとは、「暗黙知」と「形式知」という2つの知識の形態を、スパイラル状に循環させながら組織的な知識を生み出していく4段階のプロセスから成り立っています。
①共同化(Socialization)
組織的知識創造の起点。直接経験における暗黙知の獲得な共有を行います。
②表出化(Externalization)
共感を通じて直観した本質を洞察し、他者との対話を通じて、その意味や価値を錬磨して概念としての形式知へと転換します。
③連結化(Combination)
組織内外のあらゆる知を総動員して自在に組み合わせて集合知を創造します。
④内面化(Internalization)
集合知となった戦略やモデルを、実践を通じた試行錯誤によって個人に身体化し、暗黙知が個人、集団、組織、社会のレベルで豊かになり、次の共同化を駆動する源泉となるのです。
これら4つのフェーズは、直線的に一方向へ進むのではなく、スパイラルに循環し、時に戻り、時に加速しながら、組織全体の知を進化させていきます。これがSECIモデルの最大の特長であり、動的な知識創造を可能にする理由です。 では、なぜ二項動態経営とSECIモデルが結びつくのでしょうか。
それは、二項動態経営が「絶対的な正解」がない世界において、葛藤や矛盾に真正面から向き合いながら、「その都度の最善(より善い)」を模索し続ける経営のあり方だからです。 その「より善い」を導き出すためには、感性、共感、対話、直感、試行錯誤といった人間的な知のプロセスが不可欠です。
つまり、知を創造するプロセス=SECIモデルが必要なのです。 たとえば、経営者が理念を語り(表出化)、ミドルが戦略として組み立て(連結化)、現場が実践を通じて内面化し、そこから得た気づきが共有されていく(共同化)──この循環のなかで、知は生まれ続けます。
そしてこの知の創造そのものが、二項動態経営の実践でもあるのです。現場の声を拾い上げ、対話を通じて価値を再定義し、矛盾と向き合いながら創造へと転化していく。これが「問い続ける経営」であり、SECIモデルはその問いに知として応える仕組みなのです。
私たちは、物事や問題を「二項対立」として切り捨てるのではなく、「二項動態」として捉える必要があります。「あれかこれか」ではなく、「あれもこれも」を追求しながら、そこに生まれる緊張や摩擦を創造のエネルギーに変えていくのです。 対立項を排除するのではなく、それらを含んだまま共創する道を選ぶことが経営者やミドル層に求められています。
そして、そこに存在する暗黙知を見逃さず、形式知へとつなげていくプロセスが、まさにSECIモデルの本質と重なります。 経営とは、矛盾を抱えながらも創造を止めない営みです。そしてそれは、単なる合理的意思決定ではなく、経営者一人ひとりの「生き方」とも言えます。 SECIモデルは、その生き方を支える「知のスパイラル」として、二項動態経営を根底から支えているのです。
二項動態を促進する実践的リーダーシップ
実践知とは、一般原則を活用するだけでなく、個別の状況や関係性に通じる実践的な賢さを意味している。実践知を有する者は、個別具体の文脈で両極端における最適な中間(物理的な真ん中ではない)を洞察し行動する二項動態を促進する。「いま・ここ」の現実において、変わり続けるダイナミックな文脈の只中で、未来の共通善の実現に向かって、その都度の最善である「より善い」を洞察・判断し、タイムリーに行動する実践知・賢慮が、二項動態を促進する実践知リーダーシップの本質である。
著者らは二項動態を促進する実践知リーダーシップの要件を以下の6つにまとめています。
1、善い目的をつくる
何が組織と社会にとって善いことかを示す
2、現場で本質を直観する
目の前の現象の背後にある意味を洞察する
3、場をタイムリーにつくる
共感を通じて新たな意味を創造できる場を常に創り出す
4、本質を物語る
物語や隠喩を使って、わかりやすく物事の本質を伝える
5、物語りの実現に向けて政治力を行使する
人々の力を結集し、あらゆる手段を駆使して物語りを実現する
6、実践知を自律分散的に育む・組織化する
徒弟制やメンタリングなどを通じて、組織全体で実践知を育成する
知識創造理論は、「正しさ(right)」という絶対解を追い求めるものではありません。むしろ、正解が見えない、変化する現実のなかで、「いま・ここ」における本質を見極め、「より善い」目的、すなわち共通善に向かって、集合的な共通了解としての最適解を探り、実践を繰り返していく動的なプロセスに重きを置いています。
共通善とは、「われわれはなぜ存在するのか」という根源的な問いかけであり、近視眼的な利益追求ではなく、未来を見据えた志に貫かれた価値観です。この共通善は、トップ層の理念として掲げられるだけでなく、フロントラインにまで浸透し、実際の行動の規範となっていなければなりません。
その中核に位置づけられるのが「パーパス(存在目的)」です。 パーパスは単なる企業理念ではなく、個々の意思決定や日々の実践を方向づける羅針盤であり、経営の「生き方」を問うものです。壮大な理念にとどまらず、現場の文脈に即した実践が求められます。
たとえば、存在意義や存在目的となる共通善は、一度策定したら終わりではありません。時代や環境は変わり続ける以上、共通善もまた静的な理想ではなく、変化に応じて進化させ続ける必要があります。
企業もまた、自らを自己変革する主体として、パーパスそのものを絶えず更新し続けなければならないのです。 エーザイはこの思想を具現化する企業の一つです。同社は2022年、定款の一部を改正しました。
これまでヒューマン・ヘルスケア理念における主役は「患者とそのご家族」でしたが、これを「患者と生活者の皆様」へと拡大しました。この変更には、単なる言葉の置き換えを超えた本質的な意味があります。
医療の枠を超え、日常生活そのものの質を高め、他産業との連携を通じて人々の全生涯を支える存在へと進化するという決意の表れなのです。
実際にエーザイは、製薬の枠を超えて多領域でのパートナーシップを展開し、介護、予防、QOL向上といった文脈で新たな価値提供に挑んでいます。その根底にあるのは、パーパスに基づいた事業の再定義であり、共通善を軸にした意思決定の体系化です。つまり、変化する社会のニーズに合わせて、企業としてのあり方そのものを問い直しているのです。
このような取り組みは、単なるCSR的発想とは一線を画します。エーザイが掲げる「患者を起点に考える」という行動指針は、製品開発、営業、組織設計、ガバナンスにまで及び、企業活動全体が一貫して共通善に接続されている点に意義があります。
このように、パーパスや共通善は単なる理想論ではなく、実践的経営の羅針盤として機能します。そしてその実現の場は、「主観と主観のぶつかり合い」、つまり「集合本質直観」が生まれる対話の場です。
これは、共感を媒介にした知的コンバットのプロセスであり、一見相反する意見や価値観の間にある緊張関係を創造的に昇華させ、新たな意味や価値を共創する場なのです。
ここでは、メタ認知能力が問われ、組織としての認識力が鍛えられます。 価値や質を問わなければ、イノベーションは生まれません。経営とは、未来をつくる意味創造に向かう人々が、環境変化に応じてともに織りなす営為であり、集合的な「生き方」が投影されるものです。
二項動態経営では、観念論で相手を打ち負かすことを目的とはせず、異なる主観や思い、能力を持つ者同士が妥協なくぶつかり合い、暗黙知を源泉とする新たな知を創造していきます。 動いていく現実の只中で、妥協なき葛藤から「こうとしか言いようがない」という「その都度の最善(より善い)」を無限に追求する姿勢が重要となります。ときには「清濁あわせ呑む」政治力も必要です。
それでも実行にこだわり、行動によって示すことで、現実は変わり始めます。試行錯誤を繰り返しながらも、ともに前進する。この創造原理としての生き方こそが、二項動態による集合「実践知」創造の本質です。
エーザイが示すように、共通善を軸に据えた自己変革の営みは、理念と現実、理想と実践を往還しながら、未来の組織のあり方を拓く重要な道筋となるのです。
また、ソニーでは、バウンダリースパナーとしての役割を担うミドル層が、部門を越えて連携し、音楽とゲームの融合といった事業横断的なコラボレーションを通じて新たな価値を創出しています。
こうした取り組みは、単なる製品の組み合わせではなく、異なる世界観を持つ領域を有機的につなぎ合わせ、「物語り」として市場や顧客に届けていく営みです。
パーパスとナラティブが重要な理由
戦略とは、筋書きが絶えず変化する連続ドラマとして捉えるべきである。あらかじめ規定された環境で計画どおりに物事が予定調和で進むことは、現実には決してない。完全情報、完全競争における合理的選択を前提とする経済学をルーツに持つ分析思考の戦略論は、現実世界では役に立たない。戦略とは、外部環境に適応するものでも、内部環境に制約されるものでもないのである。出来事を意味あるものにして変化を自ら創造するのは、「物語り」である。動く現実の只中で、想定外の状況が起こってもその矛盾を克服し続けるプロセスを繰り返していく。
「物語り(ナラティブ)」とは、戦略を静的な計画としてではなく、現実の中で紡がれる動的な創造行為として捉え直す概念です。組織が矛盾や混沌に直面したとき、それに意味を与えるプロセスを通じて、単に変化に適応するのではなく、自ら変化を生み出していく力が育まれます。
物語りには、「未来の共通善」というビジョンに向かうプロット(筋書き)と、それを行動に移すスクリプト(行動規範)が含まれます。このスクリプトは、マニュアルのような固定的手順ではなく、状況に応じて判断し、柔軟に実践するための指針です。したがって、言葉は感性や直感に訴える「生々しさ」を伴う必要があります。
そして、物語りは必ずしも論理的で一貫している必要はありません。むしろ多少の矛盾や多義性を含んでいた方が、現実の中で意味づけされるプロセスを活性化させ、知的対話や試行錯誤を促すことにつながります。組織におけるカオスや不安定さは、むしろ創造性の触媒となるのです。
ナラティブの力は非常に大きく、場合によっては精緻な戦略プラン以上に人々を動かします。たとえば、国家間の安全保障では「戦略的ナラティブ」として活用され、非軍事領域の認知戦や情報戦でも用いられています。
これは、価値観、社会の動き、登場人物のアイデンティティや役割、過去・現在・未来の構造を含む多層的な物語によって、人々の行動や意識に影響を与える手法です。
重要なのは、これが一方向の伝達ではなく、双方向の相互作用として規範が共有・社会化される点です。戦略が「語られるもの」ではなく、「ともに紡がれるもの」になるとき、組織はより深く、より強く結びついた一体感を持ち、変化に向けた創造的な力を発揮することができるのです。
丸井グループやオムロンのような企業も、共通善の実現に向けて、利益創出と知識創造を両立させながら、社会に対する存在意義を問い直しています。彼らの実践は、トップのビジョンとフロントの現実をミドルが結びつける「ミドルアップダウン」構造の中で成立しています。
ミドルの存在は、単なる伝達役ではなく、葛藤の交差点で創造的に意味を編み出す翻訳者であり、触媒でもあります。トップが掲げる理念と、現場が直面する複雑な現実との間で起こる摩擦や矛盾に対して、ミドルはその両方を受け止め、対話と実践を通じて新たな意味を生み出す役割を担っています。
現代の経営は、トップダウンで命令するだけでは立ち行かなくなっています。複雑で変化の早い環境では、現場がその場のコンテキストに応じて素早く判断し、行動することが求められます。
こうした背景の中で注目されているのが「フラクタル組織」です。 フラクタル組織とは、トップの理念や組織の価値観が、各部門や一人ひとりの行動にも自己相似的に反映されている状態を指します。つまり、どの階層・どの現場においても、組織の「DNA」が息づいており、自律的な判断と行動が可能になります。
このモデルでは、トップは「なぜ(Why)」という大きな目的を示す役割を担い、「どのように(How)」を現場に委ねます。ただし、最終的な責任はトップが負うという大前提があり、現場側も的確な判断ができるよう、複眼的な視点とスキルを磨く必要があります。
フラクタル組織では、各人が自律的に考え、他者と共感しながら行動する力が不可欠です。そして、それを支えるのは「対話による意味づけの場」です。上からの指示ではなく、共通の価値観と目的を共有することによって、組織全体が自己組織化し、環境変化に強い“レジリエントな集団”へと進化していきます。
要するに、フラクタル組織とは、「自律と共感」「部分と全体」「個と組織」が一体となって有機的につながる、新しい時代の経営モデルなのです。
このとき求められるのが、「実践知」であり、それは一般論ではなく、状況依存的かつ関係性の中でしか発揮されない賢さです。 実践知とは、「いま・ここ」で、状況に応じて最も適切な判断を下し、行動に移す能力であり、暗黙知、直感、経験、対話などを総合的に活用する知のスタイルです。
単なる知識の適用ではなく、未来を切り拓く創造的な行為としての知であり、だからこそ、教科書通りの答えではなく、「その都度の最善(より善い)」が求められるのです。
この実践知を可能にするもう一つの鍵が、メタ認知とセレンディピティです。メタ認知は、自分の思考プロセスを客観視し、柔軟に修正できる力であり、セレンディピティは、偶然を意味ある出会いに変える発見力です。このブログでも偶然の力の重要性を繰り返し、解いていますが、野中氏も同じ考えに立っていることに勇気をもらえました。
メタ認知とレンディピティの力が合わさることで、現実に対する感度が高まり、予期せぬチャンスを捉え、組織の変革につなげることができるのです。 デジタル社会において、情報は容易に手に入りますが、その海の中から意味を見出す力が問われています。
エコーチェンバーやフィルターバブルによって、自分にとって都合の良い情報しか入ってこなくなっている今こそ、異質な他者との対話を通じて、自らの固定観念を揺さぶり、思考の深度を高めることが求められます。 そうした知のぶつかり合いは、しばしば葛藤や摩擦を生みます。
しかし、その「妥協なき葛藤」こそが、イノベーションの源泉なのです。人間の持つ暗黙知、身体性、感性、直観といった非言語的知の力を信じ、形式知だけでは捉えきれない現実の複雑さに向き合いながら、対話を通じて新たな知を創造していく。そのような知的コンバットの場を設計することが、経営の本質と言えるのではないでしょうか。
ヒューマナイジング・ストラテジーによる経営の再創造
ヒューマナイジング・ストラテジーとは、論理分析ではなく、まさに人間の「生き方」の「物語り(ナラティブ)」である。創作を巧みに入れ込んで人間の生き方を問うのが、ヒューマナイジング・ストラテジーである。そこには、Whatだけでなく、人間の生き方を示すWhyを組み入れる必要がある。
ヒューマナイジング・ストラテジーとは、戦略を「人間の生き方」として再定義する考え方です。人間を、未来に向かって意味や価値を創造する主体としてとらえる点で、経済合理性を前提とする静的な戦略論とは大きく異なります。 その特徴は3つあります。
第1に、戦略とは一人ひとりの「思い」や生き方を、他者との相互作用(相互主観性)を通じて組織の意思へと昇華させ、新しい現実を共に創り出すこと。
第2に、戦略は「いま・ここ」の状況に応じて判断し、絶えず変化の中で「真・善・美」を追求する、終わりのない価値創造のプロセスであること。
第3に、戦略は共通善の実現を目指す人間の生き方であり、未来に向かう物語(ナラティブ)として表現されることです。 ヒューマナイジング・ストラテジーの出発点は「人間の思い」です。
機械やAIはデータを処理できますが、意味を創造することはできません。イノベーションの源泉は、数値ではなく人間の主観と感情にあります。人は常に変化する現実の中で、自らの志向性を起点に、他者との関係を通して新しい意味や価値を共に生み出していく存在なのです。
意味とは、異なるものの中から共通点を見出し、差異を理解し、それらを統合して「こうとしか言いようがない」という新しい秩序を生み出すプロセスから生まれます。
つまり、意味づけそのものが「二項動態」的な創造行為なのです。 本書が強調するのは、すべての経営資源や資本の起点には「人の思い」があるということです。だからこそ、「人を活かす経営」は、人間を未来に向かって価値を創造する動的な存在としてとらえる人間観に立脚すべきだと説きます。
いくら科学やテクノロジーが発展しても、経営が人間の営みである限り、組織は必ず慣性や惰性を抱えます。過去の成功体験に安住すれば、やがて創造性は失われる。だからこそ、組織は常に自己変革し続けなければならない。その原動力となるのが「二項動態経営」と「ヒューマナイジング・ストラテジー」なのです。
これこそが、経営を再び、人間の手に取り戻すための知的挑戦なのです。経営とは組織の戦略や構造だけでなく、そこに関わる人々の「思い」や「志」そのものであり、だからこそ「ヒューマナイジング・ストラテジー(戦略の人間化)」が重要なのです。
この戦略は、数字やロジックではなく、「人間の生き方」から出発し、「なぜそれをやるのか」という目的意識に根ざしたものでなければなりません。
この30年、日本企業が「変革」を掲げながらも思うような成果を出せなかったのは、過剰な合理主義と数値信仰に囚われ、人間の創造性を阻害してきたからです。変化の時代においては、「測る力」よりも「感じ取る力」、つまり感性、直観、物語、共感といった“人間の知”が最大のリソースとなります。
今求められているのは、過去の成功体験にとどまらず、変化し続ける現実に創造的に応答しながら、理想を見失わずに歩み続けることです。矛盾するものを排除するのではなく、統合し、新しい秩序を生み出す力が大切です。
試行錯誤の中で、その時々の「最善の答え」を見いだし、共通善という理念に向かって進み続けることが重要だと著者は指摘しています。それは単なる経営の手法ではなく、人としてどう生きるかという姿勢そのものなのです。
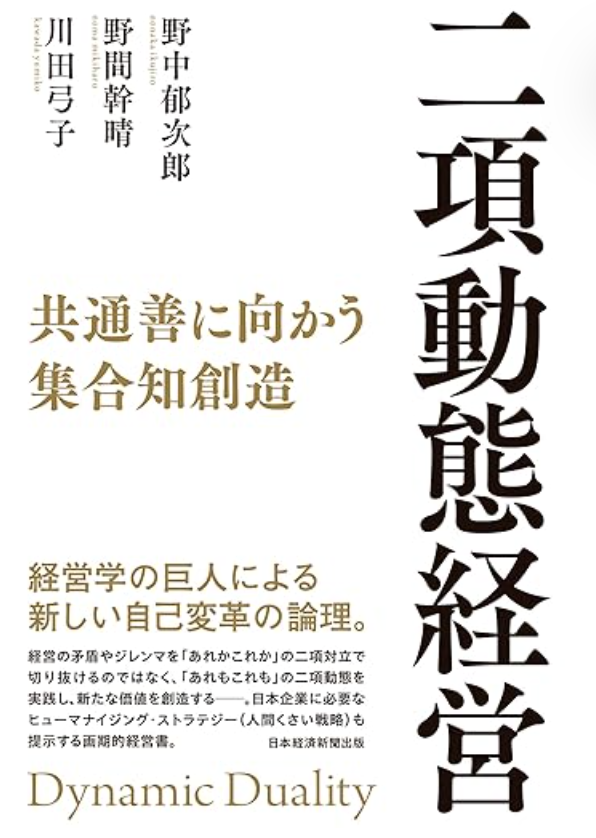









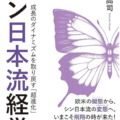
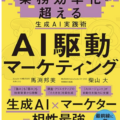







コメント