スマート・ライバル ビッグ・テックと戦う企業
フェン・ジュ, ボニー・インニン・ソウ
東洋経済新報社
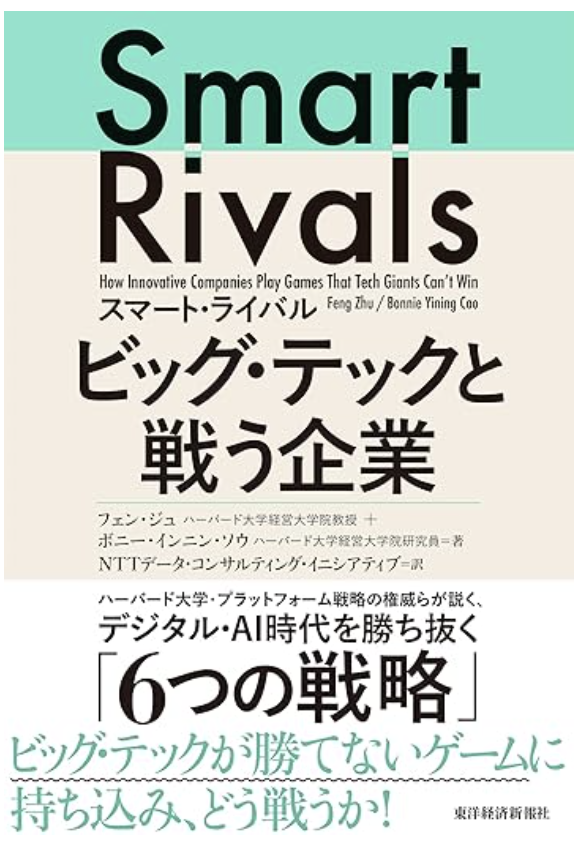
スマート・ライバル ビッグ・テックと戦う企業(フェン・ジュ, ボニー・インニン・ソウ)の要約
『スマート・ライバルズ』は、ビッグ・テックにただ追随するのではなく、自社の強みを武器に独自の戦略で競争優位を築く方法を示した一冊です。顧客中心主義の徹底、プラットフォームの隙間の活用、フレネミーとの戦略的共存、そしてディスラプションへの柔軟な対応など、6つの実践的アプローチを解説しています。
スマートライバルがビッグ・テックに勝利できる理由
スマート・ライバルは、デジタル技術を活用して競争優位を高めていく。顧客中心主義を推進し、独自のプラットフォームやエコシステムを構築する。そして、最終的にビッグ・テックとは大きく異なる製品やサービスを開発することで、ビッグ・テックや競合他社による模倣を困難にしている。(フェン・ジュ, ボニー・インニン・ソウ)
「イノベーションを起こさなければ生き残れない」。現代のビジネスシーンでは、そんな言葉が脅しのように語られ続けています。とくにシリコンバレー発のテックジャイアントたちの成功事例がメディアを席巻する中で、企業の多くが「自分たちもテクノロジー企業のように振る舞わなければならない」と感じ、彼らの戦略を模倣しようとします。
けれども、そこで見落とされがちなのは、模倣によって得られる競争力は一時的であり、しかも同じ土俵での勝負に持ち込まれた時点で、すでに劣勢に立たされているという現実です。 テック企業が持つ圧倒的な資金力、人材力、スピード感。そして、彼らが築いたエコシステムの中で日々繰り返される実験と最適化。こうした構造そのものに、従来型企業が同じモデルで対抗するのは非常に困難です。
それにもかかわらず、「DX」「AI」「サブスクリプション」「D2C」などの流行語を追いかけ、自社の本来の価値や文脈を見失ってしまう。そんな企業が増えているように感じます。かつては独自の強みを誇っていた企業も、気づけば他社との違いが見えにくくなり、価格競争や効率性の罠に飲み込まれていく。こうした状況は、ある意味で自滅的とも言えるかもしれません。
スマート・ライバル ビッグ・テックと戦う企業は、そうした戦い方に警鐘を鳴らします。本書の著者であるハーバード・ビジネス・スクール教授のフェン・ジューと、元ブルームバーグ記者のボニー・イーニン・ツァオは、従来型企業がビッグ・テックと同じような戦い方をする必要はないと、はっきりと断言しています。
もしもテックジャイアントと同じ土俵で競おうとすれば、膨大な資金力、データ量、スピードを持つ相手に追いつくことは難しく、結局は後追いに終始するだけになってしまいます。そして、そうした模倣による戦略は、自社が本来持っている競争優位をむしろ失わせてしまうリスクさえあるのです。
著者たちが強調しているのは、模倣ではなく「差別化」による戦い方です。企業がすでに持っている資産――長年にわたって培ってきたブランドへの信頼、現場との密接な関係、特定領域における専門知見や業界特有のデータ、地域に根ざしたネットワークなど――を起点に、他社では再現できない独自の価値を打ち出すことこそが、これからの競争において最も重要だと説いています。
だからこそ、スマート・ライバルたちは、模倣ではなく独自性を重んじます。彼らは、自社の既存の強みを起点に成長の道筋を描き、ビッグ・テックが踏み込めない領域で勝負することで、差別化を実現しているのです。 このような時代にこそ、求められているのは「別の戦い方」です。
ここでのポイントは、「ビッグ・テックを研究すること自体は否定されていない」という点です。むしろ、彼らをよく観察し、どこに強みがあり、どこに弱点があるのかを見極めることは不可欠です。ただし、その目的は模倣することではありません。真の目的は、ビッグ・テックや競合他社が真似できない独自の製品機能やベネフィットを提供し、自社ならではのポジションを確立することにあります。
著者たちは、テックジャイアントが構築したインフラを活用するという視点にも注目しています。つまり、彼らのエコシステムを前提にしながら、どう差別化し、どう自社の競争力を高めるかを戦略的に考えるというアプローチです。
強みを伸ばせ!ドミノピザが顧客から支持された理由
スマート・ライバルは、ビッグ・テックに対して異なる戦略を取ることが多い。ビッグ・テックの得意分野で勝負しても、永遠に追いつけないまま追従することになり、最終的に自社の競争優位を失ってしまう。したがって、スマート・ライバルはむしろ既存の強みをベースにして、成長の道筋を描いていく。
本書にはドミノ・ピザやペットスマート、セフォラ、中国の靴製造小売企業のベルといったスマート・ライバルの事例も豊富に紹介されています。これらの企業は、テクノロジーを単に取り入れるのではなく、使いこなす姿勢を持っており、ビッグ・テックとの提携においても、主導権を維持するための戦略を丁寧に練り上げています。
スマート・ライバルの本質とは、ビッグ・テックが得意とする分野であえて正面から戦うのではなく、自社の強みを軸に別の角度から戦略的に挑むことにあります。その意味で、ドミノピザの事例は、まさに「テック巨人とどう向き合うか」という現代的課題に対する模範的な答えのひとつと言えるでしょう。
一時期、ブランドイメージの低下に直面していたドミノピザは、味や品質への批判だけでなく、ドライバーの事故など顧客の不満に真正面から向き合う必要がありました。特に、ピザの到着時間は、顧客体験の中で最も大きなストレス要因でした。
この課題に対し、ドミノピザは「配達時間の正確さ」と「スピード」を自社の競争優位の核心と位置づけ、徹底的に磨き上げていったのです。 注目すべきは、フードデリバリー市場においてUber EatsやDoorDashといったビッグ・テック系のプラットフォームが台頭する中、ドミノピザがそれらの汎用的な配送インフラとは異なる路線を選んだことです。
同社は、注文から配達完了までのプロセスを自社で一貫して管理することで、独自のフルフィルメント体験を構築していきました。その象徴が「ピザトラッカー」いうアプリです。
顧客はアプリを確認すること注文したピザが今どの段階にあるのか――調理中なのか、オーブンに入っているのか、配達に出発したのか――をリアルタイムで確認できるようになりました。これは単なる便利機能ではなく、配達の不確実性という最大のストレス要素を透明化することで、顧客との信頼関係を劇的に向上させた仕組みです。
加えて、ドミノピザは配達という機能そのものを「コスト」ではなく「競争優位性」として再定義し、自社で配達網を構築・最適化することに注力しました。他社がプラットフォーム依存に向かう中、ドミノはあえて自社で人員を確保し、「配達のエキスパート」であることをブランディングの主軸に置きます。
一方で、ドミノピザは「自社完結主義」に陥ることなく、柔軟に外部との連携も模索しています。その象徴が、Uber Eatsとの戦略的提携です。一見すると、配達を他社に委ねるような判断に見えるかもしれません。しかし実際には、Uber Eatsの膨大なユーザー基盤を活用して新たな顧客層にリーチすること、そしてピークタイムや一部エリアでの需要超過に対応する補完的役割を担わせることが狙いとされています。
ドミノピザは、提携後も自社の配達網を主軸に据えており、データの主導権や顧客関係のコントロールを手放してはいません。つまり、外部との提携においても、自社の強みや戦略軸を明確に持ちながら、それを補強するためのパートナーシップを選択しているのです。
このように、ドミノピザの戦略には、ビッグ・テックが得意とするスピードやスケールに対抗するのではなく、配達体験の設計やオペレーションの最適化によって、差別化を図るという明確な意図が読み取れます。そしてそれは、まさにスマート・ライバルの基本原則と一致します。
すなわち、ビッグ・テックを模倣するのではなく、自社の土俵と資源を最大限に活かして、代替不可能な価値を生み出すという発想です。
ドミノピザの事例は、単にピザビジネスに限った話ではありません。これは、「どのようにしてビッグ・テックの影響下で自社らしく戦うか」という、すべての企業に共通するテーマへのヒントでもあります。模倣ではなく独自性を。敵対ではなく共創を。スピードではなく信頼を。ドミノピザは、スマート・ライバルの精神を体現し、デジタル時代の差別化戦略に新たな視座を与えてくれる存在なのです。
顧客体験を高め、イノベーションを起こそう!
顧客との対話は信頼関係の構築に役立つうえに、顧客が理解され大切にされていると感じれば、真のニーズや好み、困り事を率直に話しやすくなる。こうした対話は、顧客の真のニーズを理解するうえで非常に重要だ。
顧客が真に達成したいことを深く理解することこそが、イノベーションを成功に導き、顧客が本当に望む商品やサービスを生み出す鍵となります。単に「売れるもの」ではなく、「本当に役に立つもの」「生活の中で意味を持つもの」を提供するためには、顧客の言葉の背後にある目的や価値観に目を向ける必要があります。
中国の靴製造小売企業であるベルは、この考え方を体現するように、ビッグ・テックとは異なる角度からデータを活用し、独自の顧客体験を創出しています。
たとえばアリババのようなテック企業が、主に購買履歴やフィードバックといったオンライン上の明示的なデータをもとに商品を推薦するのに対し、ベルはスタイルや価格の好みといった表面的な属性だけでなく、フィット感や快適さといった感覚的・身体的な要素に着目しています。これらはオンラインでは測定しにくい情報であるにもかかわらず、実際の使用体験に直結する極めて重要な要素です。
ベルはそうした情報を、店舗での対話や試着体験を通じて丁寧に収集し、商品開発や販売戦略に活かしています。こうした情報をオフラインの顧客接点から取得し、プロダクト開発や推薦システムに反映することで、他社では提供できないきめ細かなサービスを実現しています。
このように、顧客の真の意図や感覚に迫ろうとする姿勢は、単なるデータドリブンの枠組みを超えた、より人間的で意味のある顧客理解を実現しています。それが結果的に、テック企業では提供しづらい、模倣困難な体験価値へとつながっているのです。
データ活用の背後には、「データフライホイール」と呼ばれる好循環の仕組みがあります。企業が顧客接点から得たデータをすぐにサービスや製品改善に反映し、そこで得られた顧客満足がさらなるデータ収集へとつながる。この循環が継続することで、時間の経過とともに競争優位性が高まり、模倣困難なポジションを築くことが可能になります。 この仕組みの根底にあるのが、顧客中心主義という思想です。
NetflixやAmazonといったビッグ・テックが持続的に成長を遂げている理由の一つは、まさにこのデータフライホイールを企業活動の中核に据えている点にあります。
ビッグ・テック以外の企業でもこのデータフライホイールを活用できます。アウトドアブランドのパタゴニアが行っている修理プログラムも、その好例です。同社は、修理依頼から得られる情報をもとに製品寿命や不具合傾向を分析し、平均寿命である5~7年よりも明らかに早く返品されるアイテムがある場合には、その設計や製造方法を見直しています。
顧客との接点から得られる定性的な情報を、製品改善にフィードバックしていくこの流れは、テック企業とは異なる「クラフト型の競争力」として非常に示唆に富んでいます。
本書では、このような顧客中心主義が、4つの柱によって支えられているとされています。
①製品改善
顧客からのフィードバックをもとに、より優れた製品を継続的に提供していく姿勢です。
②カスタマージャーニーの簡素化
購入や利用に至るまでのプロセスを可能な限りシンプルに設計し、ストレスを取り除く工夫です。
③パーソナライゼーション
顧客ごとの状況や好みに合わせた個別対応を行い、期待を超える体験を提供します。
④顧客の真のニーズを深く理解し、それに応えること。
顕在化された要望だけでなく、顧客自身もまだ気づいていない潜在的な期待に先回りして応えるというアプローチです。
ドミノピザ、ベルやパタゴニアは、それぞれ異なるやり方でこの4つの柱を体現しています。彼らは流行や技術に振り回されるのではなく、常に顧客の生活に根ざした「意味のある価値」の提供に集中しています。テクノロジーやデータは、その目的を達成するための手段であり、決して目的そのものではありません。
ビッグ・テックのような圧倒的なスケールを持たなくても、独自の強みと柔軟な発想を武器に、スマート・ライバルとして確かな競争力を築き上げていくことは十分に可能です。そして、その戦略こそが、今日の不確実性の高い市場環境において最も持続性のあるアプローチなのです。
従来型企業には、ビッグ・テックにはない強みがあります。それは、人と人との豊かなやり取りや、長年培ってきた業界への深い理解です。こうした資産があるからこそ、従来型企業は、顧客に寄り添ったサービスを、もっと人間的なやり方で実現できます。
ビッグ・テックのように大量のデータを収集し、瞬時に分析する体制がなくても、戦えるフィールドは十分にあるのです。 今の時代、ビッグデータに注目が集まるのは自然な流れです。しかし、それだけでは見えてこない「顧客の本音」や「現場のリアル」があります。データには限界があります。むしろ、データの精度が高くなるほど、そこに映らない人間の動きや感情が重要になってくるのです。
だからこそ、従来型企業は、自社のリソースと文脈を活かした「別の戦い方」を考える必要があります。 たとえば、中国の保険会社・平安保険は、ユーザーの申請時の行動データを重視しています。その人がどんなタイミングで入力を止めるのか、どこで悩んでいるのか――こうした振る舞いを行動経済学の視点で捉え、リスクやニーズの判断材料としています。これは、数値化された購買履歴だけに頼る分析とは異なり、よりリアルで文脈的な顧客理解の方法です。
コカ・コーラの事例は、デジタル時代のマーケティングにおいて、SNS頼みのアプローチに一石を投じるものです。多くの企業がX(旧Twitter)やInstagramといった大量のフォロワーを抱えるSNSでのコミュニケーションに注力するだけでなく、自社独自のチャネル――店舗、地域コミュニティ、リアルイベントなど――を戦略的に活用しています。
こうしたデジタル以外の接点が、SNSとは異なる文脈で顧客とつながることを可能にし、より深く、持続的な関係性を生み出しているのです。
さらに、デジタル化の進展によって、多くの製品にはIoT(モノのインターネット)機能が搭載され、企業がオフラインチャネルを通じて消費者とリアルタイムでつながることも現実となりました。多くの顧客は、日常的な利用を通じて、自分の行動や好みといったインサイトを自然と企業に提供しています。これらのデータは、製品改善や新しいサービスの発想において、非常に価値のあるヒントになります。
だからこそ、従来型企業こそ、オフラインチャネルを“販売の場”としてだけでなく、共創の場として積極的に活用すべきです。リアルな接点から得られる感覚的な情報や顧客の声は、ビッグ・テックでは再現しづらい差別化の源泉となり得ます。オフラインを活かした顧客巻き込み型のプロダクト開発こそ、これからの競争力の鍵になるのです。
要するに、ビッグ・テックのような巨大なデータインフラがなくても、十分に勝負できるということです。むしろ、従来型企業だからこそ持っている現場感覚や信頼関係、組織文化を軸に、顧客中心主義を再構築することが大切です。 ポイントは、戦わないことではなく、自分たちの土俵を定めること。リソースの違いに目を奪われるのではなく、自社の価値が最も活きる場所を見つけ、そこに集中すること。
スマート・ライバルの本質は、まさにその選び方にあります。 ビッグ・テックにできないことが、まだまだある。 その事実に気づいた企業から、次の時代の競争優位が生まれていくのです。
スマートライバルズの6つの戦略
スマート・ライバルになるには、自社の競争優位を高め、顧客中心主義を追求し、プラットフォームとエコシステムを成長させ、フレネミーとの関係を上手く誘導し、ディスラプションに適応するための独自の戦略を設計することが求められる。企業のリーダーは、スマート・ライバル志向を身につけ、ビッグ・テックが対抗しにくい戦略に一貫して取り組まなければならない。
著者たちは、スマート・ライバルとしてビッグ・テックと共存・競争しながら成長するための6つの戦略を明らかにしています。すでに紹介した内容と一部重複するかもしれませんが、ここであらためてその全体像を整理しておきます。
①自社の強みを徹底的に活かす
ブランド、チャネル、顧客との信頼、業界特有のノウハウ――テック企業が簡単には真似できないアセットに着目し、それらを磨き込んでいくこと。自社にしか出せない価値を明確に打ち出せば、スケールやスピードでは敵わなくても、違う次元での競争優位は築けます。
②顧客中心主義を本気で実践する
顧客の声を起点に、サービスや製品の提供方法そのものを再設計し、顧客が本当に望んでいる体験をつくっていく。そうすることで、信頼やロイヤルティが生まれ、それが継続的な差別化につながっていきます。
③プラットフォームの機会を見つける
デジタル化が進んだことで、製品やサービスは単なる提供物ではなく、ユーザーとの関係を深めるチャネルとしての役割を果たすようになりました。今では、ひとつの製品やサービスが、新たな体験や価値へとつながる「入口」にもなっています。だからこそ、あらゆる企業が、製品やサービスを起点にプラットフォームへと展開する可能性を積極的に検討すべきです。
その第一歩として、自社だけでなくビックテックやサプライヤーなどの競合他社を含め、どのように価値を提供できるかを考えることが重要です。
④エコシステム全体を設計・育成
スマート・ライバルは、自社を中心に据えつつ、顧客、パートナー、データプロバイダー、ビッグ・テックまでも巻き込んだ広いネットワークを戦略的に構築します。すでに整っているリソースを活用することも可能です。たとえば、YouTubeの無料教育コンテンツ、Googleのオープンソース技術、Amazonのレビューシステムなどは、誰もが活用できるエコシステムの一部です。
この視点の転換は、企業にとって大きな成長のきっかけとなります。アンカーがアマゾンだけでなく、ウォルマートやアップルストアなどとの接点を増やし、自社のエコシステムを拡張していったように、主導権を握るかどうかは見方次第なのです。
⑤フレネミーとの関係を管理する
ビッグ・テックは時に協力相手であり、同時に競争相手にもなり得ます。この矛盾した関係をどう設計し、どう使いこなすかが企業の持続性を左右します。
ベスト・バイはAmazonとの関係を再構築しました。当初はライバル視していたAmazonに対し、店舗をショールームとして開放し、顧客に触れてもらう場を提供することで協業に転じました。結果としてAmazonは、ベスト・バイの店舗を活用してFire TVシリーズを展開できるようになり、ベスト・バイはリアルチャネルの強みを収益化することに成功しています。
⑥ディスラプションから立ち直る
市場のルールが急激に変わる場面では、過去の成功体験が通用しなくなります。しかし、それは「終わり」ではなく、新たな成長軌道のスタート地点でもあります。重要なのは、自社の強みを活かして、どこに軸足を移すかという判断です。
富士フイルムが医療や化粧品に活路を見出したように、あるいはアップルがPCからスマートフォンへと軸を移したように、柔軟な再定義こそが持続可能性を生むのです。
ディスラプションのスピードが緩やかならば対抗も可能ですし、あまりにも早い場合は潔く撤退し、新たな強みの上にビジネスを構築する選択もあります。いずれにしても、変化を察知し、勝てる場所にリソースを集中する――その「柔軟さ」と「勇気」が、スマート・ライバルに共通する資質です。
これら6つの戦略は、単なる理論ではありません。実在の企業が実践し、成果を上げてきたリアルな知恵です。そして、これからの時代、ビッグ・テックの真似をするのではなく、自社らしく、そして戦略的に成長を目指すすべての企業にとって、欠かせない思考の軸になるはずです。
従来型企業の勝つための選択肢は一つではありません。むしろ、「自分たちにしかできない勝ち方」を選べる企業こそが、これからの市場で価値を持ち続けていくのです。





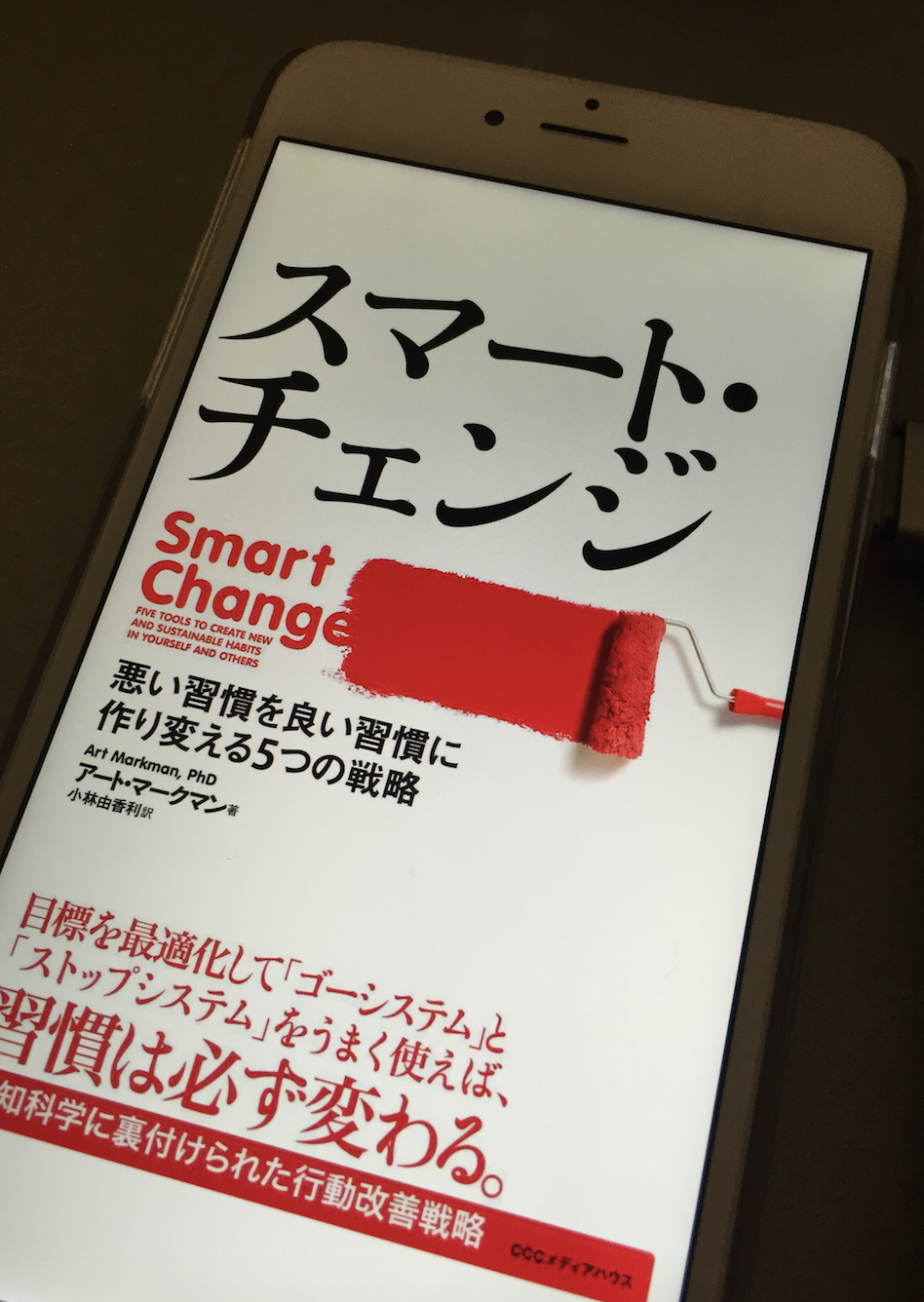



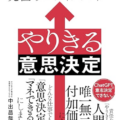
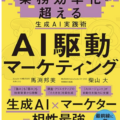

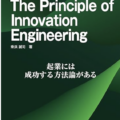


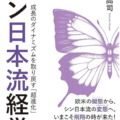


コメント