不条理な会社人生から自由になる方法 働き方2.0vs4.0
橘玲
PHP出版
不条理な会社人生から自由になる方法 働き方2.0vs4.0 (橘玲)の要約
橘玲氏の『働き方2.0vs4.0』は、日本型雇用の限界を鋭く突き、これからの時代に必要な「個人の信頼」で生きる働き方を提示する一冊です。ゼネラリスト文化や年功序列から脱却し、自らの専門性を磨き、フリーエージェントとして信頼を積み重ねることが、生き残る鍵となります。会社に依存せず、人的資本を育てながら自由に働く未来へ向け、読者に強い行動の示唆を与えてくれます。
日本型の働き方の課題とは?
当然のことながら、ジョブ型では「正社員」などという身分はなく、同じ仕事をしていても、親会社から出向してきた社員の方が給与が高いなどという慣習が許される はずもありません。ここからわかるように、本気で「差別のない働き方」を目指すなら、日本的雇用を徹底的に「破壊」してジョブ型につくり変えなくてはならないのです。(橘玲)
日本の働き方には、深層にわたる構造的な問題が根強く存在しています。年功序列や終身雇用といった制度は、かつて高度経済成長を支えた成功モデルでありましたが、現代においてはもはや時代遅れとなり、柔軟性や専門性を欠く要因として多くの弊害を生んでいます。
そうした中で、橘玲氏の不条理な会社人生から自由になる方法 働き方2.0vs4.0は、働き方の本質的な転換を促し、日本社会に深く根を張る雇用制度の矛盾を鋭くえぐり出す問題作となっています。本書は、単なる改革論にとどまらず、未来における個人の生き方そのものを問い直す意義深い一冊です。
著者は、現代の働き方を1.0から5.0までの5段階に分類し、各ステージの特徴を具体的に解説しています。働き方1.0は、日本的な雇用の原型であり、終身雇用・年功序列・横並びの評価制度に基づいています。働き方2.0は、成果主義や個人の実績に焦点を当てたグローバル標準の制度であり、日本でも「働き方改革」によってこの2.0への移行が試みられてきました。
しかしながら、著者はこの移行が表層的で、構造的な変革には至っていないと批判します。なぜなら、日本社会はいまだに「会社と運命を共にする」ことを美徳とし、年齢や役職によって評価される文化が色濃く残っているからです。
橘氏は、日本が現在もなお1.0に留まりつつ、せいぜい2.0を目指す程度に過ぎない一方で、世界では3.0や4.0の段階へと加速度的に進んでいることを鋭く指摘します。 本書の中で、特に強調されているのが、日本企業におけるゼネラリスト志向の問題です。多くの企業では社員が数年ごとに部署を異動させられ、幅広い業務経験を積むことが奨励されていますが、これは逆に言えば、専門性の欠如を意味します。
その結果、交渉の場や専門的判断が求められる局面で日本人が無力であるという実態が明らかになってきました。特に学士卒の国家公務員がグローバルのスペシャリストに太刀打ちできないことを明らかにしています。
日本の大企業の総務から営業へ、営業から経理へといった異動が当たり前のように行われる文化は、欧米のビジネスパーソンから見ると非常に奇異であり、キャリア形成において致命的な断絶を引き起こす原因になっています。
このような構造のもとで働く人々は、自分の力ではなく、企業の看板に依存する傾向が強まります。その結果、退職や定年を迎えたときに、自身のスキルや人脈がほとんど残っていないという現象が多く見られるようになっています。
特に中高年層にとって、企業を離れた後に再び社会と接続するのは非常に困難であり、そのことが精神的な孤立感や経済的不安を生む大きな要因となっています。
一方、海外ではすでにジョブ型の働き方が浸透しており、特にGAFAやNetflixのような先進企業では、専門スキルを持つ人材が高待遇で迎えられています。プロフェッショナルとしての成果が重視される文化の中では、実力がある者が正当に評価され、必要に応じて外部からも積極的に人材が登用されます。
Netflixでは、「会社は家族ではない」という考え方のもと、成果を出せなければどれだけ努力していても容赦なく契約を打ち切られますが、これは「人材の質」こそが最大の資本であるという強烈なメッセージでもあります。
こうしたジョブ型社会では、職務記述書に基づいて仕事の内容と報酬が定められており、自然と「同一労働同一賃金」が実現されています。若者とシニアが同じ職務に就いていれば、年齢やキャリアにかかわらず、同一の報酬が支払われます。優秀な人にはより高い給与が、職場にフィットしなくなった人には退職する道が示されます。
これは極めて公平で透明性の高い仕組みであり、日本のように正規社員と非正規社員が同じ仕事をしても待遇に大きな差があるような事態とは無縁です。しかしながら、こうしたジョブ型制度の導入には日本の労働組合が強く反発しており、正社員の既得権益を守るために改革に抵抗している現実もあります。
人的資本を拡大することが、豊かになる秘訣
「前近代的な身分制」の産物であるサラリーマンは、バックオフィスの一部、中間管理職、スペシャリストの一部が渾然一体となったきわめて特殊な「身分」です。こうした働き方はグローバルな雇用制度では存在する余地がありません。あと10年もすれば、サラリーマンは確実に絶滅することになるのです。
橘氏はこれからの時代、会社の名前よりも個人のプロフィールや信頼が重要になると断言します。会社の看板に頼るのではなく、自分の名前で仕事が舞い込む状態をつくる。そのためには、現役時代から専門性を磨き、信頼を積み重ねていくことが不可欠です。
雇用されている期間は、自らの人的資本を育てる準備期間と捉えるべきであり、これは将来的な自立に向けた極めて実践的な戦略と言えるでしょう。
「好きなことで生きていくなんて、甘い考えだ」と批判する声もあるかもしれません。しかし、その否定の裏には「働くこと=苦役」という前提があります。もし本当に労働が苦役でしかないのなら、60年間も苦しみ続ける人生に耐えられる人がどれほどいるでしょうか?
橘氏はむしろ、好きなこと、得意なことに打ち込みながら長く働く方が、現実的で幸福な生き方だと説いています。 人的資本をどう活かすかが、これからの時代の鍵になります。自分のスキルを高め、長く活かし、世帯全体で人的資本を運用する。
たとえば、60歳を過ぎても年収300万円で働き続ければ、70歳までに3,000万円、80歳までなら6,000万円の収入になります。「老後が長すぎる」という不安も、好きな仕事で働き続けられれば消えてしまうのです。
欧米では「長く働く」ことがすでにライフスタイルの前提となっており、日本も今後この流れに追いつくことになるでしょう。共働きによる世帯内の人的資本活用も、より豊かな将来を築く現実的な選択肢となります。
また、高度に発展したネットワーク社会では、所属する企業の規模よりも「個人の評判」が成功の決定要因になります。知識や人脈を惜しみなく他者に提供し、周囲から「信頼される人」になることが、ネットワーク内での地位を築く最良の方法です。
誰かの困っているときに、仕事を紹介する、知人を紹介する――それだけで信頼は生まれ、コストもほとんどかかりません。 未来を生き抜く鍵は、「会社員として働く時間も、フリーエージェントとしての自分を育てる時間」として活用することです。会社の名前に頼らず、自分の名前で信頼を得る。それができる人だけが、これからの時代を軽やかに生き抜いていけるのです。
私自身も独立後、人と人をつなぐ、ギバーとしての役割を意識してきました。若い世代とおじさん世代、ベンチャーと投資家をつなぐことで、多くの人から感謝され、結果的に自分のパーソナルブランドも強化されました。
実際にアメリカでは、すでに全就労者の約4分の1がフリーエージェントとして働いており、SNSや人材プラットフォームを活用して仕事を得る仕組みが整っています。こうした動きは、テクノロジーの発達によって個人の評判やスキルが可視化されるようになったことに支えられています。
この新しい働き方はコロナ禍により加速しています。リモートワークが一般化し、専門性さえあれば、場所に縛られずどこでも仕事ができることが証明されたのです。
アメリカでは、会社に縛られないクリエイティブな人々が次々に独立しており、その波は日本にも確実に広がりつつあります。 実際、ギグワーカーやフリーランスの人々は、サラリーマンよりも高い幸福度を感じているという調査結果もあります。
今後は、GAFAのような巨大なプラットフォーム企業と、それを活用して自由に働くフリーエージェントやマイクロ法人が、経済の主役になっていくと予想されます。「大企業に勤めていれば安心」という時代は、もはや過去のものになりました。
若い世代にとっては、最初に入社した会社に執着するよりも、3年ごとに自分のキャリアを振り返り、成長ややりがいを求めて柔軟に動くことが、新たなスタンダードとなっていくはずです。
「未来世界」で生き延びるのは、会社に所属しているときでも常に「フリーエージェント」として仕事をしていると考え、会社のブランドに依存するのではなく、自分自身のよい評判を増やしていけるひとです。そしてこれは、本書の読者なら難しいことではないでしょう。
本書は、単なる働き方の解説書ではありません。これは、日本的雇用の根幹に挑戦する「生き方のマニフェスト」であり、すべてのサラリーマン、すべてのビジネスパーソンに「あなたはどう生きるのか?」と真正面から問いかけてきます。
会社の上司や同僚との付き合いに疲れている人、働き方にモヤモヤしている人、将来が不安な人にとって、本書は視野を広げ、行動を後押ししてくれる生き方のガイドブックになってくれます。






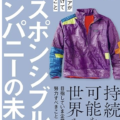

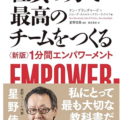



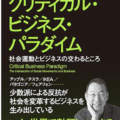




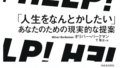

コメント