 AI
AI
山本康正氏の2025年を制覇する破壊的企業の書評
 AI
AI  チームワーク
チームワーク  セレクト
セレクト  イノベーション
イノベーション  文化
文化  イノベーション
イノベーション  イノベーション
イノベーション  セレクト
セレクト  セレクト
セレクト  セレクト
セレクト  セレクト
セレクト  セレクト
セレクト  AI
AI  AI
AI  イノベーション
イノベーション  セレクト
セレクト  セレクト
セレクト  サブスクリプションモデル
サブスクリプションモデル  コミュニケーション
コミュニケーション 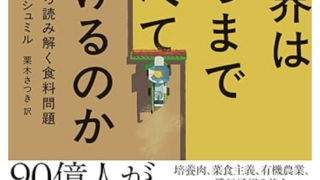 イノベーション
イノベーション 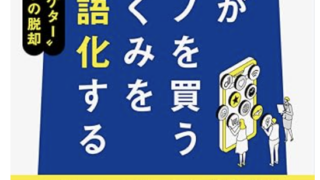 コミュニケーション
コミュニケーション 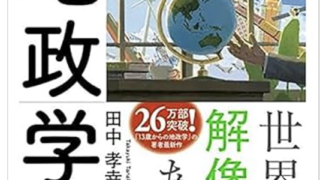 歴史
歴史  パーパス
パーパス 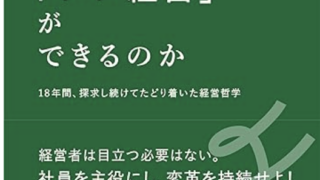 習慣化
習慣化 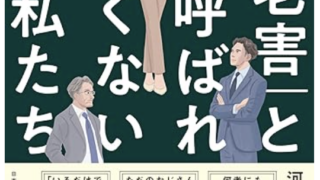 チームワーク
チームワーク  ウェルビーイング
ウェルビーイング 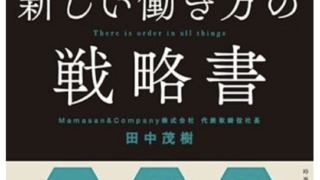 チームワーク
チームワーク 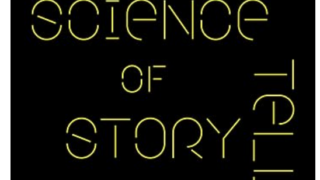 フレームワーク
フレームワーク