ベンチャーの作法――「結果がすべて」の世界で速さと成果を両取りする仕事術
高野秀敏
ダイヤモンド社
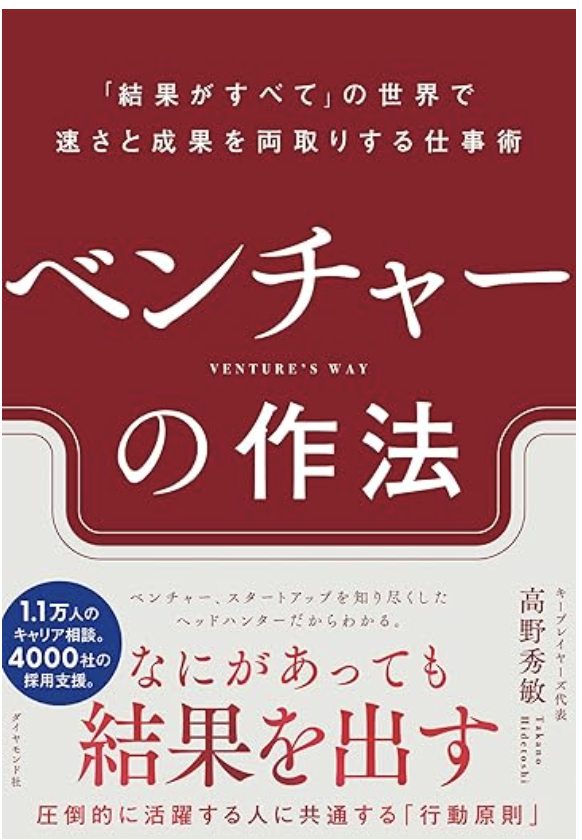
ベンチャーの作法(高野秀敏)の要約
ベンチャーは成長を求め、変化を受け入れ、挑戦し続ける企業です。結果を出せばモチベーションは上がり、経営者から評価されるのは素早く行動する「セカンドペンギン」です。変化に適応し、全力でやり抜く姿勢が重要であり、経営方針の朝令暮改も当たり前の環境です。投資家の視線を意識し、スピーディに最適な選択をし、諦めずに行動し続けることが、成功するベンチャーの条件なのです。
結果を出すために必要なベンチャーの作法とは?
成長途上の組織には、結果を出すための、「作法」がある。ベンチャーやスタートアップ。 あなたが「成長途上の組織」にいるのであれば、 この作法は必ず押さえなくてはならない。 結果を出せないやつは、不要だからだ。(高野秀敏)
成長途上の組織で成果を出すためには、独自の作法があるとされています。特にベンチャー企業やスタートアップのような環境では、限られたリソースと時間の中で、いかに効率よく結果を出せるかが求められます。
本書ベンチャーの作法では、これまで1.1万人以上のキャリア相談や4000社以上の採用支援を行ってきた高野秀敏氏の経験をもとに、実践的な仕事術が提示されています。
成果を上げるために必要なのは、単なる努力ではなく、戦略的に仕事を進める姿勢です。 仕事において最も重要なのは「結果を出すこと」です。結果を出せなければ、組織にとって必要とされません。
逆に、成果を出すことができれば、評価され、成長の機会も増えます。仕事のモチベーションや充実感も、結果を出すことで生まれるものです。まずは成果を上げることに集中し、その中で経験を積み重ねていくことが大切です。
著者は本書で以下の5つの作法を紹介しています。
・「目標設定」の作法
・「任務遂行」の作法
・「指示対応」の作法
・「連帯形成」の作法
・「職務越境」の作法
これらのマインドセットを身につけることで、結果を出せる人になれると言うのです。
スタートアップやベンチャーの組織においては、考えるだけや批評するだけでは、何も得られません。行動し、成果を積み重ねることで、新しいチャンスが生まれます。
ベンチャー企業の環境では、待っているだけでは何も始まりません。上司や経営者からの指示を待つのではなく、自ら考え、動くことが求められます。他人のせいにするのではなく、自分が何をすべきかを考え、主体的に動く姿勢が重要です。
問題に直面した際も、他責思考ではなく、自責思考を持ち、自分の行動で状況を改善することが、成長につながります。 大企業では、業務の進め方を逐一確認しながら慎重に進めることが評価される場合もあります。しかし、ベンチャーではスピードが求められます。
なぜならベンチャーにとって、現状維持は「死」と同じだから。 つねに行動を起こして、何かしらの結果を得て、それを振り返り、次につなげる。 そうやって、さらに大きな結果を出す。 PDCAをつねに回し続ける必要があります。というよりもDDDDDDDCAくらいのイメージです。 これが成長途上の組織で求められる姿勢です。
指示を待つのではなく、経営陣が考えていないことまで想像し、自分で判断しながら進めることが必要です。仕事の完成度にこだわるよりも、まずは8割の完成度で動き出し、フィードバックを受けながらブラッシュアップしていくことが大切です。
この「仮説検証」のサイクルを素早く回すことで、効率よく成果を上げることができます。 また、すべての業務に手を出すのではなく、最も成果を出せる領域に集中することも重要です。
限られたリソースを最大限に活用し、影響の大きい仕事にフォーカスすることで、短期間で大きな成果を生み出せます。 ベンチャーでは、「頭脳になるな、手足となれ」という考え方が有効です。最初からすべてを考え抜くのではなく、まずは経営者の意図を理解し、行動することが成長への近道となります。
経営陣の指示を的確に実行し、スピーディーに動くことで、組織の成長に貢献できます。経験を積む中で、次第に意思決定を行う力も身についていきます。 成果を出す過程では、必ず批判に直面します。特にベンチャーのように変化の激しい環境では、新しい取り組みに対して否定的な意見が出ることも少なくありません。
しかし、批判に対して一喜一憂するのではなく、「気にしない力」を持つことが重要です。批判をする人の多くは、実際に行動する勇気を持たないことが多いものです。批判に時間を費やすよりも、自ら行動し、結果を出すことに集中すべきです。
朝令朝改が当たり前の組織で結果を出す方法とは?
熱い想いを持っている経営者や社員がいて、ひたむきに「成長を目指している」企業のことです。 創業から数十年が経っていても、従業員数が数十人でも数千人でも、都心にあっても地方にあっても、前に進むための新たな挑戦に挑むすべての企業が「ベンチャー」です。
ベンチャーとは、熱い想いを持つ経営者や社員がいて、ひたむきに成長を目指している企業のことだと著者は定義しています。創業から数十年が経過していても、従業員の数が少なくても多くても、都心にあっても地方にあっても、前に進むために新たな挑戦を続ける企業はすべてベンチャーといえます。企業が成長を求め、変化を受け入れ、挑戦を続ける姿勢こそが、ベンチャーの本質なのです。
モチベーションは、結果を出せば自然と上がるものです。やりたくないことや苦手なことでも、実際にやってみると思いのほかうまくいくことは少なくありません。そして、それを誰かに認められたとき、人はさらに挑戦しようという意欲を持ちます。努力が結果につながり、評価されることで承認欲求が満たされていきます。その経験を繰り返すことで自分の価値を見出し、それが自己実現へとつながっていくのです。成果を出すことが、次の成長の原動力となります。
ベンチャーにおいて結果を出し、評価されるのは「セカンドペンギン」と呼ばれる存在です。勇敢に先陣を切って海に飛び込むファーストペンギン(創業者)のあとを追い、多くの「普通のペンギンたち」を引っ張る役割を果たすのがセカンドペンギンです。いち社員として求められるのは、このセカンドペンギンのような行動を取ることです。経営者が示した戦略や戦術に素直に乗り、確実に任務を遂行する人が評価されます。
主体的に考え、動くことはもちろん大切ですが、まずは組織の方針に従い、全力でやり抜くことが最も重要なのです。 仕事のスピードを上げることは、やるべきことを減らすためではありません。むしろ、やるべきことをすべてこなすためにスピードを上げるのです。
業務が多すぎるからといって取捨選択をしていては、成長の機会を失うことになります。効率化を追求しながらも、必要なことをすべてやり切る。その積み重ねが、自身の成長だけでなく、企業全体の成長につながるのです。
長く続いている企業や組織ほど、絶えず変化を繰り返しています。たとえば、京都の老舗のお茶屋が何百年も続いている理由は、「三割は常に挑戦せよ」という教えを守っているからだとされています。新しい試みに挑戦し、失敗と成功を繰り返しながら変化を重ねてきたからこそ、伝統を守り続けることができたのです。現状維持ではなく、絶えず進化し続けることこそが、企業が生き残るための条件なのです。
ベンチャー企業は、経営者の情熱だけで動くものではなく、常に投資家の厳しい視線のもとで判断が行われています。成長の速度や市場での競争力が厳しく問われるため、経営層は適切なタイミングで変化に適応し、最速で最良の判断を下すことが求められます。投資家が求めるのは、ビジョンだけでなく、実際に成長を証明するスピーディな実行力です。
市場環境が目まぐるしく変化するなか、経営者の判断が遅れれば、競争の波に飲み込まれてしまいます。そのため、指示や方針が短期間で変わることもあり、社員はその変化に柔軟に対応する力を身につけなければなりません。 経営者が社員を評価するとき、最も重視するのは「やり抜く人かどうか」という点です。
途中で諦めず、何があっても最後までやり遂げる姿勢こそが、組織にとって価値のあるものと判断されます。結果が出るまでやり続けることが、成功の鍵となります。最後に勝つのは、やり抜いた人や企業なのです。
経営者の指示が時に唐突に思えたり、納得できなかったりすることもあるかもしれません。しかし、経営者には社員が知り得ない情報が数多くあります。資金繰りの問題、重要な取引先の動向、エース社員の退職リスク、競合企業からの訴訟の可能性、さらには社内の不正など、経営者はさまざまな問題を抱えながら判断を下しています。
こうした情報をすべて公開できるわけではないため、指示が不合理に思えても、実は深い理由があるのです。社員からは見えない景色を経営者は見ています。
そのため、経営者の判断を信じ、全力で取り組む姿勢が求められます。 ベンチャーでは、経営方針が頻繁に変わることも珍しくありません。朝決めたことが昼に修正され、夕方にはさらに変更されることもあります。大企業とは異なり、朝令暮改や朝令朝改が当たり前の環境なのです。変化の激しいビジネス環境の中で成長するためには、柔軟に対応し、方向転換にも素早く適応する力が必要です。
経営者の判断に対して根拠を求めたり、陰で批判をしたりすることに時間を費やしても意味はありません。経営者の決断が正しいかどうかを疑うのではなく、その決断を「正解」にするために全力で取り組むことこそが、組織の一員としてのあるべき姿です。 成長を続けるベンチャー企業において、生き残るのは変化を恐れず、やり抜く人です。やりたくないことや苦手なことにも挑戦し、結果を出し続けることで、自身の価値が生まれ、評価されるようになります。
変化を受け入れ、スピードを上げ、指示に素直に従いながら、成果を最大化することが、ベンチャーで成功するための絶対条件なのです。投資家が見守るなかで、変化をチャンスと捉え、素早く行動を選択できる企業こそが、これからの市場で生き残る存在となるのです。
本書が示しているのは、単なる努力ではなく、成果を出すための具体的なアプローチです。がむしゃらに働くだけではなく、いかに効率よく結果を出せるかを考え、実行することが、ベンチャーで成功するための鍵となります。この作法を身につけることで、どんな環境でも結果を残せる人材へと成長できるのです。
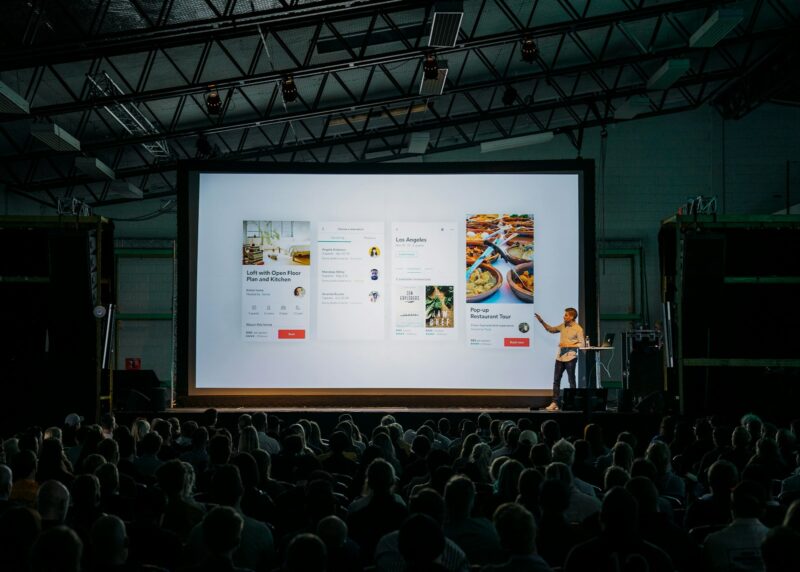














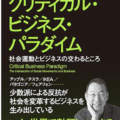


コメント