世界最高の質問術―一流のビジネスリーダー45人が実践する人を動かす「問いかけ」の極意―
マイケル・J・マーコード, ボブ・ティード他
新潮社
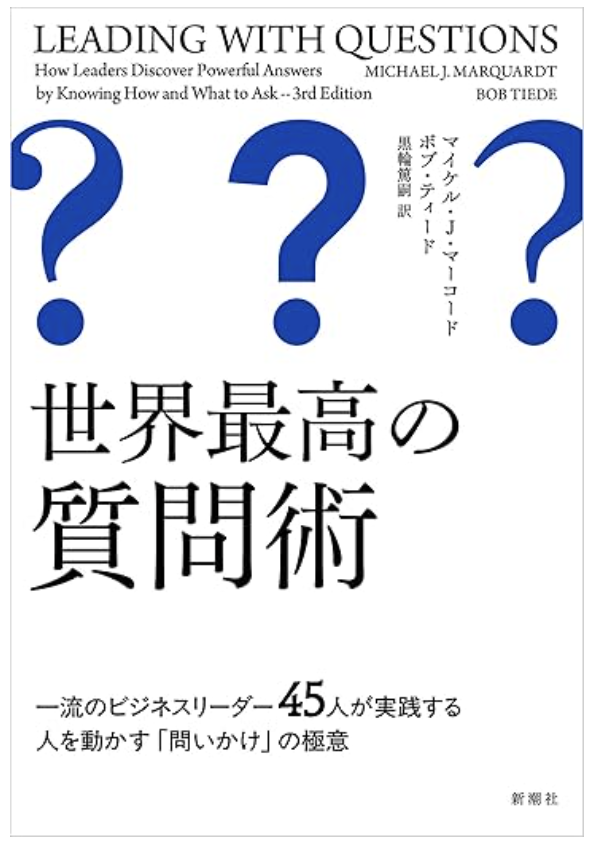
世界最高の質問術 (マイケル・J・マーコード, ボブ・ティード他)の要約
質問は、リーダーが部下の力を引き出し、組織を変革するための重要な手段です。リーダー自身がすべての答えを持つ必要はなく、適切な問いかけによってチームの知恵と創造性を引き出すことが可能になります。問いを中心に据えた文化は、学習と成長を促進し、個々の主体性や自信を育てます。変化の激しい時代において、問い続ける姿勢こそが、強くしなやかな組織を築く鍵となるのです。
エンパワーさせる質問がチーダーに不可欠な理由
世の賢いリーダーたちはメンバーの意欲向上にも、チームワークの改善にも、 画期的なアイデアや常識にとらわれない発想の促進にも、部下に権限を与えてその能力を引き出すエンパワーメントにも、顧客との関係の構築にも、問題解決にも、リーダーシップの強化にも、組織やコミュニティーの変革にも、質問を使っている。(マイケル・J・マーコード, ボブ・ティード)
ジョージ・ワシントン大学名誉教授のマイケル・J・マーコードと、リーダーシップ開発の専門家ボブ・ティードの世界最高の質問術は、質問という行為がリーダーシップにおいて持つ深い影響力を説得力をもって伝えています。彼らは、「問いかけ」を通じてチームの潜在能力を引き出し、組織の持続可能な成長を促す方法を具体的に示しています。
マーコードは、人材開発および組織学習の世界的な権威であり、「World Institute for Action Learning(WIAL)」の共同創設者として、アクションラーニングの分野で第一人者として知られています。
一方、ティードは国際的クリスチャン組織「Cru(旧Campus Crusade for Christ)」において、50年以上にわたりリーダーシップ開発に携わってきました。2人は、それぞれの経験と知見を統合し、質問術を軸にリーダーシップの新しいあり方を提唱しています。
わたしたちは往々にして、「能力を引き出す(エンパワーメント)」質問ではなく、「能力を抑圧する(ディスエンパワーメント)」質問をしてしまいがちです。それらは、責任の追及ばかりを目的としていて、情報や改善策を求める本当の質問になっていないことが多いのです。
このような質問は、チームメンバーの意欲を削ぎ、組織の活力や創造性を失わせます。リーダーが意識的にエンパワーメント型の質問を活用しなければ、せっかくの潜在力を抑圧してしまうリスクがあることを彼らは強く警告しています。
彼らが本書で強調するのは、「すべての答えを持つリーダー」よりも、「適切な質問を投げかけられるリーダー」こそが真に組織を前進させるという点です。一流のリーダー45人の具体的な事例を通じて、質問を戦略的に活用することでチームの創造性が高まり、問題解決力が飛躍的に向上することを示しています。
実際にマリオットやデュポン、カーギルなど世界的な企業の成功事例を取り上げ、質問を使ったコミュニケーションが組織文化の変革に直結することを具体的に証明しています。
質問しやすい文化を組織に根付かせることは、単にコミュニケーションを円滑にするというだけではありません。実際には、組織全体を大きく成長させるパワフルな基盤となります。
質問しやすい文化においては、個人や組織の学習が促され、意思決定や問題解決力やチームワークが改善し、変化への適応力や対処力が向上する。さらに各個人に自覚や自信が芽生えることにより、それぞれの能力が引き出されやすくもなる。
質問を歓迎する雰囲気があると、個人やチームが主体的に考え、積極的に学習しようとする意欲が高まります。これにより、メンバー同士のコミュニケーションが自然と活性化され、チーム内での共通理解が深まります。その結果、組織としての意思決定の精度や問題解決の質が大幅に向上するのです。
また、日頃から質問を自由に行える環境に身を置くことで、メンバーは変化を前向きに捉える力や、柔軟に対応する能力を育んでいきます。つまり、問いを通じて新たな視点やアイデアが生まれ、これまでにない創造的な解決策が導き出されるのです。 さらに、質問しやすい文化はメンバー一人ひとりの自信や自覚を促します。自ら問いを立てることによって、自分の役割や可能性について深く考えるようになり、それぞれが持つ潜在的な力を引き出しやすくなるのです。
このエンパワーメントの効果こそが、組織の持続的な成長を実現するために必要な原動力となります。 したがって、リーダーが率先して質問する姿勢を示し、メンバーに問いかけを促すことによって、組織全体が学び合い、進化し続けるための強力な土台を築くことができるようになるのです。
リーダーの質問によって、組織文化が変わり、成長が加速する理由
質問で率いるリーダーはビジネスを成功に導くだけでなく、働きやすい職場環境も築く。質問を使えば、リーダーは部下の能力を真に引き出して、組織を変えられる。
多くのリーダーは、経験を重ねるにつれて「自分が答えを持っている」と思い込みやすくなります。しかし、変化のスピードが加速する現在において、その思い込みこそが、組織の成長を止める最大のリスクとなり得ます。 本当に変化に強い組織とは、リーダーがすべてを語る組織ではありません。
むしろ、社員が主体的に問いを立て、自ら考え、声を上げられる環境を持つ組織こそが、時代に適応し続ける力を持っています。現場には常に未来の兆しが存在しており、その兆しにアクセスする最も有効な手段が「問いかけ」なのです。 昨日の成功体験が、明日の課題を解決できるとは限りません。過去のやり方に頼りすぎることで、変化の兆候を見逃してしまうこともあります。
だからこそ、リーダーには常に「問い直す力」が求められます。この力こそが、組織を未来へ導く羅針盤となるのです。 問いは、学びを生み出します。そして、学びは変化への適応力を育てます。問いを起点にした組織では、社員一人ひとりが自律的に考え、行動するようになります。そうした個々の学びの積み重ねが、やがて組織全体の進化へとつながっていくのです。
しかし現実には、多くの組織で「問いかけ」の重要性が軽視されています。「忙しいから」「早く成果を出さなければならないから」といった理由で、問いを立てることが後回しにされがちです。その結果、短期的な成果は得られても、長期的な競争力を失うリスクが高まります。 持続的に成長し続ける組織をつくるためには、「問い」を中心に据えた学習文化を育てていくことが不可欠です。
これは単なるマネジメント手法ではなく、組織の在り方そのものを見直す取り組みなのです。 これからの時代に求められるのは、「正しい答えを知っているリーダー」ではなく、「問い続けるリーダー」です。問いを通じて学び続ける文化こそが、変化に強い組織を生み出す鍵となります。リーダー自身が「問い続ける姿勢」を率先して示すことが、組織を次のステージへと導くための第一歩となるでしょう。
リーダーとマネジャーの違いについて、ハーバード・ビジネス・スクールのジョン・コッターは次のように述べています。「リーダーは『適切な問いを考えること』に注力し、マネジャーは『その問いに対する答えを見つけること』に力を注ぐのだ」と。まさにこの視点こそが、リーダーシップの本質を捉えていると言えるでしょう。
さらに、フォード・モーター元CEOのドナルド・ピーターセンも、「質問すればするほど、リーダーはすべての答えを知っている必要がなくなる」と語っています。リーダーが完璧な答えを持つ必要はなく、むしろ優れた問いを投げかけることが、チームや組織全体の知恵を引き出す起点となるのです。
このブログでもお馴染みの著名な経営思想家たちも、問いの力に注目しています。『ビジョナリー・カンパニー』で知られるジム・コリンズや、『学習する組織』の著者ピーター・センゲ、そして組織文化論の第一人者エドガー・シャインなどがそれぞれの観点から、問いがいかに組織に大きなインパクトをもたらすかを体系的に論じています。
特にピーター・センゲの「リーダーはどのように問いを立てるべきか」という提言は、実践的かつ示唆に富んでいます。以下に、その要点を紹介します。
・状況を把握し、より大きな文脈を捉える
現在のビジネス環境を広く見渡し、その輪郭を掴みます。状況の悪化や好転の兆しに敏感になることが重要です。
・核となる問いを見つける
問いを分類し、それぞれの問いの関係性を明確にします。背後にある深いテーマや構造的課題を見抜くことが求められます。
・「何が可能か」を思い描く
「大きな問い」に対する答えが見えてきたら、それによって生まれる可能性を明確に想像します。将来の状況をできるだけ具体的に思い描くことが鍵です。
・実行可能な戦略を練る
切実な問いから導き出された答えと、それによって喚起された展望をもとに、実行可能な戦略を設計します。
このように、問いは単なるコミュニケーション手段ではなく、組織の未来を形づくる起点になります。問いを磨くことは、リーダー自身の視野を広げ、組織全体の成長に直結するのです。
傑出した成功を収めた人たちが頂点を極められたのは、自分の身に起こったことのおかげでも、他者に命じたことのおかげでもない。自分の身に起こったことや、自分の周りの人や環境について、問い続けたおかげだ。
多くのリーダーは、問いの力を過小評価しがちです。表面的なマネジメントにとどまり、ほとんど質問をしないまま、状況に対応しようとすることも少なくありません。自分自身に問いかけることもせず、結果として、組織やチームが本来持つ可能性を引き出す機会を逃してしまいます。
一方で、有能なリーダーは頻繁に問いを投げかけます。そして、その問いは単なる確認や詰問ではなく、本質を突いた、深い思考を促すものであることが多いのです。優れたリーダーであればあるほど、問いの質にこだわり、自分自身をも問い直す姿勢を大切にしています。
つまり、リーダーとして成長するためには、まず「良い質問」を意識的に行う習慣を身につけることが重要です。質問力を磨くことこそが、自らを高め、組織の未来を切り拓くための最短ルートであると言えるでしょう。
問いをリーダーシップの中心に据えることができれば、チームメンバーの主体性が引き出され、エンゲージメントが高まります。メンバー同士の対話が活性化され、共通理解が深まり、組織はより創造的で革新的な集団へと進化していきます。
問いの文化が根づいた組織では、メンバー一人ひとりが自分の役割や可能性を自覚し、自信をもって行動するようになります。こうした文化が持つエンパワーメントの力こそが、持続的な成長を実現するための強力なエネルギー源となるのです。 これからの時代において、問いかける力はリーダーにとって不可欠なスキルの一つです。
変化が激しく、答えのない課題が多くなる中で、問いを通じて組織を導いていくリーダーこそが、真に時代に求められる存在となるでしょう。
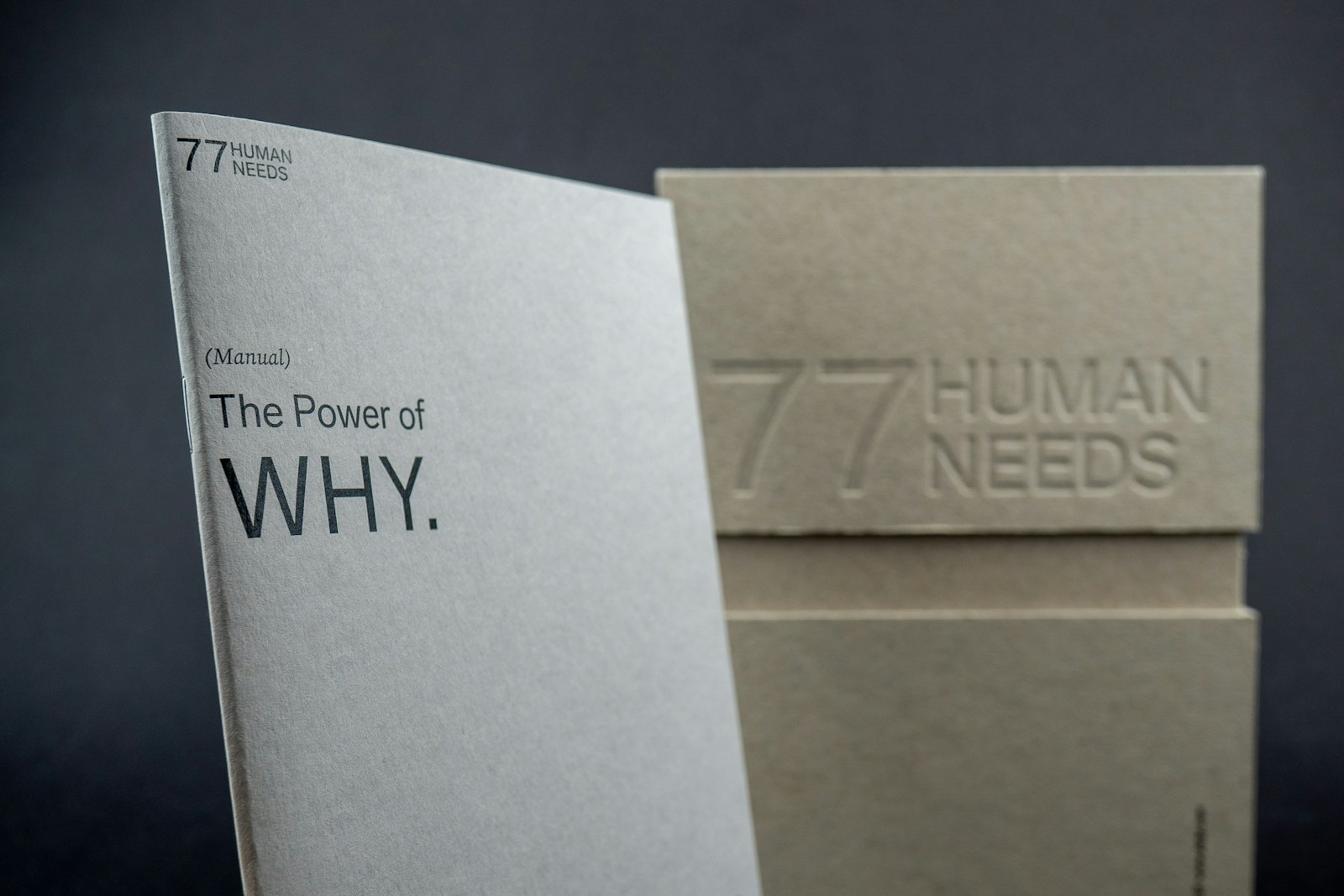




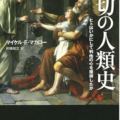
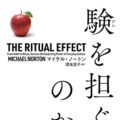











コメント