アフターAI 世界の一流には見えている生成AIの未来地図
シバタナオキ, 尾原和啓
日経BP
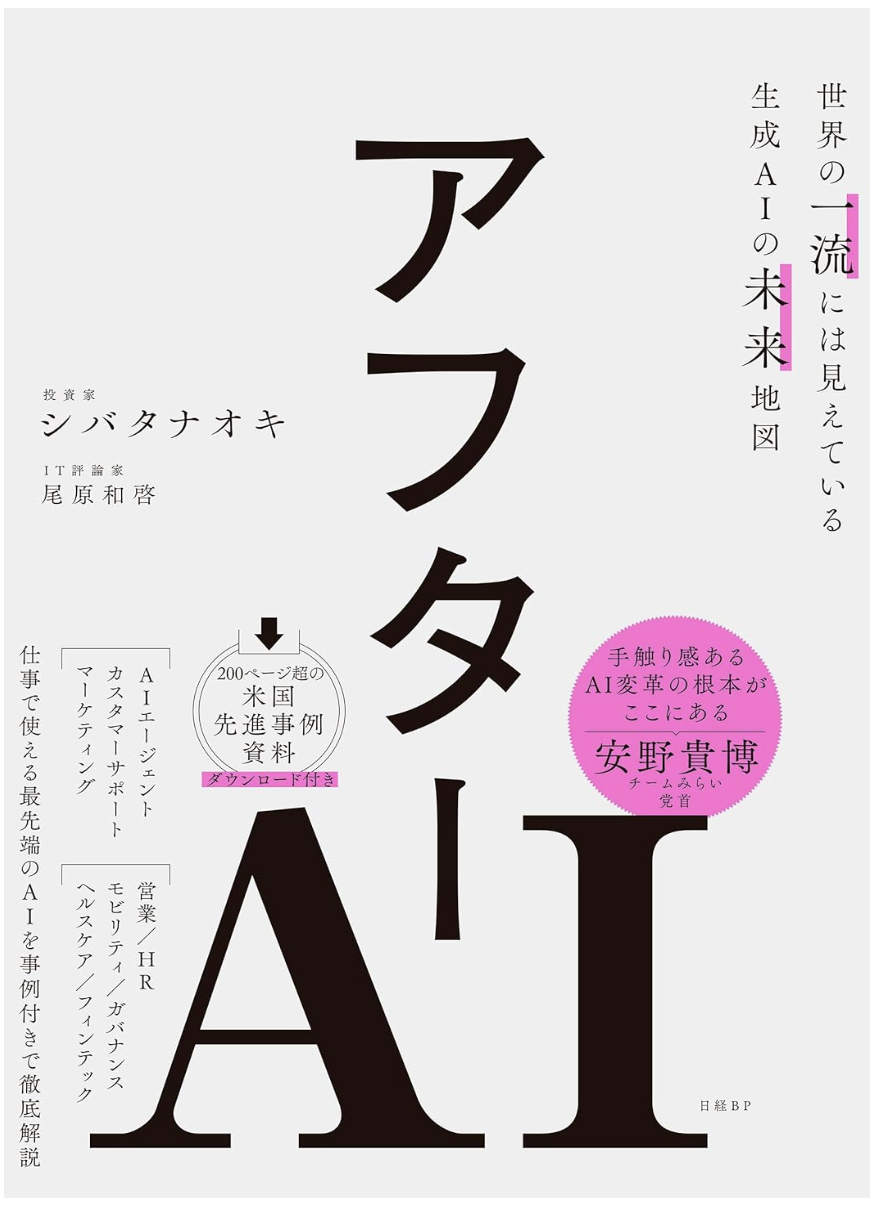
アフターAI 世界の一流には見えている生成AIの未来地図(シバタナオキ, 尾原和啓)の要約
生成AIの進化が企業の競争力を左右する時代、日本企業は慎重姿勢が目立ち、導入の遅れが課題となっています。本書『アフターAI』は、生成AIがもたらす社会やビジネスの変化を捉えつつ、日本の強みである現場力や暗黙知を活かす視点を示します。実践的なヒントに富んだ一冊です。
AI時代に日本企業が成長するために必要なこと
米国の経営者は報酬が株価に連動しているケースが多く、競合より早く最新技術を取り入れて優位性を築くことが使命です。そのため、生成AI導入を強力にトップダウンで推進するケースが圧倒的に多いです。一方、日本では「一応検討している」とは言うものの、実際には「様子見」の経営者がなお多数派で、導入段階になるとセキュリティやリスクの議論が先行し、結果として行動が遅れがちです。(シバタナオキ)
「生成AI元年」とも言われる現代、企業の競争力はテクノロジーの活用スピードに大きく左右されるようになっています。 アメリカや中国では、経営の意思決定において生成AIの導入が日常の風景となりつつあり、業務プロセスの革新や新たなビジネスモデルの創出が次々と生まれています。
一方、日本企業では、「検討中」という言葉が現場にあふれながらも、導入には慎重な姿勢が続いています。 経営者の多くは「検討中」と回答するものの、実態としては「様子見」が大半です。導入段階に進むと、セキュリティやリスクへの懸念が先行し、現場での実装にはなかなか至りません。その間にも海外企業は生成AIを活用し、業務プロセスやビジネスモデルを大胆に再構築し、目に見える成果を上げています。
アメリカでは、生成AIの導入が経営トップの主導で進められており、背景には経営者の報酬が株価に連動しているというインセンティブ構造があります。競合よりも早く技術を取り入れ、市場における優位性を確立することが期待されるため、リスクよりもスピードと効果が重視される傾向が強いのです。
米国在住の起業家・投資家のシバタナオキ氏と、数々の著作を持つIT批評家の尾原和啓氏による共著、アフターAI 世界の一流には見えている生成AIの未来地図は、そうした世界の潮流を的確に捉えています。
本書では、生成AIが単なる業務支援のツールにとどまらず、社会構造や人間の役割までも根底から変える存在であることが示されています。AIの機能や事例解説に加え、企業や個人がどのようにAIと共存し、未来を切り拓くべきかについて、実践的かつ具体的な提言が豊富に盛り込まれています。
海外の先進事例を通じて「AIが未来をどう変えるか」を立体的に描き出しており、読み終えた後には、自分自身の行動を見直したくなるような示唆と刺激に満ちた一冊です。
実際にアメリカでは、生成AIの活用が現場レベルで進んでいます。シバタ氏の体験によると、ある医療機関では、診察中の医師と患者の会話をAIがリアルタイムで文字起こしし、診療記録まで自動で生成する仕組みが導入されているといいます。医師は内容を確認して「送信」ボタンを押すだけで記録が完了します。 これは単なる業務の一部を補助するツールではなく、業務プロセスそのものを再構築する事例です。
こうしたスピーディーな実装力こそが、アメリカの競争力の源泉となっています。 一方の中国では、国家としてAIを戦略的に位置づけ、驚異的なスピードとスケールで成果を上げています。
ファストファッションのSHEINはその代表例で、SNSの投稿をAIが常時チェックし、トレンドを先読みして商品企画に反映。その後の製造・物流・販売に至るまでAIが活用されており、在庫リスクを最小限に抑えながら爆発的な販売力を実現しています。現在では、米国市場におけるファストファッションの売上の過半を握るまでに成長しています。
対照的に、日本では技術への関心は高いものの、組織内の調整や責任所在の不明確さなどが導入の障壁となっています。特に大企業が動かなければ、スタートアップも動けず、結果として国内エコシステムが育たないという悪循環に陥っているとシバタ氏は指摘します。
しかし、日本にも光はあります。著者らは、日本の大きな強みとして、製造・物流・営業・カスタマーサポートなど多岐にわたる分野で蓄積されてきた質の高い業務データの存在をあげています。これらは生成AIにとって極めて有効な学習素材となり得ます。
今後の業務変革の鍵を握るのが「AIエージェント」の存在です。AIエージェントは、従来のように人間の補助にとどまらず、自律的に業務を遂行する能力を備えています。とくに日本のように人手不足が深刻な社会においては、生産性向上の切り札ともなり得ます。
また、日本の大企業に多く見られる「タコツボ型」と呼ばれる部門最適化構造も、見方を変えれば、各部門に専門性が高度に蓄積されているとも言えます。このような環境にAIエージェントを導入すれば、きめ細かな自動化が可能となり、それぞれのエージェントが連携することで部門横断的な業務の最適化や、さらにはビジネスモデルの再構築につながる可能性もあるのです。
生成AIの導入は、もはや情報システム部門だけの話ではありません。企業全体の業務フローを根本から見直し、再構築する取り組みです。その中心にあるのが、生成AIでありAIエージェントです。 日本は「課題先進国」であると同時に、「潜在力のある国」でもあります。自社が持つデータ資産と業務知見を活かし、スピード感をもってAIを実装できる企業こそが、次の時代のリーダーになるのです。
フィジカルAIの衝撃
誰もがロボットを作れるようになり、誰もが自動運転車を開発できるような時代が到来すると、ハードウェアだけでは収益を得にくくなります。技術のコモディティ化が進む中で、本当の価値は「物理空間へのAIの実装」によって生まれていくのです。
AIとロボティクスなどのテクノロジーの民主化が進む中で、従来のようにハードウェア単体で収益を上げることは難しくなってきました。製品そのものではなく、「それをどう使い、どのようなサービスや体験を生み出すのか」が競争力の源泉に変わりつつあります。
こうした背景のもと、AIはスクリーンの中に閉じた存在から、現実空間へと活躍の場を広げています。モビリティやロボットといった分野において、AIは「フィジカルAI」として実空間での実装が進み始めています。これは単なる技術進化ではなく、AIが現実世界の課題に対してどのように価値を提供するのかという問いに向き合う動きでもあります。
その核となるのが「ワールドモデル」と呼ばれる技術です。AIが物理空間のルールを仮想的に学び、理解し、計画を立てられるようになることで、自動運転やロボティクスといった現場での適用が可能になります。
現実空間の複雑さをAIが内面化し、精緻な判断を下せるようになる――この進化は、単なる効率化ではなく、ビジネスそのものの構造を変える力を持っています。 汎用ロボットの進化もその一例です。
AIに一度教え込めば、多様なバリエーションを自ら生成し、さらに自律的に学習を重ねていくことができます。その結果、人間の専門家が担ってきた領域の再現すら可能になりつつあります。これは単なる労働の代替ではなく、「知」の構造を再編成する動きと捉えるべきでしょう。
実際に、Figureのようなヒューマノイドロボット企業や、太陽光発電の建設現場に特化したBuilt Roboticsのようなスタートアップが、この分野で革新的な成果を上げています。本書では、こうした最先端の事例を通じて、AIとロボティクスが実社会にもたらす変化が具体的に紹介されています。
自動運転も同様に、単なる移動手段の自動化ではなく、新たな収益モデルを生み出しています。テスラが構想するロボタクシーは、所有者が使っていない時間に自律的に走行し、収益を上げる仕組みを持っています。
しかしAIの導入は、サービスだけではなく、自動車そのものの価値向上にも大きな影響を与え始めています。AIは自動車に対して、航続距離の最適化、制動距離の短縮、滑らかな発進・停止、さらにはエネルギー効率の向上といった、安全性や快適性を向上させる面でも確実に成果を上げつつあります。
つまり、EVをAIで進化させていくことが、自動車そのものの付加価値を高めるのです。 SDV(Software Defined Vehicle)の時代には、ソフトウェアでアップデートができない自動車は、競争力を失っていく可能性が高まります。ソフトウェアが価値の中核を担う時代においても、自動車産業の本質的な価値は「自動車が売れること」に変わりはありません。売れる自動車を作るには、SDVとして設計・進化させる必要があるのです。
そして、走行状態などの実走行データが多いほど、ユーザーのニーズに即したアルゴリズムの開発が可能になります。つまり、販売台数が多いメーカーほど、より良いクルマを作れるポジションを手にできるという構造が見えてきます。
ここで重要になるのが、ソフトウェアとデータをいかに価値化するかという視点です。SDVにおける中核的なプレイヤーは、NVIDIAのような半導体企業をはじめ、AIによって取得された膨大なデータを分析し、アルゴリズムやUXに変換するソフトウェア企業です。
こうした企業の力が、今後の自動車の差別化要因となり、エコシステム全体において欠かせない存在となるでしょう。 そして今、リアルとバーチャルが融合する新たな価値創造のサイクルが生まれています。
AIを搭載したロボットや自動車が現実空間で稼働し、その過程で得られたデータをAIが学習する。仮想空間でのシミュレーションと、実空間でのフィードバックが循環することで、進化のスピードは加速度的に増しています。
工場内の自動ロボットが、コンピューター上のバーチャル空間で動作を検証し、最適化された動きを現実に反映するといった事例は、すでに現実のものとなっています。 このような構造変化の本質は、「モノ」から「知」へと価値の重心が移っている点にあります。
従来のビジネスモデルが「フラウンカーブ型」だったのに対し、AIやICTを活用する現在の潮流は「スマイルカーブ型」へと移行しています。製造や流通といった中間工程ではなく、研究開発やデータ活用といった前後工程に高い付加価値が集中しているのです。
AIの初期段階における技術開発が競争優位を生み、また、サービス提供後に得られるデータが継続的な成長を可能にします。この構造は、まさにモビリティやロボットの世界にも当てはまります。AIが生むのは単なる自動化ではなく、知的価値の連鎖と新たな収益モデルなのです。
AI時代の日本企業の資産は暗黙知や現場力
アフターAIの時代において、日本企業が国際競争力を取り戻す鍵は、「技術革新への即応性」だけではありません。むしろ問われているのは、自社が長年培ってきた暗黙知や現場力といった独自の強みを、いかに生成AIと統合し、価値創出のドライバーへと変換していくかという視点です。
世界の潮流を追いかけるのではなく、自らの立ち位置を起点に戦略を立てる——この構造的な思考こそが、今求められている能力だと言えるでしょう。 生成AIがもたらす最大の変化は、単なる効率化ではありません。あらゆる情報やリソース、そしてパートナー候補へのアクセスがグローバルかつ瞬時に可能になるという意味で、「探索のコストがゼロに近づく社会」が現実となりつつあります。
つまり、従来であれば長い時間と多大な労力を要した技術提携や市場調査、人材発掘などが、AIによって高度にレバレッジ可能な時代に入ったということです。この変化は、製品開発や業務改革のスピードを桁違いに引き上げる
一方で、企業の「本質的な強み」を明確に問うことにもなります。 そんな中で、現場に蓄積された経験知や組織内に染み込んだ判断基準といった、表出しにくい知の存在が重要性を増しています。これらはデジタル化の対象になりにくいがゆえに、他社が模倣しにくく、ローカルな差異を最大限に活かす戦略資産となり得るのです。
現場で磨かれてきた職能、属人的なノウハウ、文脈的な顧客対応——こうした非構造的な知は、生成AIによる情報圧縮の時代においてこそ、希少性が高く、戦略的な優位性を持ちます。
私は現在、AIおよびヒューマノイド分野のスタートアップにて取締役やアドバイザーを務めており、最前線で技術の進化と向き合う中で、日々そのスピードと可能性に驚かされています。一方で、それを単なる技術論にとどめず、どう経営に実装し、持続可能な変化へと昇華させていくかという点においては、依然として多くの企業が模索の段階にあります。
AIはあくまで手段であり、組織の変革を支えるためには、実務や文化に深く根ざした「伴走のデザイン」が欠かせません。そうした中で本書は、技術に偏ることなく、バランスの取れた視座を提供してくれました。生成AIが社会や産業に与えるインパクトを、ビジネス・人材・組織といった各レイヤーに落とし込みながら、「今、何を見て、何を準備すべきか」を整理する上で、大きなヒントを与えてくれる内容となっています。
また、マーケティング、ヘルステック、フィンテックなど、分野ごとのAIの進化やケーススタディがレポートされている点も参考になります。
特に印象的だったのは、「日本企業が世界に対して何を提供できるのか」という問いに対し、明確な方向性を示してくれた点です。暗黙知を丁寧に可視化し、AIと接続するための基盤を整える。それは単なる内部改革にとどまらず、グローバルな価値連鎖の中で自らのポジションを再定義することにもつながります。「深化」と「探索」という両輪を回し続けるという本書の示唆は、多くの日本企業にとって、現実的かつ実行可能な未来戦略の出発点となるはずです。
だからこそ、経営者や事業責任者、そしてAIに関心のあるすべてのビジネスパーソンに、ぜひ本書を手に取っていただきたいと思います。本書は、AIの技術や活用方法を解説するだけのものではありません。生成AIが普及したその先の世界で、企業や個人がどのように価値を創出していくべきかを考えるための、「思考の道しるべ」となる一冊です。読むことで、多くの気づきや新たな視点を得られるはずです。















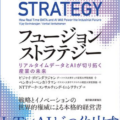


コメント