森岡毅 必勝の法則 逆境を突破する異能集団「刀」の実像
中山玲子
日経BP
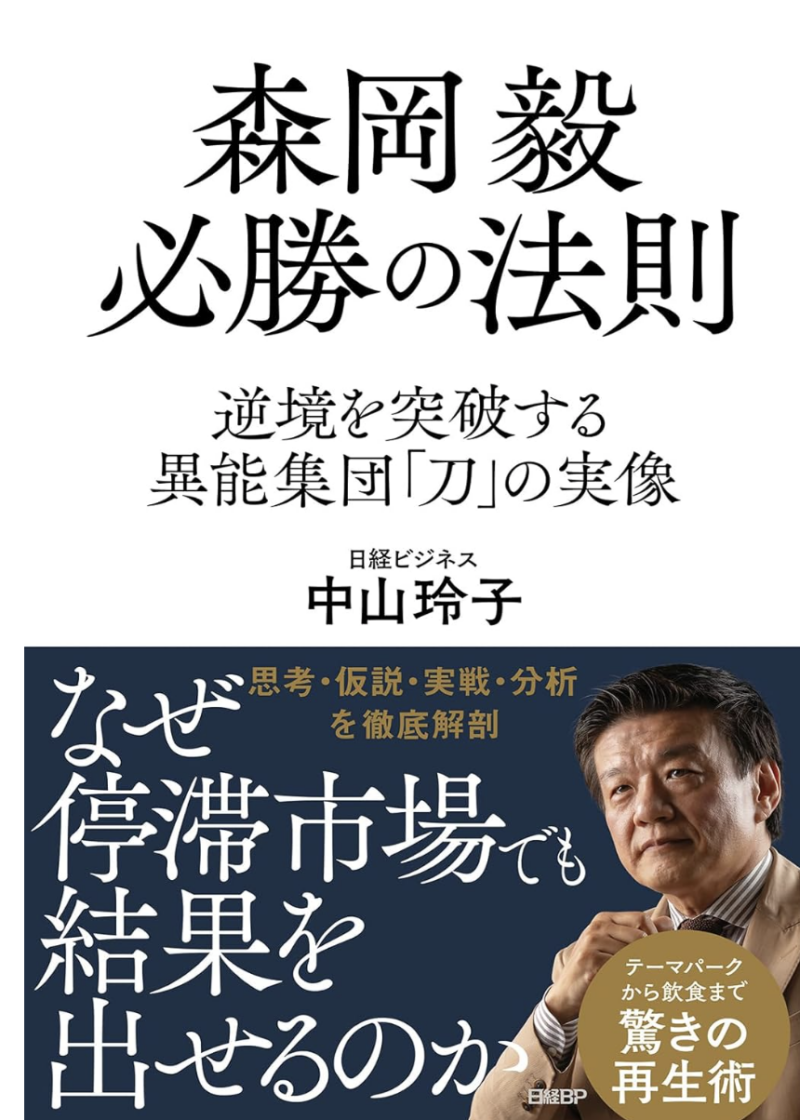
森岡毅 必勝の法則 逆境を突破する異能集団「刀」の実像 (中山玲子)の要約
刀は、人材を「T型(思考力)」「C型(コミュニケーション力)」「L型(リーダーシップ)」に分類し、それぞれの強みを活かす組織戦略を採用しています。数学マーケティングを駆使し、データ分析に基づいた精緻な戦略でテーマパーク再生や外食産業の活性化に貢献しています。さらに、「マーケティングができるゴールドマン・サックス」を目指し、投資と経営支援を融合。企業成長と地域経済の発展を促し、新たな市場価値を創造しています。
刀の「数学マーケティング」の力とは?
刀が「数学マーケティング」を中心とした独自のノウハウを多く持っていることだ。「どんな高い壁であってもしっかり階段をつくれば必ず上れる」と森岡氏が言うように、刀はたくさんのノウハウを積み上げて、1段ずつ階段をつくって上っているように感じた。(中山玲子)
沖縄の大自然と一体となった新たなテーマパーク「ジャングリア」が、2025年に沖縄北部に誕生します。那覇空港から車で1時間強の場所に位置するこの施設は、マーケティング集団「刀」が創業以来、情熱を注いできたプロジェクトです。 総事業費約700億円を投じた「ジャングリア」は、東京ドーム12.8個分という広大な敷地を誇り、その規模は東京ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンを上回ります。
「パワーバカンス」をコンセプトに掲げ、エキゾチックな沖縄の森が醸し出す独特の空気感や、燦々と降り注ぐ太陽、心地よい風など、都会では体験できない大自然の魅力を存分に活かした空間づくりを目指しています。 このプロジェクトの立役者である森岡毅氏は、2011年に最初の構想を描きました。
しかし、計画は一度白紙となり、大きな挫折を経験します。それでも森岡氏は諦めることなく、マーケティング集団「刀」を創業。独自に確立した「数学マーケティング」という手法を駆使し、再び沖縄テーマパーク計画の実現に向けて動き出しました。
彼らは、一度挫折したプロジェクトや停滞市場の事業であっても、独自の視点と緻密な分析で可能性を見出し、粘り強く取り組む集団です。刀は全てにおいて強みや特徴を生かしたビジネスを行なっています。
刀の「数学マーケティング」の核心は、確率論に基づく独自の分析手法にあります。同社のインテリジェンスチームは、少ないデータから正確な予測を導き出す数式を開発し、これを特許として取得しています。
関西大学名誉教授の宮本勝浩氏が指摘するように、刀の特徴は、一般的なコンサルティング会社と異なり、数学的根拠に基づいたマーケティングを実践していることです。客観的なデータを重視し、そこから導き出される論理的な戦略立案を行っています。
最高インテリジェンス責任者(CIO)の今西聖貴氏によれば、消費者の行動を決定づける要素は、本質的にはわずか3つに集約されます。第一は「プレファレンス(相対的好意度)」、第二は「認知度」、そして第三は商品の場合は「配荷」(入手のしやすさ)、テーマパークの場合は「距離」となります。
刀は、独自の消費者調査を組み合わせながら、これら3つの要素を緻密に数値化します。その結果、高い精度で将来の需要を予測することが可能となっています。このように、数学的なアプローチと独自の分析手法を組み合わせることで、より確実な市場予測を実現しているのです。
この手法の有効性は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の劇的な復活を通じて実証されています。森岡氏がUSJのチーフマーケティングオフィサー(CMO)として着任した2010年当時、同パークは低迷期にありました。
しかし、数学マーケティングを駆使した精緻な分析により、ターゲット層の嗜好や行動パターンを正確に把握。これに基づいて「ハリー・ポッター」エリアの導入を決断し、魅力的なコンテンツ展開を実現しました。
その結果、来場者数は大幅に増加し、驚異的なV字回復を遂げたのです。このUSJの成功事例は、数学マーケティングの実効性を示す代表的な実績となっています。
刀はこの経験で培った手法を更に発展させ、様々な事業の再生や成長に活かしています。マーケティングにおける「感覚」や「経験」だけに頼るのではなく、数学的な裏付けを持った戦略立案により、確実な成果を導き出すことを可能にしているのです。
データを徹底的に活用し、結果を出す刀の組織力
刀では、事業を担当するマーケターが、需要予測をするインテリジェンスチームと密に意思疎通をして戦略を練る。
マーケティング集団「刀」の特徴的な強みは、マーケターとインテリジェンスチームの緊密な連携にあります。日々の業務において、事業を担当するマーケターたちは、需要予測を専門とするインテリジェンスチームと密接に協力しながら、戦略を練り上げています。 具体的な数値目標に基づいた対話が、両者の間で絶えず交わされています。
例えば、「特定のエリアからの集客を1000人増やすために必要な認知度の向上幅」や「イベントへの追加投資による来場者数の伸び」といった具体的な質問が、マーケターからインテリジェンスチームに日常的に投げかけられます。
注目すべきは、インテリジェンスチームが単なる予測提供者ではなく、時には投資判断に対して慎重な意見を述べる存在となっていることです。データに基づいた分析から、「その投資では十分な集客増が見込めない」といった指摘を行うこともあります。
「刀」の組織文化において、施設やコンテンツの制作で満足したり、プロモーション活動の実施だけで終わらせたりするような姿勢は存在しません。すべての活動は、予測とその検証のサイクルの中で継続的に評価されています。
実際の運用例として、同社が運営する「イマーシブ・フォート東京」では、週間入場者数の予測と実績の差異が生じた場合、インテリジェンスチームが翌週には詳細な分析レポートを提出します。このレポートを基に、現場を熟知する担当者とマーケターが深い議論を重ね、その知見を翌日以降の予測やイベント企画、プロモーション施策に反映させています。
このように、予測・実施・検証・改善というサイクルを絶え間なく回し続けることで、予測精度の向上と事業成果の最大化を実現しています。データに基づく科学的なアプローチと、現場の知見を組み合わせた「刀」独自の手法は、従来のマーケティングの概念を大きく覆すものとなっています。
予測の精度を高めることは、単なる数字合わせではありません。それは、より多くのお客様に満足していただける施設やサービスを提供するための重要な基盤となっているのです。「刀」の取り組みは、マーケティングの新しい地平を切り開く挑戦として、業界内外から注目を集めています。
「需要予測のモデルは修正を重ねるので、昨日よりも今日はより賢くなる。そして明日はもっと賢くなる。(森岡毅)
21世紀は「データの世紀」と呼ばれ、特に近年は生成AIの活用が進んでいますが、森岡氏は現状のAI活用における重要な課題を指摘しています。 多くの企業がAIを導入していますが、そこには重大な落とし穴があります。
それは、AIに入力するデータの選択に人間の主観が入り込み、都合の良いデータだけが使用される傾向があるという点です。特に失敗したプロジェクトのデータは早々に破棄されがちで、結果として偏ったデータセットが形成されてしまいます。
森岡氏はこうした実態と異なるデータを「毒入りデータ」と表現します。このような偏ったデータを基にすると、必然的に楽観的な予測が導き出されてしまいます。そのため、森岡氏は「需要予測は保守的でなければならない」と強調し、データの質と予測の正確性に対して厳格な姿勢を貫いています。
刀では、インテリジェンスチームとマーケターが緊密に連携しながら、失敗データを含むあらゆるデータを適切に分析・活用することで、日々予測モデルの精度を向上させています。
刀の事業推進のための4つの力と諦めない精神
刀は、会社や事業推進のためには4つの不可欠な力があると考える。①市場構造を分析して勝ち筋を見極めた上で、②プロダクトを創り、③その価値を伝え、さらに④これらを全体として推進していく力だ。
刀が掲げる事業成功の要諦は、4つの重要な力の相乗効果にあります。これらの要素は、単独ではなく、有機的に結びついて初めて真価を発揮するものとされています。
まず基盤となるのが、市場構造を徹底的に分析し、勝ち筋を見極める力です。この段階で、刀は独自の数学マーケティングを駆使し、市場の本質的な課題や機会を特定します。時間軸と空間軸を拡張し、大規模な調査をせずに仮説を作ります。ここでの綿密な分析が、後の成功を左右する重要な仮説構築につながっています。 刀の分析によれば、売上を伸ばすための方策は主に3つに集約されます。
・消費者数の増加
・高額商品への移行促進
・購入頻度の向上や使用商品の拡大です。
しかし、目標数値に到達できない場合、それはこれら3つの行動が十分に引き出せていないことを意味します。 そこで刀は、なぜ消費者がこれらの行動を起こさないのか、その根本的な理由の解明に注力します。消費者の行動を妨げているバリア(障壁)を特定し、それを一つずつ取り除いていく作業が不可欠となります。
特に重要なのは、消費者とプロダクトやサービスとの間の信頼関係の構築です。刀は、新たなインサイトを提示することで、消費者の不信感や懐疑心を払拭し、確かな信頼関係を築き上げることを実現します。
2つ目の要素が、顧客やマーケットの分析結果に基づいて魅力的なプロダクトを創り出す力です。市場ニーズを的確に捉えた商品やサービスの開発は、事業成功の要となります。刀は、データ分析と顧客の徹底的な観察から、具体的な価値提供を見出します。
第3の要素は、創り出した価値を効果的に伝える力です。いかに優れたプロダクトでも、その価値が顧客に正しく伝わらなければ意味がありません。刀は、科学的なアプローチで導き出された最適なコミュニケーション戦略を展開します。
そして最後に、これら全ての要素を統合的に推進していく力が不可欠です。個々の施策を有機的に結びつけ、全体として最大の効果を生み出すマネジメント力が求められます。
ニップンは、これまでパスタの茹で時間や麺の太さなど機能性を重視してきましたが、刀との協業により、「おいしさ」に原点回帰する戦略を採用しました。森岡氏は、消費者は茹で時間の短縮よりも「おいしさ」を求めていると指摘し、市場における本質的な価値の再認識が必要だと考えました。
また、ニップンは「オーマイプレミアム」として冷凍パスタと乾燥パスタを統一ブランド化するマスターブランド戦略を導入しました。従来は個々の商品を説明する営業スタイルでしたが、統一ブランドによる訴求により、バイヤーへの印象を強化しました。
さらに、小売店の棚に商品を確実に並べるため、「認知」「好意度(プレファレンス)」「配荷」の中の「配荷」にも注力し、供給戦略を見直しました。 企業改革においては、消費者の価値観を深く理解することが重要視されました。消費者インタビューでは、社員が従来の価値観と消費者ニーズのズレに気付き、「本当に求められているもの」を再考する機会となりました。
加えて、マーケティング部門の下に開発部門を設置し、営業や広告まで一貫して消費者視点で動ける体制を整備。組織が変わっても戦略が持続する仕組みを構築しました。 こうした取り組みにより、ニップンは「おいしさ」という本質的な価値を軸に市場での競争力を高め、長期的な成長基盤を確立しました。
この体系的なアプローチにより、刀は様々な事業領域で高い成功率を実現しています。それは、単なる理論や経験則ではなく、数学的な裏付けを持った戦略立案と、その確実な実行力によって支えられているのです。バリアの特定から信頼関係の構築、そして具体的な行動促進まで、一貫した戦略のもとで展開される刀のマーケティングは、持続的な事業成長を可能にしているのです
結果を出さねば、誰も守れない。どんな難しい戦局であろうと、やる限りは結果を出す必要がある。結果を出すためには何が何でもできることはすべてやらねばならない。
刀は、あらゆる場面で「結果を出す」ことを最優先に考え、諦めないマインドセットをメンバーは、その歩みを止めることはありません。データ分析と数学マーケティングを基盤とし、客観的な数値をもとに最適な戦略を導き出すことを重視しています。
刀は、組織内の人材を「T(Thinking)型」「C(Communication)型」「L(Leadership)型」の3つに分類し、それぞれの強みを最大限に伸ばすことを重視しています。思考力に優れたT型、人とつながる力や伝える力を持つC型、人を率いて動かす力を強みとするL型の特性を活かし、組織全体の力を高めています。この考え方は、人材の適材適所を促し、各自の能力を最大限に引き出すことで、企業の成長と競争力を強化する仕組みとなっています。
この独自の組織戦略をもとに、刀はテーマパークの再生や食品・外食産業の活性化など、多岐にわたる事業領域で成果を上げてきました。森岡毅氏のリーダーシップのもと、革新的なマーケティング手法を駆使し、日本市場に新たな価値を生み出しています。
その最新の取り組みとして誕生する「ジャングリア」は、沖縄の自然や文化の魅力を最大限に引き出しながら、新しい体験価値を提供するプロジェクトです。従来の観光施設とは一線を画し、訪れる人々に没入感のある体験を提供することで、地域経済の発展にも寄与することが期待されています。
日本国内では、過去数十年にわたり、多くのパークや遊園地が廃業に追い込まれてきました。その背景には、施設の老朽化やマーケティング戦略の欠如、そして経営基盤の弱さが挙げられます。こうした現状を打破するため、刀は人材育成や経営戦略の見直しに注力し、根本から日本の観光業を変えようとしています。
単に施設を再生するだけでなく、マーケティングやブランディングを強化し、地域との連携を深めながら、持続可能な成長モデルを構築することで、新たな可能性を生み出しています。 さらに、刀はマーケティング力と資金力の両方を兼ね備えた企業へと進化しようとしています。
目指すのは、「マーケティングができるゴールドマン・サックス」としての存在です。これまで刀は、企業の再生や成長支援において、ノウハウの移植を中心にコンサルティングを行ってきました。しかし、今後はその枠を超え、成長の可能性がある事業に対して直接投資を行い、マーケティングを駆使しながら企業価値を高める手法を採用していきます。
ゴールドマン・サックスが金融市場において投資銀行としての知見を活かし、企業の成長を支援してきたように、刀もマーケティングの専門性を活かしながら、経営支援と投資の両軸で事業を展開していきます。単なる戦略コンサルティング会社ではなく、企業の成長に深く関与し、資本の側面からも支援することで、より実効性の高い成果を生み出す体制を整えていく考えです。
これにより、刀はマーケティングを軸とした投資会社へと変貌し、国内企業の再生や成長を支援しながら、新たな市場を創造する役割を担うことが期待されます。企業戦略の立案だけでなく、リスクを取って資本を投下することで、より大きなインパクトをもたらし、日本の産業構造や市場環境の変革を促す存在となるはずです。
今後、刀が展開する事業は、企業の競争力向上にとどまらず、地域経済や観光産業の発展にも寄与していきます。マーケティングと投資の融合という独自のアプローチにより、企業と市場に新たな価値を提供し、日本経済の活性化に貢献していくことが期待されます。
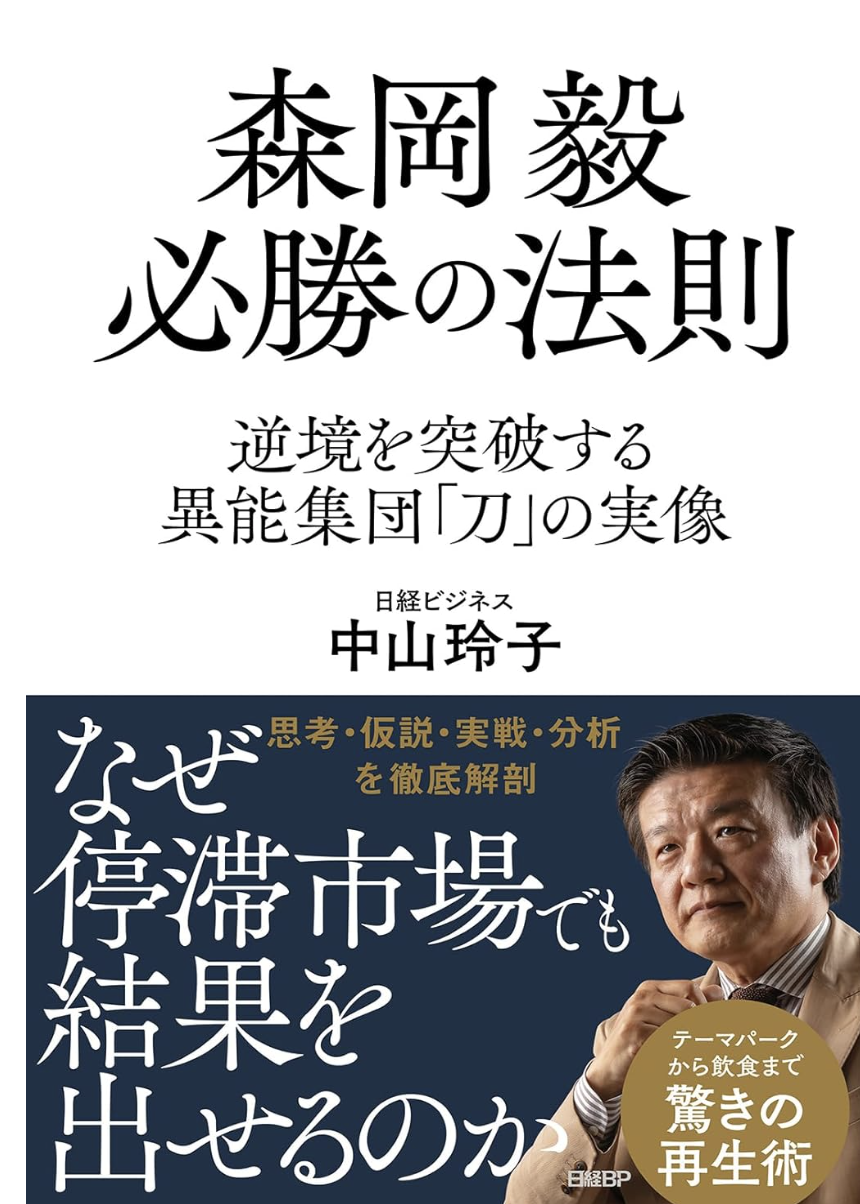
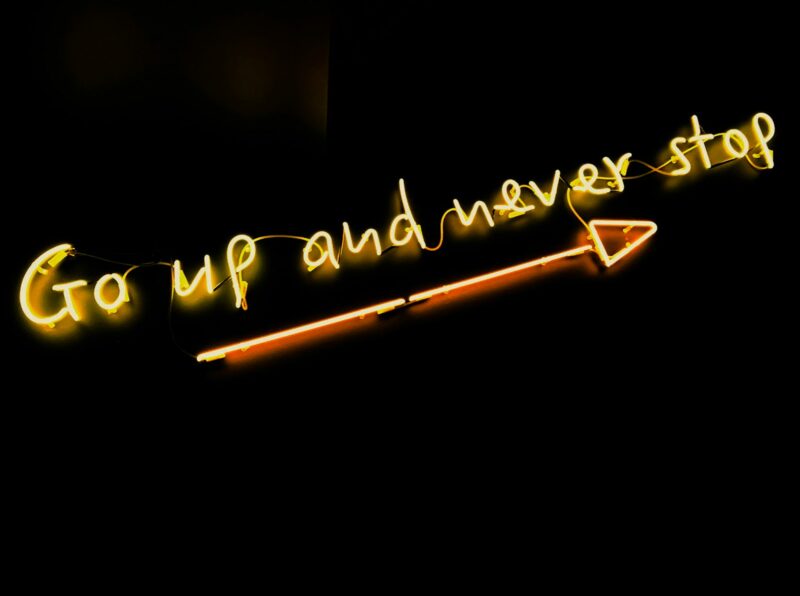














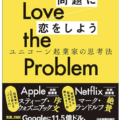

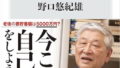
コメント