
冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法
安斎勇樹
テオリア
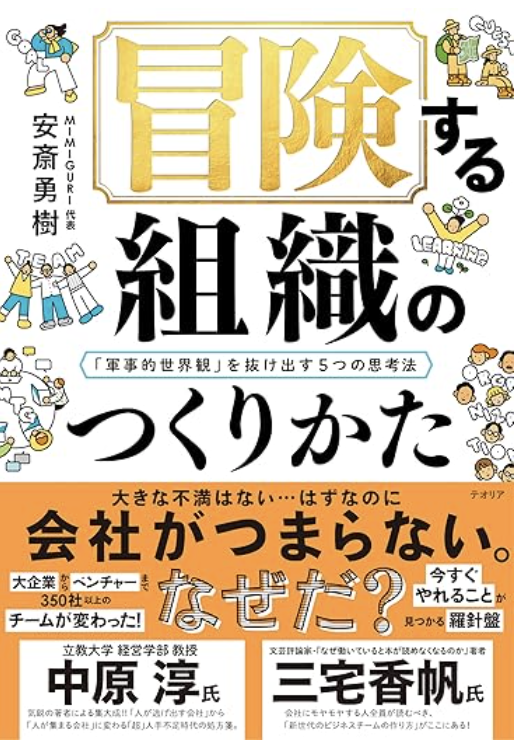
冒険する組織のつくりかた(安斎勇樹)の要約
現代の組織には、「軍事的世界観」から「冒険的世界観」への転換が求められています。個人の価値観の多様化とテクノロジーの進化を背景に、企業は従来の効率重視の階層型組織から、個々のメンバーの個性と創造性を活かす柔軟な組織へと進化する必要があります。著者の安斎勇樹氏は、理論と実践の両面から、この新しい組織モデルの実現方法を提示しています。
「軍事的な世界観」から「冒険的な世界観」へのアップデートを!
これからの組織では、不確実な世界のなかで各人が自分なりの目的を探索しながら、時には仲間たちと協力して新たな価値を生み出していく──まさに冒険者たちが持っているような世界観が求められます。 私はこれを「冒険的世界観」と呼んでいます。 現代の人・組織には、「軍事的な世界観」から「冒険的な世界観」へのアップデートが求められているのです。(安斎勇樹)
現代社会における企業組織のあり方が大きく変わりつつあります。従来の日本企業には「軍事的世界観」が根付いており、トップダウン型の意思決定と、それに従う組織構造が特徴的でした。この仕組みは、高度経済成長期においては機能していましたが、コロナ禍を経た現在、もはや有効ではなくなってきています。 社会全体の価値観が「会社中心」から「人生中心」へとシフトしています。
かつては会社の命令に忠実に従うことが美徳とされていましたが、現代の働き手にとっては自己実現がより重要になりつつあります。この変化は一時的なものではなく、企業が従来の価値観に戻ろうとしても、それを受け入れる人は少ないでしょう。そのため、伝統的な組織にこだわる企業からは優秀な人材が流出し、新しい働き方を求める人々が増えています。
これからの組織では、不確実な世界のなかで各人が自分なりの目的を探索しながら、時には仲間たちと協力して新たな価値を生み出していきます。まさに冒険者たちが持っているような世界観が求められるのです。私はこれを「冒険的世界観」と呼んでいます。
現代の人や組織には、「軍事的な世界観」から「冒険的な世界観」へのアップデートが求めらると著者の式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEOの安斎勇樹氏は指摘します。(安斎勇樹氏の関連記事)
事業成長と人的成長の両面での価値転換が進んだ結果、ビジネスの前提そのものが大きく変化しました。これまでの時代においては、ビジネスといえば「ライバル会社と競争しながら、マーケットシェアを奪い合うこと」が主流でしたが、もはやそれは万人に共有された常識とは言えません。
かつて「領地の奪い合い」だったビジネスは、いまや「仲間と共創しながらよりよい社会の可能性を探究する活動」としてとらえ直されつつあると著者は言います。
企業組織は今、大きな転換期を迎えています。その背景には、個人の価値観の多様化とテクノロジーの進化という2つの大きな潮流があります。インターネットとデジタルツールの普及により、私たちの働き方は大きく変化し、場所や時間に縛られない柔軟な働き方が可能となりました。
企業の枠を超えて、より広いネットワークの中で価値を創造できる時代が到来しているのです。 このような変化は、組織のあり方自体の見直しを迫っています。かつての閉鎖的な組織から、より開かれた柔軟な形態への進化が求められています。
そこでは、一人ひとりが自らの価値観や強みを活かしながら、主体的に未来を描いていく姿勢が重要となります。従来の組織は「機能別に編成された小隊」のように、効率性を重視する傾向がありました。しかし、これからの組織には、個々のメンバーの個性を最大限に活かし合う「仲間」としての関係性が求められます。
単なる機能的な整合性だけでなく、メンバー1人ひとりの価値観や志向性という精神的な整合性も視野に入れた新しい組織モデルが必要とされているのです。 特に注目すべきは、このような組織のあり方が現代のビジネス環境により適しているという点です。
不確実性が高く、変化の激しい時代において、異なる視点や能力を持つメンバーの協働が、より創造的な解決策を生み出す源泉となります。 さらに、デジタル技術の進化がこうした新しい組織のあり方を後押ししています。オンラインコミュニケーションツールやプロジェクト管理ツールの発達により、物理的な距離を超えた協働が可能となり、より柔軟な組織運営が実現できるようになっています。
この変化は、ピラミッド型からフラットで自律的な組織への移行も促しています。それは単なる構造の変化ではなく、組織の文化や価値観そのものの見直しを意味します。個々の才能や創造性を引き出しながら、協力してより大きな価値を生み出すことが、これからの企業には求められるのです。
この新しい組織観は、個人の可能性や自己実現を大切にしながら、企業の社会的価値や事業の成長との調和を図ろうとするものです。個人と組織が共に成長できる関係を築くことで、持続可能な発展が可能となります。 これらの課題に対して、
本書は理論と実践の両面からアプローチしています。理論的基盤を固めた上で、「目標」「チーム」「会議」「成長」「組織」という5つの観点から具体的な実践方法を示しています。特に注目されるのが、Creative Cultivation Model(CCM)と呼ばれる新しい組織モデルです。
このモデルは、従来の組織モデルが企業をベルトコンベアのような「機械」として捉え、機能的な整合性のみを重視してきた限界を超えようとするものです。ボトムアップの変化も視野に入れた柔軟な構造により、現代の組織が直面する課題により適切に対応することを可能にしています。
組織づくりとは 人と事業の可能性を最大化するための 土壌を耕す行為。
これに対し、CCMは個々の人間の精神的な整合性も考慮に入れ、組織全体のダイナミックな成長を促す仕組みとなっています。 特に興味深いのは「チーム」のあり方です。従来の組織では、部署ごとに明確な壁があり、同質的なメンバーが集まりやすかったです。
しかしCCMでは、多様な個性を持つメンバーが協働し、創造的な余白を生み出すことが重視されています。この余白があることで、新しい発想やこれまでになかった解決策が生まれやすくなります。
5つのレンズから冒険する組織を組み立てよう!
最初から「全体」を変えようとするのではなく、組織の考え方がとくに色濃く反映される「部分」を取り出して、まずはそこから「ものの見方」を変えていくわけです。 それを私は「組織のレンズ」と呼んでいます。凝り固まった軍事的世界観をほぐすには、次の「5つのレンズ」を冒険的世界観に沿って解釈し直す必要があります。
◎世界観を変える5つのレンズ
①目標のレンズ・・・行動を縛り上げる指令 →好奇心をかき立てる問い
②チームのレンズ・・・ 機能別に編成した小隊→ 個性を活かし合う仲間
③会議のレンズ・・・ 伝令と意思決定の場→ 対話と価値創造の場
④成長のレンズ・・・ 望ましいスキル・行動の習得→新たなアイデンティティの探究
⑤組織のレンズ ・・・事業戦略のための手段 →人と事業の可能性を広げる土壌
現代の組織に求められる変革の具体的な道筋として、安斎氏は5つのレンズを通じた組織の捉え直しを提案しています。 まず「目標のレンズ」を通して見えてくるのは、従来型のノルマや数値目標や司令とは異なる、創造的な目標設定の在り方です。
「好奇心をかき立てる問い」を中心に据えることで、組織のメンバーが主体的に課題に向き合い、創意工夫を発揮できる環境が生まれます。「そもそも、これは何のために必要なのか」「もっと効果的な方法はないだろうか」といった問いかけが、イノベーションの種子となるのです。
「チームのレンズ」は、多様性と創造性を重視する新しいチーム観を提示します。現代の組織に求められる変革の本質は、「探究(Quest)」を軸とした新しい組織文化の創造にあります。探究とは、既知の領域を超えて未知の可能性を追求する終わりなき旅といえます。それは目標達成や問題解決にとどまらない、より深い知的冒険を意味しています。
この新しい組織のあり方を理解する上で、漫画『ONE PIECE』の「麦わらの一味」は実に示唆に富む例えとなっています。航海士、剣士、料理人、医者など、それぞれが異なる専門性と夢を持つメンバーたちが、互いの探究を支え合いながら航海を続けています。時には効率的ではない道のりを選ぶこともありますが、それは仲間の自己実現を尊重し、その過程で育まれる絆を大切にしているからです。
この多様性に富んだチームづくりの視点は、著者が提示する「チームのレンズ」の核心部分です。一見するとバラバラに見える個々の夢や能力が、実は不確実な世界を乗り越えるための大きな推進力となっています。それぞれの専門性や視点が交わることで生まれる「余白」から、単一の視点では気づけなかった創造的な解決策が生まれてくるのです。
探究には「正解」や「終着点」が存在しません。しかし、答えのない問いに向き合い続けること自体が、組織と個人の持続的な成長を促進していきます。これは、予測困難な現代のビジネス環境において、極めて重要な組織の特質となります。
このような「探究する組織」への転換は、従来の効率性や管理を重視する組織観からの大きな変化を意味します。しかし、それは現代社会が直面する不確実性と複雑性に対応するための、必然的な進化の過程なのです。個々のメンバーの多様性を活かし、創造的な対話を重ねながら、組織全体で新しい可能性を追求していく。そんな組織づくりへの具体的な指針を、本書は示してくれています。
「会議のレンズ」は、会議を単なる情報共有や指示出しの場から、創造的な価値を生み出す対話の場へと転換することを提案しています。従来の会議では、上意下達の報告や一方的な指示が中心となりがちでしたが、これからの会議では、参加者全員が対等な立場で意見を交わし、それぞれの経験や視点を共有することで、新しい発見や解決策を生み出すことを目指します。
この創造的な会議を実現するために、3つのステップが示されています。まず第1に「察知」のステップでは、参加者間で生じている前提や認識のズレに気づくことから始まります。たとえば、同じ言葉を使っていても、その意味する内容が異なっているかもしれません。
次の「理解」のステップでは、その違いを否定するのではなく、なぜそのような違いが生まれているのかを深く理解することに努めます。それぞれの立場や経験によって、物事の見え方が異なるのは当然のことです。その違いこそが、新しい価値を生み出すための重要な素材となります。
最後の「共創」のステップでは、それぞれの視点の違いを活かしながら、新しい意味や価値を共に創り出していきます。異なる視点が交わることで、これまでになかった発想や解決策が生まれる可能性が広がるのです。 このように、冒険的世界観における会議は、単なる情報伝達の場ではありません。
「察知→理解→共創」という対話のプロセスを通じて、組織の新しい可能性を切り開いていく創造の場となるのです。それは、予測困難な時代において、組織の適応力と創造性を高める重要な機会となります。
「成長のレンズ」は、個人の成長を根本から捉え直す新しい視点を提供しています。従来の組織では、あらかじめ定められた「望ましい人材像」に向けて、画一的な研修プログラムや上意下達式の指導を通じてスキルや行動を習得させることが一般的でした。
しかし、これからの時代に求められる成長とは、個々のメンバーが自らのアイデンティティを探究し、新たな可能性を見出していく過程です。それは単なるスキルの習得を超えて、「自分は何者になりたいのか」「どのような価値を生み出したいのか」という、より本質的な問いに向き合うことを意味します。
この視点に立つと、組織の役割も大きく変わってきます。画一的な研修を課すのではなく、各メンバーの興味や適性に応じた多様な成長の機会を提供し、その探究のプロセスを支援することが重要となります。時には効率的に見えない遠回りも、その人ならではの成長には必要不可欠かもしれません。
このような成長の捉え方は、予測困難な現代において特に重要な意味を持ちます。なぜなら、既存の枠組みにとらわれない新しい発想や価値観が、組織の創造性と適応力を高める源泉となるからです。個々のメンバーが自らのアイデンティティを探究し、それぞれの方法で成長していく。そうした多様な成長の物語が重なり合うことで、組織全体の可能性も広がっていくのです。
つまり、「成長のレンズ」は、個人と組織の持続的な発展を、より深い次元で結びつける視点を提供しているといえます。それは、効率や管理を重視する従来の「軍事的世界観」から、探究と創造を重視する「冒険的世界観」への転換を、成長という観点から実現しようとする試みなのです。
「組織のレンズ」は、組織を「土壌」として捉える新しい視点を提示しています。従来の「軍事的世界観」では、組織は戦略を実行するための道具として位置づけられ、効率性と管理が重視されてきました。それは、整然と区画された農地のように、あらかじめ決められた計画に沿って成果を生み出すことが求められていたのです。
しかし、「冒険的世界観」における組織は、人と事業の可能性を育む豊かな土壌として理解されます。自然の土壌がそうであるように、時には予期せぬ雑草が生え、思いがけない生き物が住みつくこともあります。一見すると無秩序に見えるかもしれませんが、そうした多様な要素が混ざり合うことで、より豊かな価値が生まれる可能性が広がるのです。
このような組織観は、長期的な価値創造を重視します。土壌が豊かであれば、時には予想外の作物が育ち、何年も先になって実を結ぶこともあります。同様に、組織という土壌が豊かであれば、メンバーの創造性が育まれ、新しい事業の芽が育っていくのです。
重要なのは、この土壌としての組織が、画一的な管理や効率性の追求とは異なる原理で機能するという点です。むしろ、ある程度の「あいまいさ」や「余白」を許容し、時には効率的でない試行錯誤を受け入れることで、より大きな可能性が開かれていきます。
これら5つのレンズは、互いに密接に関連しながら、新しい時代にふさわしい組織の全体像を浮かび上がらせます。効率と管理を重視する従来の「軍事的世界観」から、創造性と多様性を重視する「冒険的世界観」への転換を、具体的な実践レベルで支援する枠組みとなっているのです。
さらに、これらのレンズを通して組織を見ることで、一見非効率に見える「余白」や「モヤモヤ」の価値が再評価されます。それは、不確実性の高い現代のビジネス環境において、むしろ組織の適応力と創造性を高める重要な要素として位置づけられるのです。
本書が提示する5つのレンズは、組織の未来を考える上で示唆に富む視座を提供しています。それは、デジタルトランスフォーメーションが進む現代において、組織の持続的な発展と個人の成長を両立させるための、具体的かつ実践的な指針となるでしょう。
冒険的マネジメントの3つの階層と冒険する組織を作る5つの基本原則
本当にやるべきなのは、業務構造の設計(機能面)と職場風土の醸成(精神面)の両面からアプローチする「職場デザイン」です。 これによって、組織アイデンティティを体現しながら、メンバー全員が自己実現できる「探究的な共同体」をつくっていくことができるのです。
組織変革において真に必要なのは、業務構造の設計という機能面と、職場風土の醸成という精神面の両方に目を向けた「職場デザイン」です。このアプローチにより、組織のアイデンティティを大切にしながら、メンバー全員が自己実現できる「探究的な共同体」を作り上げることができます。
この冒険的マネジメントは3つの階層で展開されます。まず職場レベルでは、個々人の自己実現と組織アイデンティティをつなぎ、各チームの業務や風土をデザインします。組織レベルでは、組織アイデンティティと事業ケイパビリティを結びつけ、組織全体の構造と文化を形作ります。そして事業レベルでは、事業ケイパビリティと社会的ミッションを統合し、事業群のシナジーとブランドを構築します。
この新しい組織づくりには、5つの基本原則があります。第1に、目標設定には「ALIVE」の法則を適用します。これは、変化への適応性(Adaptive)、学びの機会(Learningful)、好奇心の喚起(Interesting)、未来志向(Visionary)、実験的姿勢(Experimental)を重視するものです。
組織の目標設定において、効果的で測定可能な従来のSMART基準を活かしながら、メンバーの探究心を刺激するALIVEな要素を組み込むことが、これからの時代には重要となってきます。この2つの要素を組み合わせることで、具体的な成果と創造的な挑戦を両立させることができるのです。
その鍵となるのが、「問いの探究を通して、数値目標を達成する」というフォーマットです。例えば、単に「売上高を20%増加させる」という目標を掲げるのではなく、「顧客にとってより大きな価値を生み出すために、私たちは何を変えられるだろうか?」という問いを立て、その探究を通じて売上目標の達成を目指すのです。
このようなアプローチにより、無機質だった短期目標に実験的な要素が加わります。メンバーは与えられた目標をただ遂行するのではなく、その達成のプロセスにおいて、既存の方法を見直したり、新しいアプローチを試したりする機会を得ることができます。それは、日々の業務に創造性と学びの要素をもたらすのです。
ALIVEな目標は、変化への適応力を高め、学びの機会を創出し、好奇心を刺激し、未来を見据え、実験的な試みを促進します。それは単なる数値目標の達成を超えて、組織とメンバーの両方に成長の機会をもたらすものとなります。 このように、目標設定を「軍事的な業務命令」から「生き生きとした冒険的目標」へと転換することで、組織全体の創造性と活力が高まっていきます。それは、予測困難な時代において、組織が持続的に成長していくための重要な原動力となるのです。
個々のメンバーが主体的に考え、試行錯誤しながら目標に向かって進んでいく。そのプロセスにおいて、新しい発見や気づきが生まれ、それがまた次の挑戦への原動力となっていく。こうした好循環を生み出すことが、これからの組織には求められているのです。
第2に、マネジメントチームを組織の靭帯として位置づけます。経営チームやミドルマネジャーチーム内で、個々の探究プロセスを共有する場を設けることで、組織全体のチームワークを支える精神的なつながりが生まれます。
第3に、会議を「ハレ」と「ケ」の場として使い分けます。日常的な「ケの会議」では効率的なファシリテーションを心がけ、特別な「ハレの会議」では全力で取り組むという、場のデザインとモードの切り替えを意識的に行います。
第4に、学び続ける組織文化の醸成を重視します。組織の成長にとって最も重要な要素の一つが、「学び続ける組織文化」の醸成です。これは単なるスキル研修や知識の習得を超えて、組織全体が継続的に学習し、進化し続ける環境を作り出すことを意味します。
そして第5に、変革を日常的な営みとして捉え、変化を楽しむ姿勢を大切にします。この組織変革は、経営層だけでなく、現場のメンバーやミドルマネジャーも含めた全員が担い手となります。 このように、冒険する組織づくりは、従来の効率性重視の組織運営を超えて、より創造的で持続可能な組織の在り方を示しています。それは、不確実性の高い現代において、組織と個人の両方が成長できる新しい可能性を開くものといえるでしょう。
変革を前向きなものとして捉え、日々の業務の中で自然に実践していくことで、組織全体が活力を持って進化していきます。それは、一人ひとりの探究心と創造性を活かしながら、組織としての一体感も醸成していく、バランスの取れたアプローチなのです。
「冒険する組織」とは、やみくもに危険を冒す組織のことではなく、一人ひとりのメンバーが好奇心や関心に基づいて自己実現を探究し、同時に集団としての社会的ミッションを追い求める組織のことなのです。個々のメンバーが自身の興味を深掘りし、主体的に学び、成長し続けることが求められます。
そのプロセスにおいて、組織は単なる枠組みではなく、共に学び、挑戦し、創造する場として機能します。 このような組織では、一人ひとりの意思が尊重され、それぞれの個性が活かされます。多様な価値観や経験を持つメンバーが互いに刺激を与え合い、新しい視点を生み出すことで、革新的なアイデアや解決策が誕生します。
従来のトップダウン型の組織では実現が難しかった柔軟な発想が生まれやすく、組織全体の創造性が高まるのです。 また、「冒険する組織」は、失敗を許容し、それを学びの機会とする文化を持っています。従来の組織では、失敗は避けるべきものとされがちでしたが、これからの時代においては、挑戦と失敗を繰り返しながら成長していくことが不可欠です。
失敗から学ぶ姿勢を持ち、それを共有し、組織全体の成長につなげる仕組みが求められます。 この新しい時代において、リーダーシップのあり方も変わります。
従来の指示命令型のリーダーではなく、共創を促すファシリテーターとしてのリーダーが必要とされます。個々の強みを引き出し、チーム全体でシナジーを生み出すことが、今後の企業における重要な要素となるでしょう。 こうした変化を踏まえると、組織の成功は単なる売上や市場シェアの拡大ではなく、社会全体へのポジティブな影響や、個々の成長によって測られる時代が到来しているのです。
「冒険的世界観」にシフトするための20のKEY
本書は、従来の「軍事的世界観」から「冒険的世界観」への転換を提唱し、その具体的な実践方法を示しています。第2部で提示される20のKEYは、この転換を実現するための実践的なガイドラインとなっています。この20のKEYを羅針盤にすることで、組織を冒険型にシフトできそうです。
[KEY1]現場の目標にこそ〝追いかけたくなる意味〟を込める
[KEY2]経営理念は〝探究のツール〟として活用する
[KEY3]目標への納得感を〝設定プロセスの前後〟で爆上げする
[KEY4]目標に違和感が生じたら、迷わず軌道修正する
[KEY5]〝深い自己紹介〟で、心理的安全性を正しく高める
[KEY6]私たちらしさとは? チームアイデンティティを言語化する
[KEY7]チームの問題解決は〝目線合わせ〟が9割。解くべき「問い」を見つける
[KEY8]共通体験のリフレクションで、チームの学びを深める
[KEY9]全メンバーで「ファシリテーターとしての芸風」を磨く
[KEY10]日々の定例ミーティングの質を底上げする
[KEY11]ハレの場としての「全社総会」に命をかける
[KEY12]学ぶとはどういうことか? 学びのものさしを変える
[KEY13]育成の要である「フィードバック」の質を変える
[KEY14]暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする
[KEY15]変革は課題設定が9割。自社の〝もったいない〟を探す
[KEY16]トップダウンの変革は「構造」と「文化」をセットで変える
[KEY17]ボトムアップ変革なら「勉強会」。トップの関心を引く工夫を凝らす
[KEY18]ミドルマネジャーこそ変革の中枢。「調整役に収まらない自分」を尊重する
[KEY19]企業の「アイデンティティ危機」こそ、変革のチャンスにする
[KEY20]垣根を超えて〝仲間〟であり続ける。健全な「出会いと別れ」をデザインする
特に重要なのは、これらが単なる施策や手法の羅列ではなく、組織全体の文化的転換を促すための有機的なアプローチとなっている点です。目標設定から始まり、チームづくり、対話の場の創造、学習文化の醸成、そして組織変革に至るまで、それぞれの要素が相互に関連し合いながら、組織の進化を支えていきます。
目標設定では、数値目標に意味と物語を込めることで、メンバーの自発的な探究を促します。チームづくりでは、心理的安全性を基盤としながら、チームならではのアイデンティティを育んでいきます。
対話の場づくりでは、日常的なコミュニケーションの質を高めながら、特別な機会としての全社総会も大切にします。
学習文化づくりでは、学びの本質を見つめ直し、フィードバックの質を向上させ、知識の循環を促進します。そして組織変革では、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチを組み合わせながら、ミドルマネジャーの役割を重視し、組織のアイデンティティの進化を促します。
本書の結論として最も重要なのは、これらの取り組みが一時的なものではなく、継続的な探究のプロセスとして捉えられるべきだという点です。組織は生き物のように常に進化し続け、そのプロセスにおいて個々のメンバーも成長していく。このような相互作用を通じて、組織は真の意味で「冒険する共同体」となっていくのです。
そして最後に著者は、組織の垣根を超えた「仲間」としてのつながりの重要性を説いています。人々の出会いと別れを健全にデザインすることで、組織は常に新しい可能性に開かれた状態を保つことができます。これは、不確実性の高い現代において、組織が持続的に発展していくための重要な示唆となっているのです。
本書は、組織と個人の関係性を根本から問い直し、新しい時代にふさわしい組織のあり方を示しています。それは単なる理想論ではなく、具体的な実践方法とともに提案されており、現代の組織が抱える課題に対する示唆に富んだ内容となっています。これからの企業経営や組織づくりを考える上で、非常に有益な一冊といえるでしょう。



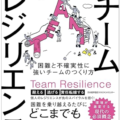













コメント