マリオット・ウェイ サービス12の真実: 世界一のホテルチェーンを築いた顧客満足の秘密
J.W.マリオット・ジュニア, キャシー・アン・ブラウン
日本能率協会マネジメントセンター
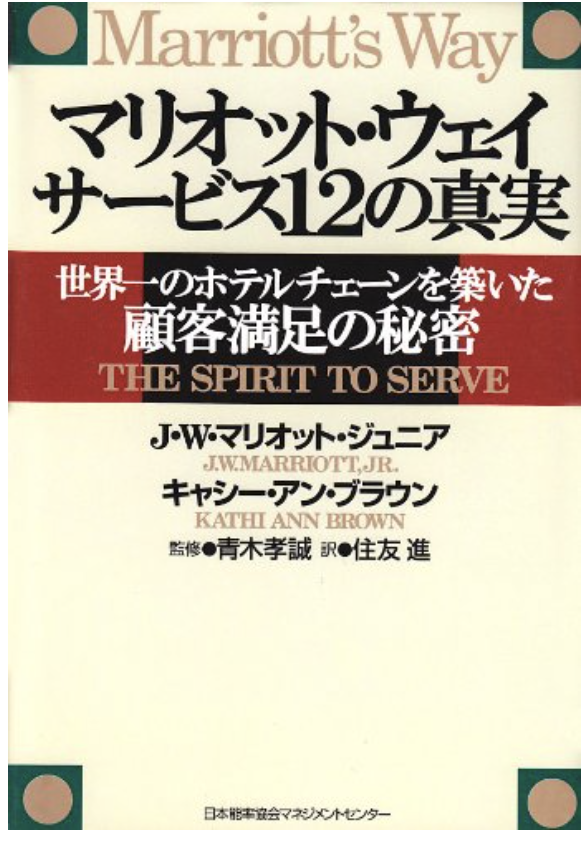
マリオット・ウェイサービス12の真実(J.W.マリオット・ジュニア)の書評
『マリオット・ウェイ』は、従業員を重視する経営哲学と徹底的な現場主義により、高度な顧客満足を実現するマリオットの成功手法を紐解く一冊です。現場の意見やアイデアを積極的に取り入れ、きめ細やかなサービス設計を徹底することで、顧客に最高の体験を提供しています。また、逆境から迅速に立ち直る回復力も、彼らの競争優位を支える大きな強みとなっています。
なぜ、マリオットの顧客体験は高いのか?
従業員を大事にすれば、従業員はお客様を大切にする。(J.W.マリオット・ジュニア)
私は仕事柄、国内外を飛び回る生活を送っており、出張時にはいつも安定したサービスを求めてマリオットホテルグループを利用しています。数あるホテルの中でもマリオットを選び続けているのは、顧客体験の良さと会員制度「マリオットボンヴォイ」の充実度が際立っているからです。
この会員プログラムでは、宿泊ごとにポイントが貯まり、無料宿泊や客室アップグレードといった特典が受けられます。単なるコストメリットにとどまらず、旅の体験そのものを豊かにしてくれる仕組みです。さらに、ポイントは航空マイルへの交換や特別イベント、レストラン・スパの利用にも使えるなど、幅広い用途で自分らしい楽しみ方ができます。
ステータスが上がれば、レイトチェックアウトや上級会員向けラウンジ、無料朝食といった特典もあり、出張や旅行の満足度を一段と引き上げてくれます。こうした細やかなサービスが、出張族の信頼とロイヤルティを高めているのだと感じています。その背景には、マリオットが長年培ってきたホスピタリティ経営の哲学が色濃く反映されています。
今回、マリオット・ウェイサ-ビス12の真実を改めて再読し、この企業がなぜこれほどまでに高い顧客満足を維持し続けられるのか、その核心に触れることができました。 この本は、単なる企業の成功事例紹介にとどまらず、マリオットグループの経営哲学や組織のあり方を通して、サービス業の経営本としても非常に優れた内容を持っています。
本書は単なる成功企業の事例紹介にとどまらず、マリオットグループの経営哲学と組織運営の本質に深く切り込む、サービス業の経営に関心を持つすべての人にとって有益な一冊です。
書籍の中では、マリオットが大切にしている12の原則が紹介されています。
以下にその内容を整理してご紹介します。
1、現場を重視すること
2、確固たるシステムの確立と臨機応変な対応
3、従業員を大切にすれば、従業員はお客様を大切にする
4、他人の意見から多くを学ぶ姿勢
5、変化しながら秩序を保つ
6、秩序を保ちながら変化する
7、成長に終わりはないという継続的向上心
8、自信過剰に陥らない謙虚さ
9、個人プレイよりチームプレイを優先する価値観
10、成功は全員でつかむものという協調意識
11、意思決定の4原則
①進んで、きっぱりと決断する
②学ぶ(調査する)
③正しい知識で判断する
④やらなかったことを後悔しない
12、悪い習慣を断ち切る明確な決意
これらの原則は抽象的な理念ではなく、現場で実際にどのように行動すべきかを明確に示している点に大きな意味があります。つまり、理論と実践が一体化されており、現場主義と経営戦略が見事に融合しています。 マリオットの経営には、「人を中心とした合理性」が一貫して流れています。単なる利益追求やシステム化だけではなく、従業員一人ひとりの価値と関係性を重視し、その存在を尊重する文化が根底にあります。
「従業員を大切にすれば、お客様は自然と戻ってくる」という理念は、サービス・プロフィット・チェーンの実例としても高く評価されるべきものでしょう。
そして、「変化しながら秩序を保つ」ことこそが、成長の本質であると、マリオットJr.は指摘します。 持続的に成長していくためには、「現状を少しずつ改善していく意識」と、「自分らしさや強みを守る姿勢」の両方を、常に意識し続ける必要があります。
一見すると矛盾しているようにも思えますが、実際には、この二つをうまく両立させることこそが、安定した成果を生み出すためには不可欠なのです。 秩序を保ちながら変化を取り入れることは、決して容易ではありません。
マリオットJr.は、この状態をバレエにたとえています。熟練した踊り手は、その難しさを感じさせませんが、ひとつでもステップを間違えると、すぐに目立ってしまいます。 つまり、ビジネスにおける成長とは、「秩序」と「変化」のあいだで、適切なバランスを取り続けることだといえるでしょう。
現場主義の徹底がマリオットの強み!
マリオットの従業員との絆を断ち切らないことに加え、ホテルを訪問することで現場の実態についてたくさんのことがわかってくる。旅に出ればかならず何かを学ぷことができるのだ。視察旅行から戻ると、ぜひとも実行すべきことや、不適切で改めなくてはならない点について、多量の索引カードに多くのアイデアが書きとめられている。このアイデアは問題を即座に解決したり、役に立つ発想を企業全体に広めていくため、本部のチームメンバーに報告している。
創業者であるJ.W.マリオット・シニアは、従業員との時間を何よりも大切にし、現場との直接的な関わりを重視していました。彼は従業員と同じテーブルで食事を共にし、誕生日には手書きのカードを贈るなど、徹底した「人間重視」の姿勢を貫いていたのです。
その精神は、息子であり後継者であるJ.W.マリオット・ジュニアにも確実に受け継がれました。彼もまた現場に頻繁に足を運び、従業員との対話を大切にしていました。ベットの下や浴室、クローゼットなど徹底的に部屋をチェックし、経営数字も綿密に検査し、良いことはほめ、悪いことは改善を求めます。
従業員からの手紙にすべて返事を書くなど、その姿勢は単なるパフォーマンスではなく、価値観に根ざした行動であることがうかがえます。 企業が成長していくうえで業務の標準化やシステム化は避けて通れません。
マリオットではその「仕組み」に「心」を吹き込む工夫が随所に見られます。たとえば、現場の栄養士と共同で作成されたレシピカードや、客室清掃のための66ステップから成るマニュアルなどは、単なる作業手順書ではなく、顧客に安心と感動を提供するための“体験設計”として機能しています。
これらの仕組みは、問題を未然に防ぐだけでなく、未知の課題に対しても柔軟に対応できる力を従業員に与えます。つまり、マニュアルは思考停止の道具ではなく、判断と行動の質を高めるためのフレームなのです。 加えて、マリオットの企業文化は、抽象的なスローガンや理念にとどまらず、従業員の日々の行動にまで浸透しています。
感謝の気持ちを持ち続けること、相手の立場に立って考えること、そして一人ひとりがチームの一員として誇りを持って行動すること。こうした文化が、企業全体の一体感を生み、ひいては顧客満足の源泉となっています。
ずっと優良企業でいられるかどうかを調査するリトマス試験は、成功した実績だけでなく、後退、失敗、困難な時代から立ち直る能力でもある。どこからみても完壁で、非の打ち所のない実績をもつ企業など一つもないのだ。(J.W.マリオット・シニア)
ここで強調しておきたいのは、企業が常に順風満帆であることなどあり得ないという点です。ずっと優良企業でいられるかどうかを見極めるリトマス試験紙は、成功体験の積み重ねだけではなく、むしろ「どのように困難から立ち直るか」にあります。完璧で非の打ち所のない企業など存在せず、創業から現在に至るまで、すべての企業が何らかの試練を経験してきたはずです。
重要なのは、失敗や後退の瞬間に、いかに迅速かつ柔軟に立ち直るかという「回復力」にあります。マリオットが真に優れた企業と評価される理由は、この高いレジリエンスにあると言っても過言ではありません。組織としての芯がぶれず、困難な状況でも人を中心とした価値観を貫く姿勢こそが、持続可能な成長と信頼の基盤を築いているのです。
『マリオット・ウェイ』は、サービス業にとどまらず、あらゆる業種に「人を活かす経営とは何か」を問い直すきっかけを与えてくれます。マリオットが体現している経営のあり方は、現代のビジネスパーソンにとって極めて示唆に富むモデルケースであると確信しています。1993年に出版されたやや古い書籍ですが、顧客体験や企業文化を重視したストーリーから、同社の先進性をうかがい知ることができます。
















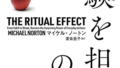

コメント