リジェネラティブ・リーダーシップ――「再生と創発」を促し、生命力にあふれる人と組織のDNA
ローラ・ストーム、ジャイルズ・ハッチンズ
英治出版
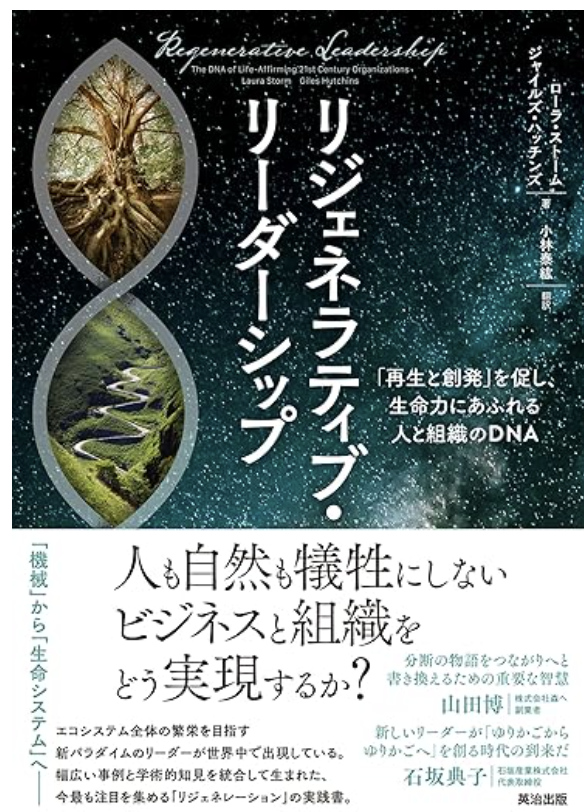
リジェネラティブ・リーダーシップの要約
ジャイルズ・ハッチンスとローラ・ストームは、収束と発散のライフダイナミクスを活用し、自己認識とシステム認識を育むことでリジェネラティブ・リーダーシップの意識を生み出す方法を示しています。このリーダーシップは、個人の内面と向き合うことから始まり、組織や生態系に広がる影響を考え、根本的な変革を促します。人々が生きる実感を取り戻し、組織が活力を持ち、生命の生態系が繁栄する未来を目指すアプローチです。
新しいリーダーシップ、リジェネラティブ・リーダーシップとはなにか?
人は、外界の自然にも内なる自然にもどのようにつながることができるのかを忘れてしまいました。生命に内在するパターンや関係性、エネルギー、知恵、知性を読み解く術を思いだし、学びなおさなければならないのです。(ローラ・ストーム、ジャイルズ・ハッチンズ)
私たちは、持続可能な社会を築くために、外的な環境への取り組みだけでなく、「内面のサステナビリティ」にも目を向ける必要があります。それは、創造性や遊び心を育み、ウェルビーイングを高め、自然の叡智と調和しながら、自らの存在目的と深く結びついた生き方を探求することを意味します。
現代社会は、物質的な豊かさを追求する一方で、自身の内面と外の世界の乖離に気づき始めています。かつての意識のままでは、未来を形作ることはできません。進むべき道は、左脳と右脳、自分自身の内と外、男性性と女性性、人と自然の関係を統合することにあります。
生命のパターンやエネルギーを読み解く力を取り戻し、自らの内側と外の世界の流れをつなぎ直すことが求められています。これは、個人だけでなく、組織や社会全体に必要な新しいリーダーシップの在り方でもあります。
リジェネレーターズ共同設立者のジャイルズ・ハッチンスとローラ・ストームは、収束と発散というライフダイナミクスを活用し、自己認識とシステム認識の両方を育むことで、リジェネラティブ・リーダーシップの意識を生み出す方法を示しています。
このリーダーシップは、まず内面と向き合うことから始まります。個人の在り方が組織や生態系に波紋を広げるため、世界の危機に対処するには、表面的な解決策ではなく、根本的な変革が必要です。傷ついた社会を癒やすには、私たち自身の内なる癒やしが不可欠なのです
リジェネラティブ・リーダーシップは、人々が生きる実感を取り戻し、組織が活力を取り戻し、生命の生態系が繁栄することを目指すアプローチです。組織や事業を生命システムとして捉え、多様なステークホルダーと共に成長することを大切にします。
そして、内なる感覚と深くつながりながら、外の世界に対する感度を高め、自然界の原理・原則に根ざしたシステムの変容を促していきます。 この変革のプロセスには、「システム思考(ひらかれた思考)」「システミック・アウェアネス(ひらかれた心)」「エコシステミック・アウェアネス(ひらかれた意志)」という3つのシフトが必要です。これらを通じて、自己、他者、世界に対する認識が微細に変化し、内外の統合が進みます。
また、このリーダーシップの土台には、「ロジック・オブ・ライフ」と呼ばれる7つの原則が存在します。 生命の営みを支える7つの原則の一つに「ライフ・アファーミング(生命指向性)」があります。生命は生命を生み育てるものであり、その本質を尊重することがあらゆる活動の基本となります。リジェネラティブ・リーダーは、生命を損なう行為を慎み、繁栄を促す選択をすることが求められます。
また、「絶え間ない変化と応答」も重要な原則です。生命は常に変化し続けています。リジェネラティブ・リーダーは変化を脅威ではなく機会と捉え、適応しながら学び成長していくことが求められます。
「関係性と協働」も欠かせません。生命は多層的な関係性の中で成り立っています。すべての事象はつながり合っており、それを理解することで、孤立した思考の枠を超えたシステム全体を見通す視点が生まれます。
また、「多様性とシナジー」は生命の本質を表しています。異なる要素の相互作用が新しい価値を生み出します。そのため、違いを受け入れ、融合させることが重要になります。
「周期とリズム」の理解も不可欠です。自然にはリズムがあり、生命はその流れの中で成長します。リーダーはこのリズムを理解し、適切なタイミングで決断を下すことが求められます。
「エネルギーと物質の流れ」も重要な視点です。すべての生命システムは、エネルギーと物質の流れによって維持されています。この流れを妨げず、循環の視点を持つことで、持続可能なシステムが実現されます。
最後に、「生命システムフィールド」についての理解が求められます。生命を支える「場」の存在を認識することで、より深いレベルでのつながりが生まれます。このフィールドへの意識が、リジェネラティブ・リーダーシップを支える要となります。
組織の進化を促すリジェネラティブ・リーダーシップ
発散と収束の動的なバランスは非常に重要です。明確な価値観、パーパスの共鳴感覚、日々の行動の指針となるシンプルなグラウンドルールによって一貫性が保たれているからこそ、リーダーはチームや組織を開放し、オープンな探索やステークホルダーとの対話、既成概念に囚われない発想をメンバーに促していくことができます。
現代のビジネス環境は、急速な変化と予測困難な状況が続く「VUCAの時代」と言われています。このような不確実性の中で、組織が持続的に成長し、社会と共に繁栄していくためには、固定化されたトップダウンのリーダーシップではなく、組織全体に意思決定を分散し、環境の変化に適応する柔軟な仕組みが求められます。
これまでのように少数のリーダーがすべてを決めるのではなく、組織全体の知恵を活かしながら、新しい可能性を探求し、進化し続ける環境を整えていくことが必要です。
組織が発展し続けるためには、「発散」と「収束」のバランスが不可欠です。発散とは、新しい視点やアイデアを取り入れ、自由な発想を促すプロセスです。一方で、収束は、発散によって生まれた可能性を整理し、具体的な行動へとつなげるプロセスを指します。
この2つの力が適切に作用することで、組織の持続的な成長が実現されます。しかし、このバランスを取ることは容易ではありません。発散が過剰になれば、アイデアが拡散しすぎてまとまりがなくなります。反対に、収束に偏りすぎると、新たな可能性が芽生える前に、創造のエネルギーが失われてしまいます。
リーダーは、この2つの動きを巧みに調整しながら、組織の柔軟性と方向性を同時に維持する必要があります。 この発散と収束のプロセスが生み出すのは、単なる試行錯誤ではなく、新しい価値を生み出す「創発」の化学反応です。異なる要素が交わることで、予測できない革新的なアイデアが生まれることは、科学の世界でも証明されています。
この現象は、まるで「アルケミー(錬金術)」のように、異なる文化や視点が交差することで新たな発見が生まれることに似ています。組織においても、異なる視点を意図的に掛け合わせることで、これまでにない創造が生まれるのです。
このプロセスを健全に機能させるためには、組織の根底にある「価値観」と「パーパス(目的)」の共有が不可欠です。組織の存在意義がメンバーに深く理解され、共鳴されているからこそ、メンバーは安心して新しい視点を持ち込み、自由な発想を広げることができます。また、パーパスが明確であることで、発散したアイデアを的確に収束させ、具体的な行動へとつなげる指針となります。
このような文化が確立されると、リーダーが全てを決定する必要はなくなり、現場のメンバーが自主的に意思決定し、状況に応じた柔軟な対応が可能となります。組織の各層に権限が分散されることで、迅速な対応が可能となり、環境変化にも適応しやすくなるのです。
組織が持続的に発展し続けるためには、閉鎖的な環境にとどまるのではなく、多様な視点とつながりを持つことが重要です。歴史を振り返ると、異なる文化や技術が交差することで、大きな変革が生まれてきました。例えば、シルクロードでは交易を通じて多様な文化が交わり、新たな技術やアイデアが誕生しました。
また、スターバックスの創業者ハワード・シュルツがイタリアのカフェ文化にインスピレーションを得て、アメリカのコーヒー文化を一新したように、異なる価値観を取り入れることで、組織の進化が促されるのです。企業においても、年齢、国籍、信条、性別など、多様なバックグラウンドを持つ人々と協働することで、新たな創造が生まれやすくなります。
リジェネラティブ・リーダーは、従来のようなトップダウン型の指導者ではありません。同時に、すべてを現場に委ねるボトムアップ型のスタイルとも異なります。
その役割は、「エコシステミック・ファシリテーター」として、組織が自律的に成長できる環境を整え、変化を促進することです。このアプローチは、明確な答えを押し付けるのではなく、環境全体の流れを整え、そこに関わるすべての人が自発的に創発していくような仕組みを作り出すことにあります。組織の文化がオープンであるほど、メンバーは新たな発想を自由に試し、自然と進化していきます。
このパラダイムシフトは、すでに世界のあちこちで静かに広がりつつあります。環境危機の到来、人工知能の発達、情報化社会の進展などを背景に、「人間とは何か」「組織の本質とは何か」を問い直す機運が高まっています。
その中で求められるのは、単に組織を効率的に運営するリーダーではなく、生命そのものに根ざしたリーダーシップです。発散と収束のバランスを調整し、組織の進化を促しながら、環境との対話を大切にすること。
これは、単なる経営戦略ではなく、より深いレベルでの「在り方」の変革でもあります。 変化が激しい時代において、組織が持続的に発展し続けるためには、このダイナミックなバランスを常に調整し、柔軟に適応していくことが求められます。
そして、その調整役としてのリーダーは、単なる管理者ではなく、創造のプロセスそのものを支え、進化の流れを生み出していく存在でなければなりません。生命そのもののリズムに寄り添いながら、未来を形作っていく。それこそが、これからのリーダーシップの本質なのです。
ジェネラティブ・リーダーシップの3つのDNA
リジェネラティブ・ビジネスの鍵は、健全な収益性を大事にしながらも、事業を取り巻く生態系全体が活き活きとした状態であるかどうかを常に企業哲学の中核に据えることです。生態系全体に貢献するのは、できた方がいいことではなく、組織が存在目的を果たし、財務的な持続可能性を担保するためになくてはならないものなのです。この考え方こそが生命システム全体のステークホルダーを巻きこみ、想像を超える成果へ導く力となるのです。
リジェネラティブ・ビジネスの本質は、単に利益を追求することではなく、企業が関わる生態系全体の健全性を維持しながら持続的に成長することにあります。収益性を確保することはもちろん重要ですが、それだけでは不十分です。
事業が成長する過程で、環境や社会、関係するステークホルダーが活き活きと繁栄できる状態をつくり出すことが、組織の存在意義を果たし、長期的な成功へとつながります。この視点を企業哲学の中核に据えることで、単なる事業運営を超えた価値が生まれ、想像を超える成果を実現できるのです。
リジェネラティブ・リーダーシップは、企業を単なる経済活動の場ではなく、生命のシステムとして捉え、環境や社会と調和しながら成長することを目指します。
その基盤となるのが、「生命システムデザイン」「生命システムカルチャー」「生命システムビーイング」という3つのDNAの領域です。これらは、組織の構造、文化、そしてリーダーシップの在り方に深く関わり、互いに影響し合いながら、持続可能な未来を形作る重要な要素となっています。
生命システムデザインとは、組織や製品、サービスの設計を、生命の原理に基づいて構築する考え方です。自然界ではすべての要素が循環し、無駄がありません。これと同様に、企業活動においても資源を最大限に活用し、廃棄物を次の資源として再生させる「サーキュラーエコノミー」の視点が求められます。 こ
のデザイン思考の中核には、「バイオミミクリー(生物模倣)」があります。バイオミミクリーとは、自然の形状や機能、システムから着想を得て、持続可能な製品やサービスを生み出すアプローチです。例えば、森林の生態系が長い時間をかけてバランスを取りながら進化してきたように、企業も長期的視野を持ち、調和の取れた成長を遂げる必要があります。
また、建築や都市設計、プロダクトデザインにおいても、「バイオフィリック・デザイン(自然と人をつなぐデザイン)」が注目されています。人々が内なる自然や周囲の環境とつながることで、より直感的で調和の取れた空間を生み出すことができます。
このように、生命システムデザインは、環境との調和を意識しながら、機能性と持続可能性を兼ね備えた新しいデザインの方向性を示します。
生命システムカルチャーとは、組織の文化を生命のシステムのように成長させ、発展させる考え方です。生命が繁栄するためには、単なる生存ではなく、発展と進化が必要です。同様に、組織も単に存続するだけでなく、環境の変化に適応しながら成長し続けることが求められます。
この文化を実現するためには、組織内での「自己組織化」と「局所適応」が不可欠です。自己組織化とは、個々のメンバーが自律的に行動しながら、全体としての調和を生み出す仕組みです。トップダウンの管理体制ではなく、現場レベルでの意思決定が促されることで、組織の柔軟性が向上し、変化への対応力が高まります。
また、多様性を受け入れ、インクルーシブな文化を育むことも重要です。異なる背景や視点を持つメンバーが集まり、それぞれの強みを活かすことで、より創造的で革新的なアイデアが生まれます。
マッキンゼーの調査でも、多様性の高い組織は業績が向上する傾向にあるとされています。組織が生命システムのように進化し続けるためには、異なる価値観や視点を尊重し、共に成長する環境を整えることが欠かせません。
さらに、組織の存在目的(パーパス)と個人のパーパスが一致することも、生命システムカルチャーの大きな特徴です。メンバーが自身の価値観と組織のビジョンを共有できたとき、仕事に対する意義を深く感じ、活力や創造性が生まれます。こうした共鳴が組織全体の推進力となり、単なる利益追求を超えた社会的なインパクトを生み出すことにつながります。
生命システムビーイングは、個人が内面的な気づきを深め、リーダーシップの在り方そのものを磨くプロセスです。組織の変化や進化は、最終的には個々のリーダーの内面から始まります。そのため、リジェネラティブ・リーダーには、環境に対する理解だけでなく、自身の在り方を見つめ直し、整える力が求められます。
この考え方には、「プレゼンス(今この瞬間に意識を向ける)」が重要な要素となります。現代社会では、目の前のタスクや情報の洪水に流されがちですが、真のリーダーシップは静けさの中から生まれます。自分自身の内なる自然と深くつながることで、環境の変化を敏感に察知し、適切な意思決定が可能になります。
また、「一貫性」も欠かせません。リーダーが自らの価値観に従って行動し、誠実さを持つことで、周囲の信頼を得ることができます。組織のパーパスを単なるスローガンではなく、日々の行動に落とし込むことが、生命システムとしての組織の持続性を高める鍵となります。
さらに、「待つ」という姿勢も生命システムビーイングの特徴です。組織の成長や変革は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。長期的な視点を持ち、焦らずに環境の変化を見極めながら、最適なタイミングで行動することが求められます。衝動的な判断や短期的な成果にとらわれるのではなく、深い洞察と忍耐を持って組織を導くことが、持続的な成長へとつながります。
また、「変化を楽しむ姿勢」も大切です。自然界のリズムと同じように、組織も常に変化し続けます。変化を受け入れ、それを創造的なプロセスとして捉えることで、新しい可能性が広がります。遊び心を持ちながら、未知の未来に対してオープンでいることが、リジェネラティブ・リーダーの本質的な資質といえるでしょう。
リジェネラティブ・リーダーシップは、単なる経営手法ではなく、組織と個人の在り方そのものを根本から問い直すものです。「生命システムデザイン」で持続可能な構造を築き、「生命システムカルチャー」で多様性と共創の文化を育み、「生命システムビーイング」で個人のリーダーシップの本質を磨きます。
この3つが統合されたとき、組織は生命システムとして自律的に成長し、持続可能な未来へと向かっていくのです。













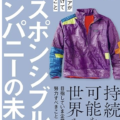
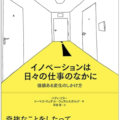



コメント