「働き手不足1100万人」の衝撃――2040年の日本が直面する危機と“希望”
古屋 星斗、リクルートワークス研究所
プレジデント社
「働き手不足1100万人」の衝撃の (古屋星斗)の要約
リクルートワークス研究所の予測によると、2040年には日本で労働者が1100万人不足するとされています。この働き手不足は「危機」であるだけでなく、「チャンス」でもあります。従業員に良い労働環境を提供し、消費者に優れたサービスを提供する企業が市場で優位に立つでしょう。
労働供給制約社会の2040年の日本は無人島のようになる?
2040年に日本では、1100万人の働き手が足りなくなるー。(リクルートワークス研究所)
リクルートワークス研究所は、2040年には日本の労働者が1100万人の不足すると予測します。特に、これまで「人手不足」という言葉が企業の雇用問題として語られてきたのとは異なり、今後の「人手不足」は日本社会全体に深刻な影響を及ぼすとされています。
実際、2040年には日本で働く人々が1100万人も不足するとのことです。この予測は、特定の業種において顕著であり、特に以下の職種が深刻な人手不足に陥るとされています。
・介護サービス職
25.2%の人手不足が予測されています。高齢化が進む日本において、介護の需要はますます高まる一方で、介護職に従事する労働者が不足することは大きな問題です。
・ドライバー職
24.1%の人手不足が見込まれています。物流や公共交通機関の運営に欠かせないドライバーの不足は、日常生活や経済活動に直接的な影響を与えます。
・建設職
22.0%の人手不足が予測されています。インフラの維持や新たな建設プロジェクトの推進が困難になることで、社会全体の発展に支障をきたす可能性があります。
これまでの人手不足問題は、後継者不足や技能承継難、デジタル人材の不足といった産業・企業視点から語られてきたが、これから訪れる人手不足は「生活を維持するために必要な労働力を日本社会は供給できなくなるのではないか」という、生活者の問題としてわれわれの前に現れるのだ。
「労働供給制約社会」とは、必要な働き手の数を供給できなくなる状況を指します。この社会では、必要な労働力が慢性的に不足するため、私たちは今までの生活を維持できなくなると著者は指摘します。それだけでなく、適切な人材配分ができなくなり、先端分野に人材を供給できなくなるため、イノベーションも起こりづらくなるとも言います。
労働供給制約社会では、実際次のような問題が起こり始めています。
・高齢者や病人への影響
介護や医療サービスを提供する人々が不足すると、高齢者や病気の人々の生活が深刻な影響を受けます。必要なケアが受けられないことで、生活の質が低下し、場合によっては命に関わる問題が生じることもあります。
・経済活動の停滞
労働力が不足することで、企業の生産性が低下し、経済成長が鈍化します。これにより、失業率の上昇や賃金の低下、さらには企業の倒産など、経済全体が不安定になるリスクが高まります。
・社会全体の影響
労働力不足により、公共サービスの質が低下し、インフラの維持や新規プロジェクトの実施が困難になることがあります。これにより、社会全体の生活水準が低下し、地域間の格差が広がる可能性があります。
「労働力率をさらに高め、多くの人に労働に参加してもらう」という取り組みは、ほぼ限界に達しつつあり、危機的な状況になっています。日本のような労働供給制約社会では、「みなが無人島に住むような」社会になる可能性があります。つまり、必要な労働力が不足することで、人々が生活を維持するためには自らの力で様々な仕事をこなさなければならなくなるということです。
日本国内において、2040年には、生活維持サービスの充足率が75%未満となっている地域が31道府県もあることが明らかになりました。これは、4人分の仕事を3人でこなさなければならない状況を示しています。特に地方では、労働供給の制約により生活維持サービスの提供が不足しており、困難な状況が広がっていることが懸念されます。
人材確保は経営課題!
人材確保を経営課題のなかで最も優先的に取り組まなくてはならない
エッセンシャルワーカーを中心に労働力が逼迫する中で、人材確保が重要な経営課題になってきました。民間企業では待遇や環境の改善を通じて若手人材の獲得競争が激化し、その結果、公務員の人材獲得が困難になっています。
公務員は民間企業と異なり、給与や労働環境が安定しているとされていますが、最近ではその魅力に陰りが見え始めています。若手が民間企業に魅力を感じる理由は、高い給与やキャリアアップの可能性、柔軟な働き方などが挙げられます。このような状況下で、公務員への応募者数が減少しているのは避けられません。
さらに、自衛官の採用状況も深刻です。過去10年間で応募者数が26%も減少し、2022年度の採用計画未達が顕著な問題となっています。自衛官は国の安全を守る重要な役割を果たしており、人材不足は国家安全保障上の深刻な懸念となります。採用計画未達により、自衛隊の運用に支障が出る可能性もあります。
民間企業であれば、採用計画未達は採用責任者にとって重大な問題となります。労働供給制約が引き起こす人材獲得難に対処するためには、効果的な施策や制度改革が求められます。今後、日本の労働社会における人材確保の重要性が一層高まることが予想されます。
生産性向上や技術開発に向き合う人材の余力がなくなると、経済の生産性が上がらず、イノベーションも生まれなくなります。この状況は、日本社会が停滞してしまう恐れを示しています。 日本は世界でもいち早くこの課題に直面しており、これまでの取り組みだけでは対応が難しいため、新たな発想と対策が求められています。
しかし、その発想を実行する余裕がなくなり、人々が生活を回すのに精一杯の状況になる前に、今こそ具体的な対策を講じる必要があります。
1. 技術革新の推進
AIやロボット技術を活用して労働力不足を補う技術開発を進めることが重要です。自動化技術により生産性を向上させることで、人手不足を緩和することが可能です。
2. 働き方改革
働き方改革が進む中、リモートワークやフレキシブルな勤務時間制度の導入により、労働市場への参加が促進されています。この柔軟な働き方は、シルバー世代や女性の社会参加を増やす一因となっています。特に育児や介護を担う人々にとって、働きやすい環境が整えられることで、仕事と家庭を両立しやすくなります。さらに、多様な人材を確保するためには、長時間労働から解放されることが重要です。
将来の日本は「労働供給制約社会」を迎え、生産年齢人口が減少する中で高齢者層の力を活かすことが不可欠となります。しかし、「シニアはもっと社会に貢献せよ」という号令だけでは持続可能ではありません。重要なのは、高齢者が無理のない範囲で小さな仕事や活動を始め、続けることです。これが結果として社会全体の助けとなり、自身のためにもなります。
今幸せな高齢期の生活と両立する仕事・活動の要素として重要な3つのポイント
・健康的な生活リズムに資する
・無理がない
・利害関係のない人たちとゆるやかにつながる
「ワーキッシュアクト」とは、「Work-ish」=何か社会に対して機能・作用をしているっぽいと 「act」=本業の仕事以外のさまざまな活動の造語で、 社会に対して機能・作用する活動のことを指します。
これまでの慈善活動やボランティア、コミュニティ活動、副業、趣味などが、労働供給制約社会において重要な役割を果たしています。これらの活動は、単なる趣味や娯楽だけでなく、誰かの困りごとを助けることに繋がっています。労働供給制約社会を迎える中で、これらの活動の価値をより前向きに捉える必要があります。
本人が自分のために行っている活動であっても、結果として他者を助けることに繋がっているのです。 ワーキッシュアクトは、社会全体の労働環境や価値観の変革に貢献しています。柔軟な働き方を通じて、多様な人材の参加を促し、労働供給制約社会においても活動の価値を高めていくことが重要です。
3. 外国人労働者の受け入れ
外国人労働者の受け入れを拡大し、多様な人材を確保することで、労働力不足を補います。特に専門技能を持つ外国人労働者の受け入れは、技術革新や産業の高度化に寄与します。各国との人材の奪い合いが激化する中、外国人が働きたいと言う国に日本変わる必要があります。
4. 教育と訓練の充実
若者や再就職希望者に対して、必要なスキルや知識を提供する教育プログラムや職業訓練を充実させ、即戦力となる人材を育成します。これにより、労働市場を活性化させることができます。 これらの対策を講じることで、日本は労働供給制約社会の課題を克服し、持続可能な社会と経済を実現する道を切り拓くことが求められます。
今こそ新しい発想で大胆な改革を行い、将来の日本社会の安定と発展を確保するための行動を起こす時です。 AIやロボティクスの導入を推進し、それに対応できる人材の育成を強化する。職業訓練や再教育プログラムの充実が重要です。
必要な変革をおこなわずに労働者に長時間労働を強いる企業、労働者を安い賃金で働かせようとする企業、過度に負荷が高い仕事を労働者に押し付ける企業、こうした企業は労働供給制約を迎える将来の日本の労働市場において生き残ることができない。
ブラック企業が生き残れなくなる一方で、業務プロセスを見直して生産性を高め、従業員に報酬として還元する企業は、業界でシェアを拡大していきます。その結果、熾烈な企業間競争の中で、従業員により良い労働環境を提供し、消費者に優れたサービスを提供する企業が市場で優位に立つと著者は指摘します。
労働供給制約下では、働き手が最も希少な経営資源となります。企業も社会も無駄な仕事に人材を使う余裕はなく、本当に必要なサービスを提供するために業務を削減し、機械化や自動化を進める必要があります。無駄を徹底的に見直すことで、企業は人材を有効活用し、働き方の自由度を高めることができます。
さらに、企業が職場での支援を強化することで、従業員が社外で多様な活動に参加する機会を促進することができます。労働供給制約が進む未来において、人々の多様な活動を仕組み化することが重要となりますが、現在の多くの社会人が本業と家庭以外の活動に参加できていないのが実態です。企業がこの役割を担うことで、社会全体の活力を維持することが可能です。
また、賃金の引き上げが企業の持続性を問う試金石となっています。賃上げによって企業が倒産するケースもありますが、今後の賃金水準の引き上げは企業の価値や信頼関係を問う重要な要素となります。社員の賃金水準を高めることで、経営の本質が問われ、企業の持続可能性が試されるのです。
2040年のポジティブな未来予測
この「危機の時代」を「希望の時代」に変えるために、新しい視点とアプローチが求められています。著者は、3つの未来予測をもとに、希望に満ちた未来への道筋を描きます。
・未来予測1 消費者と労働者の境目が曖昧になる
現代のデジタル技術の進化は、消費者と労働者の役割を大きく変えつつあります。2040年には、消費者と労働者の境目が曖昧になると予測されています。具体的には、消費者が自身のスキルや知識を活かして、サービスを提供する場面が増えるでしょう。これは、シェアリングエコノミーやクラウドソーシングの普及により、個々人が自分の時間やスキルを商品として提供できる環境が整うからです。
例えば、専門知識を持つ消費者がオンラインプラットフォームを通じてアドバイスを提供することや、趣味で培った技術を活かして副業をすることが一般的になるでしょう。このような環境では、消費者が労働者としての顔を持ち、自らの価値を高めることで、生活の質を向上させることが可能になります。
・未来予測2 働き手が神様です
2040年の労働市場では、働き手がますます貴重な存在となり、「働き手が神様です」という状況が現実のものとなるでしょう。これは、労働力の不足が深刻化する中で、企業が優秀な人材を確保するために、働き手のニーズや要求に応える必要があるためです。
企業は、働き手に対して柔軟な働き方を提供し、職場環境を改善し、キャリアアップの機会を提供するなど、働き手が働きやすい環境を整えることが求められます。また、報酬や福利厚生の充実も重要な要素となります。働き手が満足し、モチベーションを持って働ける環境を整えることで、企業の生産性や創造性が向上し、持続可能な成長が実現します。
・未来予測3 労働が楽しくなる
2040年には、労働が楽しいものになると予測されています。これは、AIや自動化技術の進化により、単調で反復的な作業が機械に代替される一方で、人間はより創造的で意義のある仕事に集中できるようになるからです。これにより、労働そのものが自己実現の手段となり、働くことが喜びとなるでしょう。 また、働き方の柔軟性が増し、リモートワークやフレックスタイムなど、自分のライフスタイルに合わせた働き方が可能になります。
これにより、仕事とプライベートのバランスが取りやすくなり、ストレスの少ない生活を送ることができます。さらに、企業は社員のスキルアップやキャリア開発を支援し、働き手が成長を実感できる環境を提供することが求められます。
「危機の時代」を「希望の時代」に変えるためには、新たな視点とアプローチが必要です。消費者と労働者の境目が曖昧になる未来、働き手が神様となる未来、そして労働が楽しくなる未来を実現するためには、技術の進化とそれを活用する柔軟な思考が不可欠です。私たち一人ひとりが自分のスキルや価値を高め、新しい働き方を模索することで、未来はより希望に満ちたものになるでしょう。
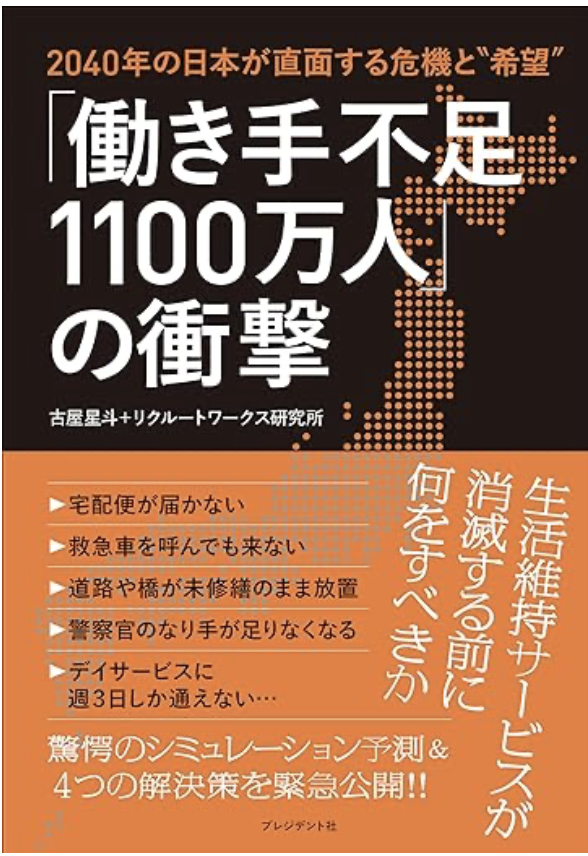

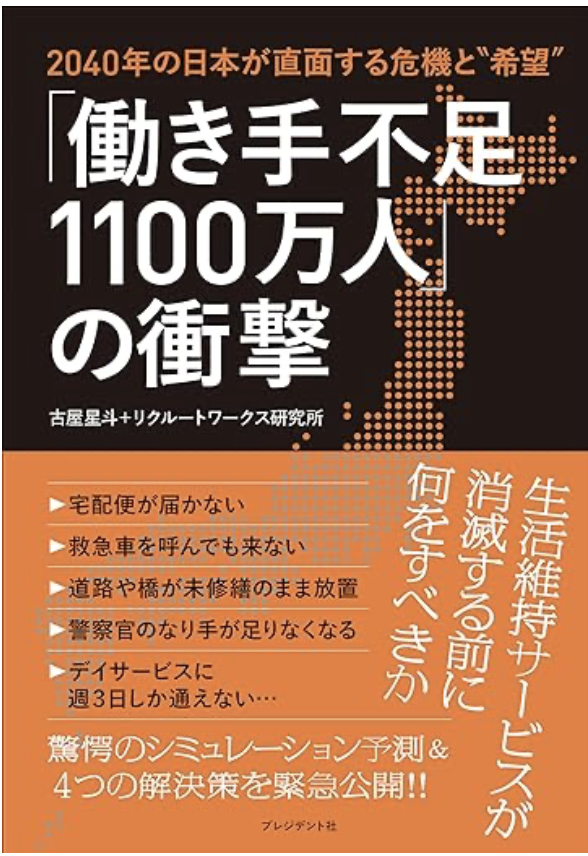
















コメント