
ATTENTION SPAN(アテンション・スパン) デジタル時代の「集中力」の科学
グロリア・マーク
日本経済新聞出版
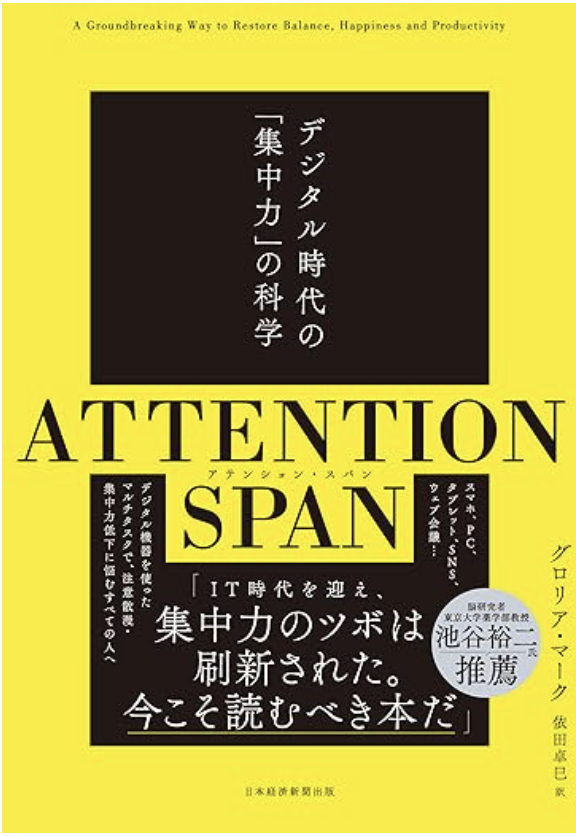
ATTENTION SPAN(グロリア・マーク) の要約
現代社会において集中力の低下は避けられない現象ですが、その影響を軽減するためには、意識的な対策が必要です。タスクの優先順位を明確にし、デジタルデバイスからの離脱時間を設け、集中力を養うことが重要です。著者のアドバイスを実践することでストレスや疲労を軽減し、より幸福で生産的な生活を送ることができるでしょう。
私たちの集中時間は47秒?
私たちの集中時間(アテンション・スパン)は、日ごとに短くなっている。(グロリア・マーク)
現代社会において、テクノロジーは私たちの生活のあらゆる側面に浸透しています。コンピュータやスマートフォン、ソーシャルメディアなどのデジタルギアの普及により、私たちの生活は便利になった一方で、集中力の低下という新たな課題が浮かび上がっています。
カリフォルニア大学アーバイン校の総長特任教授のグロリア・マークは、デジタルギアやSNSが私たちの集中時間を奪っていると指摘しています。 さまざまな科学研究によって、過去15年間でデバイスを使う際の「集中時間」が劇的に短縮されていることが明らかになっています。
現在、私たちがコンピュータやスマートフォンを使うときの集中時間は、平均でわずか47秒にしか過ぎないと言います。これは異常なほど短い時間であり、頻繁な注意の切り替えがもたらす負担は無視できません。
テクノロジーの進化により、仕事の連絡手段は劇的に増加しました。メール、チャットアプリ、ビデオ会議など、多様なコミュニケーションツールが存在し、常に仕事の連絡が取れる状態を維持することが求められます。
「動的集中」(キネテック・アテンション)とは、複数のアプリやソーシャルメディア、インターネットのサイト、あるいはコンピュータとスマートフォンなどのあいだで集中が活発に切り替わっている状態を指す。 私たちはこの動的集中をうまく使いこなせておらず、このままではさまざまなストレスや疲れ、成績低下が生じ、燃え尽き症候群にもなりかねない。なぜなら、すばやい集中の切り替えが認知リソースを消費し、枯渇させてしまうからだ。
動的集中とは、注意が複数のタスクやデバイス間で頻繁に切り替わる状態を指します。この現象は、特にデジタルネイティブ世代に顕著に見られます。例えば、スマートフォンでメッセージを確認しながら、パソコンで仕事のメールを返信し、同時にソーシャルメディアをチェックするという状況が典型的です。 動的集中は、一見するとマルチタスクを効率的にこなす手段のように思われるかもしれません。
しかし、実際にはマルチタスクによって、私たちは認知リソースを過剰に消費し、注意散漫を引き起こしてしまいます。これは、私たちの脳が本来、一度に一つのことに集中するように設計されているためです。
動的集中が長時間続くと、私たちの認知リソースは枯渇し、以下のような影響が現れることが考えられます。
・ストレスと疲労
頻繁な集中の切り替えは、精神的な負担を増大させ、ストレスや疲労を引き起こします。
・パフォーマンスの低下
学業や仕事において、動的集中が続くと、作業効率が低下し、パフォーマンスが悪化する可能性があります。
・燃え尽き症候群
長期間にわたる動的集中は、認知的なエネルギーを消耗させ、燃え尽き症候群のリスクを高めます。
動的集中の影響を軽減し、より健康的で生産的な生活を送るためには、いくつかの対策が必要です。タスクや感情的欲求に合わせて、集中力をコントロールするのです。
・タスクの優先順位をつける
一度に複数のタスクをこなすのではなく、重要なタスクに集中する時間を設けましょう。タスクの優先順位を明確にし、一つ一つ順番に取り組むことが大切です。
・切りの良いところで自ら中断する
資料作成などでは、適切なところで自ら中断し、スムーズに仕事を再開できるようにします。一定程度のタスクを終えた後に中断するようにしましょう。
・重要な未完のタスクを頭の中から追い出す。
デジタル世界が生活空間となったいま、私たちはそのなかで幸福に生きる方法を学ぶ必要がある。切りのいいところで仕事の手を休め、動的集中を制御し、未完のタスクの記憶を外部に移し替えて緊張を減らそう。中断は生活の一部なのだ。
タスクをメモに残すことで、頭の中がスッキリします。何かに残すことで、緊張を外部に移し替えられます。
・デジタルデトックス
定期的にデジタルデバイスから離れる時間を作りましょう。例えば、週末や就寝前の1時間はスマートフォンやコンピュータを使用しないなどのルールを設けると良いでしょう。
・自分の行動に気づくこと
インターネットやSNSの誘惑に負けて、中断していることに気づき、その行動を止めるモチベーションを高めるようにします。その際、その衝動に抵抗するための認知リソースが必要になります。
・集中力を養う
瞑想やマインドフルネスの練習を通じて、集中力を養うことも有効です。これにより、注意の持続力が向上し、動的集中による認知リソースの消耗を防ぐことができます。
・休息とリフレッシュ
適度な休息とリフレッシュは、認知リソースの回復に重要です。仕事や勉強の合間に短い休憩を取り、体と心をリフレッシュしましょう。睡眠不足が集中力を削ぎ、Facebookの時間が増えるという研究結果を見て、私は睡眠時間を増やしたくなりました。
動的集中は現代社会において避けられない現象ですが、その影響を軽減するためには、意識的な対策が必要です。タスクの優先順位を明確にし、デジタルデバイスからの離脱時間を設け、集中力を養うことが重要です。これらの対策を実践することで、ストレスや疲労を軽減し、より健康的で生産的な生活を送ることができるでしょう。未来を見据え、私たちは今から行動を起こすことが求められています。
中断にもメリットがある?
現代人にはFacebookやYouTube、同僚からのメッセージなどさまざまな誘惑があり、仕事をしている時の集中力が阻害されます。この中断がもたらす影響は非常に深刻です。研究によれば、人々は中断が入ることによって、かなり高い心的負荷と苛立ち、時間的プレッシャー、そしてストレスを感じることが分かっています。
中断は認知負荷を増加させ、ストレスを引き起こし、結果的に仕事の効率と品質に大きな影響を与えます。 中断によって集中が途切れることは、一見ネガティブな影響を与えるように思われがちですが、実はプラスの面も存在します。
中断にもプラスの面はある。仕事から離れることが精神的な休息をもたらし、認知リソースを回復させ、他者との社会的なつながりから一時的に遠ざかることができ、それによって新しいアイデアを生み出せるのだ。
一方、中断があることで、メインのタスクに対するアプローチを再評価し、効率的に進めるための新たな方法を見つけることができる場合があります。例えば、短い休憩を取ることで、疲れた脳をリフレッシュさせ、再び集中力を高めることができます。
仕事から一時的に離れることは、精神的な休息をもたらします。ずっと同じタスクに集中し続けることは、脳に負担をかけ、疲労感を増大させます。短い休憩や中断の時間を利用することで、脳はリフレッシュし、認知リソースを回復させることができます。このリフレッシュ効果によって、仕事に戻ったときにはより効率的に作業を進めることが可能になります。
中断は、他者との社会的なつながりから一時的に遠ざかる機会も提供します。特にオフィス環境では、他人とのコミュニケーションが絶えず続くことがあり、それがストレスの原因となることもあります。中断の時間を利用して、自分だけの時間を持つことで、心の負担を軽減し、ストレスを緩和することができます。
仕事から離れることで、頭の中がリセットされ、新しい視点から物事を考えることができます。この過程で、新しいアイデアや解決策が生まれることがあります。例えば、散歩をする、趣味に時間を費やすなど、日常のルーチンとは異なる活動をすることで、創造性が刺激されるのです。
デジタル時代には、個人だけでなく、社会全体で文化的な変化が必要です。個人の力だけでデバイスから長時間離れることは難しく、離れすぎると重要な情報を逃してしまう恐れがあります。そのため、「社会」全体で賢くデバイスを使用し、情報過多で疲れ果てない方法を見つけることが重要です。
私たちの生活を生産性の最大化だけでなく、精神のバランスがとれるように変えていくことが求められています。デバイスを使うときの目標は、精神的なリソースを維持し、最終的に幸福感を高めることにシフトするべきです。こうすることで、長期的な仕事の生産性も向上し、より豊かな生活を実現することができるでしょう。精神のバランスを重視した生活習慣を取り入れ、幸福感と生産性の両立を目指していきましょう。
フローの4象限から集中力を取り戻す方法
現代社会では、私たちの集中力は様々な要因によって左右されます。その中で、いかに効果的に集中し、最高のパフォーマンスを発揮するかは重要な課題です。グロリア・マークは、フロー理論を基にして「異なる集中状態を表す理論的枠組み」を提案し、これを図式化して説明しています。
ここでは、その枠組みを文章で紹介し、さらにその応用について考察します。 グロリア・マークは、「熱中度」の高低を縦軸に、「難易度」の高低を横軸にして集中の4象限を作り、それぞれを次のように命名しています。
・没入
難しい活動に熱中している状態
・慣れ
さほど難しくない活動に熱中している状態
・退屈
あまり難しくない活動にさほど熱中していない状態
・不満
難しい活動にまったく熱中していない状態
集中力は目標の有無に左右されます。私たちは明確な目標によって、没入できるようになります。没入状態はフローの入り口です。スポーツや芸術、あるいは仕事や勉強に打ち込んだことのある人は、時間の感覚を忘れてその活動にのめり込んだ経験を持っています。しかし、そのフロー状態は頻繁に体験できるものではなく、熟達者であっても人生の多くの時間をフロー状態にいることはできません。
退屈しているときには目標をめざす強い集中がなく、単純な活動をしているときにも目標意識が弱くなりやすいからだろう(たとえば、ソーシャルメディアの投稿をスクロールしているときなど)。集中は目標によって高まる。退屈したり単純な活動をしているときのように、はっきりとした目標がなければ、私たちの注意はあちこちにさまようのだ。
著者が導き出したのは、「リズム」を集中に活用することが重要です。先の4象限でいうと、不満は高ストレスにつながるためできるだけ避けるとしても、退屈と慣れの状態は、没入状態とうまく使い分けるなら効果的です。
生産的で創造的な没入状態は、私たちの脳と体に多大なエネルギーを要求します。この集中状態は理想的である一方、リソースの消費量も非常に多くなります。そのため、常にこの状態を維持するのは難しく、時には疲労やストレスの原因にもなります。
一方、単純な活動や退屈な状態にあるとき、リソースの消費量ははるかに少なくなります。私たちは生産的で創造的な没入こそが理想の集中状態と考えがちですが、実は慣れや退屈も私たちの集中力にとって重要です。これらの状態は、脳を休め、リソースを節約する役割を果たしているのです。
慣れや退屈な状態は、日常生活の中で多く見られます。例えば、通勤電車の中で風景を眺めたり、同じ作業を繰り返したりする時間は、退屈に感じるかもしれません。しかし、こうした時間は、脳がリラックスし、エネルギーを回復させるための貴重な機会です。リソースの節約は、健康や幸福に欠かせない要素であり、私たちの長期的なパフォーマンスにも寄与します。
また、退屈な状態は、創造性を刺激することもあります。単純な作業中や退屈な時間を過ごしているとき、私たちの脳は自由に漂うことができ、新しいアイデアや解決策を生み出すことがあるのです。これは、没入状態では得られない独特の創造的なインスピレーションをもたらします。
健康や幸福のためには、バランスが重要です。集中して没入する時間も大切ですが、慣れや退屈を受け入れ、それを積極的に活用することも必要です。これにより、リソースの消費を最適化し、長期的な健康と幸福を維持することができます。
主体的に計画・行動し、幸福度を高めよう!
アイロンがけ、手洗い、牛の観察これらに共通しているのは、頭を使わない集中であるということだ。こうした単純な活動には長所がある。認知リソースをあまり使わずに心を働かせることができるのだ。簡単な作業をすることで心は開放され、解決困難な問題からいったん離れて新しいことを思いついたり、充分検討していなかった考えを前に進めたりすることができる。
著者は、”休息をとる余裕を持とう”と提言しています。 また、慣れの効用も強調されています。”単純な活動にも大切な役割がある。さほど難しくない活動に熱中しているとき、人は幸せを感じ、くつろぎ、認知リソースを回復している”と説いています。
日常生活の些細なこと頭を使わない集中で、私たちはなんともいえない安らかな気持ちになれるのです。意図的な気晴らしが、認知リソースを高めてくれるのです。
日常生活で問題に直面したとき、その解決策を見つけるために深く考えることが多いですが、認知リソースを費やさない活動によって問題から一旦離れることが有効であることもあります。頭を使わない単純な活動は、心理的なバランスを取る上で非常に役立ちます。こうした活動を行うことで、私たちは問題に対する新たな視点を得ることができ、創造的な解決策を見つける手助けとなるのです。
ポジティブな感情は、行動の選択肢を増やす効果があります。単純な活動を通じてポジティブな感情を積み上げることで、さらにクリエイティブな発想が生まれる可能性が高まります。私たちが無意識に頭を使わない活動に惹かれるのは、その活動が心理的なバランスを保つ助けになるからです。これにより、私たちはストレスを軽減し、リラックスすることで、より自由な発想ができるようになるのです。
集中力は目標指向であり、明確な目標があるときに最大の効果を発揮します。しかし、目標を見失うと、集中力は内部の考えや外部の刺激に引っ張られてしまい、簡単でポジティブな感情の報酬が得られる活動に向かってしまいます。これが、私たちがしばしばスマートフォンをチェックしたり、他の気晴らしに走ったりする理由です。
高いレベルの目標を維持するためには、単純な活動をその目標達成の一つの手段と捉えることが重要です。たとえば、散歩や軽い運動、絵を描くなどの活動は、直接的には問題解決には結びつかないかもしれませんが、心をリフレッシュし、新たなアイデアを生むための土壌を提供してくれます。これにより、再び集中力を高めて目標に取り組む際に、より効果的に進めることができるのです。
繰り返しになりますが、没入状態を長時間持続させることはできません。だからこそ私たちが注力すべきなのは、自分の集中リズムに合わせた1日のスケジュールを立てることです。自分の集中のピーク時間を知り、集中すべき時にその時間をあわせることが重要です。
主体性を身につければ、高いレベルの集中力でタスクを完了させ、戦略的に集中状態をコントロールし、バランスを取りながら「動的集中」を有効活用することができる。
デジタル時代において、私たちは多くの情報に触れ、様々なタスクに追われています。その中で、行動に移す前に「本当に必要なことかを問いかける」ことが重要です。これは、無駄な時間やエネルギーを浪費せず、真に必要なことに集中するための方法です。
・目的を明確にする
行動を起こす前に、その目的を明確にしましょう。何を達成したいのか、どのような結果を求めているのかを考えることで、本当に必要な行動かどうかを判断できます。SNSを使う前に、自分の数時間後のタスクの完了に悪影響を及ぼさないかを考えてみましょう。後悔しないために、この「事前の考慮」を習慣にするのです。
・優先順位を設定する
すべてのタスクが同じ重要度ではありません。優先順位を設定し、最も重要なタスクに集中することで、効率的に行動を進めることができます。認知リソースが有限であると考え、1日を設計しましょう。自分の集中のリズムを考え、スケジュールを立てるようにするのです。私は重要な仕事は、可能な限り午前中に行うようにしています。
著者は、重要な仕事の前後に休息を取ることで、集中力を維持し、精神のバランスを取ることができるようになると述べています。散歩や瞑想、運動など自分が幸せを感じることに時間を使いましょう。
制限された時間内で効率よく情報を収集する習慣をつけることで、集中力が高まります。限られた時間内で成果を上げるための工夫が求められるため、集中力のトレーニングにもなります。
いま私たちにできることは、主体性の力で集中力をコントロールし、自分の集中のリズムに合わせて働き、幸福と健康の実現に向けて努力することだ。偉大な芸術家や作家は自分のリズムを見つけることがいかに重要かを知っていた。1日のなかでいつ最高の成果が出て、いつ休憩し、いつネガティブスペースを設けるべきかを知っていたのだ。
デジタル社会で集中力をコントロールすることは至難の業です。しかし、私たちは主体性を発揮し、計画・行動できるのです。
集中力はあなた自身のものであり、その力を最大限に引き出すことが成功への鍵です。動的集中をコントロールし、必要なときに集中力を発揮し、適度な休息を取ることで、効率的に仕事や学習に取り組むことができます。また、誘惑に打ち勝つための環境整備や計画的なアプローチも重要です。著者のアドバイスを実践することで、より効果的に自分の集中力を活用し、目標達成に近づくことができるでしょう。
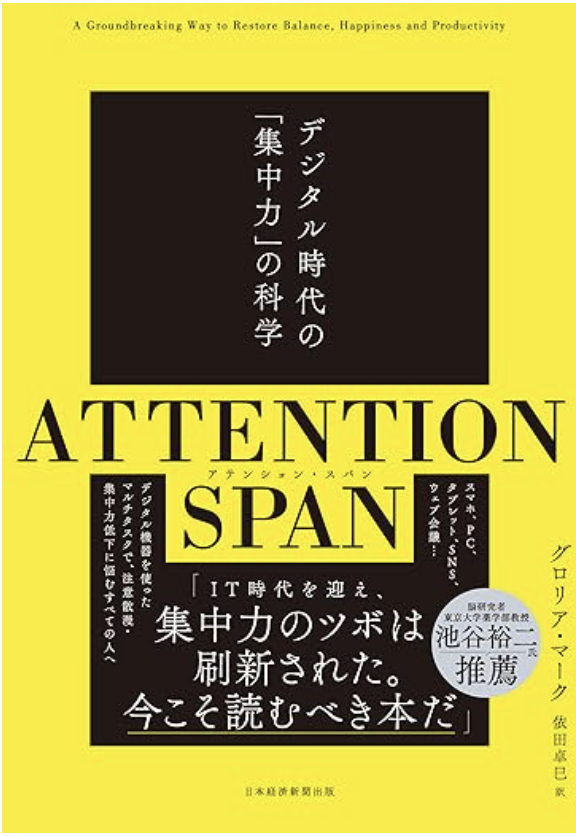


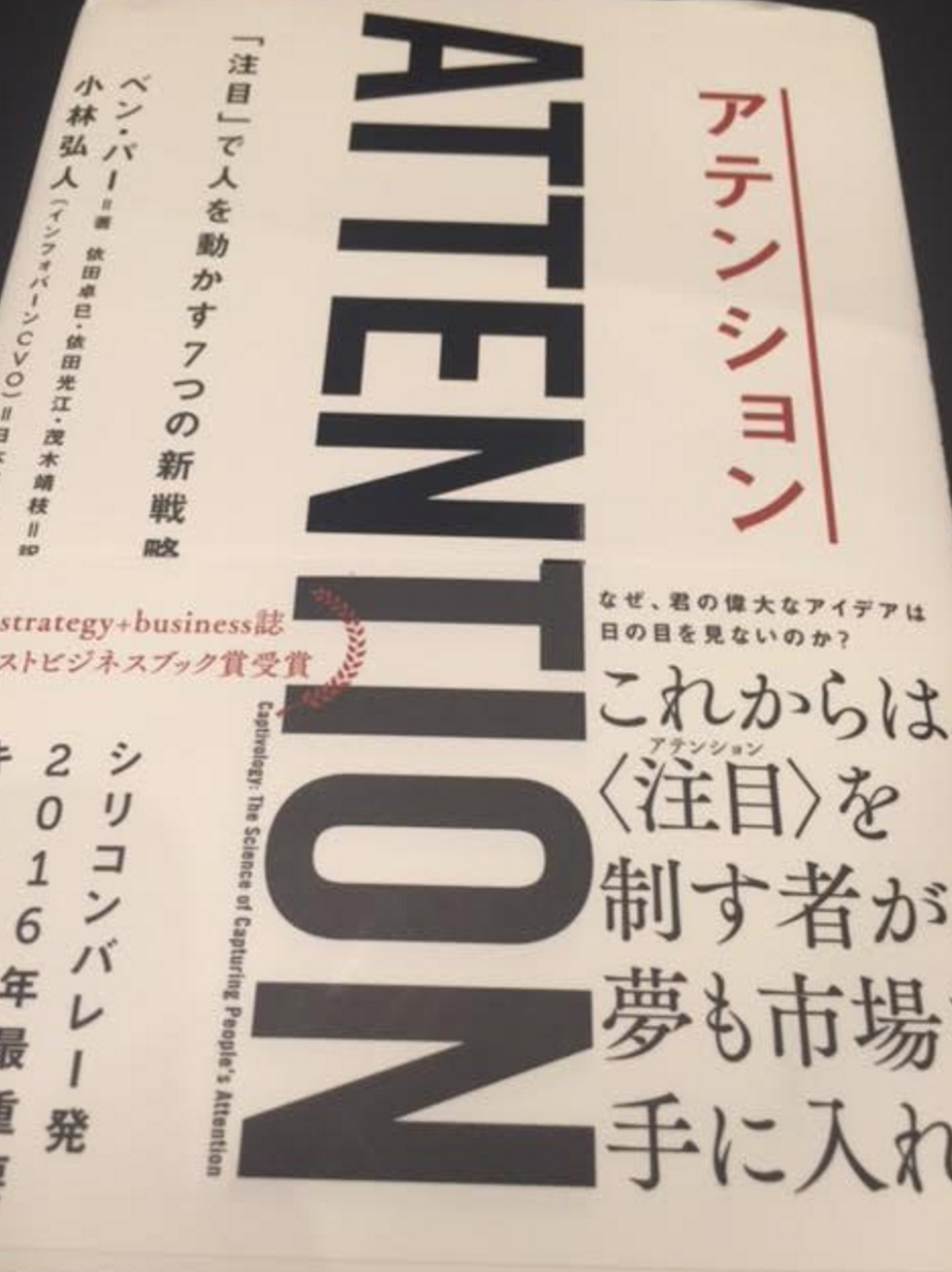
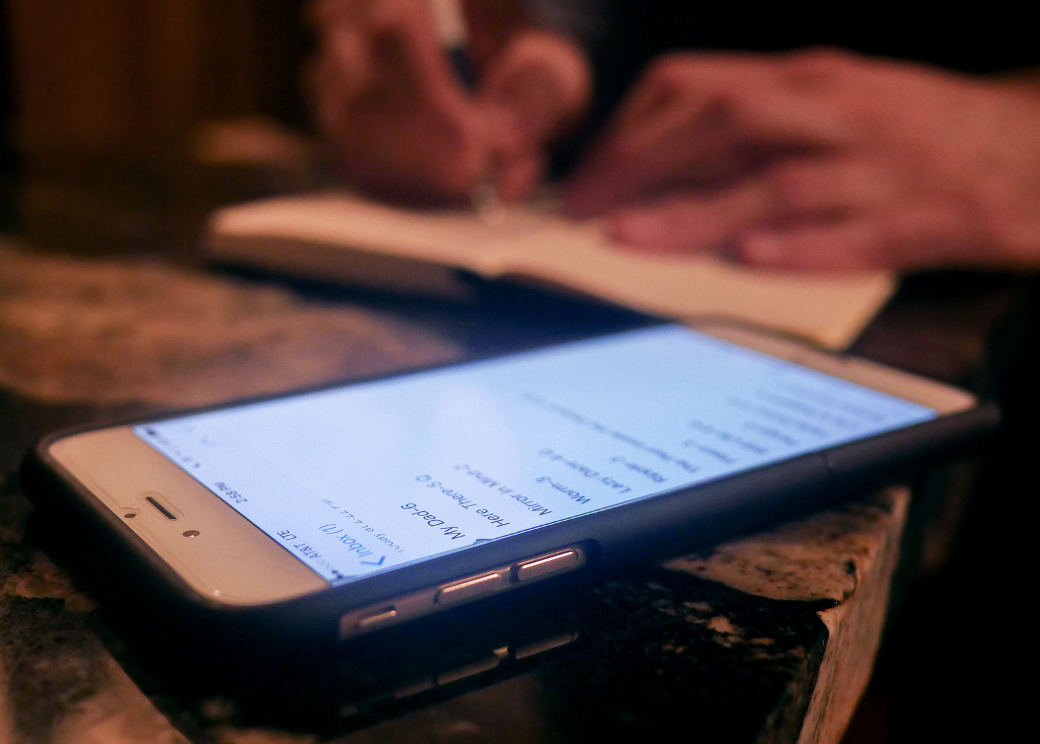










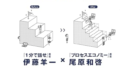

コメント